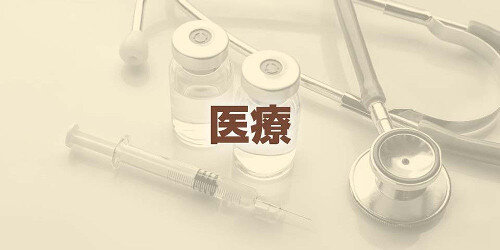認知症になるよりよほど不幸である…高齢者の20人に1人が罹患している「最悪の病」を予防する食材の名前【2025年3月に読まれたBEST記事】
2025年4月7日(月)17時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Nes
2025年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお送りします。食生活部門の第2位は——。
▼第1位 だから「コンビニごはん」のほうが健康になる…和田秀樹「できるだけ家で料理を作らないほうがいい理由」
▼第2位 認知症になるよりよほど不幸である…高齢者の20人に1人が罹患している「最悪の病」を予防する食材の名前
▼第3位 1日に必要な栄養素をイッキにとれる…医師が「合理的でバランスがいい」と勧めるコンビニグルメ"の名前"
▼第4位 「時々食べる」だけでも認知症予防になる…82歳の脳科学者が真っ先に挙げる「日本人が大好きな食べ物」
▼第5位 老化を防ぎ、血圧を下げる…「103歳で大往生」まで元気だった経営者が60歳から毎朝欠かさなかった飲み物
健康に長生きするにはどうすればいいのか。医師の和田秀樹さんは「高齢者のうつ病が増加傾向にある。うつ病は『自殺』という死に至る病なので、十分に注意すべきだ」という——。
本稿は、和田秀樹『死ぬのはこわくない』(興陽館)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/Nes
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Nes
■うつ病は「死に至る病」
一般的に、高齢になるほど、心と体の結びつきは強くなります。要するに高齢になるほど、心が弱ると体も弱りますし、逆に体が弱ると心も弱ってしまうのです。そのため、喪失体験をきっかけにうつ病を発症して体まで弱ってしまうということは、めずらしいことではありません。
そうでなくとも、高齢者のうつ病は増加傾向にあり、さまざまな地域で行われた住民調査をみると、実に20人に一人が罹患しているという割合です。うつ病は、注意しなくてはいけない病気の一つだといえます。
「うつ病は心の風邪」という言いまわしがありますが、うつ病は決して風邪などではありません。この言葉は、「うつ病は、風邪をひくくらい、なりやすく、誰もが発症する病気」という意味で使われますが、それ以外の点では、うつ病と風邪には大きな違いがあるのです。一番大きな違いは、うつ病が「自殺」という死に至る病であることです。私はむしろ「うつ病は心のガン」といったほうが正しいと思っています。
■筆者が考える「人生最大級の悲劇」とは
欧米では、自殺者が出ると、周辺の人々から生前の様子を聞く「心理学的剖検」が広く行われています。その検証作業によると、自殺者の50〜80%が「うつ病」だったと診断されているのです。それほど、注意すべき病気だということを理解してください。
「年をとっても、認知症にだけはなりたくない」と思っている人は、多いことでしょう。しかし、私のような精神科医の目から見ると、うつを患うことのほうが、認知症以上に不幸なことです。晩年、うつ病になって「何もしない暗い老人」として一生を終えるのが、人生最大級の悲劇だと思います。私自身、老人性うつにだけはなりたくないと思っています。
ひとりになったこれからの日々を楽しく、穏やかに過ごせるかどうかは、うつを防げるかどうかにかかっているといっても、過言ではありません。
体のケアはむろん大事ですが、これからは、心のケアも忘れないようにしてください。心の不調を感じたときは、ためらうことなく医者に行くことをおすすめします。
■肉を食べて悲しみを吹き飛ばす
検査をし、異常値を示した項目があると、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、肥満症とすぐに病名がついてしまうことでしょう。そして、コレステロールを下げろと、医者は指示してきます。でも、実際はコレステロールを下げる害のほうがずっと大きいのです。特に今回考えている喪失やうつ病の観点から見ると、余計に害になります。
コレステロールは脳にセロトニンという幸せホルモンを運ぶ働きがあるので、少なくしてしまうと、脳にセロトニンがうまく届かなくなるのです。セロトニンが不足してくると、不安が強くなり、気分が落ち込み、イライラしてきます。次第に感情が不安定になってくることが分かっているのです。これはまずい。うつ病を悪化させるだけです。
大切な人を亡くして、落ち込むのは仕方のないことです。食欲なんてわかないし、ましてや肉など食べる気にもならない。ごもっともだとは思うのですが、そんなときこそ勇気を出して、肉を食べてください。コレステロールたっぷりの肉を食べないことには、脳内のセロトニンは増えません。コレステロールは脳にセロトニンを運んでくれるのです。肉が難しいというなら、コレステロール目当てに牛乳やアイスクリームをとるのでもいいでしょう。
ビーフステーキ(写真=Flickr/pelican/CC-BY-SA-2.0/Wikimedia Commons)
栄養は摂らない、動かない、日に当たらないなどという日々を過ごしていたら、うつにはなるし、免疫力も下がるのは当たり前なのです。
■ひとり飲みにハマらない
寂しさを紛らわすために、何かにハマる人も多いことでしょう。それも度が過ぎると病気の範疇に入ってしまいます。中でも害があるのがアルコールです。お酒を飲むと楽になるからといって、ひとり飲みにハマるのは一番危険です。止めどもなくなります。
お酒の問題の根底には、日本のシステムがあることもお伝えしておきます。日本以外の国は23時を過ぎるとお酒が買えなくなることが多いのです。そんな中、堂々と24時間お酒が買えてしまうという日本は、異常だといえます。日本の国というのは、本当に人の命を犠牲にしても商売が儲かればいいやというところがありますね。
金儲けのためだったら、WHO(世界保健機関)がさんざんやめろといっているアルコールのCMもやり続ける。おかしなことです。これでは、ひとり飲みも自殺も増やして喜んでいるようにしか思えません。
■「ヤバいサイン」を見逃してはいけない
まぁ、それはともかくとして、お酒は人と飲むもの。それが当たり前です。夫や妻が死んでしまって寂しい。憂さを晴らすために、お酒を飲むのはいいのですが、それをひとりでやってしまうのはダメなのです。誰か話を聞いてくれる人がいる中でやらないと、あっという間にアルコールに溺れるようになってしまいます。
現在、アルコール依存症の判断基準は非常に厳しいものとなっています。たとえば、一合飲めばよかったけれど、今は二合飲まないと酔えない。アルコールの耐性ができてしまった。あるいは、酒乱的な行動を起こしてしまった。問題があるのにやめられない。そういったアルコール使用障害に、2項目当てはまったらそれでアウトです。というのも、アルコール依存症は軽いうちから注意しないと、なかなか治らない病気だからです。
寝酒を始めたらどんどん量が増えてしまった。前の量では酔えなくなっている。飲んでいるときは気分が落ち着くのだけど、飲んでいないときはイライラする。こんなことみんなそうだろうと気にも留めないかもしれませんが、実はこれらはすべてヤバいサインだということを頭に入れておいてください。
■依存しなくても生きられる
アルコール依存ほどの頻度ではないにしても、ギャンブル依存症も注意が必要です。ひとりになってしまい、寂しいからつい、パチンコ屋に足を運んでしまう。そんな話もよく聞きます。ギャンブル依存症は、あらゆる依存症の中で、もっとも治りづらいといわれているので、なめてかかると大変なことになります。
ギャンブルをやっているときは、脳内にドーパミンという快楽物質が大量に放出されます。反対に、やっていないときはドーパミンが放出されず、枯渇状態になるので、とても苦しい状態になってしまうのです。依存症ともなると、意志の力で治すことは、完全に無理です。本来であれば、ギャンブル依存症を治すちゃんとした施設をつくるべきなのです。それなのに、パチンコ業界には、警察官が堂々と天下りしているのですから、本当に日本は腐敗した国だと思います。
数は少ないですが、薬物依存もめずらしい心の病ではありません。寂しいからなどといって、薬物に手を出すのは、言語道断です。
和田秀樹『死ぬのはこわくない』(興陽館)
依存症というと、社会のレールから外れてしまった特殊な病気であるとか、通常の社会生活を送ることができないような、極端に意志の弱い人に生じる精神的な異常のように考えている人が少なくないでしょう。
しかし、現在の診断基準に照らし合わせてみると、数千万人が当てはまってしまう「もっともありふれた」精神障害なのです。
重度の依存症は、その人の社会的生命を奪い、さらに自殺に非常に結びつきやすいという問題があります。早期発見、早期治療が大切になってきます。依存症になると、失うものが非常に大きいことを充分理解すべきでしょう。
(初公開日:2025年3月8日)
----------
和田 秀樹(わだ・ひでき)
精神科医
1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。国際医療福祉大学教授(医療福祉学研究科臨床心理学専攻)。一橋大学経済学部非常勤講師(医療経済学)。川崎幸病院精神科顧問。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。2022年総合ベストセラーに輝いた『80歳の壁』(幻冬舎新書)をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『老いの品格』(PHP新書)、『老後は要領』(幻冬舎)、『不安に負けない気持ちの整理術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』(SBクリエイティブ)、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』(主婦と生活社)など著書多数。
----------
(精神科医 和田 秀樹)