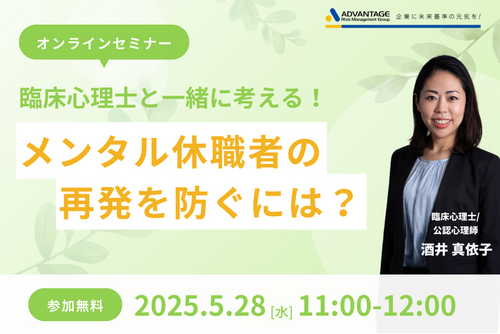病床でヨボヨボにされてからでは遅い…和田秀樹「ピンピンコロリで終わるためにすべきたった1つのこと」
2025年4月25日(金)17時15分 プレジデント社
出典=『患者の壁 [ベルトコンベア医療]には乗るな!』(エイチアンドアイ) - 撮影=藤谷清美
※本稿は、和田秀樹『患者の壁 [ベルトコンベア医療]には乗るな!』(エイチアンドアイ)の一部を再編集したものです。
■死ぬときは自宅と病院のどちらがいいか
人間は誰だっていずれ死ぬわけです。多少その時期が早まったり遅くなったりすることはあるかもしれませんが、死は確実に訪れるわけです。
患者さんが、少し長く生きるよりも、残りの人生の満足度を上げるほうを選択するという判断もあります。医者や家族が思っていたよりも早く亡くなることがあっても、本人が満足して亡くなったのであれば、それがいちばんだと思います。
死ぬときは自宅がいいか、病院や施設がいいか——患者さんが迷う選択肢です。病院は緩和ケア病棟やホスピスでなければ、ほとんどの自由が奪われます。病院に入院したら、好きなお酒が飲めなくなる、タバコも吸えなくなるというのでは、何のために生きているのかわからないという人もいます。そのためか、「最期は自宅で迎えたい」という人が増えています。私も病院で死にたいとは思いません。
撮影=藤谷清美
出典=『患者の壁 [ベルトコンベア医療]には乗るな!』(エイチアンドアイ) - 撮影=藤谷清美
■孤独死は「ピンピンコロリ」のケースが多い
自宅で最期を迎える一つのパターンとして「孤独死」が上げられます。仮に私が一人暮らしをしていて、心筋梗塞で胸が苦しくなったときに、近くに電話や携帯電話があれば119番して救急車を呼ぶことは可能でしょう。しかし近くに電話がなければ、そのまま死んで「孤独死」としてカウントされます。
孤独死は大きな社会問題として、ネガティブなイメージで報道されますが、孤独死の9割は直前まで元気だった人です。元気がなく介護が必要な方であれば、誰かが2〜3日のうちに訪問して対処しているからです。
孤独死は、いわゆる皆さんが大好きな「ピンピンコロリ」の形で亡くなるケースが多く、しかも自宅で亡くなるので、ある意味、理想に近い最期とも言えるでしょう。私は一人でいるのが好きなので、孤独死にネガティブな印象はありません。直前まで元気で、突然死ぬわけですから、それほど悪い最期ではないと思います。
読者の皆さんは、「孤独」と「孤立」が違うことを知っておきましょう。孤独は「寂しい」というような主観的な感情のことで、精神的な問題です。一方、孤立は客観的に見て他者とのつながりが少なく、周囲に助けがいないことです。そのため、周りに誰もいないほうが気楽だという人は、寂しさなどを感じていないので、孤独ではありません。
■ヨボヨボにされる医療のベルトコンベア
また、孤独死とは孤独であろうがなかろうが、一人で自宅死することです。孤独と孤独死ではニュアンスが違います。孤独死は特段ネガティブなこととは思えないので、社会問題化することに、私は少し違和感を覚えます。
いまの日本では、がんと診断されたら、当たり前のように延命治療が施されます。本人も家族も、医療についてほとんど知識がないので、医者の誘導でベルトコンベア式のラインに乗せられてしまいます。
本書(『患者の壁 [ベルトコンベア医療]には乗るな!』)の「はじめに」でも触れたように、医療のベルトコンベアに載せられてしまうと、病名をつけられ、病人にされ、薬漬けの生活が始まります。節制を強いられ、医療関係者から脅され、心配を抱え、ヨボヨボにされ、病院のベッドで最期を迎えてしまいかねません。コロナ禍以降、面会に厳しい病院であれば、親しい人とも会えずに最期を迎えることにもなります。
写真=iStock.com/warat42
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/warat42
■人生の最期は「自分で調べ、自分で決める」
アメリカや中国では、お金がない人はちゃんとした医療や医者にはかかれませんし、フランスやイギリスでは、医療費は無料である代わりに、医者にかかるまで驚くほど待たされます。
それに対し日本では、当たり前のようにすぐに医者にかかれますが、日ごろから残された人生や自分の死について深く考えていないので、医者に頼りきってしまいます。いろいろなアドバイスに素直に従い、医者に依存した状態になり、自分自身の意思や希望がどこにあるのかがわからなくなります。
一方で、医者にかかれない国では、多くの患者さんは医療について勉強します。生きるために、どのようなサプリメントを飲めば病気を予防できるのか、どのような治療を受ければ病気が治るのかといった知識を得るのに必死です。もし、がんと診断されたら、どう対処するのかも想定していて、自分の死や終末について深く考えています。
いまの時代は、インターネットが使えれば、医療情報も治療法も瞬時に知ることができます。こうした病気や命にかかわる勉強も自分でできる環境があるのですから、日本人もそろそろ自分の運命を医者任せにするのではなく、「自分で調べ、自分で決める」ことを意識的にすべきなのです。
■納得のいく自分の最期を選択するには
たとえば、日本人の二人に一人はがんになるのですから、日ごろからがんと診断されたら、どう対応するかをシミュレーションしておいてください。医者からさまざまな治療の選択肢が示されますが、選択するのは自分であり、治療を受けないという選択もあるわけです。
治療を受けなければ、どのようなことが起こり、どのくらいで最期を迎えるのか? 逆に、治療を受ければ、どのような副作用や後遺症が想定されるのか? どれほどの金銭的な負担が生じるのか?──。
こうしたことは、インターネットを検索すれば、直ちにがんに関する情報や経験者の体験談を入手できますし、専門家の話を動画で見ることもできます。
医者に言われた通りの治療や対処をしても、その結果良い方向に行けばいいのですが、悪い方向に行けば不信感が募り、納得のいく治療にはならないのです。どの病院のどの医者にかかるのかまで考え、自分の蓄えた知識や情報を医者にぶつけ、そのうえで自己決定する必要があります。そうすることで、納得のいく人生、納得のいく最期を迎えられるのです。
■「人間はいずれ死ぬ」ことを受け入れよう
もし、あなたが今日余命を宣告されたら、どうするでしょうか。慌てふためき、絶望の淵に叩き落とされるでしょうか。それとも、少し冷静になって考え、自分で調べはじめ、対処法を見つけ出し、行動に移すでしょうか。
和田秀樹『患者の壁 [ベルトコンベア医療]には乗るな!』(エイチアンドアイ)
大半の人は、当初はショックを受けますが、時間とともに現実を受け入れ、冷静さを取り戻します。高齢の方であれば、なおさら親族や友人の死をすでに経験し、多くの人が「自分も順番が来たのだから仕方がない」という境地に達していきます。現実を渋々受け入れながら、心の奥底であきらめの境地に達することでしょう。
長く人生を生きてきた高齢者であるからこそ、人間には運命があるという真理に気づき、最終的にはそれを受け入れていきます。早く死ぬ人もいれば、長く生きる人もいます。志を遂げる人もいれば、志半ばの人もいます。すべて自分の運命なのだと納得すれば、仕方がないと諦観(ていかん)できるのです。
写真=iStock.com/valio84sl
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/valio84sl
----------
和田 秀樹(わだ・ひでき)
精神科医
1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。国際医療福祉大学教授(医療福祉学研究科臨床心理学専攻)。一橋大学経済学部非常勤講師(医療経済学)。川崎幸病院精神科顧問。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。2022年総合ベストセラーに輝いた『80歳の壁』(幻冬舎新書)をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『老いの品格』(PHP新書)、『老後は要領』(幻冬舎)、『不安に負けない気持ちの整理術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』(SBクリエイティブ)、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』(主婦と生活社)など著書多数。
----------
(精神科医 和田 秀樹)