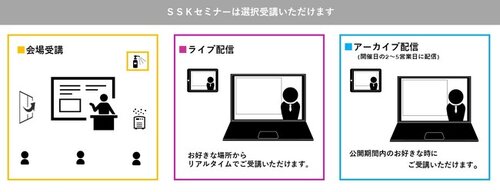交渉材料は何も持っていないのに…トランプ大統領に"日本の特別扱い"を求め続ける石破政権の無為無策
2025年4月8日(火)7時15分 プレジデント社
自民党本部を出る石破茂首相=2025年4月3日午後、東京・永田町 - 写真=時事通信フォト
■「右顧左眄」「平身低頭」「周章狼狽」
少数与党で内閣支持率が低迷していては、政府・与党の政治判断や政策遂行に当たって「右顧左眄」し、野党対策では予算や法案成立のために「平身低頭」するしかない。そこへ米国による高関税措置という「国難」に襲われれば、「周章狼狽」するしかないではないか。
石破茂政権は3月31日、参院で再修正した2025年度予算案を可決し、衆院に戻して全会一致の同意を得て、年度内成立を実現させた。参院での予算審議の間、首相が配布した10万円商品券の問題や、自民、公明両党首会談で物価高対策をぶち上げたフライングによって与野党内で批判されたが、立憲民主党などの石破政権「延命」作戦もあって、何とか低姿勢で乗り切ったといえる。
写真=時事通信フォト
自民党本部を出る石破茂首相=2025年4月3日午後、東京・永田町 - 写真=時事通信フォト
石破首相は、戦後80年談話の閣議決定による発出を見送るものの、戦争を検証する有識者会議を設置し、その成果を自身の見解とともに公表する。読売新聞が3月27日に報道した。首相に歴史を総括する見識が備わっているのかを問う以前に、新たな検証作業が自民党内や世論の分断を招き、政権の体力がさらに奪われるリスクを否定できない。
企業・団体献金の規制強化をめぐる与野党協議では、自民党と公明、国民民主両党が相互に歩み寄った。3党は3月31日の実務者協議で、企業・団体献金の存続を前提に情報公開の強化などで合意した。公開規定では、年間1000万円超の寄付をした企業や労働組合の名称や総額を公開すると主張していた自民党が、年間5万円超に大幅に引き下げるという公国案を受け入れた。
石破首相は、6月に東京都議選、7月に参院選を控え、トランプ米大統領による「相互関税」などへの対応策とともに、自民、公明両党が勝利するための政治目標や外交・安全保障、経済政策を掲げることができるのか。
■「解明なくして支持率は上がらない」
25年度予算は3月31日、参院本会議で自民、公明、日本維新の会3党などの賛成多数で修正可決された後、衆院本会議に回付され、全会一致の同意を得て成立した。
衆院の審議では予算に賛成した維新が求めた教育無償化などで3党が合意して修正され、参院審議では立憲民主党などが主張した高額療養費制度の負担上限額の引き上げ見送りを受けて再修正・提出されたものだ。参院で修正された予算案が衆院に回付され、同意を得て成立するのは、現憲法下で初めてである。
野党としても、3月4日に衆院を通過した、高額療養費をめぐる修正内容が反映されない予算が4月2日に自然成立するため、参院の採決をこれ以上遅らせる選択肢はなかった。
自民党執行部は与野党攻防の裏で旧安倍派の動きを牽制する。立憲民主党が採決を容認する条件として、自民党の派閥パーティー収入不記載事件に関わった旧安倍派幹部の参考人招致を求めたのに対し、3月28日に世耕弘成前参院幹事長(離党、現衆院議員)を参院予算委員会に招致する議決に応じたのだ。
この参院予算委での議決は、自民党も賛同する異例の全会一致だった。党執行部は世耕氏の参考人招致受け入れを事前に本人にも秘匿し、旧安倍派の予算委員11人中、同意できないとする4人を直前に差し替えて全会一致の形を取った、と報じられている。
これに関連し、石井準一参院国会対策委員長(旧茂木派)は、記者団に「『政治とカネ』で国民に不信感を抱かれたのなら、解明していく大きな責任がある。解明なくして与党の支持率は上がらない」と指摘した。旧安倍派幹部に当事者意識がなく、世耕氏が先の衆院選で自民党公認候補と戦った「反党行為」への風当たりの強さも反映しているのだろう。
■「官房機密費が使われた疑いが出る」
首相の商品券問題は、永田町の常識が世間の感覚とずれてきていることを知らしめた。
首相は3月3日の首相公邸での衆院当選1回の15人との会合で、1人当たり10万円商品券と1万5000円の懇親会費計172万5000円をポケットマネーで賄ったと説明してきている。
その後、岸田文雄首相(当時)が首相公邸での政務官との会食で、今回と同様に三越発行の10万円商品券を配布していたことを党関係者が明らかにした。大岡敏孝衆院議員(旧二階派)は21日、記者団に安倍晋三首相(当時)と12年衆院選初当選組との会食で、10万円商品券を受け取っていたことを証言し、歴代首相による慣行だったと印象付けた。
写真=iStock.com/kokouu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kokouu
21日の参院予算委員会で立民党の杉尾秀哉氏が「慣行だとしたら、官房機密費が使われた疑いが出てくる。ポケットマネーからか、証明できるか」と追及する。石破首相は「証明の仕方が難しい」と歯切れが悪かった。
支持率は急落した。3月の産経新聞・FNN世論調査(22〜23日)で内閣支持率は30.4%と2月調査から13.9ポイント下落し、昨年10月の政権発足以降で最低となった。
興味深いのは、首相の進退について「辞める必要はない」が62.6%で、「辞めるべきだ」の32.7%を上回ったことだ。世論は首相独りの問題ではないと受け止めたのだろう。
立民党の野田佳彦、国民民主党の玉木雄一郎両代表も、政治倫理審査会での弁明を要求し、直ちに首相退陣を求めてはいない。首相をじわじわと追い詰める狙いらしい。
■「予算案は強力ではなく『無力』なのか」
石破首相の「強力な物価高対策」発言は、予算の参院審議中の3月25日昼、自公党首会談後に斉藤鉄夫代表の口から飛び出した。予算成立後に「強力な物価高対策を打ち出そう」と首相から呼び掛けられた、と記者団に明かしたのだ。参院選で苦戦が予想される焦りからだろうが、審議中の予算案の内容では対策が不十分だと認めるに等しく、野党から予算修正を求められかねない、危ない発言だ。
林芳正官房長官が同日の記者会見で「新たな予算措置ではなく、物価高の克服に取り組んでいくという決意を示したものだ」と否定してみせたが、首相と斉藤氏の政治センスのなさをカバーできるものではなかった。
首相は27日の参院予算委員会で「予算成立を期して、その後もなお食料品や燃料費の高騰に適切な対応を取っていく」と説明した。立民党の辻元清美代表代行は「私たちが審議している予算案は、強力ではなくて『無力』なのか」と首相に迫る。首相は「ご迷惑を掛けた」と頭を下げるしかなかった。
■「80年談話は絶対に出すべきではない」
戦後80年談話について、石破首相は1月29日のシンポジウムで「今を逃して、戦争を検証することはできない」と述べ、前向きだった。1月31日の衆院予算委員会では「なぜあの戦争を始めたのか、なぜ避けることができなかったのか、なぜ途中でやめることができず、東京が焼け野原になり、広島、長崎に原爆が落ち、大勢の方が亡くなったのかを、検証するのは、80年の今年が極めて大事だ」と述べ、談話を発出する意向を示唆していた。
70年談話をまとめた安倍元首相を支持する勢力がこれに反発し、歴史認識をめぐる党内論争に発展しそうな空気になって、麻生太郎元首相(党最高顧問)が動く。80年談話について、首相に「絶対に出すべきではない。安倍氏がどれだけ苦労したか分かっているのか」と説いた、と産経新聞に報じられた。
2019年4月26日、ホワイトハウスで行われたドナルド・トランプ大統領と安倍晋三首相(当時)との会談(写真=The White House/Executive Office of the President files/Wikimedia Commons)
戦後70年談話に関する有識者会議の北岡伸一座長代理も3月10日の首相との会食で、80年談話を出すことに否定的な考えを伝えたという。この後、首相も「石破降ろし」の火種に繋がりかねない80年談話にはこだわらないとの判断に至った、と伝えられている。
戦後70年談話は、「侵略と植民地支配」への「痛切な反省とおわび」など歴代内閣の談話を引用しながら、国際社会の寛容の心に感謝するとともに、戦争に何の関わりのない世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」とすることで、歴史認識をめぐる国内の政治対立に終止符を打ち、国民を統合する役割を果たしたと位置付けられよう。
安倍氏は「戦後80年の時には(首相談話を)やる必要がない」「ここで終えて、歴史戦の道具にされないということだ」(船橋洋一著『宿命の子(上)』文藝春秋刊)と語っていた。石破首相は、戦争検証の成果や自身の見解を示すことが中国や韓国との歴史戦の道具にされかねないと自覚しているのだろうか。
■「禁止すれば政党交付金頼みの政治に」
企業・団体献金の規制強化を図る政治資金規正法改正案をめぐる協議では、自民党が存続を前提に透明性の向上を主張し、立民党や維新の会が原則禁止を訴えたまま、衆院政治改革特別委員会の理事間合意で期限としていた3月末までに折り合えず、4月以降も継続協議することになった。
公明、国民両党は、企業・団体献金を受け取れるのは政党本部と都道府県連に絞る案を示していたが、自民党案に譲歩し、政治資金収支報告書のオンライン提出を条件に、政党支部も受け取りを認めることで、3月31日、寄付者名の公開基準額を5万円超とすることを含めて、自公国3党が合意した。
自民党は、これまで「禁止より公開」を訴え、1月31日に年間1000万円超の寄付者名を公表するとした改正案を単独で国会に提出した。小泉進次郎政治改革本部事務局長が2月2日のBSテレ東の番組で、党の収入に占める政党交付金の割合は自民党が70%、立民党は85%に上る現状を紹介し、「企業・団体献金を禁止すれば、政党交付金頼みの政治になってしまう。多様な支援で成り立つ政党や政治活動でありたい」と主張するなどしてきた。
写真=iStock.com/oasis2me
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/oasis2me
■「存続ありきのアリバイ作りのようだ」
国民民主党も、企業・団体献金禁止ではない立場だ。榛葉賀津也幹事長が月刊誌「改革者」2月号のインタビューで、「民主主義のコストの問題だ」「一番大切なのは透明性と説明責任だ」との見解を示すとともに、後藤田正晴元副総理が「野党は政党交付金に頼るような政党になってはいけない」「自分たちの財源を政府・与党に押さえつけられるようなことになってはいけない」と話してくれたというエピソードを明かしていた。
立民党や維新などは企業・団体献金が「金権腐敗の温床になっている」と訴え、3月19日にそれぞれの禁止法案を一本化し、国会に共同提出した。この法案は企業や労働組合が作った政治団体の献金は禁止の対象外とし、抜け穴を作っている、とも言われている。
自民党の森山裕、公明党の西田実仁両幹事長は4月1日、都内で会談し、自公国3党案をベースに立憲民主党に協議を呼び掛けることで一致した。立民党の小川淳也幹事長は同日の記者会見で「企業・団体献金の存続ありきのアリバイ作りのような議論だ」「とにかく(3党に)法案を出してもらいたい」と述べ、協議に応じないとの意向を示している。
■「必要であれば私が(米国に)赴く」
石破首相は4月1日、今年度予算成立を受けた記者会見で、物価高対策やトランプ米政権の関税政策への対応に全力を注入すると強調した。
参院選向けにガソリンやコメの価格抑制や「年収の壁」見直し策などを列挙し、手取りを増やすと訴えたが、消費税減税を否定したため、与党内の一部にも不満の声が上がった。米国から3月27日に発表された日本を含む輸入自動車への25%の追加関税措置については「米国に日本の適用除外を強く求める。必要であれば私が(米国に)赴く。発動された場合、企業の資金繰り支援に万全を期す」との意気込みを示したところだった。
翌々日の米国発の「関税弾」について、石破首相はこの当時、まったく予期していなかった。事前の情報はなく、メディアに報じられることもなかったからだ。
4月3日(米国時間2日)にトランプ大統領から布告された相互関税は、自由貿易体制によって戦後の世界経済を牽引してきた米国がその役割をかなぐり捨てたもので、日本にも想定外の混乱をもたらしている。
米国はすべての国・地域にまず一律10%の関税を設定し、相手国・地域には貿易赤字、非貿易障壁などに応じた税率を上乗せするとし、日本は新たに24%が課される。中国には34%、EUに20%、ベトナムに46%などとなっている。算出根拠は貿易赤字額を輸入額で割った数字を半分にしたという杜撰なものだ。
3日には日本を含む輸入自動車への25%の追加課税が発動した。相互関税も一律10%が5日、上乗せ分が9日に発動する。鉄鋼、自動車などの商品別関税に相互関税はプラスされない。日本の対米輸出には、鉄鋼が25%、自動車は現行2.5%と合わせて27.5%が課せられる。それ以外は相互関税の24%になる。米国の相互関税には、世界全体の実質国内総生産(GDP)を0.5%押し下げるという試算もある。
■「貿易面では敵よりも友の方が悪い」
石破首相は4月3日、関係閣僚・省庁幹部から状況報告を受け、国内対策を指示した後、記者団に「日本は世界最大の対米投資国だ。日本企業は米国経済に多大の役割を果たしてきたし、今もそうだ」と不満を募らせた。相互関税や自動車への追加関税の適用対象から日本を除外するよう、3月10日に武藤容治武藤通商産業相が訪米してラトニック商務長官と会談するなどして米国政府に働きかけてきたが、徒労に終わったためだ。
2024年2月7日(現地時間)、ドナルド・トランプ大統領と石破首相は対面で初めてとなる会談を行った後、イーストルームにて記者会見(写真=内閣官房内閣広報室/CC-BY-4.0/Wikimedia Commons)
首相は4月4日、国会内で開いた与野党6党の党首会談で「トランプ関税」への対応をめぐって「言うなれば国難で、政府・与党のみならず、野党も含めた超党派で検討・対応する必要がある」と述べ、協力を求めた。立民、維新、国民3党代表は、首相に訪米して直接交渉するよう提案したという。
だが、トランプ政権に対し、日本を特別扱いして除外するよう求めるのは、おかしくないか。今回の相互関税は「雇用と工場は米国に回帰する」とし、他国に食い物にされてきた結果の貿易赤字を削減するのだという。トランプ氏は演説で、日本について「貿易面では多くの場合、敵よりも友の方が悪い状況にある」「自分たちが私たちから搾取していることを理解している」と言及している。
日本には適用除外してもらうだけのディールの材料があるのか。安全保障で米国の「核の傘」に頼っている日本にはない、と考えた方がいいだろう。EUや中国、カナダなどは報復関税などの対抗措置を打ち出しているが、日本にはその選択肢はないのだから。
トランプ政権の関税政策は、自滅に向かう道だ。関税は米国の企業と消費者が負担する。米国内の経済格差は解消されず、インフレを招くだけで、自動車などの製造業が蘇るわけでもない。対外的には多くの同盟国の信頼も失う。だが、政権内にブレーキ装置はなく、自らの支持層に不利益が及ばない限り、現行の関税政策は続くとみられる。
日本が取り得る対策は限られる。EUやカナダとも連携し、米国に対する投資や米国からの輸入を拡大しながら、最終的に米国が保護主義を脱して自由貿易体制へ回帰するのを待つしかないのではないか。
石破首相も5日、記者団に「頼むから日本だけ例外にしてください、と言ってもしょうがない」と語るようになっている。
----------
小田 尚(おだ・たかし)
政治ジャーナリスト、読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員
1951年新潟県生まれ。東大法学部卒。読売新聞東京本社政治部長、論説委員長、グループ本社取締役論説主幹などを経て現職。2018〜2023年国家公安委員会委員。
----------
(政治ジャーナリスト、読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員 小田 尚)