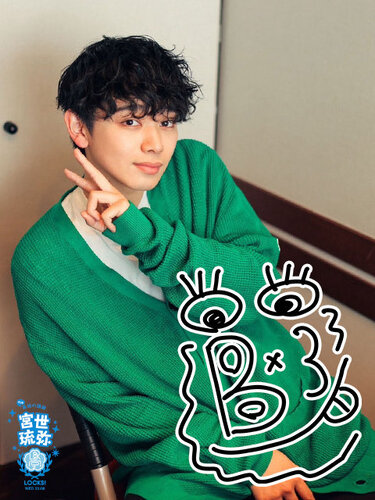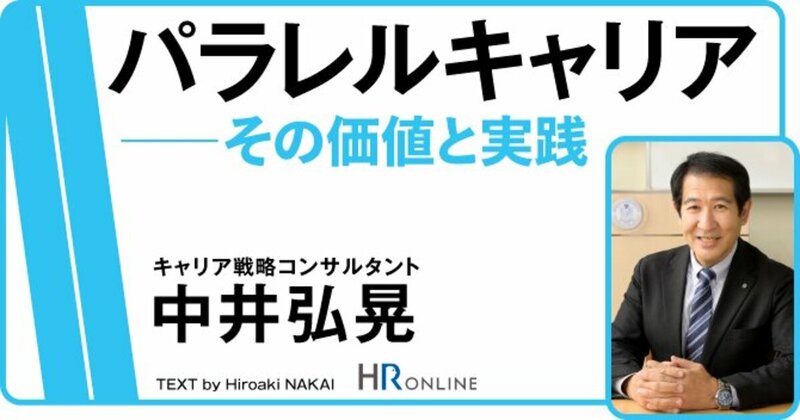“活私奉公”の時代に、ビジネスパーソンは仕事にどう向き合えばよいか?
2025年4月17日(木)6時0分 ダイヤモンドオンライン
“活私奉公”の時代に、ビジネスパーソンは仕事にどう向き合えばよいか?
働く者一人ひとりの「キャリア」がいっそう重視される時代になった。個人が職業経験で培うスキルや知識の積み重ねを「キャリア」と呼ぶが、それは、一つの職種や職場で完結するものとは限らない。「長さ」に加え、キャリアの「広さ」も、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を左右するのだ。書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア 〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』(*)の著者であり、40代からのキャリア戦略研究所 代表の中井弘晃さんは“パラレルキャリア”こそが、個人と組織を成長させると説く。今回は、いま、この時代に心がけたい“活私奉公”の働き方について考える。(ダイヤモンド社 人材開発編集部)
* 中井弘晃著『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア〜「弱い紐帯の強み」に着目して〜』(2022年10月/公益財団法人 日本生産性本部 生産性労働情報センター刊)
*連載第1回 価値ある“パラレルキャリア”とは?広義の5タイプから考える副業との違い*連載第2回 “パラレルキャリア”の効果と効果最大化のために個人と組織に必要な姿勢*連載第3回 仕事のキャリアをよい方向に導く“緩やかなつながり(弱い紐帯)”を考える*連載第4回 “偶然の出来事”をキャリアに活かす!——そのために必要なことは何か?*連載第5回 不本意な異動や出向……職場環境の急な変化で、キャリアを豊かにする方法*連載第6回 “副業”ではない、“活私奉公型のパラレルキャリア”が、個人と組織の未来を創っていく
「活私奉公」の働き方が望まれる時代になっている
「社内での仕事だけでなく、NPO活動やボランティア活動など社外での活動にも取り組み、自身の専門性や視野を広げ、人脈も作ってほしい。多様性を持った面白い人間となって、社外で学んだことを組織に持ち帰って、プラスの影響をもたらしてほしい」
これは、かつて私が勤務した富士ゼロックス(現・富士フイルムビジネスイノベーション)の会長を務めた小林陽太郎氏(社外では経済同友会代表幹事や国際大学理事長等を歴任)の言葉です。
この言葉のなかに“パラレルキャリア”のエキスが詰まっていると私は思っています。小林氏のような、外に開かれた視点を持つ経営者のもとでは、社員が安心して社外に出て積極的に活動し、スキル向上や視野・人脈の拡大が可能になるのではないでしょうか。
富士ゼロックスの社風や、私の勤務時代の出向・海外勤務経験は、私自身が「パラレルキャリア」に関心を持つ原点になっています。
同時に、冒頭の言葉は前回(連載第6回)で紹介した「活私奉公」の考え方と通じるところがあり、「活私奉公」のスタンスこそ、ビジネスパーソンに求められるものであると私は思います。
ちなみに、皆さんは「活私奉公」という言葉は聞いたことがありますか?
「『滅私奉公』なら聞いたことがあるが、『活私奉公』は聞いたことがない」という人がほとんどでしょう。造語ですから当然です。誰の造語かは定かではありませんが、私自身は、「活私奉公」という言葉を、1980年代に小林氏を通じて初めて知りました。当時は「働き方改革」も始まっておらず、「長時間労働」や「滅私奉公」が美徳とされていた時代でした。そんななか、小林氏は「個人と組織との関係は、『滅私奉公』ではなく、『活私奉公』であるべき」と主張しました。
「活私奉公」をネットで検索したところ、類義語として、「活私開公」「活私貢献」「活私豊公」といった言葉も世の中で使われていることがわかりました。各々、主に教育領域、社会活動領域、公職領域等で使われているようです。組織で働くビジネスパーソン向けには「活私奉公」がいちばんピンとくるように思います。
では、なぜ、いま、「活私奉公」的な働き方がビジネスパーソンに求められるのでしょうか?