「低賃金でも大喜びで働く人間」が続々と集結…“社員の搾取”に長けた「超有名企業」の“リアル”《「やりがい搾取」は必ずしも「悪」ではない?》
2025年4月28日(月)7時0分 文春オンライン
国際的に見て「低賃金」とされる日本企業。仕事ばかり増える一方で給料が上がらず「やりがい搾取」に苦しむ人も多い。ただ、反対に「低賃金でも大喜びで働く人」がいるのも事実だ。一体なぜなのか。背景には“良い搾取”の存在がある。日々苛烈さを増す資本主義の現代を生き抜くヒントをまとめた書籍 『働かないおじさんは資本主義を生き延びる術を知っている』 (侍留 啓介著、光文社)から一部抜粋し、アップルストアなどの事例を基に「超一流企業」による“良い搾取”を解説していく。
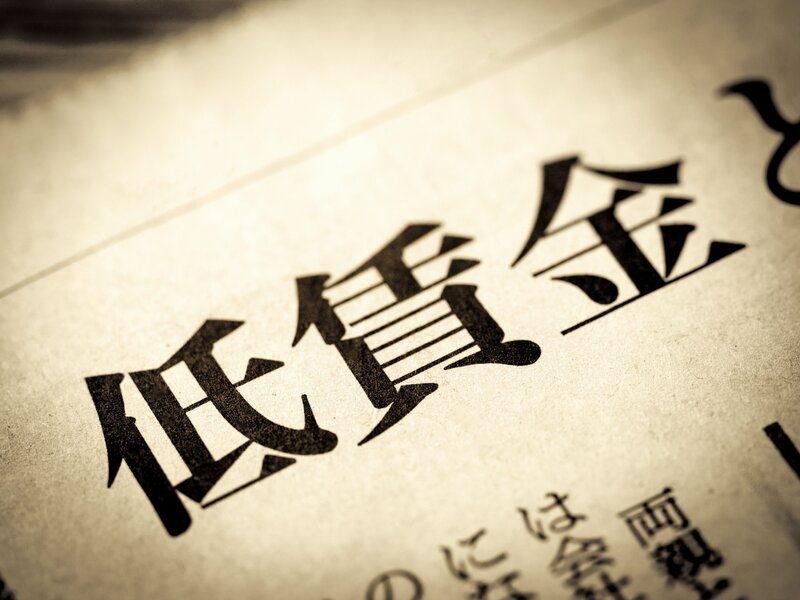
◆◆◆
安月給でコキ使う「やりがい搾取」が生まれる構造
B(経営者)が肝に銘じておかねばならないのは、再三強調している通り、「いかに安定的に搾取するか」という視点である。資本主義ゲームの中で、手段はどうあれ、利益を最大化することこそが経営者にとって唯一の生き残り策であることを思えば、この視点は避けては通れない。
「搾取」のベクトルは、顧客と従業員の双方に向かいうる。すなわち、顧客には「より多くを支払わせること」、従業員には「より少ない報酬で満足させること」が肝要となる。もちろん、最も望ましいのは、顧客や従業員とWin-Winの関係を築くことであり、この場合、一般的な意味での「搾取」には当たらないだろう。
しかし、ここで強調しなければならないのは、Win-Winの理想状態が築けない場合、相手に損をさせてでも自分や自社が生き残ることが求められる(すなわちWin-Loseとなる)ということである。そして、Win-Loseの状態では、搾取構造がとられやすい。
まず前者──顧客からの搾取について見てみよう。
企業は、あの手この手で顧客からより多くの代金を支払わせるべく努力している。しかも、なるべく顧客の「内発的動機づけ」(第2章参照)によって支払わせたい。顧客が自らすすんでその対価を支払いたくなるよう仕向ける、ということである。これがマーケティングの基本となる。価格体系を意図的にわかりにくくすることも、しばしば講じられる手段である。前述の携帯電話のわかりにくい価格構造はその典型例だ。
現代マーケティングとは「搾取」かもしれない
実はこうした価格をみえにくくする手段は、資本主義のごく初期の段階から、企業活動に組み込まれていた。第1章で触れたミシシッピ・バブルを思い出してほしい。18世紀のフランスで起きた株価の乱高下で多くの人が財産を失った。この狂乱の立役者であったスコットランド人ジョン・ローの墓碑銘には、こう綴られていたという。
〈 代数の法則を使って
フランスを破滅させた
たぐい稀れな計画家で
有名なスコットランド人ここに眠る。〉
一説にはパロディとして流布されたものとも考えられているが、バブルを引き起こしてフランス国外へ逃亡したローに、人々がどんな目を向けていたかが示されている。要するに、「理屈でごまかしてフランス人たちをひどい目に遭わせた」ということである。
ローの才能は、数学などを引き合いに、もっともらしい話を聞かせて、相手を煙に巻くのがうまかった、という点にある。話を聞いている方も、実際には理解できていないのだが、理解できたふりをせざるをえなくなるように仕向けられていたのである。
ローを単に詭弁家として片づけることは簡単である。しかし、ローの才能を、科学的な理屈でもって緻密に練り上げた事業戦略に基づき、顧客を説得する技術だと考えれば、これは現代マーケティングそのものである。
断っておくが、価格体系をわかりにくくさせて値上げしていくことは、これ自体が問題なのではない。ことにサービス業にとって、価格を上げていくことは生命線である。サービス業は、製造業と違って原価構造が複雑になるわけではないので、顧客に足元を見られやすい。このため、企業にとっては、原価構造を当然のように「見えない化」して、不断の努力によって単価を上げていくことが重要なのである。
「高付加価値化」「ブランディング」などのマーケティング手法は、突き詰めればこの「見えない化」による価格の最大化である。サービス業に限らず、どの企業も等しくこの方向性を目指しているし、またそうあるべきである。
顧客側としては、マーケティングに踊らされるのではなく、その適正価格を冷静に考えなければならない。その上で、商品やサービスを購入することは、個人の判断であり自由である。
「やりがい搾取」は必ずしも「悪」ではない
また、従業員をいかに安く用いるのか、という視点も、経営者には欠かせない。「搾取」と否定的に言ってしまえばそれまでだが、私はむしろこの「搾取」に肯定的な見方をしている。何度も繰り返すが、利潤を確保することは企業の使命である。そもそも、従業員からすれば、給与がそこで働く唯一の目的だとは限らない。問われるべきは、給与以外のベネフィットを与える仕組みが企業にあるかどうかである。
ひとつには、経営者の人格が重要である。人格というと高尚に聞こえるかもしれないが、これは第2章の〈「一攫千金教」のためのM&A入門〉で述べた「人たらし」のスキルのことである。「この社長についていきたい」というような気持ちを従業員に起こさせることができれば、必ずしも従業員を金銭だけで惹きつける必要はない。
入社希望者が絶えない「良い搾取企業」の特徴
ノーラン・ブッシュネルとジーン・ストーンの著作『 ぼくがジョブズに教えたこと 』(飛鳥新社)は、伝説のゲーム会社アタリの創業者であるブッシュネルが、アタリ社の40人目の社員であったスティーブ・ジョブズに授けたヒントに基づいて、創造的な会社を作り上げる秘訣を51カ条にまとめたものである。たとえば25条の「手柄はチームのものと心得よ」をみてみよう。
〈 アップルストアの店員は、安めの賃金で、3カ月で75万ドルも売り上げる。そういう環境をアップルが作りあげたからだ。4万3000人いるアップル社員のうち約3万人がアップルストアで働いており、その給与は年間2万5000ドル程度にすぎない。だが、皆、大喜びで働いているという話しか聞こえてこない。 愛国心に匹敵する気持ちがなければできない献身だろう。〉
優れた企業には、お金でない「何か」がある。その「何か」で優秀な人を惹きつけている。それを「やりがい搾取」と呼ぶのか、内発的動機づけと呼ぶのか、優れた企業文化と呼ぶのかは解釈の問題であろう。
また、企業のブランドやそこで提供できる経験の質も重要である。きちんと統計を取ったわけではないが、どの業界でも優良企業になればなるほど、他の同業に比べて給与が低く抑えられる傾向がある。
今は異なるかもしれないが、私が新卒として入社した三菱商事も、MBA取得後に入社したマッキンゼーも、同業他社に比べると、少なくとも初任給は高くなかった。他社より給与が低くても、そこで得られる経験や、そこで働けるステータスに魅力があれば、優秀な人材は応募してくる。経営者としては、このような採用戦略を目指すべきであろう。
(侍留 啓介/Webオリジナル(外部転載))













