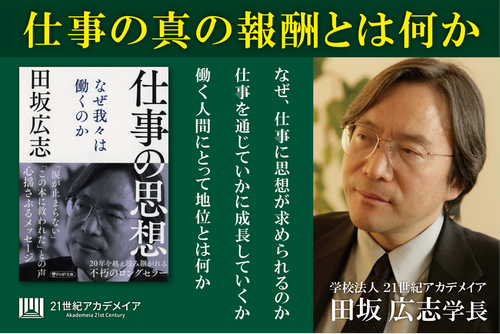「ならば半導体に特化した大学院も作ってしまおうと…」熊本大学学長が語るTSMC工場建設が“100年に1度の大チャンス”である理由
2025年5月3日(土)7時0分 文春オンライン
台湾・TSMCの工場が熊本にやってきたことは、“100年に1度の大チャンス”だと語る熊本大学学長の小川久雄氏。小川学長は、日本の技術再興のために、根本にある学術レベルを一刻も早く回復することが必要であると力説します。
◆◆◆
求められる人材像と教育対策
残念ながら、わが国の学術レベルは急激に低下しているというのが偽らざる現状です。例えば、自然科学の分野で質が高い論文の指標とされる「トップ10%論文」の本数がそれを物語っています。これは国の学術レベルを示す指標のひとつで、医学や工学などの分野ごとに、他の研究者からの引用回数を順位付けし、その上位10%以内に入る論文の本数を比較したものです。

日本は2000年代には世界4位でしたが、昨年発表されたランキングでは過去最低だった前回と同じく13位という結果になりました。一方、中国は10年ほど前から一気に本数を急増させ、いまや世界一をキープしています。「指標のひとつに過ぎない」と見ることもできますが、私はこの結果から日本人は目を逸らすべきではないと考えています。
この国家的なレベルダウンを打ち破るための有効な手立ては、やはり「教育」しかない。なかでも最優先で取り組むべきは、日本経済回復の鍵となる半導体産業を支える人材の育成だと思うのです。
ある試算によれば、九州全体の半導体産業で今後10年間にわたって、年間1000人程度の半導体人材が不足すると見込まれています。これまでも熊本大から毎年約50人の卒業生が半導体産業に就職してきましたが、2027年度に100人まで増やすことを目標にしています。そのために立ち止まっている暇はありません。
では具体的にどのような人材が求められているかというと、半導体の研究開発を担う人材はもちろんですが、同時に、テクノロジーを社会に実装するユーザー産業の分野で活躍できる人材の育成が重要です。
まずは、熊本大の取り組みからお話しさせていただきましょう。
熊本大は旧制第五高等学校などを前身として1949年に発足した、長い歴史を誇る大学です。よくも悪くも伝統を重んじる、おっとりとした校風ですが、それではこれからの時代を生き抜いていくことはできません。
通常、国立大学を改革するには、計画を立てて予算を取って……と、何年もの時間を要しますが、経済産業省や内閣府からの交付金もあったおかげで、熊本大はわずか4年弱で人材育成の環境のセットアップを完了しました。産官学が一体となって本気を出せば、これほどのスピード感で変化を起こせるのです。
75年ぶりの新学部
まず取り掛かったのは、優秀な教員の確保です。教育において最も重要なのは、やはり「人」です。産総研(産業技術総合研究所)出身で半導体の三次元積層実装技術の第一人者をはじめ、他大学や研究機関から優秀な先生方をスカウトしました。半導体関連の教員数は当初10人程度でしたが、現在は42名まで増えました。人手不足の時代に、これだけの人材補強ができたのは異例のことです。
そして2022年春に「半導体研究教育センター」(2023年4月より半導体・デジタル研究教育機構)を設置。産官学の連携強化、半導体研究・人材育成の拠点として始動しました。
翌年春には、学内にある600平方メートルほどの場所を改装して、先端半導体の研究開発に不可欠であるクリーンルームを作りました。清浄度が最も高い「クラス1」のクリーンルームを有しているのは、九州の国立大学では熊本大のみです。
2024年春には、工学部に「半導体デバイス工学課程」を創設しました。これは国内の大学で初となる半導体技術者・研究者の育成に特化した学士課程です。「学科」では一つの学問分野を集中的に学習しますが、この課程では化学・電気・機械といった枠を超えて、半導体の研究開発に必要とされる専門的能力を習得できるのが特徴です。
同じタイミングで立ち上げた学部相当の「情報融合学環」には、「DS半導体コース」があります。このコースではデータサイエンスを駆使して半導体の製造プロセスにおける品質管理や工場機能の最大化などに貢献できる技術者・研究者を育成します。ちなみに熊本大に新たな学部が設置されるのは、1949年の大学発足以来初でした。いかに改革とは無縁の大学だったかお分かりいただけるでしょう。
そして2025年春には、半導体に関する高い専門性を持つ人材を育成する大学院を設置します。もともと熊本はソニーセミコンダクタマニュファクチャリングや東京エレクトロンといった半導体メーカーと縁が深いのですが、それらの企業が求めているのは修士課程以上の人材です。ならば半導体に特化した大学院も作ってしまおうというわけです。
国内外の他大学との交流も活性化しています。2023年には東京大学と連携協定を結び、熊本大のキャンパス内に分室を設置。東大の教員が常駐し、熊本大や地元企業と共同研究を行っています。ありがたいことに、地方大学に東大の分室ができるのも初めてです。TSMCの工場が近くにあり、産学連携を積極的に推し進める本学の環境は、東大にとってもメリットになりうる。そんな地の利も生かして、日本最高峰の大学から多くを学んでいきたいと考えています。
さらに工学部がある黒髪南キャンパスでは、二つの新施設が建設中です。一つは半導体やDXを学ぶ学生や研究者が入居し、新たな研究や学びを実践する場。隣接する施設には、共同研究ラボやクリーンルームを設置し、企業や他大学との共同研究の場とします。この二つの施設が隣接することで産学連携と人材育成の相乗効果が生まれてほしい。そんな狙いがあります。
※本記事の全文(約5000文字)は月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されています(小川久雄「 TSMC工場建設は100年に1度の大チャンス 」)。
(小川 久雄/文藝春秋 2025年4月号)