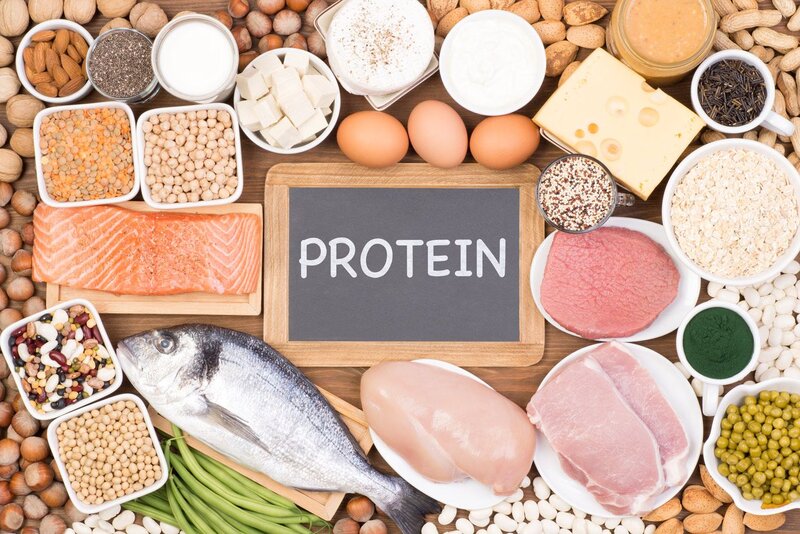「タンパク質といえば肉」では不十分…管理栄養士が「60歳を超えたらコレ」と強く勧める"高タンパクおやつ"
2025年5月18日(日)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/photka
※本稿は、大柳珠美『糖質を“毒”にしない食べ方』(青春出版社)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/photka
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/photka
■食事のたびに肉・魚・卵・大豆製品の摂取を
皮膚や髪や爪、骨や筋肉、内臓、ホルモンや酵素、抗体に至るまで、私たちの体のほとんどはタンパク質でできています。脳も半分はタンパク質、残り半分は脂質です。
これほど重要なタンパク質が不足してしまうと健康を維持することはできませんから、食事のたびに肉・魚・卵・大豆製品などからタンパク質を摂取する必要があるのです。
タンパク質は、たくさんのアミノ酸がつながってできています。アミノ酸は自然界に数百種類も存在していますが、タンパク質を構成するアミノ酸は20種類だけ。
20種類のうち11種類は体のなかで合成できるため「非必須アミノ酸」といい、合成できず食品から摂取しなくてはいけない9種類を「必須アミノ酸」といいます。20種類のアミノ酸のうちひとつでも欠けてしまうとタンパク質を合成することはできません。
食事で摂取したタンパク質はそのまま使われるのではなく、消化酵素によってアミノ酸に分解されます。分解したアミノ酸を、髪や爪、ホルモンや酵素といった目的に合わせてタンパク質に再合成して使用します。
アミノ酸の分解・合成を経てつくられる人体のタンパク質は10万種類といわれています。わずか20種類のアミノ酸でこれほどの種類をつくれるのは、アミノ酸がつながる数、つながるときの形、別の物質との結合など、さまざまなバリエーションがあるからです。
■高齢になるほどタンパク質が必要になる
人間の体は分子レベルで常に分解と合成が行われ、古い細胞と新しい細胞が入れ替わっています。爪や髪が伸びるのは、古い細胞と新しい細胞が入れ替わった結果。1年前の自分と今日の自分は、細胞レベルでは全くの「別人」です。
細胞の入れ替わりが「新陳代謝」であり、生きている限り止まることなく続くので、細胞の材料となるタンパク質は命ある限り必要となるのです。
育ち盛りの子どもやアスリートはたっぷり摂るべきで、高齢になればさほど食べなくてもよいと思われがちですが、若かろうが高齢だろうが、細胞は入れ替わっているのですから、タンパク質が必要であることに変わりはありません。
タンパク質がなければ心筋も維持できず、切れない血管、折れない骨も維持できないのです。脳出血や骨粗鬆症を予防するためにもタンパク質をしっかり食べましょう。
写真=iStock.com/Thai Liang Lim
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Thai Liang Lim
加齢によってタンパク質を分解する消化吸収能力も落ちていき、そもそも食べる量も減っていくのですから意識しないとタンパク質は不足する一方です。60歳からは健康法のひとつとして積極的にタンパク質を食べてください。
慶應義塾大学と川崎市が2017年から共同で行っている「川崎元気高齢者研究」で自立した生活を送る85歳以上の食生活を調査したところ、タンパク質の摂取量が多いほど死亡リスクが低いことがわかりました。
また、タンパク質の摂取量が多い高齢者は、炭水化物の摂取が少ない傾向があったとのことです。元気で長生きのカギは、タンパク質と糖質制限にあるということでしょうか。
■「健康のためには野菜が一番」は大間違い
繰り返しになりますが、タンパク質は高齢になっても必要。
生きている限り必要なのです。
とはいえ、古い栄養教育を受けてきた世代には、まだ誤解があるようです。
①卵はコレステロールが多いから食べない。
②健康のためには野菜が一番。野菜から食べて、余力があればお肉かお魚を食べる。
③肉は胃もたれする(胃腸に負担になる)から食べない。
そんな方はすぐに次のように知識を刷新してください。
①→体のなかでは卵に含まれるよりもはるかに多いコレステロールが合成されています。食べ物でコレステロールを摂れば体内の合成量が減って調整されます。入手しやすくて完全栄養食の卵は1日1個を目安に食べましょう。
②→野菜から先に食べてお腹いっぱいになってしまうとタンパク質の量が減ってしまいます。三角食べのところで述べたように「食事はタンパク質から先に食べる」が60歳からのルールです。
③→お肉が苦手という患者さんは結構いらっしゃいます。無理に食べて食事が憂鬱(ゆううつ)になるより「おいしく食べられるタンパク質」を選んでいきましょう。鶏肉なら大丈夫、豚肉もしゃぶしゃぶなら好きということもあります。また、肉にこだわらずに、魚・卵・大豆製品に目を向けていきましょう。
■タンパク質の推奨量は「達する」ではなく「超える」を目標に
筋肉は20〜30代で最も発達し、以降10年ごとに約8〜10%ずつ低下していきます。最も発達していた頃に比べて、40代では約10%、50代では約20%、そして60代では約30%も減少することになります。
高齢になるほど筋肉がつきにくくなるのは、筋肉の合成を促すアミノ酸が作用しづらくなっているから。20代の頃と同じ量のタンパク質を摂取しても若い頃のように筋肉を合成できないのです。
筋肉量は低下していくのに、新たに筋肉をつけるのも難しくなる一方では、フレイルやサルコペニアへと進むしかありません。こうした高齢者の身体的特徴を改善するために、世界的に食事ガイドラインの見直しが行われ、タンパク質摂取を増やす流れになっています。
厚生労働省からは「日本人の食事摂取基準(2025年版)」でタンパク質摂取量と筋肉量に関して、次のような比較試験の報告がありました。
○70歳以上の高齢男性を対象とした10週間の比較試験
タンパク質推奨量(0.8g/kg/体重/日)を摂取する群→筋肉量低下
タンパク質推奨量の2倍(1.6g/kg/体重/日)を摂取する群→筋肉量を維持
※(1.6g/kg/体重/日)は、「1日あたり体重1kgにつき1.6gのタンパク質を摂る」という意味。
○過体重または肥満の高齢者を対象にした比較試験
タンパク質推奨量(0.8g/kg/体重/日)摂取群
→体重減少、筋肉量も減少
タンパク質推奨量の2倍(1.6g/kg/体重/日)を摂取する群
→体重減少したが、筋肉量の減少は少ない
現時点ではフレイルやサルコペニアの発症予防のために必要なタンパク質量の研究はまだまだ不十分としています。
しかし、比較試験の結果から推奨量(0.8g/kg/体重/日)よりも多め(1.6g/kg/体重/日以上)に摂取すると、フレイルとサルコペニアを予防する可能性があるとしています。
例えば、サバ一切れ80gに含まれるタンパク質は約17.0gです。ただ、17.0gがそっくりそのまま体に入るのかというと、そうとは限りません。
加熱調理でタンパク質量が減ることもあれば、体調によっては消化吸収できないこともあるでしょう。先に食物繊維をたっぷり摂っているとタンパク質の消化が阻害されることもあります。
こうした「タンパク質のロス分」を見越して、タンパク質の推奨量に「達する」ことを目標とするのではなく「超える」ことを目標としましょう。「食品100gあたりのタンパク質含有量」の表を参考にしてください。
出所=『糖質を“毒”にしない食べ方』(青春出版社)
■1日3食に「タンパク質系のおやつ」もプラス
筋肉量が低下すると足元がおぼつかなくなり、立つ・歩く・止まる・階段を昇降するといった日常生活の動作に不安を感じるようになります。不安感から活動量が減ってしまうと運動量も減って、余計に筋肉量が低下していきます。
大柳珠美『糖質を“毒”にしない食べ方』(青春出版社)
こうした悪循環にタンパク質不足が加わると、ますます筋肉が落ちて転倒の危険が高まり、骨折の確率も上がってしまいます。骨を守るクッションの役割である筋肉が薄くなると少しの衝撃でも骨折してしまうのです。
さて、1日の食事の回数についてはさまざまな見解があります。とくに朝食については「1日の活力源。食べたほうがいい」「寝起きに固形食はダメ」と賛成・反対の意見がありますが、60歳からは朝食は抜かないようにしてください。
さらにタンパク質摂取の観点からすると、1日3食に「タンパク質系のおやつ」もプラスするほうが望ましいといえます。小分けにしたほうが確実に消化吸収でき、無駄にならないからです。
タンパク質系のおやつになるのは、ゆで卵、納豆、豆乳、干しただけのスルメ、鮭(さけ)とばなど。「おやつは甘いもの」という思い込みを捨てて、「おやつは補食・タンパク質」を習慣にしましょう。
【まとめ】60歳からの筋肉を守るタンパク質の摂り方
□肉にこだわらず、魚や卵、大豆製品など口に合うものを選ぶ。
□理想は「1日あたり体重1kgにつき1.2gのタンパク質」。
□1日3食におやつをプラスしてタンパク質を小分け補給。
----------
大柳 珠美(おおやなぎ・たまみ)
管理栄養士
2006年より糖質制限理論を学び、都内のクリニックで糖尿病、肥満などの生活習慣病を対象に、糖質の過剰摂取を見直し栄養不足を解消する食事指導を行う。講演、雑誌、インスタグラムなどで、真の栄養学による糖質制限食の情報を発信している。著書に『腸からきれいにヤセる! グルテンフリーレシピ』(青春出版社)などがある。
----------
(管理栄養士 大柳 珠美)