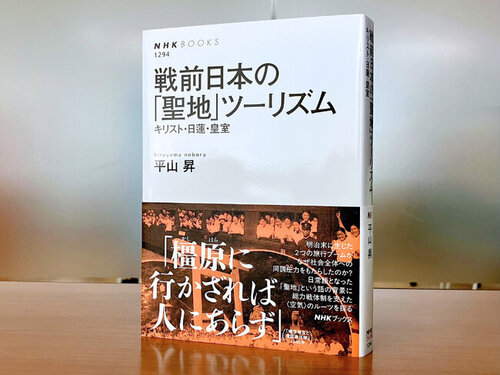こうしてNHKは私を「若い美男をカネで買う尼僧」にした…「べらぼう」に出演した作家が見た"すさまじい作り込み"
2025年5月25日(日)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/egadolfo
■まさか私に『べらぼう』の出演オファーが来るなんて
今年のNHK大河ドラマは江戸時代の吉原を舞台に、後に江戸のメディア王などと呼ばれる蔦重こと蔦谷重三郎を主役に据えた『べらぼう』だ。
写真=iStock.com/egadolfo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/egadolfo
ご存じのように昔の吉原は幕府公認の遊郭であり、今もソープランドが並んでいるため、やっぱり今現在もあの辺りは吉原と呼ばれ続けている。
『べらぼう』放映前は、もちろんソープに関係ない住人もたくさんいるが、だいたいはソープ嬢とその客、店のスタッフが目立つ地帯だった。
江戸の吉原は、貧しさゆえ親に売られて来た女達が過酷な身売りをさせられ、若死にする女も多かったという負の歴史、陰惨な過去があるのも事実だが、江戸の様々な文化が花開いた場であるのもまた確かなのだ。
精鋭揃いの制作陣に、主演の横浜流星さんをはじめ、今の日本の芸能界を代表する綺羅星のごとき役者が勢揃いしている『べらぼう』は、大河ドラマとして異色のようで王道だ。
歴史に造詣深い知識人や、心底から江戸物が好きな濃いマニア達が新聞雑誌やネットなどにも続々と鋭くも深い感想や歴史的考察、わかりやすい解説を載せてくれ、読んでいるだけでにわかに江戸文化に詳しくなれる気にもなった。
本気のファン、ガチ勢の批評家らに圧倒され、あなたも『べらぼう』について何か書いてみますかといわれても、手練れの皆様に圧倒され私の出る幕なし、と腰が引けていた。
それがなんとしたことか、『べらぼう』のプロデューサー様からドラマへの出演依頼をいただき、演者としてドラマに登場してしまったのだ。
■架空の人物・寂連に感じた因縁
蔦重が見出した絵師、作家、援助した文人は多いが、代表的な絵師の一人に喜多川歌麿がいる。歌麿は謎多き人物で、生年や出生地なども諸説あるため、脚本家が想像と創作も入れ造形したところもあるそうだが、ドラマで描かれる姿は、ほぼ史実と思わされる真実味がある。
『べらぼう』の歌麿は、過酷な幼少期を送っていたとなっている。人別、今でいう戸籍がなかったため、成長しても世間から隠れるようにして生きるしかない境遇に置かれ、絵の才能は発揮していたが、男女問わず体を売ってもいた、という設定だ。
その馴染み客の一人に、エロい年増の尼さんがいた。名は、寂蓮。
これは脚本家の創作らしい。というのも、「寂連」で検索すると平安時代から鎌倉時代にかけて僧侶、歌人として生きた俗名は藤原定長、この人しか出てこなかった。『べらぼう』のエロ尼とは、まったくの別人だ。時代も性別も何もかも違う。
そして今は、寂蓮とは岩井志麻子と、検索結果に出てくるようになっている。
しかし、その役を岩井志麻子に振り当てたプロデューサーの慧眼は間違いないとして、これはもしや前世からの因縁であろうかとも震えた。
■「生臭さがすごい」と誉められた
歌麿でなかった頃の歌麿を演じる染谷将太さんの住む長屋を訪ねてきて、一晩を過ごし翌朝、満足げに出ていく。寂蓮なる役名もあったが、出番は一分に満たず、台詞なし。
写真=Wireimage/ゲッティ/共同通信イメージズ
俳優、染谷将太、東京国際映画祭=2017(平成29)年10月25日、東京・六本木 - 写真=Wireimage/ゲッティ/共同通信イメージズ
それでも、なんだか淫猥な雰囲気は醸し出していたようで、いろいろネット記事にされ、話題になれたのはありがたかった。生臭さがすごい、と誉められていた。
最初、私は寂蓮をお金で色事を割り切れる俗な尼と解釈し、若い美男という属性が好きなだけ、快楽をむさぼったらけろっとして帰る、という演技をした。
そこに登場したのが、所作指導の花柳寿楽先生だった。ただ立っているだけで上品な色気を漂わせ、普通に歩いているだけで艶っぽい、という御仁。
「寂蓮は本当は、割り切れてないの。歌麿に、本気で恋をしているの。でも、割り切らなきゃと自分にいい聞かせ、恋なんかしてはいけないとも悲しんでいる」
といった指導を受け、物悲しげに、いや、物欲しげにだったかもしれないが、去り際に未練たっぷりさを隠さず歌麿の手を握ってしまった。
未練、執着、色欲。尼が捨て去らねばならぬものばかりを抱え、自分をみじめだ、みっともないと自覚しつつも、彼も私を好いてくれているかもしれないと期待し悶々するのは、汚れた欲か、あるいは幼い乙女心か。
私は心の中で、「惚れたが悪いか」とつぶやいた。
■素の自分を曝け出してしまった
これは太宰治の『カチカチ山』に出てくる狸のセリフだ。元のお伽噺と違い、ウサギを乙女に、狸を無様なオヤジに変えてある。ウサギに惚れてさんざん痛い目に遭わされ、最後は無残な死を遂げる狸、いや、オヤジが絞り出す台詞。
これはたいてい、「惚れただけでそこまでひどい目に遭わされるなんて」という心情から出ていると解釈されているが、私が心の中だけでつぶやいたその台詞には、そもそも惚れるという気持ちがあること自体に罪悪感を持っている、というのが正しい。
そして、私個人の場合は謙虚さとは遠い卑屈さが男関係のしくじりを増やし、なおかつネタとして昇華できるものになっている、と改めて知る。
おことわりしておくが、俳優の染谷将太さんは色男の名優であるが、岩井が染谷さんに惚れたのではなく、寂蓮が歌麿に惚れているということだ。
なのに私は架空の人物を演じたつもりで、素の自分を曝け出してしまったのだった。
■「元遊女の尼」を思い出した
私が演じた寂連はどんな女性をモデルにしたのだろうか。
蔦重より一回りほど若い、根岸(ねぎし)鎮衛(やすもり)の怪談集『耳嚢(みみぶくろ)』に、元は吉原の遊女だった尼の話が出てくる。
その尼が語るには、自分は金持ちの商人に身請けされたが、夫が死んだ後は世の無常を感じて出家した、とのこと。その尼は和歌が上手く、人相を見て死期を占う力もあったという。
写真=iStock.com/kumikomini
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kumikomini
なんとなく寂連ぽい気もするが、遊女が身請けされたり年季が明けたりした後、出家するのはよくあるとまではいわなくても、特に珍しいことではなかったようだ。
私が演じた寂連、架空の人物だとしても、実在した人だとしても、どのような経緯で尼になったのかを想像してみると、確かに最もありそうなのが『耳嚢』の尼の半生だ。
人相を見て死期を当てられるというのは、吉原で遊女だけでなく数多の客や遊郭の関係者、様々な人を見てきてのデータ蓄積と分析によるものでもあるだろう。
医者や薬屋や、今の警察に当たる奉行所の関係者なども高確率で他人の行く末や死期など当てていた。
■私なら遣り手婆にはならない
さらに私は考えた。『耳嚢』の尼はどんな遊女だったのだろうか。
遊女は、厳しい年季奉公を課せられ、年季が明けるまでに命を落とす女もたくさんいたが、位の高い太夫と呼ばれるほどの遊女となれば、大富豪に身請けされることは『べらぼう』でも描かれている。
そこまでの地位につけなくても、幸運にもそれこそ惚れてくれた男に身請けされ奥様になれたり、年季が明けて無事に故郷に戻れ、後妻になるだの商売するだの、そこそこ平穏な余生を送れた女もいたようだが。
年季が明けても身請けされず、様々な事情で故郷にも戻れず、といった女達の中から、遊郭にとどまって遣り手婆になる、という第二の人生もあった。
遣り手婆とは、遊女の監視や管理も行い、客との仲介、紹介なども務めた年配女性だ。遊女にとっては、ときに客より厄介、客よりも気を遣う怖い存在であった。
だが遣り手婆になる女は、帰る場所がない、引き受けてくれる男がいないという事情があるとしても、そこまで遊郭や吉原に嫌な思い出や揉め事もなく、当人の中では居心地がまあまあ良い場所だったのだ。でなきゃ、何が何でも吉原を去ろうとする。管理能力やコミュニケーション力も必要だから、行き場のない女がみな遣り手婆を希望しても、残れなかった女も多くいたと想像する。
■私の前世は本当に「寂蓮」だったのか
ふと、私が江戸時代の遊女であったらと想像する。無事に年季が明けることとなっても引き受ける男もいない、戻る実家もないとなれば、遣り手婆として残るか、出家して尼になるかとなれば、後者を選ぶ気がする。
まず、若い女達を厳しく監督するなんて重圧、重責すぎる。ヘタレなので女達に舐められ、逆に虐められるはずだ。
尼になれば、いろんにものがリセットされるし、徳がなくてもとりあえず僧形でいればなんとなく尊敬もしてもらえると期待する。しかし中身は俗なまんまで、まさに寂蓮のごとく貧しい若い美男を買いに行き、酒も飲んで博打もやりそうだ。
ところが妙に口の達者な詐欺師気質のところもあり、人相を見られるだの霊感が強いだの、そういう商法に走り、過去の様々な経験やしくじりをおもしろおかしく、時には涙を誘う苦労話に作り替えて信者やファンを増やし……。
と、ここまで書いてきて、私はもしや本当に前世はそんな遊女あがりの尼だったのではなかろうかと思えてきた。『べらぼう』の寂蓮は、実在した前世の私か。
1分に満たない、台詞もない役柄であったが、ここまで考えさせ想像させ創作の原動力もかき立ててくださった『べらぼう』には、感謝しかない。
----------
岩井 志麻子(いわい・しまこ)
作家
1964年、岡山生まれ。少女小説家としてデビュー後、1999(平成11)年「ぼっけえ、きょうてえ」で日本ホラー小説大賞受賞。翌年、作品集『ぼっけえ、きょうてえ』で山本周五郎賞受賞。2002年『チャイ・コイ』で婦人公論文芸賞、『自由戀愛』で島清恋愛文学賞を受賞。近著に『でえれえ、やっちもねえ』(角川ホラー文庫)がある。
----------
(作家 岩井 志麻子)