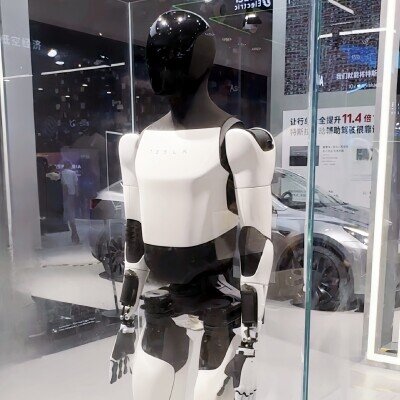イーロン・マスクが提唱する高速輸送システム「ハイパーループ・アルファ」は、本当に実現可能なのか?
2024年8月14日(水)4時0分 JBpress
人類史において、新たなテクノロジーの登場が人々の生活を大きく様変わりさせた例は枚挙にいとまがない。しかし「発明(インベンション)」と「イノベーション」は、必ずしも輝かしい成功ばかりではなかった。本連載では『Invention and Innovation 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』(バ−ツラフ・シュミル著、栗木さつき訳/河出書房新社)から、内容の一部を抜粋・再編集。技術革新史研究の世界的権威である著者が、失敗の歴史から得られる教訓や未来へのビジョンを語る。
第2回は、2013年にテスラCEOのイーロン・マスクが発表した「ハイパーループ・アルファ」構想を紹介、200年も前から提案され続けてきた高速輸送システムの実現性について考える。
<連載ラインアップ>
■第1回 技術開発の“後発組”中国は、なぜ巨大イノベーションの波を起こすことができたのか?
■第2回 イーロン・マスクが提唱する高速輸送システム「ハイパーループ・アルファ」は、本当に実現可能なのか?(本稿)
■第3回 「火星地球化計画」「脳とAIの融合」などの“おとぎ話”が、なぜ大真面目に取り上げられるのか
■第4回 自転車、電磁波、電気システム…現代文明の基盤を築いた“空前絶後の10年間”、世界を変えた1880年代とは?(8月28日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
2013年8月12日、テスラ社CEOのイーロン・マスクが超高速輸送システム「ハイパーループ・アルファ」構想を発表した。冒頭で、このアイデアが生まれるまでの経緯を説明するにあたり、彼は尋ねた。「まったく新しい輸送の手法があるでしょうか?」と。
それは航空機、電車、自動車、船舶に次ぐ第五の手法となり、もっと安全で、もっと速く、もっとコストが安く、もっと便利でありながら、天候に左右されず、自己動力供給を持続し、地震に強く、沿線の住民に悪影響を及ぼさないものになるだろうと、彼は説明した。
そしてマスクは「こうした特徴をもつ輸送システムとして、これまでさまざまなアイデアが提案されてきた。はるか昔のロバート・ゴダードから、近年のランド研究所〔訳注:アメリカのシンクタンク〕やET3社〔訳注:アメリカの輸送システムのスタートアップ〕によるここ数十年の提案にいたるまで多々あるものの、残念ながら、そのすべてがうまくいっていない」と述べている。
彼の二番目の言及に関していえば、まさにそのとおりだ。そして一番目の発言は、このアイデアがどのようにして生まれたかをよく表現している。つまり、超高速輸送システムに関する理論的な提案が初めてなされてから長い時間が流れたにもかかわらず、近い将来、このアイデアを商用化できるという謳(うた)い文句には懐疑的な態度を示し、慎重を期すべきなのだ。
まず指摘したいのは、マスクがこの輸送システムに見当違いの呼び名をつけたことだ。そもそも「ループ」とは、曲げたり交差させたりできる曲線が生みだす形を指す。となれば、「ハイパー」(「超」、「過度」の意)ループとは、いったいどんな形を指すのだろう?
すなわち「ハイパーループ」という名称は、それ自体が不正確であり、大きな誤解を与えかねない。マスクの構想では、カプセル(ポッド)のなかに乗客を密封して、チューブ内を猛スピードで運ぶ。チューブ内では空気がクッションの役割を果たすのでポッドが浮く(磁気浮上を利用した設計もある)。
まっすぐな金属製チューブを高架またはトンネル内部でつなぎ、チューブ内部の圧力は非常に低い(真空に近い)。磁力の反発を推力として利用し、直線状のチューブの上部に装着されたソーラーパネルで発電し動力を得る(ほかの方法で動力を得る設計もある)。
マスクはこのように、第五の輸送手段としてハイパーループを分類しているのだが、その分類自体が誤解を与えかねない。さらに、この輸送システムは複数の要素で構成されているのだが、その特徴が設計によっててんでんばらばらなのだ。
目に見えるインフラは「チューブ」で、ごく少数の乗客しか運べない「ポッド」という呼び名の車両が収まる程度の直径しかない。このチューブは地上の高架か地下トンネルに(もっともコストが安い例ではプレハブ工法で)設置される。
ポッドの大きさは乗客の人数によって異なり(ハイパーループ・アルファ構想では最大乗車定員28人、ほかの設計では4〜100人とさまざま)、リクライニングチェアでくつろげるものから仰向けになって横になれるものまで、快適性もさまざまだ。
スピードも亜音速から音速(時速1235キロメートル)に迫る速度まであり、それだけの高速を達成するには完全な真空状態(真空状態にするだけでも高いコストがかかるうえ、スピードの維持にも費用がかかる)にするか、きわめて低圧(真空状態よりも維持はしやすいが、管理がむずかしい)でのみ可能になる。
ハイパーループ・アルファのチューブ内の気圧は100パスカルに減圧されていて、海抜0メートルでの標準大気圧の1000分の1未満だ。ポッドは空気をクッション代わりにして滑るか、磁気浮上する。最新のシステムでは、先進的なリニアモーターを利用するという。
200年以上前からあるコンセプト
だが歴史を振り返れば、こうしたアイデアに目新しいところがまったくないことがわかる。「第五の輸送手段」という基本コンセプトは200年以上前からあり、以来、さまざまな特許が出願され、いくつか詳細な提案がなされ、なかには実際に部品が製造され、模型や実物大模型がつくられたものもあった。
それでも、真空チューブや低圧チューブを利用した超高速輸送システム(輸送するのは乗客のみであれ、貨物のみであれ、その両方であれ)は一例も完成していないし、稼働もしていない。設計の基本的な構成要素をすべて揃えたシステムでの短距離の試験さえおこなわれていないのだ。
ハイパーループの構成要素のなかでもっとも古くからあるのはチューブだが、低圧を利用するという考え方もまた2世紀以上前から存在していた。意外なことに、画期的な第五の輸送手段なるもののおもな特徴は、リヴァプール&マンチェスター鉄道よりも古くから取り沙汰されていた。
つまり、1830年に蒸気機関車が初めて大都市を結び、乗客と貨物を運ぶようになる前から、チューブを利用した輸送手段というアイデアがあったのだ。
イギリスの時計職人で発明家のジョージ・メドハーストは、チューブ内での高速移動を明確に提案した先駆者で、1810年に『空気で手紙や貨物を確実かつ迅速に運ぶ新たな手法』という小冊子を出版し、チューブ内の空気圧(蒸気機関で発生させる)で前進させる小さな中空容器で手紙を送る方法を提案し、同じ原理を使えば(相応に圧力を上げれば)、運河や馬車と比べて最低10倍のスピードで物品を運べると述べた。
1812年、彼はこの案をもっと詳細に説明した小冊子『空気の力と速度によって、断面積30平方フィートのチューブを利用した鉄路で物品と乗客を迅速に運ぶ計画に関する計算、所見、実用性の証明、その効果と利点』を出版し、1827年(彼の没年)には、さらに長いタイトルの小冊子『全国に輸送網を拡大可能で、馬などの役畜の力を借りずに、現在の移動手段の4分の1以下の費用で、時速60マイルであらゆる物品、家畜、乗客を運ぶ斬新な内陸輸送手段』を出版した。
彼が出版した小冊子はどれも広く知られることはなかったが、1825年になると、チューブ・真空状態・高速を利用して、ロンドンーエディンバラ間の600キロメートル以上の距離を5分未満(そう、なんと単位は「時間」ではなく「分」)で走破するという大胆きわまる提案を、イギリス国民は目にすることになった。
新たに創業されたロンドン・エディンバラ真空トンネル会社の出資者たちは、「計画を慎重に吟味した結果」をエディンバラ・スター紙に発表し、このプロジェクトは「ロンドンーエディンバラ間に金属製のトンネルまたはチューブを建設し、2都市間で、また途中にある町にも物品や乗客を運ぶことを目的とし、社は1株100ポンドで20万株の株式を発行し、英貨2000万ポンドの資本金を獲得する」と述べた。
このプロジェクトでは、2本並んで設置するトンネル(チューブ)に付随して、2マイルごとにボイラーを設置し、そこから発生した蒸気で真空状態をつくりだす。
出発した列車の最後部車両のうしろで真空状態の封印が解かれると、なだれこんできた空気によって車両がチューブの奥へと突入していき、「非常に頑丈で気密性の高いスライドドアが用いられた車両が、摩擦を和らげるために設置された複数の小さな円筒状のローラーの上を走る」のだ。
チューブの直径はわずか4フィート(約1.2メートル)しかないので、列車は貨物だけを運び、乗客はチューブ上部に固定されたレールの上を走る鉄道車両に乗る。鉄道車両はチューブ内の貨物列車と強力な磁石で連結していて、猛スピードで走る貨物列車が客車を引っ張り、800キロメートル近い距離を5分以内で走破するという。
ロンドン機械学報は「社会の労働者階級」に科学的知識を広めるために刊行された新たな定期刊行物だったが、「投資の対象となる前に、荒唐無稽な計画を嘲笑する」べく、警告を述べた学報を増刷した。
まさに慧眼(けいがん)! 当時のイギリスでは蒸気を利用した産業が推進されていたため、とんでもない主張、投資詐欺、技術的な奇跡が起こるというニセの予言などが次から次へと登場しており、当時有名だった風刺漫画家は、真空チューブを利用した旅行ができるという初期の謳い文句を風刺するチャンスを逃さなかった。
ウィリアム・ヒース(1794〜1840年)は当初「肖像画家・従軍画家」と自称していたが、1820年代には風刺的な手彩色銅版画を発表するようになり、当時の政治情勢を揶揄したり、人間の愚行を風刺したりするようになった。
1829年、ロンドンのトーマス・マクレーンがヒースの手彩色銅版画を集めて『知性の行進。世界はどう進歩していくのか』(March of Intellect. Lord how this world improves as we grow older)を出版した。
あるページには、南アフリカのケープタウンとインドのベンガルをつなぐ吊り橋、速度(VELOCITY)という呼称の蒸気機関で走る馬の形の4輪車、4個の気球に吊るされた台に銃などの武器をもつ乗客を乗せて飛ぶ台、イギリスからオーストラリアへ移送する囚人を乗せた大きな翼のあるトビウオなど、近未来的で珍妙な機械類のイラストがぎっしりと描かれている。
この銅版画でもっとも目を引くのは「グランド真空チューブ社」なる企業の革新的な発想によって、ロンドン東部のグリニッジからインドのベンガルまで直接乗客を運ぶ、継ぎ目のない巨大金属製チューブだ。
ヒースがイギリスとインドを結ぶ大陸間輸送システムをカラーで描いた頃には、真空に関する理解が進んでいて、チューブ内で空前のスピードをだすには真空が最適であることがわかっていた。
しかし、その程度の理解では、どんな素材が必要なのかはわからなかった。1820年代には、鋳鉄(ちゅうてつ)は豊富に製造されていたが、張力の高い鋼鉄を安価に大量生産することはできず(1856年に特許を取得したベッセマー転炉の発明後にようやく大量生産が可能になった)、数百キロメートルも続くチューブ内に非常に低い気圧をつくりだし、その状態を維持する信頼の置ける手段はなかったし、真空状態で密封された車両に人を安全に乗せる方法も見つかっていなかった。
<連載ラインアップ>
■第1回 技術開発の“後発組”中国は、なぜ巨大イノベーションの波を起こすことができたのか?
■第2回 イーロン・マスクが提唱する高速輸送システム「ハイパーループ・アルファ」は、本当に実現可能なのか?(本稿)
■第3回 「火星地球化計画」「脳とAIの融合」などの“おとぎ話”が、なぜ大真面目に取り上げられるのか
■第4回 自転車、電磁波、電気システム…現代文明の基盤を築いた“空前絶後の10年間”、世界を変えた1880年代とは?(8月28日公開)
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:バーツラフ シュミル,栗木 さつき