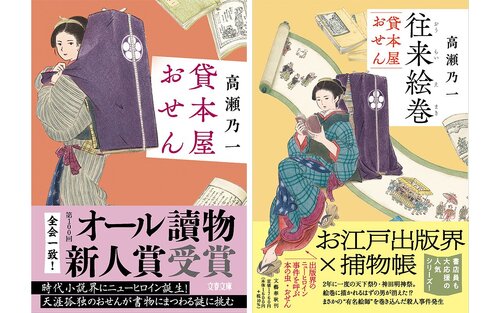“立ち読み”はどこで始まった? 本屋でも古本屋でもなく…「話は江戸時代までさかのぼる」立ち読みが発生した“意外な場所”とは
2025年5月20日(火)12時10分 文春オンライン
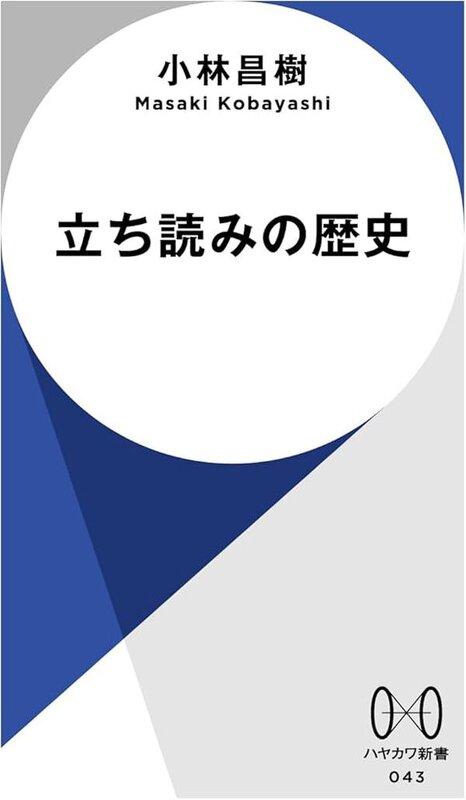
立ち読み。この当たり前にある行為、いつどのように始まったのか、実は明らかになっていなかった。
「調べようと思う人もいなかったのでしょう。正確には一つだけ、昭和40年の業界誌の無署名記事にそのことについて言及しているものがあるのですが、『古今東西の文献を漁っても残念ながらわからない〜』と」
このたび『立ち読みの歴史』を上梓した小林昌樹さん。国立国会図書館で15年にわたりレファレンスを担当し、その経験を活かした『調べる技術』はベストセラーに。本書は、そんな小林さんの面目躍如とも言うべき一冊だ。埋もれていた文献にあたり、立ち読みの歴史、現在のような本や読書のあり方がいかにして成立したかにまで迫る。
「立ち読みについての文献を総ざらいしながら、一方で、万引きについても調べていました。かねてより立ち読みは万引きとセットで発生したのではと考えていたのです。ある物事を探していてなかなか文献が出ないとき、同時に出てくるはずの別の物事も探す『同時に出るもの探索法』という手法があります。また、紙の文献に拘らず、ネットを合わせて駆使するのも有効ですね。今回も、大正期の万引き犯の懲らしめ方についてのSNS投稿をきっかけに、立ち読みの起源について証言している文献を見つけることができました」
明治から昭和前期まで活躍し、「滑稽新聞」などの刊行物で知られた特異なジャーナリスト、宮武外骨。彼が書いた大正7年の記事に、その証言はあった。
「宮武の記事に『明治30年頃までは、雑誌販売店で立読みして居ると〜』という部分がありました。この証言から、明治20年代には立ち読みが発生し、それは雑誌販売店で行われていた、とわかります。ここで言う雑誌販売店とは、戦前一般に『雑誌屋』と呼ばれていた業種のこと。本屋とは店舗構造から異なるもので、戦後は完全に忘れ去られていた存在でした」
話は江戸時代まで遡る。当時の本屋は現在と違い、注文に応じて店の奥から本を出してくる座売りをし、売っている本も学問書などのエリート向けのものだった。対して、絵草紙屋という存在があった。庶民のための浮世絵や草双紙(大衆的な絵入り小説本)などを売り、それらは軒先に吊るされ、面陳列されていた。
「明治に入り、新聞や雑誌が登場。雑誌に関して言えば、明治20年代に普及しはじめ、それは絵草紙屋が時代に合わせて業種変更した雑誌屋で売られていました。その頃まだ本屋は座売りをしており、陳列販売が始まったのは明治20年代半ばで大正初期に全国化。立ち読みは本屋ではなく、雑誌屋で発生したのです」
その後、本屋でも雑誌は置かれるようになり、立ち読み癖を身につけていた庶民を引き入れることになる——といった謎解きは、ぜひ本書を手に取って楽しんでほしい。その過程で検討される、別の疑問や考察もとても興味深い。立ち読みという言葉が初めて登場する文献は、勝海舟の談話? 洋行知識人いわく、海外には立ち読みはない?
はたまた、立ち読みという習俗が、国民レベルで黙読の訓練になっていた?
「江戸時代は、何かを読むときは音読が普通でした。それが明治になって、黙読が普通になっていて、その移行の内実もよくわかっていないのです。立ち読みは音読ではできませんし、仮説とはいえ、もしかしたら当たっているんじゃないかと(笑)。ただ、立ち読みの歴史が、そうやって読者の歴史と密接に関わっているのは間違いないのです」
こばやしまさき/1967年、東京都生まれ。図書館情報学を研究するかたわら近代出版研究所を主宰し、年刊誌『近代出版研究』編集長を務める。国立国会図書館で15年にわたりレファレンス業務に従事、その経験を活かした『調べる技術』が3万部を超えるヒット作となる。その他の著書に『もっと調べる技術』など。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年5月22日号)