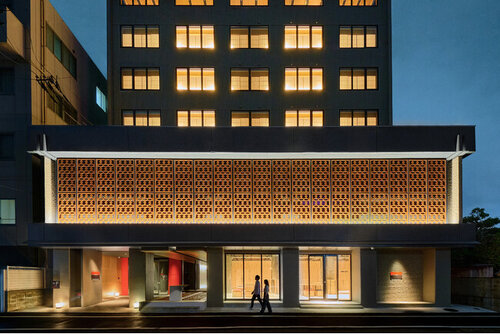坂本龍馬の陰に隠れた近藤長次郎、知られざる偉人の生い立ち、勝海舟との出会い、土佐藩を脱藩し薩摩藩士へ
2025年1月29日(水)6時0分 JBpress
(町田 明広:歴史学者)
坂本龍馬の陰に隠れた近藤長次郎
幕末維新期には、たくさんの人物が現れ、歴史を動かしたことによって、その名を歴史に刻みこんでいる。一方で、その人物群をつぶさに観察してみると、実は過大評価されている人物も少なくない。
また、その人物の存在によって、過小評価されたり、存在そのものが知られていない人物も少なからずいることは、多くの読者にも共感していただけるのではなかろうか。むしろ、そうした不当に評価された人物の方が、圧倒的に多いのかも知れない。今回扱う、近藤長次郎もその典型であろう。
誰もが知っている幕末史のヒーローとして、坂本龍馬の存在がある。確かに、龍馬の存在なくして幕末維新史は回転しなかったかも知れない。その龍馬の最大の功績として語られるのは、薩長同盟であることは論をまたないであろう。
確かに、龍馬の存在はなくてはならないものであるが、龍馬の功績として語られてきた活動の中で、実は近藤長次郎の功績が龍馬のそれとして、今まで語られてきたことは意外と知られていない。
今回は6回にわたって、知られざる偉人の典型的な存在として、近藤長次郎を取り上げ、中でも近藤と薩長同盟の関わりについて、特に龍馬の活動と対比しながら明らかにし、かつ、薩長融和が水泡に帰す可能性も秘めた知られざる大事件、ユニオン号事件の実相に迫ってみたい。
近藤長次郎の生い立ち
天保9年(1838)3月7日、近藤は水通町(高知市上町)で生まれた。生家は「大里屋」(餅菓子商)であり、「饅頭屋長次郎」というのは、後世になって付けられた通称であるが、その由来はここにあるのだ。
水通町は商人や職人が多数居住しており、近藤は経済感覚やビジネスのノウハウをこの地で学修した。近藤は幼年期から学問好きで、家業の手伝いをしながら読書に勤しみ、また、叔父の門田兼五郎に師事した。坂本龍馬の生家にも非常に近く、もしかしたら、幼少期から交流があったのかも知れない。
安政2年(1855)、近藤は大里屋から近い築屋敷にあった河田小龍の塾に入門した。河田の本業は画家であり、海外事情に精通していた。ジョン万次郎の聞き取りから、『漂巽紀畧』を執筆したのは、この河田である。その後、近藤は神田村(高知市神田)の岩崎弥太郎に師事した。後に岩崎は、三菱財閥の創始者となったことは周知の事実である。
近藤の江戸行きと勝海舟との出会い
安政6年(1859)頃、藩の重役である由比猪内に従って、近藤は江戸に遊学し、安積艮斎の塾に入門した。しかし、同年、父母がともに死去したため、急遽帰藩せざるを得なかった。学問の道をあきらめきれなかった近藤は、家督を妹に継がせて、翌万延元年(1860)に再び江戸に遊学し、洋学を手塚玄海、砲術を高島秋帆のもとで学修したのだ。
文久2(1862)年、勝海舟の塾に入門した。恐らく、坂本龍馬も同年の10から12月頃に入門したと考えられる。もしかしたら、近藤の手引きがあったかも知れない。近藤は勝の下で、そのずば抜けた才能を開花させた。
ところで、近藤の優秀さに関する情報は各地に広まっており、諸藩からスカウトしたいとの申し出が、勝の許に相次ぐ事態となった。極めて特殊な事態が起こったのだ。こうした事実を知った土佐藩は、近藤を放ってはおかなかった。
土佐藩は、近藤に名字・帯刀(武士の特権)を許可し、藩士に昇格させた。近藤は、その飛び抜けた学問の才と勝門下である事実から、土佐藩からも認められ、晴れて士分に取り立てられた。近藤の面目躍如たるや、さすがである。
文久3年(1863)1月、勝とともに上京し、6月下旬に神戸の地に新設された勝私塾に入門を果たした。元治元年(1864)5月、神戸海軍操練所が開設された。しかし、入所資格は関西在住の旗本・御家人の子弟および四国・九州・中国辺の諸家家来に限定されたため、近藤は「勝阿波守家来」で聴講するレベルに止まった。なお、龍馬が塾頭という通説は、この条件では当然のことながら、成立しない。
同年6月5日、池田屋事件が勃発し、勝門下の望月亀弥太が討死し、そのことなどから勝に嫌疑がかかり、失脚してしまった。近藤を含む土佐藩士グループは、行き場を失い脱藩せざるを得なかった。勝は、薩摩藩に彼らの援助を要請し、薩摩藩も軍艦への乗組員の不足に難渋していたことも相まって、近藤らは薩摩藩に取り込まれることとなったのだ。
薩摩藩士・近藤長次郎(上杉宗次郎)の誕生
薩摩藩は元治元年1月から安行丸(前年9月に購入)の運行を開始し、同年中に平運丸・胡蝶丸・翔鳳丸・乾行丸・豊瑞丸を長崎で購入した。しかし、軍艦は手に入れたものの、薩英戦争や長崎丸事件などによって、乗組員の不足解消にはほど遠い状態にあった。そこで、 白羽の矢は近藤を含む勝門下である土佐藩脱藩浪士グループに立ったのだ。
薩摩藩大坂屋敷に潜伏したメンバーは、近藤を始め、高松太郎・菅野覚兵衛・新宮馬之助・白峯駿馬・黒木小太郎・陸奥宗光であった。加えて、幕府士官と争って出奔していた、幕船翔鶴丸の船舶器械取扱者・火炊水夫(機関員・ボイラー員等)らと推測される。
慶応元年(1865)2月1日、近藤らは安行丸で鹿児島に向かい、18日から大乗院坊中威光院が居所となった。龍馬は江戸に行っていたため、同年5月1日、小松帯刀・西郷隆盛とともに胡蝶丸で鹿児島にむかった。龍馬の居所は不明だが、近藤らと同居の可能性も十分にあり得る。なお、この段階で龍馬と近藤は薩摩藩士となり、その他は小松帯刀のお抱え(家臣)として陪臣となったと考える。
次回は、薩摩藩に仕官する直前に近藤長次郎が小松帯刀に提出し、島津久光の閲覧に供した上書を取り上げてみたい。その内容を詳しく紹介し、そこで展開される征韓論やアジア征服などを視野に入れた、その広大な未来攘夷構想を紐解き、近藤の先見性に触れてみたい。
筆者:町田 明広