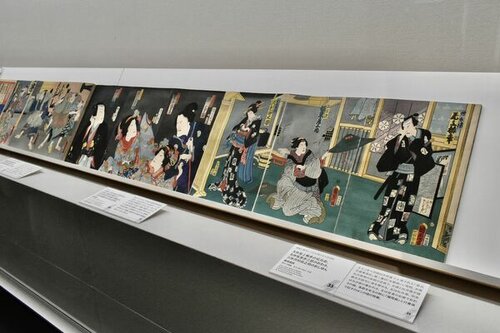土佐藩士・武市半平太、幕末前半の政治史に大きな足跡を残した尊王志士の生涯
2025年4月23日(水)6時0分 JBpress
(町田 明広:歴史学者)
武市半平太は正当な評価を受けているのか?
幕末土佐藩における人物を挙げるとすると、読者の皆さんは誰を思い浮かべるだろうか。やはり、坂本龍馬がダントツの一番人気であることは想像に難くない。その他の人物として、例えば、山内容堂、板垣退助、後藤象二郎、中岡慎太郎、中浜万次郎といった名前が挙がりそうだが、その二番手のグループの中に武市半平太も入るのではなかろうか。
武市は、文久3年9月(1863年11月)には投獄されており、慶応元年閏5月(1865年7月)に切腹している。つまり、武市は元治・慶応期(1864〜67)の政治史(政局)には関わっていないため、印象が薄れるのかも知れない。しかし、幕末政局が最も激しく動いた文久期(1861〜63)において、主役級の役割を演じたのが武市半平太であることは間違いない。
2025年は、その武市の没後160年にあたる節目の年である。今回は、幕末前半の政治史に大きな足跡を残した武市半平太を7回シリーズで取り上げ、その壮絶な人生の実相に迫り、武市という尊王志士の歴史的意義について考えてみたい。
武市の生い立ち
文政12年(1829)9月27日、武市半平太は土佐国吹井(ふけい)村(現在の高知市仁井田)の白札(功績によって上士扱いされた郷士、3人扶持・切米7石)である武市半右衛門の長男として誕生した。幼名は鹿衛、諱は小楯、号は瑞山または茗澗、変名は柳川左門と称した。
武市家は、長宗我部氏の一領具足(兵農分離前の武装農民や地侍を対象に編成・運用された、半農半兵の兵士および組織の呼称)に属し、関ヶ原合戦(1600)の後に浪人したが、享保11年(1726)に山内家の家臣・郷士となり、文政5年(1822)には白札格に昇任したのだ。
叔母は国学者・鹿持(かもち)雅澄と結婚しており、その鹿持は私塾・古義軒を開設し、武市を始め吉村寅太郎・大石弥太郎・佐々木高行ら多くの人材を輩出した。武市も鹿持から甚大な影響を受けたが、両者間の交流には不分明な点が多い。
武市の幼年期の学修状況は詳らかにできないが、勉強熱心であったと伝えられている。12歳頃から剣術を習い始め、高知城下・新町の千頭伝四郎(足軽身分)の道場で小野派一刀流の修行をした。武市の天賦の才が、急速に開花した時期である。
武市の剣術・砲術修行
天保14年(1843)、武市は14歳の時、父の眼疾から藩の仕事に出仕し始めた。弘化2年(1845)9月、16歳の時に正式に父の代役勤務を申請している。なお、同年1月、西洋流砲術の修得のため、徳弘孝蔵の塾に入門したが、坂本龍馬の同塾入門より10年も前であった。
嘉永2年(1849)、20歳の時、8月に母が、また翌9月に父も逝去した。80歳近い祖母の面倒を見るため服喪期間にもかかわらず、同年12月に郷士・島村源次郎の長女・富子と結婚した。このことによって、武市は藩の仕事および武術の修行に専心することが可能となったのだ。
武市の師匠である千頭伝四郎が病死すると、麻田勘七(大身・馬廻の次男)に師事した。道場は城に近い鷹匠町に立地し、門人の多くも身分の高い藩士であった。しかし、武市はそんなことは意に介さずに剣に打ち込み、嘉永3年(1850)、21歳で初伝に昇進した。
その後、武市は富子の実家(高知城下の東の外れ、新町の田渕)の近くに屋敷を持ち、庭に道場を設置して弟子に教授し始めた。引っ越しによって、武市には時間に余裕ができ、一層剣に磨きをかけることができたのだ。そして、麻田道場でも瞬く間に頭角を現し、嘉永5年(1852)には早くも中伝に昇進、安政元年(1854)には免許皆伝に至った。
江戸出府と剣術修行
嘉永6年(1853)10月21日、武市半平太は目付方から西日本出張の沙汰を受けた。目的は、「臨時御用筋」(内容は不分明ながら、剣術修行か)であった。しかし、僅か10日ほどで取り消しとなった。詳細は不明ながら、土佐藩主山内容堂はペリー来航を踏まえ、藩政改革を志向しており、海防や大砲製造などの要員として武市に期待していた可能性を指摘したい。
安政元年(1854)11月5日、安政の南海地震が発生し、埋立地である新町はすべての家屋が全壊する大被害を被った。本町に仮住まい後、武市は自宅を再建し、4畳と3畳が1間ずつの小さな家にもかかわらず、立派な道場を建築したのだ。
午前は槍、午後は剣の稽古時間とし、富子の叔父島村寿之助が槍を、武市が剣を教授した。島村の指導中は、武市は麻田道場で指導と稽古に勤しんだ。剣の名声が増して、藩政府から田野・赤岡の剣術指南に任命された。いずれも郡奉行所があり、郷士や庄屋とその子弟ら(中岡慎太郎など)が多数修行しており、武市にとって遣り甲斐のある仕事となったのだ。
安政3年(1856)8月、武市は藩命により江戸へ出立した。9月下旬には、武市は土佐藩築地中屋敷内で坂本龍馬・大石弥太郎と3人で同宿を開始した。浅蜊河岸の鏡新明智(きょうしんめいち)流・桃井春蔵の道場・士学館に岡田以蔵とともに入門し、直ぐに頭角を現した。
入門した頃、塾生の多くは酒や女に溺れており、「安方(あほう)塾之者」(島村源次郎宛書簡、安政4年〈1857〉8月17日)と蔑視されていた。武市は堪り兼ねて、塾内の弊風を糺さねば師の名を汚すと直訴したため、桃井は武市を塾頭に指名した。武市は早速塾の規則を定め、乱れきった人の出入りを厳格化し、違反した門人には厳しく対処したため、塾内の空気が劇的に変化したのだ。
一方で、師範代・山本琢磨(土佐郷士)が内弟子・田那村作八(備中松山藩)と一緒に時計を奪って質に入れ、藩目付方に追われたため、武市は逃亡を幇助することもしている。ここでは、武市の郷党への甘さが目に付こう。
安政4年9月、武市は鏡新明智流の免許皆伝となった。同月、祖母(万延元年〈1860〉死去)の急病で帰藩した。10月には、「一生之中格段弐人扶持」の沙汰をいただき、安政6年(1859)、白札・郷士以下の剣術世話方を拝命した。翌万延元年8月15日頃、久松喜代馬・島村外内・岡田以蔵を伴って、武者修行に出発した。丸亀藩から始め、備中松山藩、広島藩、徳山藩、長州藩、12月に飫肥(おび)藩をもって終了とした。このころの武市は、剣術家としてのみ名を馳せていた。しかし、いよいよ武市も、激動の政局に翻弄されることになるのだ。
次回は、将軍継嗣問題と条約勅許問題を軸とした、当時の中央政局の状況に触れながら、武市による土佐勤王党の結成の経緯やその実態、武市の政治的動向などについて、詳しく迫ってみたい。
筆者:町田 明広