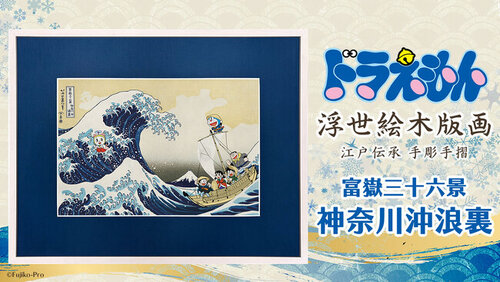五世尾上菊五郎を筆頭に、幕末明治を彩った人気役者が勢揃い!刷りたてのように色鮮やかな、静嘉堂の浮世絵に注目
2025年2月4日(火)6時0分 JBpress
(ライター、構成作家:川岸 徹)
美人画と並ぶ浮世絵の二大主要ジャンル・役者絵。初期浮世絵から錦絵時代を経て明治まで、役者絵の歴史をたどる展覧会「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く—秘蔵の浮世絵初公開!」が静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)で開幕した。
実は浮世絵も多い静嘉堂コレクション
三菱二代社長・岩崎彌之助(1851-1908)とその嗣子で三菱四代社長の小彌太(1879-1945)によって築かれた静嘉堂コレクション。東洋古美術6500件以上、古典籍20万冊という圧倒的なスケールを誇り、絵画に絞って見ると仏画や絵巻、水墨画、琳派、南画が主要ジャンルとして知られている。
そんな構成から静嘉堂コレクションは「文化人や知識人好みの格式ある作品揃い」との印象を受けるが、意外なことに庶民のアート「浮世絵」も含まれている。その数がまた、半端ではない。江戸期の「1枚もの」の浮世絵は500〜600点。幕末明治期の大判錦絵を表裏に貼り合わせてつなげた「錦絵帖」は全69冊。その内容は、美人画19冊、源氏絵13冊、風景画11冊、東錦絵(役者絵、合筆もの、その他)21冊、明治版画5冊。静嘉堂の蔵はいったいどこまで深いのだろう。
摺りたてのような鮮烈な色彩
さて、これまでなかなか鑑賞する機会がなかった静嘉堂の浮世絵コレクションだが、近年の展覧会で徐々にお披露目されつつある。以前、「静嘉堂文庫の古典籍 第二回 歌川国貞展—美人画を中心に」にて美人画が特集されたが、今回の「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く—秘蔵の浮世絵初公開!」は役者絵がテーマ。出品作の大部分が初公開となる。
静嘉堂文庫美術館の安村敏信館長はこう話す。「浮世絵の一番の保存方法は人に見せないこと。一度展覧会に出すと、会期中から退色が始まってしまう。だから、本当は見せたくない(笑)。今回の出品作は初公開作品が多く、しかも錦絵帖の形で保管されていたものが中心。刷りたてのような鮮やかさがあり、これぞ錦絵と感じていただけると思います」
その言葉通り、本展最大の見どころは今摺ったばかりのような錦絵の数々。会場に入ると、赤、青、黄、緑、紫といった華やかな色彩が、発色まばゆく目に飛び込んでくる。なんともヴィヴィッドで刺激的。錦絵とは多版多色刷りの木版画のことで、錦(高級織物)のように美しいことから錦絵と呼ばれるようになった。日の光に当たらず、大切にしまい込まれていた錦絵から、その言葉の由来を実感することができる。
彌之助夫人の早苗が収集した?
展示されている役者絵は、幕末から明治にかけての名だたる絵師によるもの。歌川国貞(三代豊国)、歌川国芳、落合芳幾、二代歌川国貞、そして本展のタイトルにもうたわれている豊原国周。描かれた役者も多彩な顔触れで、三世中村歌右衛門、五世坂東彦三郎、五世尾上菊五郎、四世中村芝翫……と、幕末明治の人気者がずらり。
これらの役者絵は岩崎彌之助・小彌太によって築かれた静嘉堂コレクションに収められているもの。だが実際に役者絵を集め、錦絵帖として編集したのは「彌之助の妻、早苗夫人ではないか」と本展の担当学芸員・吉田恵理氏は指摘する。
早苗夫人は徳川慶喜に大政奉還を説き、維新後は新政府の要職に就いた後藤象二郎の長女。明治7年に岩崎彌之助に嫁いでいる。フランス語を学ぶなど西洋に強い関心を示す一方で、和歌や長唄を習得。観劇に足繁く通うなど、彌之助同様に趣味が広い。
「錦絵帖には編集した人の個性が表れます。静嘉堂の錦絵帖は同じ舞台に出演した役者を絵師が異なるのに隣同士に並べたり、五世尾上菊五郎が描かれた作品を巻末にまとめたり、そんな独特な偏りがあります。もしかしたら早苗夫人は菊五郎贔屓で、観劇の記念に錦絵を購入していたのではないかと想像したくなります」(吉田恵理氏)
必見!「梅幸百種」
確かに、展示されている役者絵には五世尾上菊五郎を題材にしたものが多い。特に役者・五世尾上菊五郎×絵師・豊原国周×版元・具足屋(福田熊次郎)の組み合わせによる錦絵が目に付く。絶大な人気を誇る役者と、「役者絵の国周」「明治の写楽」と呼ばれるなど名声をほしいままにした絵師と、技術力に定評のある版元。3者の力が結集した錦絵はリアルな躍動感にあふれ、芝居を生で見ているかのようにハラハラと胸が高鳴ってくる。早苗夫人が夢中で集めたとしても不思議はない。
この3者による集大成が「梅幸百種(ばいこうひゃくしゅ)」。五世尾上菊五郎の舞台姿とコマ絵に俳句などを描いた大判100枚の揃物で、明治26〜27年に2年間をかけて制作された。早苗夫人が愛玩した静嘉堂所蔵の「梅幸百種」は目録付きで、一冊の錦絵帖の表裏に100図すべてが貼り込まれている。
この「梅幸百種」、見れば見るほど細かな技巧に驚かされる。着物の布地の表現には空摺(墨線の部分を、凸状ではなく凹状に彫り込んだ版を作り、絵の具はのせずに強い圧力をかけて摺る)、布目摺(色版となる部分に布を張りつけ、その上から圧力をかけて布目の効果を出す)、きめだし(深く彫り込んだ版の上に色摺りが終わった版画をのせ、圧力をかけて画面に凹凸を出す)といった“技”を駆使。人物が浮かび上がってくるような立体感が醸し出されている。
まさに役者絵の最高峰。「梅幸百種」をとくとご覧あれ。
「豊原国周生誕190年 歌舞伎を描く—秘蔵の浮世絵初公開!」
会期:開催中〜2025年3月23日(日)前期:〜2月24日(月・振休) 後期:2月26日(水)〜3月23日(水)
会場:静嘉堂@丸の内
開館時間:10:00〜17:00(毎週土曜日は〜18:00、2月19日(水)、3月19日(水)、21日(金)は〜20:00)※入館は閉館の30分前まで
休館日:月曜日、2月25日(火)(2月10日(月)、24日(月・振休)は開館)
お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
https://www.seikado.or.jp/
筆者:川岸 徹