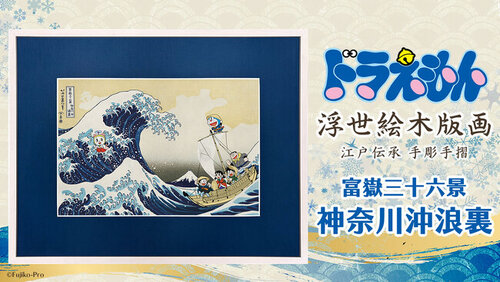「おれが写楽、歌麿をみつけた!」 5/2からグンゼ博物苑「集蔵」にて、蔦屋重三郎の浮世絵展開催
2025年4月24日(木)12時17分 PR TIMES
この浮世絵展では、西陣織・内閣総理大臣賞受賞・とみや織物八代目冨家伊兵衛の繊細な技術、西陣美術織で織り上げた写楽、歌麿、北斎らの浮世絵を再現した作品が一堂に会します。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/23550/687/23550-687-3bd4382f72bf4614924dda133aed0176-3277x1623.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]
■蔦屋重三郎の浮世絵展について
[表: https://prtimes.jp/data/corp/23550/table/687_1_dd25ab6e751c8a1829e241b96a73ddaf.jpg ]
■西陣美術織について
西陣美術織は、一般的な西陣織より細い十数色の糸を組み合わせて織り上げられています。明治初期創業のとみや織物(京都市)が、西陣織の技術を応用して生み出しました。少し離れて見ると写真と見間違える精緻さで、立体感もあり、見る人の心をひきつけます。作品に使われるよこ糸の数は和服の帯の倍以上で、浮世絵の微妙な陰影を表現するため多数の絹糸が使われています。そのため、織り方は難しく、機械織では対応できず、一本一本職人の手で織られています。
■展示作品の紹介
[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/23550/687/23550-687-25594273c2e19c082d47c5391bb553e6-366x590.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]西陣美術織「写楽 市川富右衛門の蟹坂藤太・佐野川市松の祇園町白人おなよ」
写楽の大首絵とは、人物の上半身を大きく描き、その表情を強調した浮世絵の一形式です。この作品は、元禄14年に実際に起こった「花菖蒲文禄曽我:幼い兄弟が父と兄の仇を28年を経て伊勢国亀山城下で討ち取った亀山の仇討ち」をモチーフに脚色されたものです。
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/23550/687/23550-687-83a54b9bbaea918cefb0460ade69b005-401x594.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]西陣美術織「歌麿 寛政三美人」
歌麿の見立てとは、遊郭の女性や花魁といった華やかな女性だけでなく、市井の町娘たちの姿も生き生きと描いた繊細で品のある描線が特徴的で、女性の様々な仕草や表情の美しさを華麗に表現したものです。寛政三美人は、芸者の富本豊雛、茶屋の看板娘であった難波屋のおきた、高島屋のおひさをモデルにしたものです。