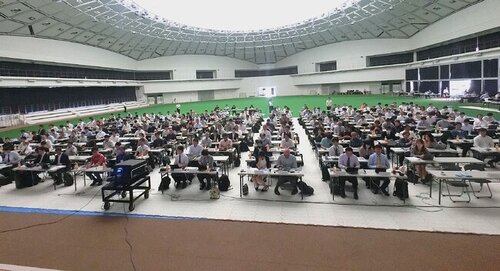『徹子の部屋』の特集に故・鈴木登紀子さん登場。「お料理を伝えることで、次の世代へ幸せをつないでいけたら」
2025年3月27日(木)11時0分 婦人公論.jp

料理研究家の鈴木登紀子さん。2018年撮影(撮影:藤澤靖子)
故・鈴木登紀子さんが、3月27日の『徹子の部屋』「匠の味〜愛すべき料理人たち」の特集に登場。料理へのこだわりや得意料理を紹介する。鈴木さんが自身の戦争体験と食への思いをまとめた『婦人公論』2018年10月9日号の記事を再配信します。
********
NHKの番組「きょうの料理」に長年出演し、「ばぁば」の愛称で親しまれた料理研究家、鈴木登紀子さんが12月28日、肝細胞がんのため亡くなりました。享年96。料理ページにはもちろんのこと、インタビューも何度か応えてくださった鈴木さん。弊誌で最後にご登場いただいたのは、2018年、「私と戦争」というテーマでした。「食べることは生きること」と語るに至った体験とはーー詩人・エッセイストの堤江実さんが取材した記事を再掲します。(撮影:藤澤靖子)
* * * * * * *
「ばぁば」の愛称で親しまれる料理研究家、鈴木登紀子さん。青森県八戸市で育ち、女子挺身隊として飛行場の庶務課に配属された鈴木さんには、大都会とはまた違った戦争体験がありました。
****
料理上手で 評判だった母
生まれは、1924年11月14日、青森県の八戸です。海があって、山があって、畑があって、食べ物の豊富なのんびりした田舎町でした。それが今、93歳(取材当時)。なんだか自分でも信じられませんけどね。
父は長野の人で、篆刻家。お酒が好きで、うちではいつも晩酌2時間。そのうえ、呑ん兵衛仲間のお客様がしょっちゅうあり、母は毎晩、酒の肴を用意するのに一所懸命だったわ。大酒飲みだった父は腎臓を悪くして、私が小学1年生の頃に亡くなりました。
母は、岩手県一戸町の宿屋の娘。読み書きは達者じゃなかったけれど、お料理、お裁縫、なんでもよくできたのです。女学校のない時代、母の妹が1期生でしたが、今考えますと、母のほうが「女大学」の感がありました。
四季折々のものを本当においしく食べさせてくれて、近所でも料理上手と評判だったの。母が黙って何か考えている時は、決まってお料理のこと。家族一同、いつでも一番大事だったのは、おいしいものを食べることでした。
私は、兄が3人、姉が2人の6人きょうだいの末っ子です。今思えば、平和で幸せで、楽しいことばかりの子ども時代でした。
戦争のことを初めて現実的に感じたのは、37年の日中戦争の前あたりだったかしら。大人たちが新聞を読んで、戦争になるんじゃないかと話す声が聞こえてきて。でもその前年にはベルリンオリンピックがあり、みんなで真夜中にラジオの前に集まって、「前畑がんばれ!」と応援しました。田舎ですから、ドイツがどんなところか、オリンピックがどんなものかも想像がつかない。でも、日本中が大興奮で応援しましたね。
日中戦争では、上の兄2人は年齢が上だったので徴兵はされませんでしたけど、3番目の兄だけは満洲に派兵されました。無事に帰ってきて、「夜中に銃を持って見張りに立ったら凍えるほど寒かった」「満洲で食べたフーヨーハイ(蟹玉)がおいしかった」と話してくれました。うちは明けても暮れても食べ物のことばかり。
あの時代のことで一番印象に残っているのは、33年、今の天皇陛下(取材当時。現在は上皇陛下)のお誕生。あの時はもう、のろしは上がるわ提灯行列は出るわで、町中でお祝いムード。まだまだ平和でのんびりした時代だったわね。
女学校を卒業し、飛行場の庶務課に
飛行機の材料になるアルミの国内生産を目指して、八戸に日東化学工業ができたのが1939年。飛行場も造られて、そこでは200人ぐらいの若い女性が「女子挺身隊」として、板金加工や整備などに従事していました。私は女学校を卒業して、そこで庶務課に配属されました。簡単なお仕事でしたが、何かしら楽しい日々でした。
最初に赴任してきた方は陸軍大学出の大佐で、カイゼル髭をたくわえて頭はツルツル。いつも怒って頭から湯気を出していたから、「タコ」というあだ名でした。この方がなぜか私を可愛がってくれましてね。お茶をお給仕しに部屋に入ると、「おいでおいで」と手招きして、引き出しから貴重品のチョコレートやキャラメルなんかを出してくれるの。こんなものがまだあったんだわ、と思ったわ。
朝、山の上の職場まではバスで通いましたが、それが木炭バス。ガソリンは飛行機のほうに使わなきゃならないので、バスは木炭を燃やして動かすんですよ。これが山のふもとまで来ると坂を上がれなくて、ウンウンうなって止まってしまう。乗客が降りて、後ろからバスを押したりもしましたが、しまいには山道を歩いてのぼることになりました。
雪がちらついていたある日、バスを降りて歩いているとタコさんが車で通りかかって。お国のためなら、いくらでもガソリンはあったの。私の横でパッと車を停めると、「おう、乗れ、乗れ」と助手席に乗せてくれまして。道行く兵隊さんたちが私に向かって敬礼するものですから、助手席で恐縮しておりました。
戦闘機が不時着すると、タコさんのところに報告があるの。私は庶務にいましたもので、「海軍不時着!ちょっとのぞきに行かなくては」と。海軍の方って制服のマントが短くて大体素敵なんですけれど、「今日はおイモさんだったわね」なんて(笑)。戦争のつらい思い出より、年頃だったから面白いことがたくさんあって。あまり悲愴感はなかったわね。
宮様へのお給仕で 大騒ぎに
ある時、賀陽宮さま(恒憲王。香淳皇后のいとこにあたる)が飛行場の視察に見えるというので、さあ、大変。200人くらいの女の子のなかから、私がお給仕役に選ばれました。
姉の御召(上等な絹織物)をほどいて、新しくモンペと上着に仕立て直してもらいました。お草履もない時代、母がお酒の一升瓶とお金を持って行って、南部表の草履を用意してくれました。にわか仕込みでお作法のお稽古もしましたよ。なにしろ私、お作法は「丙」でしたからね。
賀陽宮さまは、風格のある素晴らしいお方でした。熱いタオルに、オーデコロンをほんのりとふりかけてお出しして。「歳はいくつ?」「どんなお仕事?」といろいろお言葉があって、「19歳でございます」「庶務におります」とお答えしました。その後、すかさず副官から、「何とお言葉を賜った?」と聞かれましたのよ。
いただいた御下賜品の菊の御紋章のついた煙草を、母は「わが家の誉れ」と神棚と仏様に上げて、もう大変でした。ご近所に一本ずつ配って、みんながありがたがって。でもあれ、最高にまずいんですってね。(笑)

「毎日夕方になると、どこの家からも大根を切るトントントンという音が一斉に聞こえるの。お米が足りませんでしたから、大根を混ぜて炊くのです」
粟とか稗を混ぜてかさを増やす
八戸でも、さすがに戦争の最後の頃は、食べるものが不足しました。食料切符とか衣料切符とか、すべて配給制。でも、切符はあってもモノはないのよ。つまり、空手形。
毎日夕方になると、どこの家からも大根を切るトントントンという音が一斉に聞こえるの。お米が足りませんでしたから、大根を混ぜて炊くのです。でも大根飯はまだ良いほう。粟とか稗を混ぜてかさを増やすのよ。戦争になってからはどこの家庭でもそう。手の甲や足の裏が黄色くなるくらい、かぼちゃを食べました。
都会と違って、細々とでもなにか食べるものはありましたから、母はいろいろ工夫して、おいしいものを作っていました。すいとんも、ただ小麦粉を練るだけじゃないの。よくよく練って寝かしたものを手で引っ張って、摘む。「ひっつみ」っていうのよ。それは鰯の焼き干しのおだしでいただくの。とてもおいしかったのよ。
終戦間近になると、新聞には良いことばっかり書いてあって、とにかく頑張りましょうというばかり。「欲しがりません勝つまでは」という標語ができて、みんな我慢しましたよ。広島と長崎に原爆が落とされた時は、何か恐ろしいものだっていうことは聞きましたが、原爆が何かはわかりませんでした。
なんだか変だと思ったのは、夜、飛行機がビラをまくのよ。紙がキラキラ光りながら落ちてきて、それに「降伏しなさい」と書いてあった。今思えば、敵は余裕だったのね。それで兄たちも、「ああ、もう日本はだめなんだな」と言っていたのは覚えています。
次の世代へ 幸せをつないで
戦後、1947年に結婚して、東京での生活が始まりました。母は、「おめさんには過ぎたお人じゃ」と言いました。
夫と上京した時は、モンペをはいて、食べ物いっぱいのリュックを背負って、すし詰めの汽車に乗りました。私は洗面所の窓から押し込まれて、女性3人、上野までの14時間そこで立ちっぱなし。途中で一時停車した日暮里の駅で、別の車両に乗っていた夫がホームに降りて、私の様子を見に来てくれました。窓の外で夫はニコニコしていましたが、私は「日の暮れる里」という駅名を見たらさみしくなってしまって。うちに帰りたくてべそをかいたものです。
夫は戦争でフィリピンに行っていました。もともと戦争は大嫌い、軍人とか権力っていうのが大嫌いだったのに、主計(経理)の試験に受かって軍隊に行ったのです。戦地ではとてもとても苦しい目にあったようですが、時折、「大変な思いをしたよ」と言うくらいで、私も根掘り葉掘り聞くことはできませんでした。
日本の兵隊たちは食べるものなんて何もなくて、夜になって攻撃がやむと、夜中に食料をあさりに出たらしいわ。アメリカ兵はその点では恵まれていたって。ひとりひとりに乾パン、お肉やスープの缶詰、食後のお菓子や煙草までが入った「レーション」という糧食が支給されていた、と。
夫は敗戦とともにアメリカの捕虜になりましたが、通訳を命じられて、45年の12月には日本に帰国できました。私が彼から聞いた戦争の話はそれくらい。話すのも嫌なほど、ひどい経験をしたということではないでしょうか。
私は今でも、「母から受け継いだお料理を伝えることで、次の世代へ幸せをつないでいけたら」と、お料理教室やテレビのお仕事を続けております。それも平和だからこそ。食べることは生きることだと、いつも感謝しているのです。