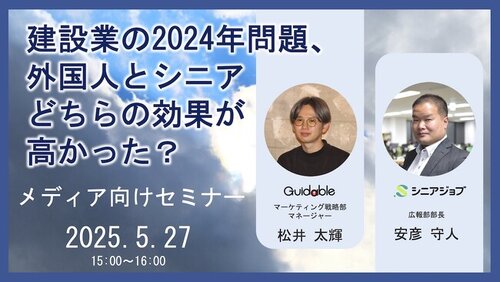「長々と言い訳する」は逆効果。失敗をチャンスに変えられる〈頭がいい人〉の言い訳とは
2025年4月20日(日)12時30分 婦人公論.jp

長い言い訳(写真提供:Photo AC)
「忙しい自慢をしてしまう」「自分の正義を押し付ける」「教えたがる」「長々と言い訳をする」など、認めてもらいたいという人ならだれでもある欲求が高じると、頭が悪い人に見えてしまう危険性があります。ベストセラー『頭がいい人、悪い人の話し方』の著者・樋口裕一さんが、考察するそのような言動をとる理由、そして知的習慣が身につくヒントを綴った著書『頭のいい人が人前でやらないこと』より、一部を抜粋して紹介します。
* * * * * * *
長々と言い訳をする
現代人にとって、言い訳そのものは決して否定するべきものではない。人間は必ず失敗する。
人間であるからには失敗するように宿命づけられている。失敗は防ぐことはできない。では失敗したらどうするか。言うまでもなく、上手に言い訳をすることだ。
失敗したとき、どう言い訳するかによって、失敗が二度と立ち上がれないほどの痛手となる場合もある。ともあれ許してもらえることもある。
逆に上手に言い訳することによって新たなチャンスを得ることもある。たとえば、大事な会合に遅刻したとする。
そんなとき、「もっと大事な用を済ませていたので遅くなった」、「危険が起こりそうなので、それを食い止めるために必死の努力をしていたために遅れた」、「この日のために万全の準備をしていたために遅れた」などという方向で言い訳をするのが正攻法だ。
ところが、説得力のない言い訳をして、あきれさせる人が多い。
最も多いのは、「寝坊しました」「忘れていました」という言い訳だ。もちろん、そのような言い訳は怠慢や意欲のなさを示すが、一度や二度であれば、特に愚かと言われるわけではない。
あまりにありふれた理由であるだけに、特に問題にはされないだろう。だが、それが続くと、愚かな遅刻常習犯という烙印を押されることになる。
中には、もっと愚かな言い訳をする人がいる。多いのは、長々と言い訳をする人だ。
「携帯電話の置き場所がわからなくなって探しているうちに電車1本のがしてしまいました」で済むところを、「昨日の夜、接待でA社の方と飲んだんですが、どうしても先方の申し出を断れなくて、いつもよりたくさん飲んでしまって、帰ったのが遅くて、しかも酔っていたもので……」などと長々と説明してしまう。
見苦しい言い訳
言い訳が長いと、たとえ事実であったとしてもウソくさくなってしまって、説得力をなくす。詳しく説明すればするほど意味がなくなる典型的な例だ。
そのほか、その場逃れのありそうもない話をする人もいる。「ひかれそうになったお年寄りを助けていたので、遅くなりました」「外国人が道に迷って困っている様子だったので、案内をしていました」などなど。
これについても一度ならそんなこともあるだろうが、二度三度とテレビドラマの中の1シーンのような話をされると、ウソつきの愚か者とみなされることになる。
もっと見苦しいのは、予防線を張るタイプの言い訳だ。このタイプの人はしばらく前まで威勢のいいことを言っていたのに直前になるとトーンダウンする。
難しい仕事の指示をされると、「ほかの仕事がたくさんあって十分に準備する時間が取れませんので、可能かどうかわかりませんが」などと言い出す。
要するに、「もし失敗しても、能力が劣っているわけではありません。たまたまできなかっただけなのです」と言おうとしているわけだ。
これについても、事あるごとにこのタイプの言い訳を使っていると、周囲に愚かさが伝わってしまう。

『頭のいい人が人前でやらないこと』(著:樋口裕一/青春出版社)
不平不満が多い
世の中には満足できることなどあるはずがない。幸せな気持ちになったとしても、それは一時期のことでしかありえない。
なぜなら幸せが日常化すると、今度はその幸せな状態が通常になって、それを幸せに思わなくなる。
もっと幸せでないと幸せを感じられない。だが、次々と幸せ度を増すことなど不可能なので、新たな不満が募る。つまり、人間は常に不満を持つようにつくられている。
それに、完全なものを思い浮かべ、その理想に対してのマイナスを強く意識して不満を持つからこそ、人間は理想を追い求め、進歩を続けてきた。不満を持つからこそ、努力をしてきた。
不満こそが人間の人間たる要素だ。不平不満を口にする人は、ストレス解消を行っているのだろう。いやいやながら実行するとストレスがたまる。だから、それを口にする。「ああ、いやだいやだ」と口にすることによってはけ口ができる。
「うちの会社、ひどいよなあ。俺をこんな目に遭わせるんだ」と口に出すことで同僚と傷口をなめ合える。集団でストレス解消ができる。そもそも昭和の人々が会社帰りに飲み屋に寄ったのも、そのような愚痴を言い合ってストレス解消をするためだった。
しかし、そうであればあるだけ、周囲の人を不愉快にさせる。たまたま同じように感じている人が数人集まって不満を言い合うのであれば、愉快な気分になるかもしれないが、同じように思っていない人が交じっていると、空気が悪くなる。
周囲の人々は他人の不平不満を聞くと、どうしても士気が下がる。言っている本人はストレス解消になっているのだろうが、その分、周囲の人にストレスがたまる。
せっかくほかの人は心の底に不平を感じていても、それを考えないようにして意欲を高めていたのだ。それなのに、それを口にされると、せっかく食い止めていた不満が噴出してくる。

不平不満が多い人(写真提供:Photo AC)
不平不満を語るのはマイナスの自己満足
それに、不平不満を語る人は、その不満を行動に移さない。それが周囲の人間には不甲斐なく見える。
そもそも行動に移す気がないからこそ、不平不満を語ろうとする。あまりに非生産的であって、何も意味がない。マイナスの自己満足でしかない。
行動に移す気のないマイナス思考は聞いて気持ちの良いものではない。「だったら、もうやめたらどうなの」「不満があるんなら、堂々と正式の場でしっかりと議論して、改革のために行動したらどうなんだ」と言いたくなってくる。
不平不満を口にして、周囲を不愉快にさせる行為自体、きわめて愚かといえるだろうが、それだけではない。このタイプの人は、自分の愚かさをさらけ出している。
不平や不満というのは、基本的に自分の境遇、自分のしている事柄について納得がいかない、理想からほど遠いという気持ちの表れだ。
言い換えれば、自分はこの境遇にはふさわしくない、自分はもっと恵まれた状況にいるべき人間なのだという主張でもある。
つまり、不平不満は裏返しの自己主張でしかない。卑劣な陰口という形で「本当は、私はこんな立場にいるべき人間ではない。もっとよい地位を与えてほしい」という叫びにほかならない。
不平不満には、そのような陰にこもった必死さがある。そのような必死な欲望を表に出して語っていることが滑稽なのだ。
※本稿は『頭のいい人が人前でやらないこと』(青春出版社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 「寝る間もないんですよ」は頭が悪く見えるので要注意。悪気がないのに忙しい自慢してしまう人の意外な心理
- 61歳の妻に先立たれたことで「死」と向き合って…ロシュフーコー、三木清、夏目漱石。古今東西の賢人は死と生をどうとらえてきたのか
- なぜ10歳年下の妻は少しも死に動じないまま<あっぱれな最期>を迎えることができたのか…夏目漱石の名句から見出したそのヒントとは
- 手術が成功するも癌が再発…医者から「緩和ケアしか残されていない」と告げられた妻が言った「私あんまり頭がよくなくてよかった」の真意とは
- 61歳で先に逝った妻。生命力がなくなる中でも嘆くことなく明るい声で語り、笑って…ベストセラー作家の夫を驚かせた<あっぱれな最期>