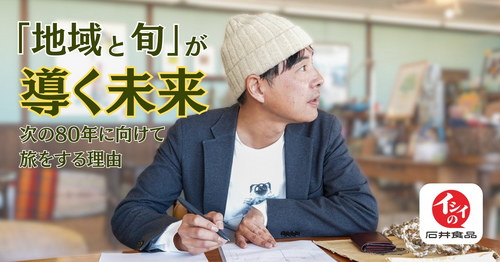「社長室はキャンピングカー」譲り受けた幼稚園の送迎バスを改造して全国へ…! モンベル創業者が乗っていたキャンピングカーがすごかった
2025年5月10日(土)8時0分 文春オンライン
〈 「心が押しつぶされそうになりました」62歳で大腸がんを宣告されたモンベル創業者が気づいた“恐怖心”の受け入れ方 〉から続く
モンベル創業者、辰野勇氏はかつて自作のキャンピングカーを乗り回し、“移動式社長室”で仕事をしていた時期があるという。いったいどんな車なのか。
辰野氏の著書『 自然に生きる 不要なものは何ひとつ持たない 』(角川新書)の一部を抜粋し、当時のエピソードを紹介する。(全2回の2回目/ 最初 から読む)
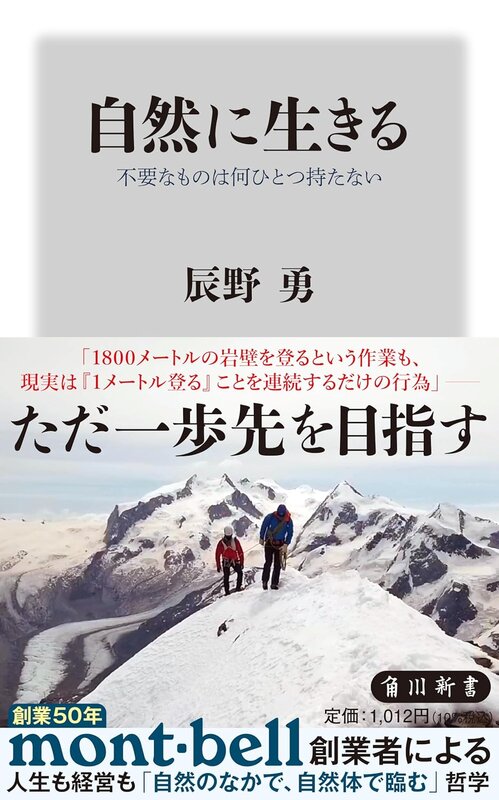
◆◆◆
それは「できない」ではなく、「やらない」という選択
人は、できないことを「他人のせい」や「環境のせい」にしがちです。
「仕事が忙しいから旅に行きたくても、行けない」「まとまった休みが取れないから登山がしたくても、できない」……。でも、「本当にやりたい」のであれば、多少の障害があったとしても、「やる」のではないでしょうか。
私は以前、キャンピングカーで日本全国を旅しながら、仕事を続けたことがあります。
「社長室はキャンピングカー」というわけです(笑)。
しかも私のキャンピングカーは、幼稚園の送迎バスでした。
そうなったきっかけは、今から30年ほど前、幼稚園の園長先生が集まる会合に招かれて、八王子(東京都)にある幼稚園で講演をしたことです。
質疑応答の時間に園長先生から、「辰野さんはこれまでさまざまな冒険をされていますが、これからやってみたいことはありますか?」という質問をいただきました。
ふと窓の外に視線をやると、幼稚園の送迎バスが目に入ったので、「あそこに止めてあるようなバスが手に入ったら、キャンピングカーに改造して、リタイアしたあとに日本中を回ってみたいですね(笑)」と答えました。するとその園長先生が、「辰野さん、あのバスでよかったら差し上げましょうか? 最近では園児が減ってきてバスが余っているので、中古でよければ使ってください」と言ってくださったのです。
またとない申し出でしたので、モンベルのテントと交換していただきました(園長先生自ら、バスを大阪まで運んでくださいました)。
改造に必要な資材をすべて自分で調達して、当時高校生の息子と一緒に、キャンピングカーを自作しました。座席を取り払い、トイレとキッチンを設置して、ベッドになるテーブルをつくり、屋根の上にはソーラーパネルを装備。
リタイアを待つまでもなく、自作のキャンピングカーに乗って、妻と2人で九州から北海道まで全国を、数回に分けて1年ほどかけてまわりました。
風の吹くまま、気の向くまま。川を見つけたらカヌーで下ってみる。山があれば登山靴を履いて登ってみる。自由でした。バスは窓が広いので、360度、景色を楽しむことができます。冠雪の阿蘇山の外輪山の圧倒的な美しさは、今でも脳裏に焼き付いています。
旅をしながらでも経営ができる
当時は携帯電話が市場に出たばかり。軍用の衛星通信機を彷彿させる重い携帯電話とファックスを搭載して、移動式社長室をつくりました。モンベル・アメリカの社長から電話がかかってきて、阿蘇山を眺めながら、アメリカの市場について意見を交わしたこともあります。当時は、今ほど通信インフラは整っていません。それでも、場所や時間にとらわれない「テレワーク」や「リモートワーク」が可能だったのです。行く先々のアウトドアショップを訪ねたり、即席の講演会を催したりすることもありました。
私の友人のイヴォン・シュイナード(アウトドアウエアメーカー「パタゴニア」の創業者)から、以前、「私も辰野も、MBAだよな(笑)」と言われたことがあります。
MBAといっても、経営学修士(Master of Business Administration)の学位の意味ではありません。イヴォンは、「マネジメント・バイ・アブセンス(Management By Absence)」、つまり「欠席しながらマネジメントをする」「どこにいても経営はできる」という意味に置き換えて、捩ったのでした。私はこのキャンピングカーで、「旅をしながらでも経営ができる」ことを身をもって経験しました。
園長先生が「自由に旅ができない」ほんとうの理由
旅の最後に、バスを譲ってくれた幼稚園に立ち寄りました。「自由に旅ができてうらやましい」と園長先生がうらやむので、私が「やってみたらどうですか?」と勧めると、園長先生は、こうおっしゃいました。
「いや、うちは小さな幼稚園で教員の数も少ないので、休めないんですよ。だからできません」
園長先生が「できない」のは、教員の数が足りないからだけではありません。
本気で、バスの旅を「うらやましい」と思っていたのではなく、旅に出ること以上に、幼稚園で子どもたちが元気に遊ぶ姿を見ていることを選んでいたのだと私は思いました。
園長先生にとって、自分が安心できる居心地のいい場所は幼稚園だったに違いありません。園長先生は、「できない」のではなく、「バス旅に行かない」という選択をしていたのです。「やりたいけど、できない」ではなく、「今は幼稚園にいることを選択して、行きません」と言ってほしいと思いました。
私にも仕事はあるし、家族もいる。
物理的なハードルや、犠牲にしたものもある。それでもキャンピングカーを社長室にして旅をしてみたいという思いが優っただけのことです。
「できない」と考えるか、「やらない」と考えるかでは、人生の幸福感が変わります。
ただ一歩先を目指す
以前、ある進学校の理事長から、「勉強ができる生徒の共通点」についてうかがったことがありました。名門大学に入学できる生徒には、「集中力と持続力と判断力」の3つの力が養われているというのです。
「3つの力は人間が生きていく上で最も大切な『生きる力』であり、その力を身につける方法は無限にあります。勉強でも趣味でもスポーツでも、その道を真剣に求めることで、その力が養われる」とおっしゃっていました。
学生時代の私は、お世辞にも勉強ができたとは言い難く、むしろ落ちこぼれ的な存在で、卒業も危ぶまれたほどです。
それでも私には、人並みの「集中力と持続力と判断力」が備わっていると自負しています。それは、登山やカヤックを実践したなかで身につけることができたのだと思います。
アイガー北壁(ヨーロッパ・アルプス三大北壁のひとつ。1969年、筆者が当時の世界最年少記録〈21歳〉・最短登攀記録〈21時間〉で登攀)を登攀する前夜、緊張と不安で寝つけませんでした。「生きて帰れないかもしれない」……。
ですが、登攀の日を迎え、岩に取り付いた瞬間に、心が無になりました。ただやるべき次の瞬間を目指す。ただ一歩先を目指す。その感覚は、「禅の境地」に近いものなのかもしれません。
1800メートルの岩壁を登るという作業は、想像を超えた果てしないことだと思われます。ですが、現実は「1メートル登る」ことを連続するだけの行為なのです。
(辰野 勇/Webオリジナル(外部転載))
関連記事(外部サイト)
- 【最初から読む】「心が押しつぶされそうになりました」62歳で大腸がんを宣告されたモンベル創業者が気づいた“恐怖心”の受け入れ方
- 「登校中に左足から大量出血して、靴の中が血だらけに…」中1で“難病”発覚→19歳で左足を失った“義足モデル”(26)が語る、切断手術を決意した理由
- 骨転移の進行、輸血頻度の高まり…がん闘病の過程で浮上した「自宅での看取り」という選択肢《「余命半年宣告」から5カ月》
- 「生存期間が数カ月短くなっても…」余命半年宣告の医療ジャーナリストが「骨転移治療ラジウム223」を断った理由
- 「また元気になられたら」と番組出演を中止され…「“がん患者は仕事するな”と排除された気持ちに」梅宮アンナ(52)が語る、がん治療と仕事のリアル