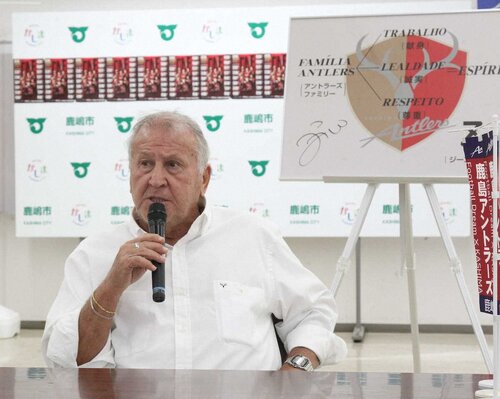多動な人はなぜ集中力が続かないのか?『スマホ脳』著者が解説。「注意散漫」「刺激に敏感」現代社会では重荷になる特徴も、昔は生きるために必要なことだった
2025年5月14日(水)12時30分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
集中力を保つことが苦手、整理や計画が苦手などの特徴がある発達障害の一種<注意欠如・多動症(ADHD)>。累計120万部を突破した『スマホ脳』シリーズの著者であり、精神科医のアンデシュ・ハンセンさんは「誰でも多かれ少なかれADHDの傾向がある」と話します。そこで今回は、アンデシュさんによる書籍『多動脳:ADHDの真実』から、一部を抜粋してご紹介します。
* * * * * * *
この世界は退屈すぎる!
人間も種の1つにすぎない──かなり特殊な種ではあるが。自分たちの本質がいかにして進化を遂げたかを解せずして自己を理解することはできない。
──マット・リドレー(生物学者、作家)『赤の女王──性とヒトの進化』
自分をやる気にさせるもの、それは何だろうか。恋愛? お金? それとも周りの人からの承認? 安心? 未知の経験かもしれないし、切り立った崖をスキーで滑り降りたり、パラシュートで空から飛び降りたり、マラソン大会に出たりといった「限界への挑戦」かもしれない。
医学的には単純な答えがある。人間をやる気にさせるのは脳の奥深くにある豆ほどのサイズの脳細胞の集まりで、医学用語では「側坐核」、俗に「報酬系」「脳の快楽中枢」などと呼ばれている。
自分が好きなこと──美味しいものを食べたり、友達と会ったり、音楽を聴いたり、フェイスブックに「いいね!」がついたり、セックスやランニングをしたり──はどれも側坐核から始まるのだ。
報酬系はよく神経科学の雑学ネタで紹介され、セックスをしたり、仕事で昇進したり、美味しいものを食べたりするとクリスマスツリーのようにぴかっと点灯するイメージが定着している。しかし側坐核は心地良さを提供するだけでない。実は他にも重要な役割を担っている。
報酬系は上司に褒められたら急にスイッチがオンになり、その後はオフになるというものではなく、常に「待機モード」になっている。教室で授業を聴いている最中もいくらか活動しているし、この一文を読んでいる間もそうだ。
活動が下がるとこの記事に退屈しているということで、他に活性化してくれるものはないかと探し始める。例えばスマホ──スマホには報酬系を活性化させるとんでもない力がある。先生の話が長いからスマホを手に取りたくなるのには側坐核が関わっている。
側坐核はその人がやろうとしていることに「時間をかける価値があるかどうか」を常に伝えてくるが、そこで「価値がない」という判断になると、別のものを探したい衝動が起きる。つまり側坐核は先生の話を聞いたりこの記事を読み続けたりする価値があるかどうかを伝えてくるのだ。
報酬系が違ったはたらき方をする人
報酬系を活性化させるものは人類共通で、美味しい食事、人との交流、セックスなどだ。ただし個人差もあり、私の場合は音楽を聴くと活性化するが、テレビでスポーツの試合を観ても何も起きない。人によって活性化される要因が違うのは不思議でも何でもない。蓼食う虫も好き好きということわざがあるくらいなのだ。
ただ、生まれた時からこの報酬系が少々違ったはたらき方をする人がいる。報酬系が鈍くて、普通なら活性化されるようなことではされないのだ。誰かの話を黙って聞いたり、テレビを観たり、新聞を読んだりするぐらいではだめで、もっと強烈な体験が必要になる。エンジンをかけるのに普通より多く燃料が要る車のような感じだ。人間の場合、燃料に相当するのが「強烈な体験」ということになる。
そんな人たちにとって世界は陰鬱で退屈だ。たいがいの人が「ちょっと退屈だな」と思うようなことが「苦痛なほど退屈」になるし、ドイツ語の単語を覚える努力といったようなことが耐えがたい苦行になる。
普通なら「面白いから続けた方がいい」と語りかけてくる報酬系が「この先生の話は面白くない。だから他のことを探せ!」「この本もちっとも面白くない。だから探し続けろ!」と命じるのだ。そのため報酬系を活性化してくれるものを大小かまわず探し続けることになる。
しかしそんな調子では集中力が続かない。「これは面白い? いいや、面白くない。じゃああれは? いいや、あれもだめ。じゃあもっと探そう!」となるのだから。
絶え間なく刺激を探し回る人は集中することができず、注意散漫だと思われるし衝動的で多動にもなる。どこかで聞いたような特徴だろうか──そう、ADHDだ。
集中できないのはわけがある
今の社会では集中できないと様々な弊害が生まれる。ではなぜうまく機能しない報酬系を持つ人間が存在するのだろうか。集中できる度合いが他の人とは違っているが、そこに理由はあるのだろうか。おそらくあるはずなので、ここで時間を巻き戻してみよう。
祖先2人がサバンナで食べ物を探している。1人はなかなか作動しない報酬系の持ち主で、木の上や茂みでちょっと音がしたりさっと風が吹いたりしただけでそちらに気を取られる。
「ん? 今のは何だ? いや何でもないようだ。じゃあ、あれは? あれも何でもないか。でもこれは?」という調子だ。常に周囲を観察しているので、自分の周りで起きていることを完璧に把握している。どんなに小さな感覚刺激も脳が排除しないので、どうでもいいようなことまで認識している。

(写真提供:Photo AC)
もう1人はどうだろうか。食べ物を探すという任務にはもちろん集中しているが、脳はそれとは無関係な音や刺激の大部分を排除している。茂みの中で聞こえるかさっという音はおそらく風だろうから耳にも入っていない。実はウサギの可能性も捨てきれないのに……。レイヨウやライオンがそばに現れれば気付くだろうが、茂みでかさっと音がしたくらいの情報は脳が排除してしまう。
では、この2人のどちらが食べ物を見つけて生き延びられる可能性が高いだろうか。私なら当然、すぐに気を取られる人に一票を投じる。かさっという音は10回中9回までは風だろうが、最後の1回は食料になるウサギかもしれないのだ。
現代社会で重荷になる
このように、すぐに気を取られる人の方がサバンナで生き残れる確率が高かったはずだ。さらに想像を膨らませ、2人を現代に連れてきて教室なりオフィスなりに座らせてみるとしよう。すると今度はすぐに気を取られる人の方が優秀だという保証はない。
教室やオフィスではかさっという音にも反応する敏感さが足を引っ張ることになる。クラスメートが咳をしたり椅子をずらしたり、車が外を通っただけで先生の話を聞けなくなってしまうのだから。
すぐに気を取られない人の方は重要ではない情報を排除するのが得意で、ウサギやライオンには気付けなかったかもしれないが、先生の話には集中できる。こうして2人の立場は入れ替わった。サバンナでは〈強み〉だった特性が教室やオフィスでは〈問題〉になるのだ。
何もかもに気を散らされて集中できない──私が診てきたADHDの患者たちもそう言っていた。些細なことで集中が途切れ、どうしてもそっちを見たいという誘惑に勝てない。換気扇が回る音、外を通り過ぎる車、チクタクいう壁時計、4列前で咳をするクラスメート。
常にそばにあるスマホは言うまでもない。刺激が常に最大音量になっている状態だ。その上、頭の中では何百もの考えがぐるぐる回っている。そういったことに集中を邪魔されているのだ。
祖先の例でもわかるように、刺激に対して敏感なことが〈弱み〉だとも言い切れない。時と場合によっては〈強み〉にもなるのだ。誰も気付けなかったウサギに気付き、それを食べて生き延び、遺伝子を子孫に伝えたのはすぐに気を取られた人なのだから。
しかし人間は急激にライフスタイルを変化させてしまった。サバンナを出て食べ物を狩るのをやめ、クリック1つで食べ物が家に届く世界を創り上げた。サバンナからフェイスブックまでかかった時間はわずか1万年──1万年というと永遠のように感じられるかもしれないが、進化の見地からすると瞬く間だ。
その間、人間の脳は基本的に変わっていない。サバンナで生活するために進化した脳を今でも持っているが、当時命をつないでくれた特徴が現代社会では重荷になっている場合があるのだ。
今ではADHDと呼ばれるようになった特徴──それは過去のライフスタイルに適応するよう進化したからこその特徴なのだろうか。かつては役に立ったが生活が激変したため負担になってしまったのか? 私はそうだと思う。
※本稿は、『多動脳:ADHDの真実』(新潮社)の一部を再編集したものです。