NHK『あさイチ』で「氷河期世代」特集。日本の6分の1にあたる「就職氷河期世代」。バブル期の売り手市場との落差が語られがちだが、特に<99年3月卒業生>以降の就職率や求人倍率は…
2025年5月21日(水)6時30分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
2025年5月21日放送のNHK『あさイチ』は「氷河期世代」特集。そこで労働経済学を専門とする近藤絢子教授から寄稿いただいた、2024年10月21日の記事を再配信します。
******
1990年代半ばから2000年代初頭に就職活動をした「就職氷河期世代」は、2024年時点で30代の終わりから50代前半にあたります。今も多くの問題を抱えており、厚生労働省が様々な支援を続けています。このような状況のなか、近藤教授は「コロナ禍の経済活動への影響が落ち着いた今、改めて就職氷河期世代に目を向けなおすべき」と語っていて——。今回、近藤教授の著書『就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差』から一部引用、再編集してお届けします。
* * * * * * *
「就職氷河期世代」とは
就職氷河期世代。1990年代半ばから2000年代初頭にかけて、バブル崩壊後の不況の中で就職活動をせざるをえなかった世代を指す言葉である。
「就職氷河期」という言葉が初めてメディアに登場したのは1992年秋と言われている。1994年には新語・流行語大賞特別賞を受賞している。
このころ、バブル景気の崩壊を受けて雇用情勢が急激に悪化し、新卒の就職市場も冷え込んでいった。この就職難は、90年代末にはさらに深刻さを増し、2000年代半ばまで続いた。
具体的にいつからいつまでを就職氷河期と呼ぶか。
本記事では、2019年の「就職氷河期世代支援プログラム」関連の公文書の定義に倣い、1993〜2004年に高校や大学などを卒業した世代を就職氷河期世代とする。
生まれ年で言うと、1970年(1993年に大学を卒業)から1986年(2005年に高校を卒業)が該当する。
「国勢調査」(総務省統計局)の人口データと「学校基本調査」(文部科学省)の進学率などを使って大まかに計算すると、1993年から2004年の間に高校・短大・大学を卒業し社会に出た就職氷河期世代の人口は、約2000万人だ。これは日本の人口の約6分の1にあたる。
ただし、既存の文献における就職氷河期世代の定義には若干の幅がある。卒業年ではなく、生まれ年や特定の時点における年齢で定義されることもある。
ロストジェネレーション
また、「就職氷河期世代」と似たような意味で、「ロストジェネレーション」「ロスジェネ」といった言葉もしばしば使われる。
こちらは、2007年に朝日新聞社が、当時25〜35歳の若者を指して名付けた言葉だ。
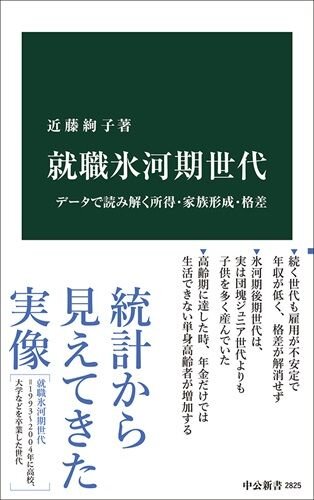
『就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差』(著:近藤絢子/中央公論新社)
1972〜82年生まれに相当し、そのほとんどが就職氷河期に学校を卒業して社会に出た。
このように定義に多少の幅はあるものの、バブル崩壊後に10年あまり続いた就職難の時期に社会に出て、2024年の現在30代の終わりから50代前半となった世代が就職氷河期世代である。
若年期に良好な雇用機会に恵まれなかった結果、中年となった今でも経済的に不利な立場にあるとされる就職氷河期世代だが、当時の就職状況を再確認したうえで、この世代がこれまでどのような形で語られてきたのかを、振り返ってみたい。
マクロ指標で見る就職氷河期
1980年代後半から直近までの、新卒採用市場関連の指標を図示する。網掛けの部分が就職氷河期である。
図序−1は大卒・短大卒の就職率及び大卒求人倍率、図序−2が高卒の就職内定率と求人倍率で、どちらも横軸は卒業年である。

<『就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差』より>
図序−3は日本の労働力人口全体に対する失業率で、実際に就職活動をしていた時期と対応させるためには卒業年よりも1年前にずらして見る必要がある。
バブル崩壊後の景気後退は1991年から始まっていたが、その影響が本格的に新卒採用市場に及びはじめたのは93年卒である。
図序−1を見ても、93年卒から急激に就職率や求人倍率が落ち込みはじめたのがわかる。
92年卒から95年卒までの3年間で、就職(内定)率は10〜20%下がり、求人倍率は半分以下になっている。
短期間にこれほど急激に雇用情勢が悪化したのは過去30年間でもこの時期だけである。前述のとおり、「就職氷河期」という言葉が生まれて定着したのもこのころである。
このように急激な変化を経験する一方で、就職率や求人倍率、失業率などの水準自体は、2000年代半ばの「景気回復期」とされていた時期と同じくらいだった点にも注目したい。
就職氷河期の初めのころは、就職率自体はその後の25年間の中で必ずしも悪いほうではないのである。
しかし、その直前のバブル景気の時代が極端な売り手市場であったため、そこからの落差が問題だったのだ。
前期世代と後期世代
その後、景気はいったん底を打ち、1995、96年ごろは徐々に回復傾向にあるようにすら思えた。
ところが、97年の秋になって、北海道拓殖銀行と山一證券が相次いで破綻、金融危機の様相を呈し、翌98年にかけて景気が一段と悪化した。
この影響が出始めるのは、98年に就職活動をし、翌99年3月に卒業した学年からである。
図序−1を見ても、99年卒から、就職率や求人倍率ががくんと下がり、2000年代初頭にかけては過去30年間で最低の水準まで落ち込んでいたことがわかる。
このように、97〜98年の金融危機の前後で、雇用情勢はかなり異なる。
この点を踏まえて、本記事では、93〜98年卒を「氷河期前期世代」、99〜04年卒を「氷河期後期世代」と定義して、区別する。
氷河期前期世代はそれ以前の売り手市場との激しい落差を経験した世代、氷河期後期世代は雇用の水準そのものがどん底だった世代だ。
就職氷河期世代の陰
ところで、図序−1を眺めていると、04年卒と05年卒の間にそれほど差がないことにも気づく。
確かに、05年卒はその直前の学年よりは多少数字が改善しているものの、就職氷河期が終わったといってよいほどの回復ぶりではないように思う。
しかし05年卒以降の学年を就職氷河期世代に含めている文献はほとんどなく、就職氷河期世代向けの政策対象からも外れることが多かった(ただし、現行の「就職氷河期世代支援プログラム」では2000年代に卒業した世代は全て含むよう対象が拡大されている)。
本記事も他の文献との整合性を考えて04年卒までを就職氷河期世代と定義するが、本当は06年卒くらいまで就職氷河期世代に含めるべきなのかもしれない。
その後、07〜09年卒でいったん90年代半ばと同水準まで回復するものの、08年秋のリーマンブラザーズの破綻に始まる世界同時恐慌(リーマンショック)の影響を受けた10年卒以降の数年にわたって再び落ち込む。
就職氷河期世代の陰に隠れて注目されにくいが、そのすぐ下の世代についても注意深く目を配る必要があるだろう。
※本稿は、『就職氷河期世代-データで読み解く所得・家族形成・格差』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- <バブル世代>に比べ、企業規模は小さく福利厚生の悪い就職先が増えた<就職氷河期世代>。「業種はサービス業や小売業が増えて…」
- 「就職氷河期世代」はどう語られてきたのか?90年代にはフリーター増や高離職率から<若者の意識変化が原因>とも見られていたが…
- 卒業15年後の平均年収<バブル世代>477万円、<氷河期後期世代>415万円。「卒業後の年数がたつほど世代間の差は広がり…」
- 青木さやか「誰でも就職できる会社」まで落ちた就職氷河期を経てタレントになって。「どこ見てんのよ!」は女性をウリにするのが当たり前だった時代に生まれた<心の叫び>
- 不妊治療に経済的不安を抱える年収450万円・33歳の電車運転士「リーマン氷河期世代も気にかけてほしい。社会に出た時期や世代で苦労するのは納得いかない」













