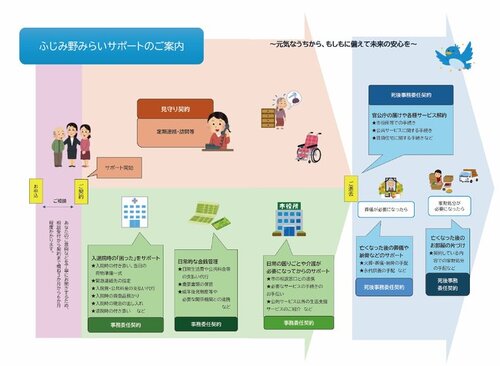【水野誠一 連載】小池一子(下)「くりかえし原点、くりかえし未来」。原点に立つアイデンティティーと未来への展開の両立を
2025年5月22日(木)7時0分 ソトコト
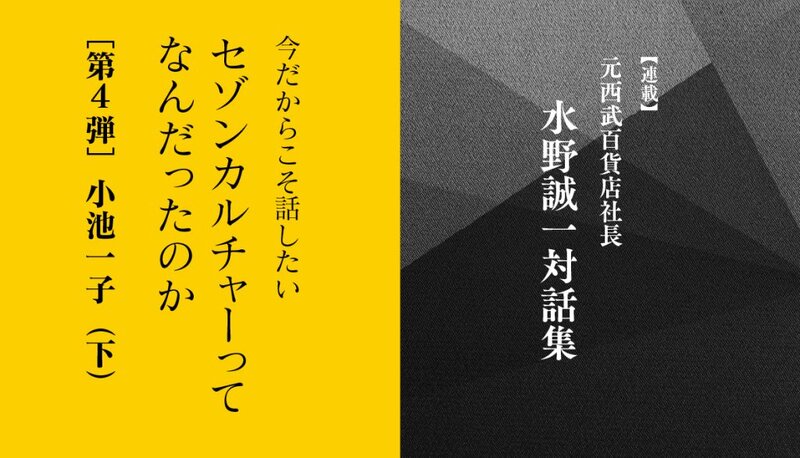
グラフィック・デザイナーの田中一光とともにセゾンカルチャーを、そして無印良品を創生した人物でもあるクリエイティブ・ディレクター、小池一子。西武百貨店に育った水野誠一と、日本のアートとすべてのカルチャーに通じる原点を語る。

時代にヒントを与えていくのはアートの役割のひとつ
水野 小池さんのお仕事の中ですごく印象深いのは、1983年に江東区の昭和初期のビル内にアートスペース「佐賀町エキジビット・スペース」をスタートされたことですね。
小池 2000年ぐらいまでやりましたね。
水野 あれは普通のそのギャラリストがやる仕事とは全く質の違う内容でしたね。
初期の話題は大竹伸朗さんの展覧会だったんだけど、これがまたすごくて。
自分の作品を積み重ねていくような方だから、ひとつ間違うとゴミの山みたいな作品に見えてしまう。
小池 実際にそうでした(笑)。最初の展覧会で、東京のゴミで作った大作が出たんですよ。
でも今後どこにこれが置かれるんだろうと思っていたんですが、今、東京都現代美術館のコレクションになっているんです。
東京のゴミで作った肖像なんかもあるんですけどね。
水野 それは小池さんじゃなければ認められなかったんじゃないか、というような展覧会が、佐賀町エキジットスペースではいろいろありましたね。
小池 ありましたねえ。あのオープニングでは、まだマガジンハウスにいた都築響一さんが、いい原稿を書いてくれたんですけど、予想しないぐらいのたくさんの人が詰めかけてくれて。
時代が待ち望んでいた、新しいアーティストの出現。そういうお祝いができましたね。
それを見に来ていたのが村上隆さんで、後になって村上さんは「俺はあの展覧会を見て現代美術をやると決めた」とおっしゃっています。
水野 いろんな人にいろんな意味でいい刺激を与えましたね。
時代をリードしていく、時代にヒントを与えていくというのは、アートの世界の役割だと思うんですね。
ただ、そういう次なるその時代に繋いでいくことができるプロデューサーというのは、世の中、なかなかいないんですよ。
例えば西武美術館にコレクションとして一流アートがあるんだけれど、そこからヒントを得て、次なる事業に繋げていくようなことを考えるのも百貨店の役割だと、堤清二は考えていたように思うんです。
ところが現代の百貨店は、人気のあるブランドさえ置いとけば安泰であるというようなところに来ちゃってる。じゃあそこに新しいクリエイターを見つけて、ものづくりを一緒にして、次なる時代のシンボルになるようなブランドを作っていこうなんていう気持ちは、今は本当にないですよ。
小池 そうですね。探して押し出す、という姿勢が少ないです。今、本当にどこにもそれが見られないですね。
バブルは正しい文化にお金を回さなかった
水野 結局、佐賀町をやっていらした頃はバブル時代とも重なっているけれど、ミラノがオペラ座を呼ぶなんて言うと何億円とか平気で使うのに、そういう日本の国内の文化には行き渡らなかったということもありますね。
小池 だから決して楽ではなかったですね。
助手に「小池さん、仕事で資生堂やSONYの会長と会っていらっしゃいますよね。なんでそういう方たちにお願いして、お金が来ないんですか」と言われたことがありますけれど。
そういうものでもないですよね。
メセナをやっている会社であっても、結局、その担当の方たちの話し合いで、オタクどうするとかってそれぞれ50万円ぐらいずつとかもらっても、もうちょっとしょうがないので。そういう世界は追求しないできましたね。
水野 バブルというのは、いい意味でも悪い意味でも日本が経験した非常に貴重なタイミングだったとは思いますが。本当に正しい、使うべきところにはお金は回らなかったという意味で、非常に不毛な時代でもありましたね。
小池 それは言えますね。
本当にもっと日本の文化の未来を育成する、助成することにお金を遣ってほしかったです。
そういえばセゾンは、文化財団が演劇の助成だけをやっていますよね。それには本当に感嘆しています。
何を見ようとしているかをプロダクトと言葉で送り出す
水野 文化を引き継いでいくということは、企業にとっては非常に難しい。だから無印良品の話に戻ると、今は健全でありつつ、問題もあると思うんですね。
ここまで大きくなってしまうとね。
その次に何を目指すべきかということを考えると、堤さんがいたら何と言っただろうと思ったりします。今、考え直してもらうということは、僕は非常に重要だと思いますね。
小池 そうですね、組織が大きくなりましたから。
無印良品のなかで、もう1回、全体の方向性を見つめて勉強した方がいいのかもしれないですね。
アドバイザリーボードみたいなものがあるっていうことは、ひとつのらしさを作っていくやり方だとは思いますけどね。
トップマネジメントとの会議は、月に1回、しているんですが。
水野 ただ、今はテレビコメンテーターがそうであるように、社外顧問や社外役員は、経営者にとって都合の良いことしか言わないのかもしれないけど。小池さんはそんな耳優しいことばかりは言わないだろうな。原点を守るためにも、それがいいんですよ。
そういう環境のなかで、小池さんが何かプロジェクトをお考えになるとしたら、どんなことをやりたいですか。
小池 2005年に、私は武蔵野美術大学の先生を辞めて、また勉強の時間が欲しいなと思っていたんですね。無印良品もお休みをしようと思っていたら、金井さん(金井政明前会長)が『くらしの良品研究所』というのを作るから、それをやりませんかと言われて。
これが面白くて、ロンドンでの生活と半分ずつぐらいで行ったり来たりしてきたんですけどね。
そういうことで言うと、シンクタンクみたいなものは必要なんじゃないかなと思って。
そこでいくつかの冊子を出して、無印良品は何を見ようとしている、何を見ているかということをプロダクトと合わせて送り出したいと思いまして。
それで編集もやりました。
つまり、情報と物との双方が消費者に渡されるというのはいいなと今も思っているんです。私は人でもいいんですけど、何か小さなものでも、言葉でまとめて説得をするということは重要だと思うんです。
水野 そうですね。本当に個人がやっているような小さな企画の中に実は光るものがあって。いまだに大企業じゃないと相手にしないみたいな雰囲気がすごくあるなかで、その小さな専門店みたいなものの手渡しの説得力が大事なんじゃないかと思いますね。
小池 若い人はそれをいち早く察知しますよね。
私の住んでいる場所でも、小さなお店で本当にいいパンを作る店や、昔からジジババストアって言われているような、お惣菜も作るし、築地からの取ってきかたがうまい魚を置くような小さな店があります。なんかこう、そういう街づくりっていうのはね、大事なんじゃないかなと思います。
考える人と作る人は身近な方がいい
水野 「くらしの良品研究所」にも何かコピーを書いたのですか。
小池 「くりかえし原点、くりかえし未来。」というのを書いたんですよ。
それは単純なことで言えば、木綿も大事なんだけど新素材も大事っていうようなことにも入れ替えられる。
今までの生活で培ってきたものと、それから未来で展開するものを恐れずに、という意味で書いたコピーが、なんかすごく気に入ってもらえて、ときどきみんながそれを言ってくれるんです。
本当になんかこう、原点に立つということを恐れるとアイデンティティがなくなっちゃう。
だからやっぱり、無印良品がおかしいなと思うときは、その原点のアイデンティティを失った時じゃないかなというふうに思いますね。
水野 いいコピーですね。迷いそうになったら何度も原点に戻って考えてみる。でもそこにとどまらず、未来に展開していくことにも挑戦していく。
小池 考える人と作る人っていうのは身近な方がいいですね。
それで、何かその時代に新しい価値を作り出すっていうのかな。
今でも思いつつある人はたくさんいるのかもしれないけれど、ちょっと拡散しちゃって距離ができているような気がします。
水野 会ってよく話す、というのは大事ですよね。そこからしか生まれないものもありますね。

対談を終えて
小池一子さんとは、2024年11月、松濤美術館で行われた須田悦弘展のプレビューで久しぶりに再会しました。その折、今回の対話企画をお話したのですが、半年かかってようやく実現することができました。今回は、堤清二さん、田中一光さん、三宅一生さんとの繋がり、そこから始まった、無印良品のプロジェクトについての話を中心に対話させていただきましたが、図らずも、小池さんが1983年から2000年の閉廊まで情熱を傾けてこられた「佐賀町エキジビット・スペース」にも話が及びました。
1927年竣工の美しいランドマーク・「食糧ビル」をリニューアルして蘇らせ、現代美術のためのオルターナティブスペースとして、大竹伸朗、森村泰昌、杉本博司など、数多の後に有名アーチストとなるヒト達の活動を推してきた空間でした。規模こそ小さいとはいえ、5mもの天高と全く支柱の無い空間では、西武美術館などと比べても決して引けを取らない見事な企画を実現することができたのです。
バブルと共に百花繚乱状態だったアートブームは、バブルの崩壊と共に一気に萎みましたが、そんな表層的な景気の変化に翻弄されずに、ビルが解体された2002年まで細く長く紡がれてきた小池一子さんの活動からは、細くとも`たおやか‘で’しなやか‘なヒトの強さを感じ、さすがだと今更ながら痛感させられました。
小池さん、いつまでもしなやかにご活躍ください!
構成:森綾 http://moriaya.jp/