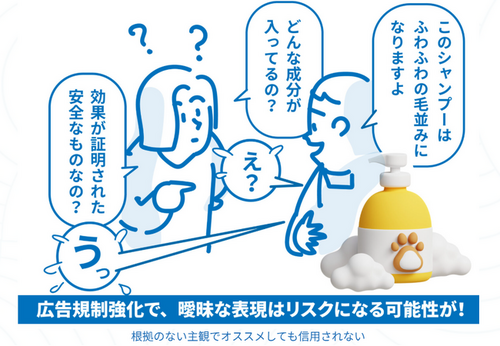巨大なヨコエビ類「ダイダラボッチ」は世界の深海の半分以上に生息している可能性
2025年5月26日(月)21時0分 カラパイア

Youtube
深海は不思議と謎と神秘に満ち溢れている。新たな研究によると、世界の深海の半分以上に「ダイダラボッチ」と呼ばれる大型のヨコエビ類が潜んでいる可能性が高いそうだ。
ダイダラボッチは、甲殻類の一種、端脚目ヨコエビ類最大の種で学名を「Alicella gigantea」という。
19世紀に初めて発見されたダイダラボッチは、これまで超レアな生物とされてきたが、どうやらそうではなかったのだ。
西オーストラリア大学の研究者によると、なんと世界の深海の最大59%に生息しているという。
この研究は『Royal Society Open Science[https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.241635]』(2025年5月21日付)に掲載された。
世界最大のヨコエビ類「ダイダラボッチ」
ダイダラボッチ科ダイダラボッチ属のダイダラボッチ[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%80%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%81_(%E7%AB%AF%E8%84%9A%E9%A1%9E)]は、世界最大のヨコエビで、体長は最大34cmに達する。
ちょっと肩透かしだっただろうか? 30cm程度で巨人の名を与えられるなんて、少々大袈裟すぎと思うかもしれない。
だが西オーストラリア大学の深海学者ペイジ・マロニ博士は、「ほかのヨコエビと比べれば、まさにバカでかい」とで語っている。
ヨコエビ類の多くは数mm程度しかなく1cmを超える種は限られているのだ。

ダイダラボッチをつかむマロニ博士/Credit: Paige Maroni
滅多に姿を見せないダイダラボッチ
エビといっても、ヨコエビ(ヨコエビ目/端脚目)は食材としてよく目にするエビ(エビ目/十脚目)とはまた違うグループだ。それでも姿はエビに似ており、世界中の海や淡水域に生息している。
非常にバラエティ豊かで9000種以上が知られており、暖かい地域や寒い地域の淡水にいたかと思えば、1万mを超える深海でも発見されたことがある。
そんなどこにでもいるヨコエビたちだが、ダイダラボッチは超レア認定されてきた。捕まえようとしても滅多なことではお目にかかれないからだ。
深海生物の研究者は、死んだ魚やイカのようなエサを仕掛けて、集まってくる生き物を調査する。だがマロニ博士によると、ダイダラボッチはなかなか姿を現さないのだという。
「ヨコエビがやってくるときは、短時間で何百匹も集まります。ですがダイダラボッチは1匹か、せいぜい4匹ほどでしか捕獲されません。それも何週間もかけてやっとのことなのです」
姿は現さないが実は深海の半分以上に生息している可能性
だが、どうもそれは勘違いである可能性が高い。
今回、マロニ博士らは、これまでダイダラボッチが観測されてきた深さから、「生息適性モデル」を構築し、彼らがどこに生息しているのか推測している。
深海は広大な領域だが、そのわりにどこも同じような環境なため、深さから、圧力・温度・海流の速さや方向といった海の状況を知ることができる。そうしたデータからダイダラボッチの生息域を推定しようというのだ。
これまでダイダラボッチは、深度3,890〜8,931mの深海帯下層から超深海帯上層で発見されてきた。
そこから構築された生息適性モデルによると、ダイダラボッチは世界の深海の最大59%、6つの主要な海すべてで生息している可能性が高いことがわかった。

ダイダラボッチの採取地(黒点)とその水深(色)を表したマップ。珍しい生物と思いきや、深海の半分に生息しているだろうことが判明/Credit: Maroni et al 2025, Royal Society Open Science DOI:10.1098/rsos.241635CC BY 4.0
さらに、これまで1度も捕獲されたことのない太平洋北東部にも生息していると予測された。
そこでマロニ博士らが北太平洋を東西に走るマレー断裂帯にカメラを設置してみたところ、本当にダイダラボッチがいたのである。しかも群れで!

マレー断裂帯の水深6,500–6,700mの深海で大量に捕獲されたダイダラボッチ(スケール:20cm)/Credit: Maroni et al 2025, Royal Society Open Science DOI: 10.1098/rsos.241635CC BY 4.0
今回、1〜2匹ではなく、20数匹を確認できたことで「ああ、彼らは本当は珍しいわけじゃない。ただ捕獲方法がまずかったか、群れで捕まえるのが難しいだけだったんだ」と確信できました(マロニ博士)
世界中のダイダラボッチはどれも同じ種
こうして世界中で採集されたダイダラボッチの遺伝子を調べてみると、意外なことが明らかになった。
海や大陸で隔てられた場所に生息するにも関わらず、どれも全く同じ種だったのだ。
「ダイダラボッチは自分の生態的ニッチを見つけて、数百万年にわたってそれを維持してきたのでしょう」とマロニ博士は語る。

右上:北太平洋マレー断裂帯の水深6,746mで採取されたダイダラボッチスケール(2cm)
中央:DNA解析に使用された標本の採取地点を表す地図。色は深海の地形を表す
左と下:本研究で解析対象とされたDNA変異のセット。色は対応する標本が採取された場所を示す
/Credit: Maroni et al 2025, Royal Society Open Science DOI: 10.1098/rsos.241635CC BY 4.0
気候変動の影響で変わりつつある深海
マロニ博士によると、深海の環境はよく安定していて、過去3,000万〜4,000万年にわたってあまり変わっていないのだという。
毎年、極地から同じような量の酸素と冷水が深海に流れ込み、海流の速度も一定に保たれていた。地球全体の海洋循環パターンも基本的には同様だった。
だが、そうした状況は気候変動によって変わりつつあるという。そしてその本当の意味をほとんどの人はわかっていない。
深海は地球最大の生態系で、数百万もの未知の生物が生息していると考えられている。にもかかわらず、「私たちはそれを見ることも、意識することもありませんでした」とマロニ博士。
「多くの人は、深海で起きることが確実に沿岸地域・島・気候・漁業・モンスーン・農業に影響していることを理解していません」
彼女の願いは、今回のような研究がきっかけで、「すべてはつながっている」ということを多くの人に気づいてもらうことだという。
References: The supergiant amphipod Alicella gigantea may inhabit over half of the world’s oceans[https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.241635] / ‘Supergiant’ sea creature could lurk in more than half of the deep ocean[https://cosmosmagazine.com/nature/marine-life/deep-ocean-alicella-gigantea/]