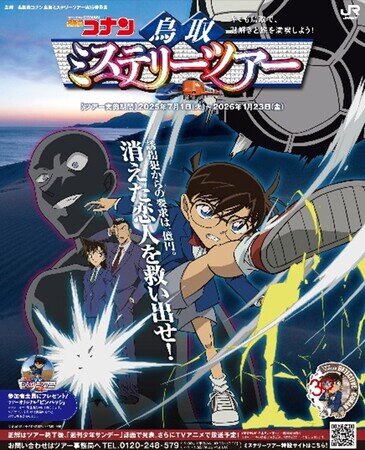吉田修一の新刊、江戸川乱歩賞受賞作…秋の夜長に読みたい本格ミステリーは、コクの深い「男と女の物語」を
2024年11月12日(火)8時0分 JBpress
時代や社会にこびりついたものに、男女ともいやおうなく影響を受ける。世の非常時には男は救国に走り、女は唯一差し出せるものを用いて、身近な者の命を救おうとする。ジェンダーは哀しい、男も女も。しかしそれらが、歴史のヒダになってきたのも事実。そのヒダには、愛や真心や寛容や慈悲が宿る。今回はある種の密室ミステリーながら、密室という本格パズルへの興味よりも、男と女の物語としてコク深い2冊を。
選・文=温水ゆかり 写真=shutterstock
物語の名手が映し出す、貧困と飢餓の中のひとひらのぬくもり
著者:吉田修一出版社:角川書店
発売日:2024年10月18日
【概要】
横浜で探偵業を営む遠刈田蘭平のもとに、一風変わった依頼が舞い込んだ。九州を中心にデパートで財をなした有名一族の三代目・豊大から、ある宝石を探してほしいという。宝石の名は「一万年愛す」。ボナパルト王女も身に着けた25カラット以上のルビーで、時価35億円ともいわれる。蘭平は長崎の九十九島の一つでおこなわれる、創業者・梅田壮吾の米寿の祝いに訪れることになった。豊大の両親などの梅田家一族と、元警部の坂巻といった面々と梅田翁を祝うため、豪邸で一夜を過ごすことになった蘭平。だがその夜、梅田翁は失踪してしまう……。
吉田修一さんは、綿密な取材を重ねた大作や、現代の諸相を映すような慟哭作の間に、自らも楽しみながら書く遊戯的なエンタメをものする。10月の新刊『罪名、一万年愛す』もそんな遊び心に富んだ1冊。舞台は、長崎の風光明媚な島だ。
長崎県佐世保市に属し、東シナ海に浮かぶ九十九島群島。群島のほとんどは、無人島や海面に突き出た岩礁なのだが、富裕層の中にはプライベートアイランドとして所有する者もいるらしい。
米寿を迎えようとしている梅田壮吾(そうご)もそんな富裕層の一人である。戦前生まれの壮吾は佐賀市内の呉服問屋の下働きから身を起こし、戦後、高度成長の波に乗って九州各地にスーパーマーケットを展開。福岡の一等地である天神に梅田丸百貨店を開業して支店を増やしていった辣腕の経営者。
引退後、50年近く前に購入し、愛猫のノラから取って野良島と名付けた島で、優雅な余生を楽しんでいた。88歳ながら壮吾は現役時代の活力を彷彿させるほど壮健である
お話は、その梅田翁の奇行を案じた孫の梅田豊大(とよひろ)が、横浜の野毛地区で私立探偵事務所を営む遠刈田蘭平(とおがった・らんぺい)を訪ねたシーンから始まる。豊大の話はこうだ。
住み込みの家政婦さんによれば、壮吾が夜な夜な「一万年愛す」という宝石を探し回っている。しかし聞かれた家族の誰もそんな宝石に心当たりはない。いよいよ認知症か。疑った家族が医師同伴で野良島を訪れると、老人扱いされたことに憤った壮吾に、その日のうちに追い返されたという。
梅田家には、18歳を迎える者に、サザビーズやクリスティーズで欲しいものを落札して贈るという習慣があった。顧問弁護士が言うに、もしそんな宝石があるとすれば、自分が梅田家を担当する前にオークションで落札したものではないか、と。
豊大は有名なオークション会社の過去のデータに当たってみる。するとあったのだ、「一万年愛す」という名の、血のように濃い赤のルビーのペンダントが。アンナ・ボナパルト王女のコレクションだったそれは、1940年代のスイスで、現在の価値に換算して35、36億円の値で匿名者に落札されていた。
遠刈田は豊大に対して首をひねる。あるのかないのか分からないそんなものを、私に探せとでも? 豊大は言う、近々祖父の米寿を祝うパーティが野良島で開かれる。「一万年愛す」の謎に少しでも近づくため、野良島に同行してほしい、と。
孤島、近づく嵐、謎の宝石、富豪の相続人達による密室舞台
こうして野良島に招待客が集まる。梅田翁の息子夫婦である一雄と葉子夫妻、夫妻の子供である豊大と野乃華の双子、探偵の遠刈田に、元警部の坂巻という6人である。
島内には梅田翁を筆頭に、住み込みの家政婦・清子、専属の看護師・宗方、ボートハウスに住み、電気工事など一切の雑事を引く受ける三上と、計4人の住人がいた。
招待客の坂巻元警部は、梅田翁と因縁の間柄である。1970年代半ば、当時光り輝く場所だった多摩ニュータウンで、幸せそうに暮らしていた一人の主婦が突然消える。彼女が元吉原の遊郭に身を置いていた娼婦だったことが分かり、その落差に報道は過熱する。世にいう「多摩ニュータウン主婦失踪事件」である。
捜査線上に、梅田荘吾の名が浮かぶ。主婦が消息直前に、すでに若き実業家として顔を知られていた梅田と会っていたという目撃証言が出てきたのだ。が、捜査はすぐに行き詰まる。坂巻がどう調べても、主婦と梅田が繋がらないのだ。事件はいつしか忘れさられた。
坂巻が定年退職するとき、梅田壮吾は古伊万里の皿を贈る。富豪の気まぐれだろうか。それとも「捜査人vs容疑者」という関係を、露悪的に面白がっているのだろうか。
以来、梅田翁が坂巻に「さて、あらたな証拠は見つかりましたかな」と楽しげに会話の口火を切り、坂巻も笑いながらいなすという関係が続いている。坂巻自身は梅田翁の露悪的なからかいも、この一家の仲のよさも大好きだ。
折りしも、それるはずだった大型台風が長崎方面に舵を切る。孤島、近づく嵐、謎の宝石、富豪の相続人達。と、出来すぎの密室舞台が出来上がる。吉田修一さんったら、とニヤけてしまう本格ファンは私だけではないだろう。
シャンパンの泡燦めく米寿の宴のテーブルで、梅田翁は上機嫌である。絶海の孤島に(すぐ孫娘に反論される、高速ボートで対岸はすぐなのに大袈裟だと)、金持ちの一族、客人には探偵に元警部がいる。「こんな状況で殺人事件が起こらないなんてことがありますか?」と、呵々大笑しかねないご機嫌ぶり。
しかし事件は起こる。翌朝、梅田翁の姿が消えるのだ。ベッドの枕の下からは遺書が見つかる。そこに自筆で書かれていたのは「私の遺言書は、昨晩の私が持っている」という謎めいた文言。
この時点で(読者にとっては)全員が容疑者だ。翁の場合は自作自演の大芝居、翁が他殺だった場合は、9人が容疑者。翁が就寝前に会ったのは看護師だけだったはずが、互いのチクリで、清子も三上も豊大も野乃華も会っていたことが判明する。
焼け野原の記憶を抹殺して生きようとした人々以前の、もう1本の映画
とはいえ、読みながらなんとなく察知するのは、このミステリーには『シャイニング』のジャック・ニコルソンのような狂気の男は出てこないだろし、アガサ・クリスティの名作『そして誰もいなくなった』のような、島内住人全員抹殺みたいな惨劇も起こらないだろうということだ。
冒頭に誰とも特定できない語り手が出てくる。その語り手は華麗なショーが始まる前に前口上を述べる司会者よろしく、登場人物を上空からの視点で紹介。するすると引っ込んで、本編が始まる。
九十九島の陽光は明るく、梅田翁は上機嫌、物語自体が〈The Show Must Go On〉 の精神で進行していると感じさせるのだ。
枕の下の遺言の謎は、意外にも役者を目指して劇団の研究生だったことがある遠刈田のシェイクスピア知識で解かれる。昨晩、梅田翁が宴席で「年寄りの祝いなんてものは、悲しみだけ行く手にはあり」と呟いた言葉。あれはシェイクスピアのソネット(14行詩)集の中の文言だ、と。
読書家だった梅田翁の書架を探すと、やはりシェイクスピア全集の第一巻「ソネット集」があった。新たな遺言書が挟まれている。そこにはこうあった。「一万年愛すは、私の過去に置いてある」。
過去と来れば、因縁のある坂巻元警部の出番だろう。彼は「多摩ニュータウン主婦失踪事件」を詳しく語り始める。
手がかりはまだあった。翁は地下のシアタールームに、3本のDVDパッケージをこれ見よがしに放置していた。『砂の器』『飢餓海峡』『人間の証明』。昭和の名作映画だ。元タレントで結婚を機にきっぱりと芸能界を引退した葉子夫人は、どれも大好きな映画だと、うっとりとしながら反芻する。
「『砂の器』に出てた島田陽子さんの魅力的だったこと」「私、本当はああいう映画に出られるような女優になりたくて芸能界を目指したんですよ」「『飢餓海峡』の左幸子さんの演技なんてもう、思い出しただけで鳥肌が立っちゃいそう」
昭和という時代を象徴する映画は何を示唆しているのか? 半世紀近く前の多摩ニュータウン主婦失踪事件に翁は本当に関係していなかったのか? 血のように赤い「一万年愛す」というルビーは本当にあるのか? なにより姿を消した翁は自死を遂げたのか? それとも誰かの手で殺されたのか。とすればその動機は?
これらの疑問が有機的に連結して、このミステリー列車は進む。ミステリーは通常、作者が仕掛けたレッドヘリング(偽の手がかり)に騙されないよう、一行一行目を丹念に追う緊張感を強いるが、この『罪名、一万年愛す』は、ただただ物語という列車の揺れに身を任せればいい。洞窟アドベンチャーまで用意されている。
最後にいっこ。貧困、飢餓、生き延びるための手段、その中にあった、忘れられないひとひらの温もり。たどり着くエビータ風の(←気にせず流し読みして下さい。はい、レッドヘリングです)結末に、そっか、これは焼け野原の記憶を抹殺して生きるという保身に抗った、もう1本の映画だったのだなあということだった。忘れがたいということが、これほどの重みをもっていたとは。
忘れがたいということが、これほどの重みをもっていたとは。映画化されるといいですね。
2作同時受賞となった、第70回江戸川乱歩賞受賞作
著者:霜月 流出版社:角川書店
発売日:2024年10月23日
【概要】
幕末日本。幼いころから綺麗な石にしか興味のない町娘・伊佐のもとへ、父・繁蔵の訃報が伝えられた。さらに真面目一筋だった木挽き職人の父の遺骸には、横浜・港崎遊廓(通称:遊廓島)の遊女屋・岩亀楼と、そこの遊女と思しき「潮騒」という名の書かれた鑑札が添えられ、挙げ句、父には攘夷派の強盗に与した上に町娘を殺した容疑がかけられていた。伊佐は父の無実と死の真相を確かめるべく、かつての父の弟子・幸正の斡旋で、外国人の妾となって遊廓島に乗り込む。そこで出会ったのは、「遊女殺し」の異名を持つ英国海軍の将校・メイソン。初めはメイソンを恐れていた伊佐だったが、彼の宝石のように美しい目と実直な人柄に惹かれていく。伊佐はメイソンの力を借りながら、次第に事件の真相に近づいていくが……。
『遊郭島心中譚』は2作同時受賞となった江戸川乱歩賞作。日野瑛太郎著『フェイク・マッスル』が8月に出て、本書の刊行は10月。遅れたのは、選考員達が改稿を条件にしたためのようだ。
『フェイク・マッスル』の受賞はあっさり決まり、選考時間のほとんどは、この『遊郭島心中譚』の論議に費やされたらしい。この作品が目指した世界観を壊さず、技術的にどう展開すればよりよいものになるか。創作論、技術論などが議論されたのだろう。
選考委員の一人である辻村美月さんが、著者の霜月流(しもつき・りゅう)さんが熱い論議の場に同席できるはずもなかったことを残念がりつつ、自身も「小説を書く者の一人として、大いに勉強になった」と書いているほどだ。
幕末の生麦事件を背景に、父の死の謎を探して横浜の洋妾に
時代は幕末。早くに母を亡くし、父の繁蔵と深川で暮らしていた伊佐は、訪ねてきたお役人に告げられた事件に言葉を失う。
生麦事件の余波で幕府は英国公使館に償金を支払うことに。金箱を運ぶその行列を、繁蔵が襲って強奪しようとしたばかりか、ピストル誤射の犠牲となって虫の息になっていた娘の首を切り落とし、持ち去ったというのだ。
が、繁蔵はすぐ、焼死体として発見される。船饅頭(安価で春をひさぐ女)の苫舟が突然燃え上がり、女は川に落ちた。繁蔵だけが骸となって引き揚げられたという。傍らにあった幕府発行の鑑札には「岩亀楼 潮騒」との文字が……。
「おとっつあんが、強盗とか斬首とか、そんなことをするはずがない」と固く信じる伊佐を、父の弟子だった幸正が訪ねてくる。
職人から周旋業に転身したこの男、口がうまい。父の無念を晴らして名誉を守りたい」という伊佐に、「あんた、横浜で綿羊娘(らしゃめん)にならないか」と持ちかける。
綿羊娘(らしゃめん)とは、綿羊の毛織物「羅紗綿(らしゃめん)」を着て外国人に春を売っていた女達の姿に由来し、外国人の妾になった娘のこともそう呼ぶようになった。かつての師の娘に、洋妾になることを勧めるとは、幸正、相当食えない男だ。
繁蔵が持っていた鑑札の岩亀楼は、開港したしたばかりの横浜港に、幕府が用意した「港崎(みよざき)遊郭」で、豪華絢爛を誇った最大の妓楼。伊佐は横浜に行くため、岩亀楼に乗り込んで潮騒に近づくため、洋妾になることを決意する。
伊佐は幸正に言う。「あたしを横浜に連れていって」、ただし「あたしは、異人の旦那様に決して肌を許しません。身体を差し出さなくても、心を通わせることは、きっとできます」。
当時、横浜の遊女には四つのタイプがあったという。日本人だけを相手にする「日本人館の遊女」、外国人相手の「異人館の遊女」、異人館から異人の居宅に通って夫婦として暮らす「異人館付きの綿羊娘」。
しかし異人館付きのらしゃめんは、幕府のお墨付きゆえ守るべき規則があった。国の秘密をもらすなとか、妊娠出産は御法度とか。異人達は考えた。妓楼を介さず、周旋業者に女性を斡旋してもらったほうが煩わしくない、と。
幸正は講釈を続ける。そこで第四のタイプが出てくる。それが伊佐のような「野良のらしゃめん」だと。幕府が取り締まれば、武器弾薬の取引はなかったことにするなど脅してくる連中ゆえ、侍女だと言い張れば、見逃される。
伊佐は、父の汚名を晴らすという可憐な決意のもと、メイソン大尉の妾となる。伊佐とメイソンが引かれ合ったのは、ともに“石集め”が大好きだったことだ。伊佐のそれは道ばたや海っぱたで拾う石ころで、メイソンのそれは美しい宝石だったのだけれど。
「野良のらしゃめん」は、最もきままで、夫の寵愛を存分に受けられる立場。しかし男が本国に帰る別れの日は必ず来る。本気で愛すれば、愛の荒野の野良になりはてる。このときの伊佐は、そんなことは想像もしていない。
色鮮やかな独特の世界観で、「スパイと娼婦」の純情を
その一方で、洋妾となったもう一人の女がいた、お鏡(きょう)。心中をはかるも、酷薄な男に見捨てられて一人で死んでいった姉のことが忘れられず、怪しげな心中箱を考案。「信実の愛」を探し、証明しようとしている女だ。彼女は異人達の動向をさぐる間者(スパイ)でもあった。
世界最古の職業は「スパイと娼婦」とされている。くっつけばハニートラップだが、本書はどこまでも純情、もしくは一途。よくこんな抽象的なテーマをミステリーに持ち込んだなあと感心する。
幕末当時の外国人居留地や、大門をくぐり1本しかない橋をわたって行く遊郭島(橋が落ちれば孤島に)、シャンデリアの下でくつろぐ異国の男達や、どこからともなく聞こえてくる三味線の音色など、きらびやかでありながらどこかレイジーな独特の世界が眼前に現出する。余談ながら「港崎遊郭」は現在、横浜公園に碑として遺る。
見たこともない極彩色の世界を現出させるセンスを選考員が惜しんだのだろう。読者としては、改稿前の原稿も読んでみたい気もするが、もちろんそれは叶わない。
若い女が身を売るしか家族の者を飢えから救う手段がなかった幕末遊郭の時代、そして敗戦後の飢えの中にもあった温もり。歴史は女達の涙と犠牲と献身で出来ている。などと言いたくなってしまったのだった。
※「概要」は出版社公式サイトほかから抜粋。
筆者:温水 ゆかり