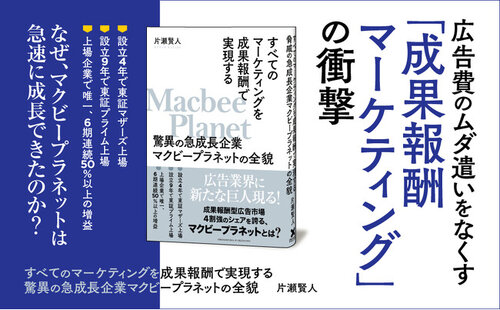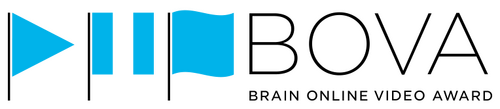食用コオロギの養殖と商品開発を展開してきたベンチャー企業グリラス、自己破産を招いた本当の理由
2024年12月19日(木)6時0分 JBpress
(昆虫料理研究家:内山 昭一)
食用コオロギの養殖と商品開発を展開してきたベンチャー企業グリラスが、本年11月7日付で徳島地裁に自己破産を申請した。昆虫食業界を先導してきたグリラスがなぜこのような事態を招いたのか。昆虫食研究家の内山昭一氏は「グリラスの企業活動の実態は『商売』ではなく『研究』だったのではないか、このことが今回の事態を招いた主因のように思えてならない」と指摘する。
順調な船出に見えたが
徳島大学に「生物資源産業学部」が新設されたことがグリラス創業の端緒になった。社会に役立つ研究が求められるなか、「フタホシコオロギ食用化プロジェクト」がクラウドファンディングで自動飼育装置の作成費のための目標金額を達成した。バイオテクノロジー部門でフタホシコオロギの発生研究を行ってきていた三戸太郎氏と渡邉崇人氏が「将来の食料不足を解消する研究を進めていきたい」と熱く語っていたのを覚えている。
2017年12月、昆虫料理研究会(現在のNPO法人昆虫食普及ネットワーク)では昆虫食を推進する立場からこのプロジェクトに共感し、徳島大の食用コオロギと餌用コオロギを食べ比べるワークショップを開催した。開催日がちょうど24日だったので、題して「徳島大コオロギとふつうのコオロギ食べ比べ実験〜今年のクリスマスはchickenの代わりにcricketで祝おう!〜」だった。
案内には「いま世界各地で食べられているヨーロッパイエコオロギ(=ハウスクリケット)よりも、フタホシコオロギは大きくて肉厚です。徳島大学の『フタホシコオロギ食用化プロジェクト』で収穫されたフタホシはどんな味がするのでしょうか。市販の普通のフタホシと食べ比べてみましょう」とある。
参加者12名の味についての評価(甘味、塩味、苦味、旨味、香り)をみると、徳島大の方が旨味と香りが強いと答えた人が8名いた。このことから飼育環境や餌によって食味が変わることが分かったことは、このプロジェクトの大きな成果だった。
こうした研究成果を世に問うため、翌々年の2019年に満を持して創業、廃校になった美馬市の小学校舎で食用コオロギの量産を開始した。2020年には「無印良品」のせんべいに粉末が採用されて一躍脚光を浴びることになる。同時に農林水産省が事務局となるフードテック官民協議会の昆虫WTに所属し、養殖ガイドラインの作成など精力的な活動をしてきた。
そうした活動の一環として、2023年1月、NTT東日本がグリラスと連携して“食用コオロギ”飼育を開始したとのニュースが流れた。センサーを使ってこれまで手作業で行っていた温度管理や給餌を遠隔地からできるようにする「スマート養殖」を導入し、コオロギ養殖の自動化を進めるとした。当施設を訪問した筆者に担当者は、当施設で得たコオロギ養殖のノウハウを全国の電話局の施設で展開したいとの抱負を語っていた。
SNSでの「炎上」の誘因とは
このニュースが流れた直後の2月18日に、『日刊ゲンダイ』に「コオロギを食べるのは危険」という記事が掲載され、昆虫食批判の口火が切られた。これを契機に潮目が変わり、「給食にコオロギなどとんでもない」などのコメントがSNSで「炎上」し、グリラスの売り上げは急激に低下、50名いた従業員も削減し、美馬市の生産工場も閉鎖となった。これまで食用に限っていたのを動物用飼料の拡大も図って申請した補助金が通らず、自己破産という事態に陥った。
グリラスの「商売」よりも「研究」という姿勢が、この事態を招いた誘因と筆者は考える。元々社長の渡邉氏はフタホシコオロギの発生を専門とする研究者だった。「グリラス」という社名がそれを象徴的に物語っている。フタホシコオロギの学名Gryllus bimaculatusから採っているのだ。
フードロス食材を飼料として育てたコオロギを「サーキュラーフード(循環型食品)」とし、自社ブランドを『Circulated Cultured Cricket』(循環型で養殖されたコオロギ)の3つ(TRIA)のCから採ってC. TRIA(シートリア)と命名するなど、研究者ならではの嗜好性がうかがえる。
2021年に行われた⾷品技術研修会第267回例会での講演要旨を見ると、研究開発計画として、今年2024年を目途に「完全自動システム開発」「機能性成分の抽出法開発」が挙げられている。これだけの研究には多くの人員が必要であり、この当時従業員数が19名だったものが最大で50名あまりに膨れ上がっている。
この時点で「食用」に限っていたのも多くの他社との違いである。「商売」で最も大事なのは取引先をいかに拡大していくかではないか。そこへの注力に欠けていた感は否めない。不足する運転資金を大学の信用から得た資金で補っていたことは容易に想像できる。たとえば2020年にシリーズAにて総額2.3億円の資⾦調達を実施、2022年にシリーズA1にて総額2.9億円の資⾦調達を実施などとある。
「美味しくて安全」が普及の決め手
「食べるか、食べないか、好きか、嫌いか」は、その食べ物が「循環型食品」かどうかで決まるわけではない。筆者が関わった研究で昆虫を食べたことのない人の理由で一番多かったのは「理屈抜きで拒否する」「今までの食習慣から食べられない」だった。約9割の人が昆虫食を避けるというアンケート結果もある。
雑食性動物である人間の心理は「食物新奇性恐怖」と「食物新奇性嗜好」の間で揺れ動く。9割の人は「サーキュラーフード(循環型食品)」だ、「シートリア(Circulated Cultured Cricket=循環型で養殖されたコオロギ)」だといくら言われても触手が伸びない。
人は良い匂いがして美味しくて体に良いのが食べたいのだ。先に述べたように昆虫料理研究会が2017年に行った食べ比べでは、徳島大のコオロギの方が旨味と香りが強いと答えた人が多かったのである。つまり美味しかったのだ。商売として考えるなら「シートリア」からは匂いも味も伝わらないし、食料不足の実感が乏しい日本人への説得力にも欠ける。「美味しくて安全」が普及の決め手なのだ。無印良品の「コオロギせんべい」がそのことを如実に物語っている。
徳島の高校の給食を再現、その味は?
順調と思えたグリラス倒産の契機となったのは先に触れた徳島の高校での「給食」だった。徳島の高校の場合は「小中学校のような学校給食ではなく、(食物科があり)、専門科目の集団給食として実施しています。生徒がみな一斉に食べるわけではなく、希望する一部の生徒だけが試食しています」と徳島県教委の学校教育課はJ-CASTニュース編集部の取材に答えている。
当時のネットを見る限り「給食」という単語が独り歩きし、その味についての評価は皆無だった。そこで筆者は評価の大前提である美味しさを知りたいと思い、担任の先生にお願いしてレシピを送ってもらった。「コオロギパウダー入りカボチャコロッケ」と「コオロギエキス入り大学いも」の二品だった。
揚げたてを一口噛むとサックリした衣に包まれたクリーミーなかぼちゃの甘みが心地よい。さらに噛み締めると甘さの奥から濃厚な旨味が感じられる。フタホシコオロギの持つ独特の味。換言すればバッタ目に共通するエビ系の旨味に近い。コオロギパウダーが微細で混ぜやすく、カボチャと渾然一体となることで、滑らかで調和のとれた一品となっている
ホクホクのさつまいもを一口齧っただけで、バターの濃厚なコクと旨味とコオロギエキスが醸し出す魚介系の風味が渾然一体となって口腔全体に拡散する。まさに旨味の相乗効果といえよう。さつまいもは揚げていないので、濃厚な旨味がストレートに舌に染みわたる。いくらかの塩味が効いていてみたらし味に近い。旨味を凝縮させたエキスを使ったことで、フタホシコオロギの香りや味を惜しげもなく感じさせる秀逸な一品に仕上がっている。
以上のようにとても美味しい料理に仕上がっている。この美味しさをそれこそ「拡散」する手立てはなかったかと悔やまれる。
昆虫食はこれで終わりではない
自己破産を申請した1か月後の12月「炎上に負けないビジネスモデルを再構築したい」と渡邉氏は語る。当面は飼料分野で再建を考え、次のステップとして2050年までに再び人向けの食品市場に挑戦したいと続ける。こうした発言からは食用コオロギ研究の第一人者としての矜持が感じられる。
同時に「挑戦」を考えるなら、食習慣は極めて保守的であり、普及の決め手は「地球に優しい」からではなく「食べたくなり、食べて美味しい」からに心してほしい。渡邉氏の実家が飲食店で、中学生の頃から店で料理を手伝っていたことを考えれば、商売繁盛には味が決め手なのは身に染みて実感しているはずである。ともあれ当面は研究者の道に立ち返って昆虫食のあるべき未来を先導してほしいと願っているし、渡邉氏にはそれができると確信している。
(編集協力:春燈社 小西眞由美)
筆者:内山 昭一