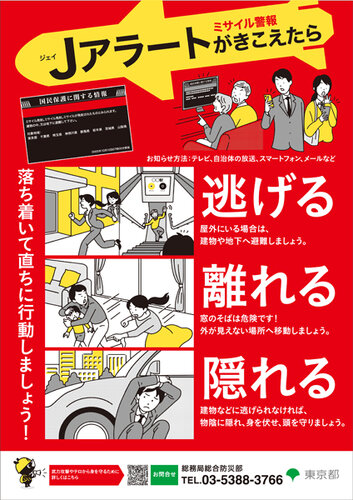避難や求職で離れても「故郷との絆忘れないで」…能登の被災者らに「ミニコミ紙」広がる
2025年4月2日(水)15時0分 読売新聞
金蔵新聞の最新号を住民に配る井池さん(中央)(3月27日、石川県輪島市で)
能登半島地震後、仮設住宅や避難先で生活する同郷の住民に地元の現状を知ってもらおうと、被災者らが独自にミニコミ紙を発行する動きが広がっている。避難や求職で地区を離れる人もいるなか、「故郷との絆を忘れないでほしい」と復興の状況や祭事などを伝えていく。(武山克彦、佐野真一)
「見守り」にも
石川県輪島市の
金蔵新聞はNPO法人の協力を得て昨年4月29日に創刊し、2、3か月に1度のペースで地区内外に届けられる。53世帯95人いた住民は地震後に半減したが、編集を担当する井池光信区長(69)は「地元のニュースを知ることで、愛着を持ち続けてほしい」と言う。配布は見守り活動にもつながっている。
正確な情報を
輪島市深見町地区でも、住民有志が昨年3月から「深見町復興ニュース」を定期的に配っている。避難先では混乱から情報が
広がる発信
金蔵新聞を知った住民の提案で、
珠洲市北部の大谷地区でも昨夏から、「外浦地区たより」が発行されている。市の広報誌に折り込み、月1回200部ほどを配布している。編集作業を担う地元のNPO法人代表の重政辰也さん(37)は「避難先での情報不足から、住民同士の分断が生じることがないように取り組みたい」と力を込める。