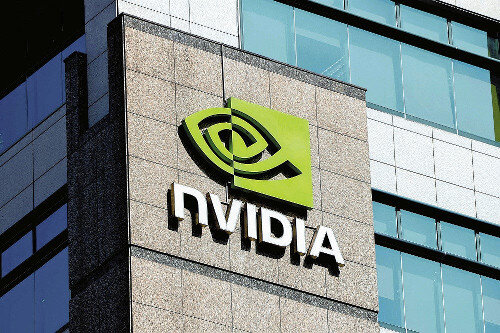元日立専務の「ミスター半導体」牧本次生氏が語る日本半導体「シェア急落の真因」
2025年1月16日(木)6時0分 JBpress
1980年代後半、日本の半導体産業は世界シェアの50%を占め隆盛を極めたが、その後の半導体摩擦を経て凋落し、現在は海外企業に大きく後れを取っている。2024年9月に著書『日本半導体物語 パイオニアの証言』(筑摩書房)を出版した「ミスター半導体」こと元日立製作所 専務取締役の牧本次生氏は、その原因がファブレス企業の台頭にあると強調する。前編に続き、日本の半導体産業が衰退した原因と、これから向き合うべき真の課題について聞いた。(後編/全2回)
日立製SHマイコンのヒットを支えた「拡販作戦の中身」
——前編では、変化が激しい半導体業界の特性や、日立とモトローラの提携秘話について聞きました。著書『日本半導体物語 パイオニアの証言』では、H8マイコンやSHマイコンの拡販プロジェクトについて述べられています。日立製のマイコンが世界でシェアを広げることができた背景には、どのような要因があったのでしょうか。
牧本次生氏(以下敬称略) マイコンをはじめとする半導体市場は日本よりも海外の規模がはるかに大きいため、その販売戦略についても「とにかくグローバル市場を意識する」ということを念頭に置いた結果だと考えています。
しかし、同じ半導体でもマイコンとDRAMでは売り方を変えなければなりません。DRAMの場合、スペックを記した資料が1枚あれば、多くの営業担当者がそれを理解して販売活動ができます。一方、マイコンは各社の思想が込められているので、営業担当にスペックを渡して販売を頼んでも、顧客への具体的な説明は困難です。
そこで、日立では「MGO(マイコン・グランド・オペレーション)」という作戦を実施しました。MGOとは、マイコンを拡販するための生販一体プロジェクトの呼称です。従来の拡販活動では付けないような呼称にすることで、プロジェクトにかける決意を関係者に伝えることが目的でした。
MGOには、現役の設計グループからエンジニアを選抜して、国内のみならず海外の販売部隊と客先に同行し、顧客に対して直接SHマイコンを説明してもらいました。こうした体制であれば、顧客からの質問にも即座に答えられますし、顧客からのフィードバックもすぐに得られます。大胆な作戦ではありましたが、結果としてマイコンの売り上げは国内のみならず海外でも大きく伸び、着実に成果を得ることができました。
日立が海外営業の最前線に半導体技術者を送った「あるきっかけ」
——製品をグローバル市場で広めるために、作り手が顧客に直接メッセージを届ける体制を整えたのですね。
牧本 そのとおりです。従来であれば、社内のマーケティング担当者が資料を作り、国内・海外の営業部隊や販売代理店に資料を共有する、という流れになります。しかし、複数部門、複数社を介することで情報の精度は低下し、伝達速度も遅くなります。MGOでは、この情報の精度と伝達速度の向上を目的としました。
——日立が自社の技術者を海外にまで派遣しようと考えた背景には、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
牧本 1970年代後半、インテルとモトローラとの間で16ビット・マイコンの激しい市場争奪戦が繰り広げられました。そこで「インテルがどのように勝利したか」を記した『マーケティング・ハイテクノロジー』(ダビドウ,ウィリアム・H./著)という書籍があります。この本を読んだところ、MGOのヒントとなる営業手法が記されていたのです。
当時のインテルは、会社のトップが最終顧客に出向くなどのことも含めて直接的なコミュニケーションラインを強化することで、モトローラとの競争に勝利したことが記されていました。この戦略を知り、日立でもこのようなコンセプトを導入する必要性があると強く感じたのです。
——著書では、日本企業がかつて世界の半導体市場で50%のシェアを占めていたものの、半導体摩擦をきっかけに大きくシェアを低下させた経緯が語られています。この原因について、どのように分析されていますか。
牧本 世界の半導体産業が「How to make(製造)」指向から「What to make(企画・設計)」指向へシフトする中、日本の半導体メーカーはその変化に対応できませんでした。ここに日本の敗因があると考えています。この点については、1988年と2023年の半導体業界上位10社を比較すれば一目瞭然です。
1988年時点での上位10社のうち6社を日本企業が占めており、「日本圧勝」のかたちになっていましたが、2023年に日本企業は圏外に去りました。一方で、米国企業が上位10社のうち7社を占めるようになり、そのうちの5社は自社で製造設備を持たず半導体の開発・設計のみを行うファブレス企業です。つまり、1988年当時に上位10社に入っていた日本企業は2023年にはファブレス企業によって取って代わられたのです。
1988年当時、日本企業の強さの原動力の一つは、高品質なDRAMにありました。DRAMの仕様は世界標準だったため、「16Kビットならば、このスペック」「1Mビットならば、このスペック」という具合に、皆が同じものを作る競争ルールで成り立っていました。
つまり、この当時は「How to make」が強さの源泉になっていたのです。ここでの競争軸は「いかにたくさん投資し、大量に生産できるか」「いかに丁寧に作り、歩留まりを上げられるか」ということであり、ここに日本企業の強みがありました。
一方、近年になって急成長を遂げたファブレス企業は、工場を有していないため「How to make」の能力がありません。彼らの得意分野は「市場が何を求めているのか」を丹念に調べ、そのニーズに合ったものをつくる「製品定義」です。市場に合った製品を定義して設計し、工場を持つファウンドリー(半導体受託製造)企業に製造してもらい、それを販売することが役割であり、戦略なのです。
つまり、ファブレス企業は「How to make」のノウハウを持たない代わりに、「What to make」の知見が圧倒的に強い、といえます。製品定義にたけた企業が昨今の半導体市場を牽引(けんいん)していることからも、今後もファブレス企業は増えると予想されます。
日本の半導体が「世界市場シェア0%」を回避するために必要なこと
——苦境に立たされる日本の半導体産業ですが、今後どのような方向にかじを切るべきでしょうか。
牧本 政府や業界のトップ、アカデミアの専門家に考えてほしいのは「日本は半導体の変化する潮流に対応できるのか」という点です。経済産業省が2021年6月に公開した資料「半導体・デジタル産業戦略」を見ると、「2030年、日本の半導体シェアは0%になるかもしれない」という衝撃的なことが記されています。もはや一刻の猶予もないのです。
「半導体シェア」には二つの種類があります。一つは「半導体デバイス出荷」の市場シェアです。かつて50%に達していた日本半導体の出荷シェアは、2024年5月時点で約9%まで低下しています。一方、半導体最強の国といわれる米国の世界市場シェアは50%を誇り、その差は歴然です。
もう一つのシェアは、「ウエハー生産能力」のシェアです。ウエハー生産能力とは「国内に半導体の工場をどれだけ持っているか」の目安を示したものです。米国の生産能力シェアは相対的に小さく、約11%しかありません。米国は半導体デバイスの出荷量に対し、ウエハーの生産能力が低いのです。なぜかと言えば、生産の大部分を台湾など海外に委ねているからであり、これが大きなリスクになっています。
そのリスクとは台湾有事による地政学的リスクです。台湾を喪失してしまうと半導体の生産が止まってしまうため、米国はリスク解消に向けて懸命に動いています。数兆円を投じて国内生産の能力向上に努めているのです。
一方、日本に目を向けると、ウエハー生産能力シェアは約13%であり、出荷シェアの9%と比べて相対的に見て低いとはいえません。日本の深刻な問題点は米国と大きく異なっており、出荷シェアが低く、将来はゼロになるかもしれない、という懸念すらあります。その原因の一つが「国内需要の低さ」にあると考えています。
1980年代には家電産業が盛んで、半導体を使う企業が国内にたくさんありました。世界の需要の4割が日本にありました。今ではそのような企業が少なくなり日本の需要は世界の1割以下となっています。日本の出荷シェアを上げるには国内で大量に半導体を使う産業を振興して、それを支えるファブレス企業を増やさなければいけません。
——国内需要を増やすためには、どのような可能性が考えられますか。
牧本 日本に一番適しているのはロボット産業を振興することだと思います。少子高齢化のわが国ではAIを搭載した介護ロボットや救助ロボットには大きなニーズがあるでしょうし、AIを用いた自動運転分野の発展も期待できます。「賢くて人にやさしいロボット」をたくさん開発して、国内のみならず海外にも展開し、多くの人に使ってもらうことです。こうすれば国内での半導体需要が旺盛となり、半導体企業も元気が出てきます。
政府は半導体に関してさまざまな施策を打ち出していますが、重点は「ファウンドリなど工場の生産能力を増やすこと」にあります。これは地域経済の活性化には役立ちますが、半導体デバイスの出荷シェアが上向くことは期待できません。
今の日本が真に向き合うべき課題は「デバイス出荷シェア」の低下傾向に歯止めをかけて上向きにすることであり、そのためには「半導体を使う産業の育成」、そして「それをグローバルに展開する人材の育成」という2点だと考えています。
グローバル人材の育成は国内のみで行うことは難しいため、世界の上位大学への留学生の数を大幅に増やすことが必要です。日本は内向き志向から脱して、世界からもっともっと学ぶ必要があります。
■【前編】良好な関係だった日立とモトローラの提携、破談と熾烈な特許戦争を招いた「埋められなかった溝」とは
■【後編】元日立専務の「ミスター半導体」牧本次生氏が語る日本半導体「シェア急落の真因」(今回)
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:三上 佳大