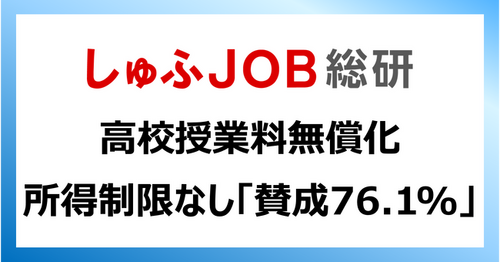「高校無償化」で公立の約半数が定員割れ…「大阪モデル」が地方の教育現場にもたらす"悲惨な現実"
2025年4月4日(金)9時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/10max
写真=iStock.com/10max
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/10max
■「高校授業料無償化」で保護者は喜ぶが…
所得制限なしの「高校授業料無償化」が、突如4月から始まった。公立高校の現場では怒りと諦めが交錯する。保護者は家計が助かると喜ぶ。両者の格差が著しい。なぜか。
保護者が喜ぶのは当然だ。高校進学を控える子供がいるならなおさら。無料(ただ)なのだから。公立/私立どちらを選ぶか。「設備が良い」「制服がかわいい」などは有力な選択肢になる。無論、私立に分がある。「総合的な探究の時間(総探)」で環境問題に取り組んでいるから公立を選んだ、なんて話はまず聞かない。そもそも「総探」が何なのか、認知度が低すぎて選択肢にすらならない。
「スクールバスでの送迎」——これも選択肢のひとつだ。筆者が住む福岡県内には、7路線でバスを走らせている私立高校もある。公共交通機関がない所にも送迎、と至れり尽くせりだ。
生き残りをかけ、私立高校の生徒募集は熾烈だ。少子化の厳しい中を戦う経営姿勢には恐れ入る。
私学系団体の猛烈な「ロビー活動」を目の当たりにしたこともある。
毎年11月頃、東京の自民党本部で次年度「予算・税制等に関する要望」の会合がある。同党組織運動本部と団体総務局が、衆参議員や省庁関係者とともに、複数の団体と意見交換を行う。私学系団体が多数参加。豊富な資料を基に、要望を伝える。
■私学の猛烈なロビー活動と「地方公立の危機」
日本私立中学高等学校連合会が「経常費助成費」や「ICT環境の整備」などの拡充強化を要望していた。「就学支援金」に関して「教育の実質無償化は道なかば」と強く訴える場面にも遭遇した。3年前だ。
「高校授業料無償化」は、民主党政権下で2010(平成22)年に始まった。高校での学習機会の均等化を図るため、授業料を公立高校は不徴収、私立高校に同等額を就学支援金として補助する。年11万8800円×生徒人数分が国庫から私立高校に振り込まれる。当時、「理念なきばらまき」と批判したのは自民党だった。
自公政権となって所得制限を設け、低所得世帯への支援を厚くした。ところが20(令和2)年に大幅改定。4月入学の私立高校生の場合、年収590万円未満世帯に、年39万6000円の給付となった。
この改定で福岡の公立高校の志願倍率は1.15倍(前年比0.04減)に。中でも筆者の住んでいる筑豊地区は0.85倍(同0.11減)で、地区内11校中9校が定員割れを起こした。一方、福岡県私学協会は、「私立高校授業料実質無償化」と銘打ったテレビCMを連日放映し、私学専願は1477人と大幅増、多くの私立高校が推薦段階で定員を満たす。
■「103万円の壁見直し」の代わりに実現
その所得制限が、この4月から撤廃される。26(令和8)年度からは私立高校への給付額は45万7000円に引き上げられる。国が出すのだ、きっちり満額まで引き上げ、あとは「施設設備費」などで保護者から別途徴収、と考えるのは自然だ。経営不振の私学は外国人留学生を増やし、その分の授業料を国に賄わせればよい。建物あっての「建学の精神」なのだから。
文部科学省からのパブリック・コメントを聞かない。突然の「高校無償化は教育予算」で、「教育予算が増えることについては好意的に捉える」くらいの腹積もりなら、「(公的機関の)成果とはより多くの予算獲得である」(ピーター・ドラッカー)の言葉通り、お役所対応としては正解かもしれない。
今回の経緯については、『週刊新潮』3月6日号が詳しい。
「今回、自民は維新と国民民主党を天秤にかけました。国民民主党が主張する103万円の壁の見直しには7〜8兆円が必要です。その点、維新の高校無償化は約5500億円の財源で済むと考えた。自民は予算と引き換えに、より政策コストのかからないほうを選んだ」とは政治アナリストの伊藤惇夫氏。
自民(というより首相)は「予算と引き換えに」教育を犠牲にした。では日本維新の会はどうか。
写真=時事通信フォト
2025年度予算案修正を巡る合意文書に署名し、撮影に応じる自民党総裁の石破茂首相(中央)、公明党の斉藤鉄夫代表(右)、日本維新の会の吉村洋文代表=2025年2月25日午後、国会内 - 写真=時事通信フォト
■「先行実施」した大阪では約半数の公立高校が定員割れ
「家庭の経済事情によって教育の機会が制限されることはあってはなりません、幼児教育から高等学校までの教育無償化を目指し、すべての子どもたちが平等に学び、未来を切り拓ける社会を実現と、すべての世代が安心して暮らせる社会の実現」を目指す、その言や良し。文字通り「家庭の経済事情によって教育の機会が制限される」家庭に配慮し、「所得制限」を設けるならわかる。しかし「所得制限のない」高校無償化を維新の地元・大阪で先行実施した昨年度、公立高校の半数近い70校が定員割れ。今年度も同様の状況だ。
さらに「3年ルール」。大阪府は12(平成24)年成立の府立学校条例で、3年連続定員割れした学校を再編対象にした。「学級減」ではなく「再編対象」だ。すでに10年で17校が閉校している。吉村洋文知事は、この高校無償化を「全国でやるべき」と公言、衆院選の公約にも据えた。実証済みかつ現在進行形なのが、公立高校の解体劇だ。
吉村知事は先日、府立高校の定員割れを報じるメディアに、「公立だけじゃない。私立も半分が定員割れ」と息巻いていた。「府」知事なので公立存続を心配するのかと思いきや、「私立も半分」と息巻く。なるほど知事所管の私学への目配りを忘れていない。だが「公私の棲み分けが理想」とはならない。
■教育に「効率」を持ち込んでいいのか
維新は公約の「教育分野においても市場原理の下で多様なプレイヤーの競い合いによる質の向上を目指」すという新自由主義的発想で、過度の競争をあおる。水道でも教育でも「公」につながるものを見つけ次第、「効率」を前面に打ち出す。
「3年ルール」もそう。公/私ともに「存続」ではなく、結果「閉校」に追い込む。たしかに「少子化だから統廃合」のほうが安くつく。だが定員割れの学校(生徒、教職員、同窓生、地域)を心配するという思考回路が働かない。ノスタルジックな感傷に浸っている場合か、努力不足の結果が定員割れ、という発想のようだ。この思考経路には教育哲学が欠落している。新自由主義的発想には恐れ入るばかりだ。
ここ数年、少子化をめぐって公/私間で生徒の獲得競争は過熱気味。温度差もあり、私立高校の少ない地方ではピンと来ない。東京のように私立学校の数が多く、もともと私立志向の高い地域もある。それでも少子化で学校を統廃合せざるを得ない地方自治体は、確実に増えている。
競争自体は大切だが、「市場原理の下」の競争が「質向上につながる」という乾いた発想が、いかに「教育本然」の姿からかけ離れているか。
定員割れした大阪府立寝屋川高等学校=2007年7月2日(写真=Bakkai/CC-BY-SA-3.0-migrated/Wikimedia Commons)
■企業経営と学校経営の「決定的な違い」
「教育」は語りやすい。誰しもが経験済みのため、個人の事績を基に語れる。一方で語りにくい。各々の経験が多岐にわたり規模が巨大、個人の一生、国家の命運を左右するため深淵すぎて語るに困難。よって的を絞って声低く語るしかない。
私見では、今回の件の背後には、「経営」に関する捉え方のズレがある。
「スピードスケート」と「フィギュアスケート」は同じ「スケート」だが、土俵は氷上でも同列に勝敗を比べられない。同じ「経営」でも「企業経営」と「学校経営」とでは、「不採算部門」の取り扱いが違う。
民間企業は不採算部門を抱え込むわけにはいかない。倒産するからだ。公立学校は不採算部門を抱え込んでも倒産しない。赤字解消に努め、どうしようもないなら、乱暴な言い方だが、企業なら不採算部門を切り捨てればよい。
公立高校ではそうはいかない。部活動で○○部の大会実績が悪いから廃部とか、停学者が出た△△クラスは廃止、とはいかない。成績が悪いから、反抗的だからといった理由でその生徒を切れない。授業が下手、といった理由でその教員を減給にもクビにもできない。不採算部門を丸抱えにしたまま行わねばならないのが、学級や学校の経営だ。
■学校という組織の「ゴール」とは
さらにいえば、公立高校の経営者(=学校長)には「人事権」と「給与決定権」がない。不採算部門を抱えたまま、「人事権」「給与決定権」を持たない経営者が、学校経営にあたらねばならない。
では、不採算部門丸抱えのまま、「人事権」「給与決定権」がない学校という組織のゴールは何か。生徒たちを前に日々株価の動向や売り上げを気にする職員のいない、損得勘定抜きの風土の中、学校経営や学級経営が行われる。生徒指導や教科指導などを通じ、子供たちの個人的成長と、社会人としてのルール・マナーの修得が経営目標だ。
昨今では公私ともに校則は批判を浴び、子供を叱ればSNS上で責められ、不登校、いじめ、自殺は増加、日本語のできない外国籍の子供もおり、教員の数が足りない中、学校経営は行われる。公立はさらに「人事権」「給与決定権」がないまま不採算部門を丸抱えの経営を余儀なくされる。私立との条件がそもそも違う。「スピードスケート」と「フィギュアスケート」とでは勝敗を比べようがないのだ。にもかかわらず政治が同じ土俵で競わせるよう仕向ける。
写真=iStock.com/coffeekai
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/coffeekai
■教育は「サービス産業」ではない
「教育とは流れる水に文字を書くようなはかないものである。だがそれを巌壁に刻みこむような真剣さで取り組まねばならぬ」(森信三)が「教育本然」の姿だ。「師道を興さんとならば、妄りに人の師となるべからず、又妄りに人を師とすべからず。必ず真に教ふべきことありて師となり、真に学ぶべきことありて師とすべし」(吉田松陰)が教師に課せられた使命だ。
教育はサービス産業ではない。「市場原理の下で多様なプレイヤーが競い合」う場でもない。個人の一生、国家の命運を左右するため、やりがいと恐ろしさとが身に染みる仕事だ。流れる水に文字を書くようなはかない業は、単にやる気だけでも成り立たない。「日本人」としての人材育成を図る公教育は、「国家観」「使命感」が経営指針になる。「妄りに人の師となる」わけにはいかず、「妄りに人を師とする」わけにもいかない。
「少子化対策→学校の統廃合」という粗雑な発想を、地方「叢生(そうせい)」を推進する政治家が、場当たり的に取り上げたのが今回の愚策だ。その際、語りやすい「教育」という言葉を用いたため、「教育本然」の姿が隠れた。
■なぜ「現場の声」を無視するのか
公立高校の現場の声を拾えば「また公立つぶし」と怒り。「今に始まったことではない」と諦め。大阪の話を聞いて「うちもなくなるのか」と悲嘆。
「経済的に厳しい家庭には仕方ないが、富裕層に使う必要があるのか」「英検の検定料に充ててほしい。無料で全員受検させている私立高校もある。模試と違い検定だから子供たちも必死。ところが公立には家計が厳しくて受けたくても受けられない生徒がいる」「不登校対策に充ててほしい」「教員確保に」「不妊治療に」「老朽化した設備の建て替えに」「温水便座に」「校舎内の託児所設置に」「まだ空調のない特別教室や体育館に空調設置」等々。
続出するこうした現場の声を聞くこともなく、予算通過のためだけに、「理念なきばらまき」がまた行われた。
■このままでは「教育の二極化」が進んでしまう
政治家に、国家を、地域を担う有為な人材を育てるという教育哲学がない。ないまま、「効率」の観点から公教育にちょっかいをかけるなら、失われた30年は40年になるだろう。
今後、「定員割れ→統廃合」が相次ぎ、生き残った学校に不合格なら、高校が皆無の地域には中卒者が残る。機会均等のために公金をばらまいた結果、二極化が進み、全体主義の萌芽する土壌(=中間層不在)が地ならしされる。公立高校の現場では行く末が肌感覚でわかる。だから「怒りと諦め」が交錯する。
自民党はかつて大規模小売店舗法を廃止、地方の商店街を廃墟にした実績がある。そこに大型ショッピングモールが叢生した。シャッター通りは自民と民主の合作だった。今回は自公と維新の合作で廃校作り。元公立高校跡地にはセイタカアワダチソウが豊かに実る。地方「叢生」も近い。
写真=iStock.com/vicm
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/vicm
教育は大切と自認する政治家の方々に尋ねたい。失われた50年後の世界地図に日本は載っているのか。
----------
山内 省二(やまうち・しょうじ)
福岡教育連盟 執行委員長
1967年福岡県北九州市生まれ。1985年福岡県立小倉高校、1991年広島大学文学部卒。読売新聞西部本社記者を経て、1993年福岡県立直方高校教諭に。県立鞍手高校教諭、県教育センターの長期派遣研修員を務め、2009年から県立嘉穗高校教諭。2020年から現職。
----------
(福岡教育連盟 執行委員長 山内 省二)