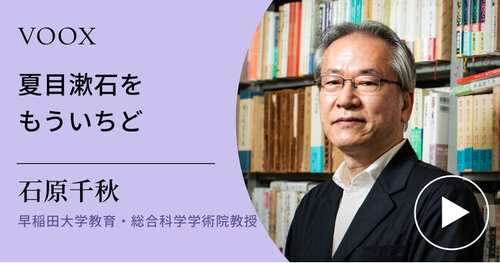「まともな高等教育をしているのは慶應義塾ただ一つ」と豪語…福澤諭吉の著作が教える「私立学校」本当の意義
2025年4月6日(日)10時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mizoula
※本稿は、内田樹『沈む祖国を救うには』(マガジンハウス新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/mizoula
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mizoula
■「教えたいこと」があるから教育活動を始めた
神戸女学院は、明治8年創建なので、もうすぐ150年になります。アメリカからやってきたタルカットとダッドレーという二人の女性宣教師が神戸で開校した小さい塾から始まりました。
この二人の宣教師はサンフランシスコから船に乗って太平洋を横断して日本に来たわけですが、出航時点においては、まだ日本ではキリシタン禁制の高札が掲げられていました。「社会のニーズ」どころではありません。「来るな」と言われている土地に来たのです。
それはこの二人の宣教師には、どうしても教えたいことがあったからです。伝えたいことがあったからです。そうやって神戸で小さい学塾を始めた。そこに少しずつ、惹きつけられるようにして子どもたちが集まってきて、だんだん大きな学校になり、150年が経っていました。建学の時点において、日本社会のどこにも「こういうような教育をしてください」というニーズはなかった。それでも教育活動を始めた。学校教育というのは本来そういうものなのです。市場の需要に応えて、教育商品を提供したわけではなく、教えたいことがあるから教えに来たところから始まるのです。
■市場のニーズに合わせるのが教育ではない
日本の大学は75%が私学ですが、私学は「教えたいこと」がまずあって創建されました。「どこもやっていない教育」をしたかったからです。他にやっているなら、別に身銭を切って新しい学校を建てる必要はありません。まず建学者の強い意志があり、それが学校を創り出した。
しかし、90年代から、もう教育者たち自身がそういう考え方をしなくなりました。その時期から教育を語るときにビジネス用語が頻用されるようになりました。「マーケットのニーズに対応した教育プログラム」とか「保護者や生徒に好感されるカリキュラムの展開」とかいう言葉を教授会でぺらぺらと言い出す人が出てきた。さらには「質保証」とか「工程管理」といった工学の用語で教育を語る人まで出てきた。
そのとき僕ははげしい違和感を覚えました。それは違うだろうと思ったのです。市場のニーズに合わせて教育するのではなくて、「教えたいこと」を教えるのが私学なんじゃないかと思ったからです。
■福澤諭吉の『福翁自伝』に「社会的なニーズ」への配慮などない
例えば、慶應義塾は「私学の雄」ですが、福澤諭吉の『福翁自伝』を読むと、「社会的なニーズ」への配慮などかけらほどもないことがわかります。彰義隊の戦争のさなかに、江戸中が火の海になるかというときにも福沢諭吉は世の中にきっぱりと背を向けて英書を読んで経済学の講義をしている。徳川時代の藩校はもはや教育機関として機能していないし、明治政府にはまだ学校をつくる余裕がない。いやしくも今の日本を見回して、まともな高等教育をしているのはわが慶應義塾ただ一つである。そう福澤は豪語するのです。人々が右往左往している中で、われわれはひとり悠々と学問を講じている。社会の目先のありようとまったく関係ないことをしている。僕はこの福澤の非社会性こそが私学の基本にあるべきだと思います。
福沢は若い頃に大阪の適塾にいて、ひたすらオランダ語の文献を読んでいました。哲学書を読み、工学や化学の書物を読み、医学や薬学の書物を読み、とにかくオランダ語で書かれている文献を片っ端から読んだ。もちろん、オランダ由来の知識や技術についての「ニーズ」があるから読んでいるわけではありません。意地で読んでいる。「こんなにややこしいもの」を読んでいるのは日本広しといえども、われわれしかいない。そういう自尊心から読んでいる。
写真=iStock.com/Viorika
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Viorika
■「一体何をやっているんだ」と言われる教育の気概
それはエリート意識というのとはちょっと違います。エリート意識というのは、すでに支配階級に席がある人間が持つものだからです。適塾の貧乏書生たちは権力とは無縁です。時流にきっぱり背を向けて、金にもならないし、出世にも結び付かない学問をしている。そんな変なことをしている俺たちは「ただものではないぞ」という苦しまぎれのプライドだけを支えに貧しさや飢えに耐えて学問をしている。
学ぶ人間の気概というのは、本来そういうものではないかと僕は思います。「日本広しといえども、『こんな変なこと』を研究しているのは我一人である」というような意地や痩せ我慢が知的な緊張を持続するためにはどうしたって必要なのです。
学校教育もそうなんだと思います。世の中とうまくなじんで、社会のニーズにぴったりと対応した教育をしているような学校にはなりたくない。そう腹を括って、世間からは「一体あんたのところは何をやっているんだ」と白眼視されるような教育をする。そういう学校側の気概は、在校生にも卒業生にもきちんと伝わる。だから、「今の日本であんな変な教育をしている学校はわが母校しかない。だったら、守らなければ」という気持ちを在校生も卒業生も持つようになる。そういう形で僕は学校を続けていけばいいと思っています。
■「自由」は本来は教えるものではない
今日の演題は「教育と自由」というものです。でも、いきなり演題に文句をつけるのも申し訳ないのですが、「教育と自由」というのはそもそも食い合わせが悪いのです。「自由を教える」ということができるのか。主体性は教えられるか、自立は教えられるか、自由は教えられるか……。どれも本来は教えるものではない。自得するものです。
教えることはできないけれど、学校には、「自由」や「自主」や「自立」や「自在」を子どもたちが自得できる環境を整備するはできます。教育者としてできることのそれが最大限だと思います。子どもたちが「自由」を自得できるような環境を整える。あとは待つ。教育者にできることはそれだけではないかと僕は思います。
「教育と自由」について僕が言えるのは、さしあたりそれだけです。またのちほどこの演題に近いトピックに触れることができるかも知れませんが、とりあえずは、これしか僕には言えません。
写真=iStock.com/xavierarnau
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/xavierarnau
■韓国の講演で一生懸命に話を聞いていた「地元の高齢者」
実は、今日は高校生たちに「人口減の未来」をどう生きるかという話をするつもりで来ました。でも、来てみたら、聴衆はほとんどが大人の人だし、演題は「教育と自由」だし、予定がすっかり狂ってしまいました。でも、せっかく考えてきたので、ちょっとだけその話題について話をさせてください。
この学校がある地域でも、人口減ということが結構シリアスな問題になっていますが、僕は『人口減社会の未来学』という本で編著したせいもあり、人口減問題に関してよく講演依頼があります。先日も岐阜県のJAに呼ばれて、地方の人口減問題と農業の問題について語ってきました。どこでも言うことは同じです。
韓国からもお呼びがかかりました。僕は10年ほど前から、毎年韓国に講演旅行に行っています。一昨年は韓国の田舎のほうからお呼びがかかって、山の中の公民館のようなところで、50人ぐらいの聴衆を前に講演をしました。その時にいただいたテーマが「韓国における急速な人口減と地方の生き残り」というものでした。聴衆はほとんどが地元の高齢者でした。もちろん彼らは僕の名前も、何をしている人間かも知りません。でも、その人たちが実に一生懸命に話を聞いていました。
■韓国第2の都市「釜山」は中高年ばかり
どうして僕みたいな人間をわざわざ日本から呼んでそんな話をさせるのか。たぶん韓国国内には「地方の人口減問題と生き残り」について真剣に考えてくれる知識人がいないということではないかと思います。
韓国の合計特別出生率は0.78です。少子化が叫ばれる日本でさえ、1.20ですから、韓国の人口減のすさまじさが知れます。
首都圏への人口の集中が進んでいて、ソウル周辺だけで全人口の45.5%が住んでいるというデータがあり、この数字を講演や文章に何度か引用しましたが、さきほど最新データに更新しようと思ってチェックしたら、55.5%でした。1年間に10ポイント上がっている。今や若い人がいるのは、ソウル周辺だけなのです。
去年講演に行ったのは釜山です。釜山は韓国第2の都市で、日本でいうと京都や大阪のようなランクの都市です。感じのいい、カジュアルな下町なんですが、街を歩くと、出会うのは中高年ばかりで、街には若者がいない。子どもの歓声も聞こえない。
■この数年で大学4校が廃校になっている
釜山大学は国立ですからまだ残っていますが、まわりにあった大学が次々と廃校になっている。この数年間で大学が4校廃校になったそうです。若い人がソウルに行ってしまうからです。釜山大学は京都大学くらいのランクの大学ですが、志願者が激減して、入学偏差値が下がっており、今はソウル近辺の二流、三流大学の後塵を拝しています。
内田樹『沈む祖国を救うには』(マガジンハウス新書)
韓国の首都圏に人口が集中していることについて、日本ではあまり報道されていません。出産率が下がったことは時々ニュースになりますが、ソウルに人口が集中していて、地方が没落していることを大手メディアはあまり伝えたがらない。
これは現代日本における人口減問題に対するメディアの姿勢の特徴だと思います。新聞もテレビも必ず「人口減問題」と言いますね。でも、これは正しくない。僕らが直面しているのは「人口減問題」ではなく、「人口一極集中問題」だからです。問題なのは、人口減少よりもむしろ人口の分布の偏りなのです。
同一国内に過疎地と過密地ができていること、それが問題なのです。人口がどれほど減っても、それが全国に均等に広がっていれば、今「人口問題」と言われている問題の多くは解決します。首都圏には今4400万人が暮らしています。東京、千葉、埼玉、神奈川の4都県だけに日本の人口の35%が集っている。しだいに韓国の人口集中に近づいています。
----------
内田 樹(うちだ・たつる)
神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長
1950年東京都生まれ。東京大学文学部仏文科卒業。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門はフランス現代思想、武道論、教育論など。2011年、哲学と武道研究のための私塾「凱風館」を開設。著書に小林秀雄賞を受賞した『私家版・ユダヤ文化論』(文春新書)、新書大賞を受賞した『日本辺境論』(新潮新書)、『街場の親子論』(内田るんとの共著・中公新書ラクレ)など多数。
----------
(神戸女学院大学 名誉教授、凱風館 館長 内田 樹)