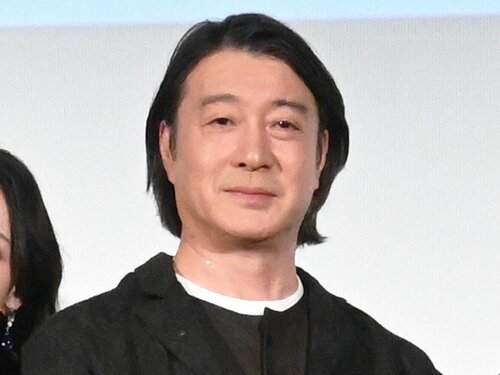完全攻略するのは万博会場より難しい…大阪駅の地下に「地元民ですら方向感覚が狂う迷宮」ができたワケ
2025年4月19日(土)10時15分 プレジデント社
大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」の「泉の広場」=2014年5月20日、大阪市北区 - 写真=時事通信フォト
写真=時事通信フォト
大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」の「泉の広場」=2014年5月20日、大阪市北区 - 写真=時事通信フォト
■大阪の地下街のすさまじいややこしさ
複雑な構造から思うように目的地にたどり着けず、世に「迷宮」「ダンジョン」と称される駅がある。そのひとつが、大阪(梅田)駅だ。
駅地下に広がる地下街は「梅田ダンジョン」とも呼ばれる。その総面積は約8万平方メートルと日本最大級。地下街ではないものの、地上に出ずアクセスできる4棟の「大阪駅前ビル」地下フロアを合わせると、面積はさらに大きい。
「関西・大阪万博」の開幕を前に、3月21日には「グラングリーン大阪」の南街区が開業した。グラングリーン大阪が位置するのは、もともと貨物駅があった「うめきた」エリアだ。関西最後の一等地とされ、2027年の全面開業に向け、さらなる開発が進む。地下・地上ふくめ、梅田ダンジョンの複雑性はまだまだ高まり続けているのだ。
撮影=プレジデントオンライン編集部
再開発が進む大阪駅前の「うめきた」エリア - 撮影=プレジデントオンライン編集部
筆者は関東に住んでおり、同様に複雑とされる新宿や渋谷に行く機会も多い。その慣れもあるだろうが、実際に梅田を歩くと確かにダンジョンと呼ばれる理由も分かる。
例えば新宿であれば、代表的な地下街の新宿サブナードや京王モールは一直線な道になっており、方向も分かりやすい。近年では駅構内に東西自由通路が通り、移動しやすくなった。
一方、梅田の地下街はとにかく方向が分からない。直角に交わる道も当然あるがラウンドアラウンドや三叉路のようになっている部分があり、東西南北のどちらに向かっているのか、混乱した。
■前に進んでも後ろに進んでも大阪駅
方角だけでなく、自分が今どのフロアにいるのかも分かりにくい。地下街は運営会社によって、「ホワイティうめだ」、「ディアモール大阪」、「ドージマ地下センター」、「阪急三番街」などありややこしい。
さらに、ところどころにちょっとしたスロープがあり、微妙に上ったり、下ったりする。厳密には地下街ではないが、大阪駅前ビルの地下1階を歩いていると、窓越しに下を通る通路が見え、地下を歩いているのに地上を歩いているかのように錯覚さえする。
極めつきは駅の多さである。JRの「大阪駅」と大阪メトロ御堂筋線「梅田駅」に加えて阪急、阪神にそれぞれある「大阪梅田駅」、さらに大阪メトロ谷町線「東梅田駅」、同四つ橋線「西梅田駅」、地下街を進むとJR「北新地駅」といくつもの駅が存在する。
それぞれが点在しているだけでなく、改札も複数あるのがまた難しい。大阪駅を背にして進んでいたはずが、ある場所では戻る方向と進行方向のいずれも「大阪駅」と指す案内板があって混乱した。
日本人だけでなく、インバウンドも混乱しているようだ。歩いていると、韓国人の2人組に「京都に行きたいのですが、どこに行けばよいのですか」と聞かれた。JRの改札は目と鼻の先にもかかわらず、駅構造が複雑すぎて思うように目的地にたどり着けなかったようだ。
写真=iStock.com/Mirko Kuzmanovic
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Mirko Kuzmanovic
■梅田の意外な由来
その複雑性を受けて「攻略サービス」も生まれている。先駆けが2010年に開始したWebサービス「うめちかナビ」だ(現在はサービス終了)。地下街を管理する企業が始め、改札や店舗など目的地までの経路を表示するもの。2016年には立命館大学の研究室がスマホアプリを開発していた。
2014年にスタートしたのが「梅田まち案内エスコート」。地元商店街などからなるキタ歓楽街環境浄化推進協議会が実施しており、もともとは違法な客引きやぼったくりの撲滅を目指して開始したという。
それにしても、このような迷宮はどのように生まれたのか。
梅田地下街の歴史に詳しい、立命館大学の加藤政洋教授に聞いたところ「研究している身でありながら、久しぶりに行くと迷ってしまうのが梅田の難しさです」と笑いつつ、歴史を説明してくれた。
現在の大阪駅周辺はかつて都市の外縁部にあたり、「湿地」でもあった。梅田の由来はその湿地を埋め(梅)た(田)場所という説もある。なんばや心斎橋のような繁華街ではないので、市街地を破壊せず土地を取得できたことから鉄道駅の立地として目が付けられたのだ。
加藤教授によると、戦前に地下鉄の御堂筋線が建設され、その一環として地下道などの整備が進んだ。その結果、1942(昭和17)年までに国鉄大阪駅の中央口から地下鉄・阪神を結ぶ「梅田地下道」が完成した。梅田の地下街はもともと地下道だったのだ。
■なぜ地下に飲食店が集まったのか
構想段階では単なる通路ではなく、両側に売店などを設置する見込みもあったという梅田地下道だが、戦災もあって商業化の工事は中断。戦中は防空壕、戦後は戦争で身寄りを失った人たちが生活するシェルターとして機能していた。闇市などもあったという。
その後、管理者である大阪市が1949(昭和24)年に悪質な業者を排除する目的で、新聞の立ち売り業者にのみ占有許可を出す。許可がない業者を排除したわけだ。
その一方で、同年には立ち食い串カツの「松葉」もオープン。1953(昭和28)年には串揚げ屋や居酒屋などが軒を連ねる「ぶらり横丁」も開業し、地下道に無秩序に散らばっていた人たちが徐々にゾーニングされていった。
筆者提供
ぶらり横丁の様子 - 筆者提供
「ぶらり横丁の存在は、近年の『横丁ブーム』の元祖ともいえます。もともとは地下道を占有していた人たちを“周縁”に追いやるのが目的でしたが、大阪らしい猥雑な空気を帯びた一角としてコアな人気を博し、その後は飲食店を横丁のように集積させる方式が地下街建設のモデルとなっていきました」(加藤教授、以下同)
当然ながら地上に比べて家賃の安さもあるだろう。このように「道」から「街」へと機能を移していった梅田地下道だったが、あくまで「道」。梅田の正式な地下街としては、1963(昭和38)年に大阪地下街株式会社のオープンした「ウメダ地下センター(現:ホワイティうめだ)」が嚆矢だ。さらに第2期、3期として拡大していき、堂島地下街(現:ドージマ地下センター)や阪急三番街も続いてオープンしたことで、国内随一の地下街が形成されていった。
■串カツ店の横に高級時計販売店
加藤教授によると、このように大阪地下街株式会社や阪急など複数の事業者が独自に開発を進めたことが、梅田地下街の複雑性を生み出すきっかけになっているという。「やってみなはれ」の精神、といったところか。
大阪駅の南側、阪神大阪梅田駅(地下駅)のすぐ南に「ダイヤモンド地区」と呼ばれるエリアがある。
Map data=OpenStreetMap/CC BY SA 2.0
主要道路に囲まれた五角形エリアで地上には高層ビルや大型建造物が立ち並ぶ一等地だ。ここを中心に、地下街とビルがいくつも接続されている点も、複雑性を高めていると加藤教授は指摘する。
「地下道は基本的に地上の道路に沿って掘られるので、本来は方向感覚をつかみやすいはずなんです。例えば同じ大阪でも、なんばの地下街は直線的で迷いにくい。対して梅田は『面を線で結ぶ』構造、かつ多層的です。これが方向感覚を失わせる一因になっているのではないでしょうか」
筆者提供
ぶらり横丁の様子 - 筆者提供
いくつもの事業者が比較的自由に“領地”を拡大し、単なる通路や飲食店エリア、物販エリアなどが無造作に接続されてきた梅田の地下街。
迷いやすくはあるが、その結果として串カツ店の横に高級時計の販売店が並ぶなど、カオスな街並みや猥雑な空気は大阪らしい、魅力の一つでもある。
■コントロールして生まれるものではない
しかし近年は「公」の介入が強まっていると加藤教授は話す。2010年代には、各地の名産品を狭小スペースで販売する店舗が並んでいた「アリバイ横丁」や先述のぶらり横丁が立ち退きを余儀なくされた。
「梅田地下街のカオスな魅力は、コントロールして生まれるようなものではありません。変化は必ずしも悪いことではありませんが、多様な店、人の個性が混ざり合っている梅田地下街の特徴が失われてしまわないか、危惧しています」(同)
なんば、道頓堀、心斎橋といった「ミナミ」の特徴が、織田作之助の『夫婦善哉』や、松竹、吉本の劇場を中心とした文化など大阪的な土着の雰囲気とすれば、他の都市との往来や大資本の開発で発展してきた大阪駅周辺の「キタ」は脱・大阪的な場所といえる。
現在は大資本による開発も相次ぎ「梅田一強」(加藤教授)ともいえる勢力を誇るが、歴史を振り返ると、大阪において商業や文化の中心地はもともとなんばだ。
対して梅田は都市の外縁部にあたり鉄道駅が立地したことで、賑わいの中心がミナミからキタへと移っていった。その中にありながら、地下街は逆行するように猥雑な雰囲気を増し、“ミナミ的”な土着の雰囲気をまとっていた。
加藤教授が指摘する通り、その場所性は徐々に失われつつある。超大規模の再開発が進む「うめきた」がキタエリアの北部に位置しているのは、偶然とはいえ面白い。
ややこしいことを言えば、中心地の「ミナミ」に対して大阪駅周辺の「キタ」はもともと都市の外れだった。その意味で、現在もっとも「キタ」の要素を残しているのが梅田地下街といえるだろう。
こう書いていると、梅田地下街は果たして「キタ」なのか「ミナミ」なのか、混乱してくる。うめきたの再開発に合わせて、どちらの要素が強まっていくのか。はたまた、全く異なる立ち位置に変貌していくのか——。まだまだ攻略は難しそうだ。
----------
鬼頭 勇大(きとう・ゆうだい)
フリーライター・編集者
広島カープの熱狂的ファン。ビジネス系書籍編集、健保組合事務職、ビジネス系ウェブメディア副編集長を経て独立。飲食系から働き方、エンタープライズITまでビジネス全般にわたる幅広い領域の取材経験がある。
----------
----------
加藤 政洋(かとう・まさひろ)
立命館大学文学部教授
1972年長野県生まれ。専門は人文地理学。著書に『大阪 都市の記憶を掘り起こす』(ちくま新書)、『酒場の京都学』(ミネルヴァ書房)、共著に『おいしい京都学 料理屋文化の歴史地理』(ミネルヴァ書房)などがある。
----------
(フリーライター・編集者 鬼頭 勇大、立命館大学文学部教授 加藤 政洋)