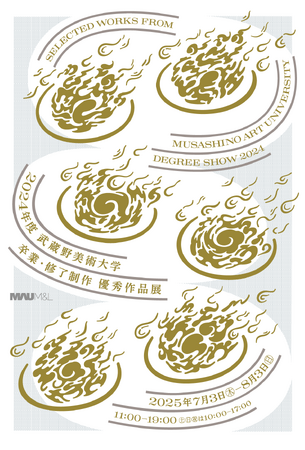【武蔵野美術大学 美術館・図書館】展覧会「2024年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作品展」の開催について
2025年5月20日(火)16時17分 PR TIMES
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-80b5df333cb7d3b7b5fc504e805fd2eb-1182x1749.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版1:「2024年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作品展」メインヴィジュアル(デザイン:大崎奏矢)
武蔵野美術大学 美術館・図書館では、約1年間の改修工事を経て、今年度最初の展覧会として「2024年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作品展」を開催します。
武蔵野美術大学では、学部卒業制作および大学院修了制作において、特に優れた作品や研究成果を発表した学生に対し「優秀賞」が贈られます。優秀作品展は前年度の約100名の受賞者の作品や研究成果を学科やコースを越えて一堂に展示する、1967年の当館開館以来続く展覧会です。
学生たちが在学期間中に取り組んできた制作・研究の集大成はいずれも秀作揃いであり、本学で実践される美術教育のいまが映し出されています。美術とデザインをめぐる、新たな世代の活力に満ちた作品を総覧することで、これからの表現の可能性を感じていただけますと幸いです。
概要
会期:2025年7月3日(木)-8月3日(日)
時間:11:00-19:00(土・日曜日、祝日は10:00-17:00)
休館日:水曜日
入館料:無料
会場:武蔵野美術大学美術館
主催:武蔵野美術大学 美術館・図書館
詳細:https://mauml.musabi.ac.jp/museum/events/22454/
本展の見どころ
美術館全体を使った展示
建築家・芦原義信(1918-2003)の設計により1967年に竣工し、藤本壮介(1971-)が2011年に改修を手がけた美術館棟全体のユニークな空間を活かして多種多様な作品を展示します。吹き抜けの開放的なアトリウムや大小5つの展示室、上映設備を備えた美術館ホールのほか、建物の外壁や図書館棟との連結部分であるテラスなど、普段展示ではあまり使われないスペースにまで作品を展開します。[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-b91024dcceddb17bf3de7f12db2b80e2-3000x2000.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版2[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-0a9ae0ef841eb97bc949f1ade886fb90-3000x2000.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版3[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-97113027ea0cbe74f433701c4ab696eb-3000x2000.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版4
図版2-4:「2023年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作品展」会場風景 2024年(撮影:稲口俊太)
総勢113名による多彩な表現
本学大学院修士課程(2科2専攻12コース)および学部(2学部12学科)の2024年度優秀賞受賞者113名による作品を展示します。卒業・修了制作展では鷹の台キャンパスと市ヶ谷キャンパス、通学課程と通信教育課程に分かれて発表された作品を、同時にご覧いただける機会です。絵画や彫刻、デザイン、工芸などの作品展示に加え、パフォーマンスやショー形式の作品は記録映像とともに紹介します。さらには実写映画やアニメーションなどの上映作品、プレゼンテーションや研究論文など、展示作品の表現形式は多岐に渡ります。
また、優秀賞受賞者には卒業・修了後に第一線で活躍する作家やデザイナーも数多く、展示作品はいわば今後の活動の萌芽とも言えます。彼らの新鮮な視点と柔軟なアイデアにご注目ください。
[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-5f5cb82c1a6012ccd1b873e74f64b5c1-1800x1201.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版5:島田涼平(造形学部 日本画学科)《方舟》[画像6: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-301a8831e5936f275cde179ef6ec37f8-1800x1201.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版6:浜崎真帆(造形学部 空間演出デザイン学科)《LOBBY》[画像7: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-e5555acf7c81445d47cce44bfe7a8914-1800x1200.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版7:野嶋慶乃(造形学部 デザイン情報学科)《棘の琴線》[画像8: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-e376723164937c90086ddba45e98b7f2-1920x1281.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版8:中本八尋(造形構想学部 クリエイティブイノベーション学科)《AIがつくる、あなたの「記憶」》
出品者による解説と教員による選評
各作品のキャプションには鑑賞のガイドとして出品者本人による解説・コメントと、担当教員による作品選評を記載しています。作品選評例(抜粋)
[画像9: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-b043d000ba753835ec9fac6fe99e28ed-1800x1201.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版9:繆 念何《when i tell a story》ミクストメディア(部分)繆 念何(大学院造形研究科 美術専攻 油絵コース)《when i tell a story》日々の必ずしも良いことばかりではない出来事に注目し、それらを積極的に昇華して人生を進めるため、ユーモアを交えたオブジェとして作品化してきた。修了制作においては留学生ならではの翻訳についての気づきと問題意識を作品化の原点とした。『創世記』を対象としながらその古今東西の翻訳についてまとめるうちに、それらについての彼女の感想を作品化していくようになる。『創世記』巡りのために展示コーナーに楽しく配置された作品は、『創世記』の翻訳とそれに関する彼女の驚きを含んだ感想と解釈の場となっている。共通感覚(コモンセンス)を着眼点としたユーモア溢れる彼女の魅力的な作品群は、鑑賞する人の価値観を穏やかに揺さぶる。選評:赤塚祐二(造形学部油絵学科教授)
[画像10: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-2475b024b693ceb11aafba1daebad572-1800x1201.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版10:工藤俊祐《日本語のリズムとタイポグラフィ》本、Webアプリケーション、モーショングラフィックス(部分)工藤俊祐(造形学部 視覚伝達デザイン学科)《日本語のリズムとタイポグラフィ》戦後の日本のグラフィックデザインは、西洋のデザインに羨望の眼差しを向け摂取するという歴史を背景に進展してきた。とりわけ前世紀までの書体制作は、ラテンフォントのようであれと、均質な組版のグレートーンをただひたすらに求めてきた。工藤の詳細な調査・体験・分析(日本の風土と日本人の生活、慣習、心象風景、身体性および視・聴・嗅・味・触覚に基づくリズム)と先進的なデジタル技術における具体的検証は、日本語組版における歪な濃淡こそが組版の本質であるとしたこれまでの感覚的な論を、「リズム」と仮定し、それを論理と科学で実証したものである。漢字・両がな、数字を交えて記される記述システムの意味を求めた根源的探求の成果がここにある。
選評:白井敬尚(造形学部視覚伝達デザイン学科教授)
[画像11: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/83551/170/83551-170-db2c8f9db48e3a6ef3011cca5c03357a-1800x1201.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]図版11:高野桜蘭《脈動》鉄、磁石、モーターなど高野桜蘭(造形学部 彫刻学科)《脈動》《抱擁》転がる石のように、とはどこかの歌手の曲のようだが、高野の石は転がらない。鉄は転がりそうだが、やはり転がらない。作品は、じっとそこに佇みながら何かをしているのである。重要なのは音という第四の存在だ。発生源は鉄だが、全体を見渡した時、鉄から音が聞こえることよりも音が存在していることに意識が向くと思う。音に存在=実感を与えるのは、石であり鉄である。二つの石は空間の圧力と踊っているようなフォルムをもち、さらりとした表面は私たちの視線をフォルムの先の方へと誘う。鉄は空間と組み合い、キュビスムかピクセルか、ごつごつと溶接された面が視線をとめる。その有りようが音を存在たらしめ、対する私たちの認識の解像度を上げる。
高野は形をつくることで、形とは違うものを空間に仕立てようとしている。関係性とか出会いとか、そんな言い方は生ぬるい。シンプルなこと-物を扱い、形をつくり、配置する-が複雑なことになる。それがこの作品の魅力です。
選評:冨井大裕(造形学部彫刻学科教授)
webサイト「武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作品集」では、過去の優秀賞受賞作品がご覧いただけます。
https://selected.musabi.ac.jp