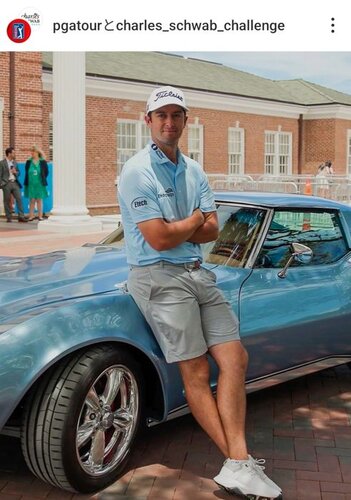いつまで男系男子にこだわるのか…皇統を守るには「女系天皇の可能性を排除すべきではない」
2025年5月23日(金)7時15分 プレジデント社
衆参両院正副議長、与野党代表らが出席した皇族数の確保策に関する全体会議=2025年4月17日午後、東京・永田町 - 写真=時事通信フォト
■「女性宮家の創設を」「夫・子も皇族に」
読売新聞が5月15日、安定的な皇位継承の確保を求める、皇室典範の改正に関する提言を大きく報じた。内容は①皇統の存続を最優先に②象徴天皇制維持すべき③女性宮家の創設を④夫・子も皇族に——という4項目である。①②は国民のコンセンサスをほぼ得ている。③④は皇統を安定的に存続させるため、女性天皇・女系天皇の可能性を排除すべきではないとの現実的な方策を示したものだ。国民世論も女性天皇・女系天皇を概ね支持している。
永田町では、自民党の保守系右派などによる男系継承維持論が根強く、2005年に小泉純一郎内閣が有識者会議の報告書に沿って策定した女系容認の皇室典範改正案は、悠仁さまご誕生もあって、お蔵入りしたままだ。
写真=時事通信フォト
衆参両院正副議長、与野党代表らが出席した皇族数の確保策に関する全体会議=2025年4月17日午後、東京・永田町 - 写真=時事通信フォト
現在の衆参両院議長の下での与野党協議でも、女性天皇・女系天皇の議論は回避され、①女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する②旧宮家の男系男子を皇族との養子縁組で皇室に迎える——の2案が議論の対象となっている。2案は2021年12月の岸田文雄内閣の有識者会議の報告書が基になっているが、①では配偶者と子は皇族としない②では養子本人は皇位継承権を有しない、と付記している。
各党・会派による与野党協議を経て、額賀福志郎衆院議長が25年4月に衆参両院正副議長の取りまとめ案を7月の参院選前に提示すると各党・会派に伝え、最終調整は首相経験者である自民党の麻生太郎最高顧問と立憲民主党の野田佳彦代表の非公式協議に委ねられている。
両氏の見解は、女性皇族が結婚後も皇室にとどまれるようにすることでは一致しているが、野田氏が女性宮家の創設を念頭に女性皇族の夫と子に皇族の身分を与えるよう求めているのに対し、麻生氏は戦後に皇籍離脱した旧11宮家の男系男子と結婚するケースに限定すべきだと主張し、合意のメドは立っていない。
■宮内庁参与は皇統の存続に危機感を抱く
話は7年前に遡る。宮内庁参与だった渡辺允(まこと)氏に2018年1月9日夜、東京・九段北の中華料理店に呼び出された。読売新聞に17年12月16日に載った以下のコラムを読んで、社会部を通じて、話がしたいとのことだった。
渡辺氏は、外交官を経て、1996〜2007年、天皇陛下の側近No.1である宮内庁侍従長に就いた。退任後も12〜20年に宮内庁参与を務めるなど、上皇ご夫妻の信頼が厚かった。22年2月に85歳で死去している。
7年前の当時は上皇陛下の退位の期日が決定したばかりだった。そして男系による継承を重視する安倍晋三首相が権勢を振るっていた。渡辺氏は、皇統の存続に危機感を抱く。
[補助線]皇位の安定継承のために
論説主幹 小田 尚
政府は8日の閣議で、天皇陛下の退位の期日を2019年4月30日と定める政令を決定した。改元は翌5月1日に行われる。
政府は、年明けから、光格天皇以来約200年ぶりとなる退位に向け、新元号選定や儀式のあり方を検討するという。
残る重要課題は、皇族の減少と高齢化が進む中、皇室制度をどう安定的に維持するかである。
■皇室典範特例法の付帯決議が求めるもの
天皇陛下の退位を実現する皇室典範特例法は、6月の国会で成立した。付帯決議で、「安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等」について、法施行後、速やかに検討するよう政府に求めている。
宮家は、「宮号」と呼ばれる家名で、結婚したり、独立したりする時に天皇から贈られる。秋篠宮や常陸宮がこれに当たる。
これに対し、野田内閣が創設を検討した「女性宮家」は、皇室に生まれた皇族女子が結婚後も皇室に残ることを可能にするもので、皇室典範の改正が必要になる。
皇族女子の結婚で皇籍離脱が続けば、皇族が分担している公務の遂行に支障が出てくる、という問題意識もあった。
付帯決議をめぐっては、民進党が「女性宮家」の速やかな検討を求めたのに対し、自民党は父方が天皇の血を引かない「女系天皇」につながりかねない、として女性宮家の明記に強く反発した。
このため、妥協の産物として、皇位継承と切り離す、と読める表現で決着した経緯がある。
写真=iStock.com/golaizola
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/golaizola
■万世一系は側室たちに支えられていた
だが、安定的に皇位を継承するには、女性・女系天皇や女性宮家を認めるべきか、という議論も早晩、必要なのではないのか。
2005年の小泉内閣の「皇室典範に関する有識者会議」は、女性・女系天皇に道を開く報告書をまとめた。側室制度が廃された以上、男系継承が行き詰まるのは時間の問題だという認識だった。
06年9月、秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さまが生まれ、議論が止まったが、これは問題から逃避したに過ぎない。天皇陛下の孫世代の皇族男子は悠仁さま1人だ。皇太子に就く段階で、宮家皇族がだれもいなくなる可能性もある。
皇統は、125代の今上陛下まで、一貫して男系で続いてきた。だが、政府資料によると、明治天皇以前の121代の天皇は、嫡出が66代、非嫡出が55代だった。万世一系の奇跡は、側室たちに支えられていたとも言える。
明治天皇も、大正天皇も、非嫡出だった。明治天皇は美子皇后のほかに5人の側室がいた。男子5人、女子10人が生まれたが、10人が早世し、男子で成人したのは、大正天皇のみだった。
1889年に制定された皇室典範(明治典範)では、非嫡出子も皇位継承資格を有した。「皇嫡子孫」「皇庶子孫」という言葉を用い、「嫡出ヲ先ニス」と規定された。1947年の現行典範では、嫡出子に限定している。
大正天皇の貞明皇后が男子4人を産んだこと、昭和天皇が側室を拒んだことが背景にあるが、戦後の社会倫理などが反映された。
■悠仁さまに頼り切っていいはずがない
安倍首相は、先月22日の参院本会議で、皇位の安定継承の方策を問われ、「男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、慎重かつ丁寧に検討する」と述べるにとどめている。
首相は、かつては、現行典範制定時に皇族の身分を離れた旧宮家の男系男子孫の皇籍復帰を検討すべきだ、という立場だった。
70年前に皇籍を離脱したのは、山階宮、賀陽宮など11宮家の51人で、男子は26人いた。今上陛下との関係は、600年前に遡る室町時代の伏見宮貞成親王を共通の祖先とするものだという。
首相の周辺からは「未婚の皇族女性が、天皇家の血筋の人と結婚されるといいが、簡単ではない」という声も漏れる。
女性宮家などについては「いざという時に考える」との定番フレーズで議論が先送りされようとしている。
現在の危機的状況は、悠仁さまが結婚され、男子が2人以上生まれないと、解消されない。悠仁さまと将来の妃(きさき)には相当なプレッシャーがかかるだろう。
悠仁さまには、昨年11月、中央道で紀子さまとともに乗っていたワゴン車が、乗用車に追突するという交通事故もあった。その時、首相もヒヤリとしたらしい。
天皇の地位は、憲法によって、「日本国民の総意に基づく」。国会も、憲法審査会などで安定継承の手立てを正面から議論すべきだろう。政治が、悠仁さまに頼り切っていいはずがない。
出所=「皇室典範に関する有識者会議 報告書」(国立国会図書館デジタルコレクション)
■「男系の主張は皇室を途絶えさせる」
その夜、渡辺氏は端的にこう語った。
「男系の継承を主張するのは、皇室を途絶えさせることになる。女系を認めるべきだ。どうやったら、そういう議論ができるのか」「女性宮家は、公務分担の観点からも必要だ」「あなたのような考え方の人がもっと増えたらいいのだが……」
記者は、読売社説が、小泉内閣の有識者会議がまとめた、女性天皇・女系天皇容認、第1子優先の継承、女性宮家設立という報告書の内容を「最善の方策」と評価して以来、基本的に立場が変わっていないことを説明し、引き続き女性宮家や女系天皇を支持していく考えを伝えたが、渡辺氏は「安倍さんはやる気がないだろうね」と、政治の動きを冷静に見ていた。
実際、当時の安倍首相は「旧宮家の男系の男性が、佳子さまのような皇族女性と結婚されるといいのだが、簡単ではない。皇族の女性たちは皆、皇室を出て自由になりたいからだ」と周辺に嘆いたり、「いざとなったら、愛子さまに摂政になっていただき、その間に後継を考えればいい」と呟いたりし、安定的な皇位継承に関わる政治判断を先送りしようとしていた。
安倍首相に限らず、政治家はそんな責任ある歴史的な決断をしたくないものだ。次代の政治家と国民世論に委ねるというのは、それなりに理解できるが、逃げてはいけない。
永田町と世論との乖離は広がるばかりだ。今上陛下が即位され、皇位継承権を有する男性皇族が3人に減少した時点の2019年5月の読売新聞世論調査で、皇位を安定的に継承させるために制度の「見直しが必要だ」とした人は67%に上った。皇室典範を改正し、女性天皇を認めることに「賛成」は79%に上り、「反対」は13%だった。女系天皇を認めることに「賛成」62%、「反対」22%だった。
■「朝日新聞かと思わず二度見した」
話を現在に戻そう。5月15日の読売の提言のポイントは、以下のくだりにある。
「皇統の存続を最優先に考えれば、女性皇族が当主となる『女性宮家』の創設を可能にし、夫や子にも皇族の身分を付与することで、皇族数の安定を図ることが妥当だろう」
「皇統を安定的に存続させるため、女性天皇に加え、将来的には女系天皇の可能性も排除することなく、現実的な方策を検討すべきではないか」
皇統には「本来、男系・女系の区別はない」(所功京都産業大名誉教授)ことが重要だ。
同日の社説では、こうも記されている。
「旧宮家の人たちは、戦後長く一般人として暮らしてきた。そうした人に唐突に皇位継承資格を与えて、国民の理解が得られるのだろうか。憲法は天皇の地位について『国民の総意に基づく』と定めている」
反響もあった。長島昭久首相補佐官は15日のX(旧ツイッター)で「何とも面妖な紙面でした。朝日新聞かと思わず二度見してしまいました」と茶々を入れた。
国民民主党の玉木雄一郎代表も同日、「女性皇族が結婚後も皇籍を保持し続けることを認める場合に、その配偶者や子にも皇籍を認めることとしている。これは政府の有識者会議の報告書とも異なる内容。読売新聞がこのタイミングで出してきた背景が気になる」と疑問を投げ掛ける。
立民党の野田代表は16日の記者会見で「インパクトのある提言を出して世論喚起、世の中に関心を持ってもらう意味で大きな貢献をしていただいたのではないか」と語った。
■「女系を完璧に否定していいのか」
今回の提言の内容は、突然示されたものではなく、以下の24年5月19日の読売社説の延長線上にある。
「皇族女子の配偶者と子を一般国民とした場合、政治活動や自らの意見表明が自由にできることになる。皇室の政治的中立性や品位を保てるのだろうか」
「旧宮家出身の男系男子の皇族復帰案についても、戦後長い間、一般国民として過ごしてきた人を皇族とし、さらにその子に皇位継承資格を与えることが『国民の総意』に沿うと言えるのか、慎重な検討が必要だ」
若干の重複を含めて引用したのは、旧宮家出身の男系男子復帰案の成否が、今後の議論の方向を決めていくとみられるからだ。
旧11宮家の旧皇族と子孫には久邇、賀陽、東久邇、竹田の4家系に、20代以下の未婚の男系男子が少なくとも10名いる、と読売新聞に報じられている。この中に皇族復帰の候補者はいるのか、どう意思確認するのか、最終的に国民世論が受け入れるのか、見通せないのが実情だ。
この皇位継承問題での石破茂首相の影が薄い。24年総裁選を控えた6月、BSフジ番組で「女系を完璧に否定していいのか」とし、女系天皇容認に前向きだった。8月のインターネット番組でも「男系の女性天皇の可能性、女系の男性天皇の可能性、これを全部排除して議論するのはどうなのか」と語っていた。
だが、首相に就任すると、10月8日の参院本会議で女系天皇を認めるかどうか問われ、「個人的な考えを今この場で申し上げることは差し控える」と、逃げてしまった。現在の与野党協議にも言及してはいない。
----------
小田 尚(おだ・たかし)
政治ジャーナリスト、読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員
1951年新潟県生まれ。東大法学部卒。読売新聞東京本社政治部長、論説委員長、グループ本社取締役論説主幹などを経て現職。2018〜2023年国家公安委員会委員。
----------
(政治ジャーナリスト、読売新聞東京本社調査研究本部客員研究員 小田 尚)