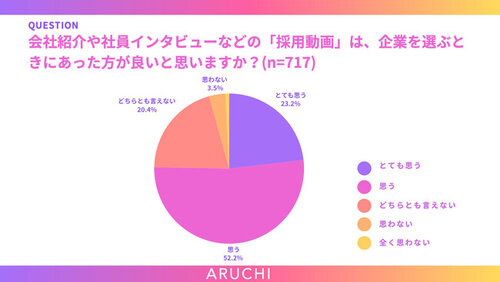「就職マッチングの実証実験」は軽視できない…「AIが人生を左右する」時代を前に人類に問われていること
2025年5月26日(月)8時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/georgeclerk
写真=iStock.com/georgeclerk
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/georgeclerk
■『サピエンス全史』ユヴァル・ノア・ハラリの警鐘
世界的ベストセラー『サピエンス全史』で知られるイスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリが、著名なテック系雑誌『WIRED』で受けたインタビューのなかで、なかなか興味深い話をしていた。いわく、馬やゾウが人間社会の仕組みを(かれらの知能や認知能力にとっては複雑で難解すぎるがゆえに)まったく理解できないまま人間によってその運命を握られ翻弄されているのと同じように、今度は人間がAIによって馬やゾウがいま置かれている立場になるかもしれないと。
私が最近WIREDで読んだ記事では、AIが宗教を作って聖典まで書いたうえに新しい暗号通貨の普及にまで関与したという話が紹介されていました。このAIの資産は計算すると4000万ドルに上るそうです。
もしAIが自らのお金を所有しその使い道を自分で決めたら何が起こるでしょうか? もし株式市場に投資を始めたら? つまり今後は金融の動きを理解しようと思ったら、人間の考えだけでは追いつかずAIの思考や意図も理解する必要があるのです。
AIは人間の理解を超えた発想をするかもしれません。たとえば馬はお金という人間の概念を知りません。私が馬をお金で売っても馬にはその状況がわかりません。お金を知らないからです。そして今度は人間が馬の立場になりつつあります。馬やゾウは自分たちの運命を左右する人間社会の仕組みを知りません。私たちの人生は高度で理解不能なAIネットワークによって決められるのかもしれません。
WIRED.jp(YouTube)『ユヴァル・ノア・ハラリが情報の未来をアップデート | The Big Interview | WIRED Japan』(2025年4月29日)より引用
■人間は「馬やゾウ」のような立場に置かれるかもしれない
AIが人間社会の制度設計や意思決定のレイヤーに深く関与し、私たち一人ひとりの日々の「営み」の方向性に大きな決定権を持つようになったら、私たちはたしかに、人間社会の仕組みに翻弄される(≒なにが起こっているのか主観的によくわからないまま自分の状況や運命が右往左往する)馬やゾウと同じような立場に置かれてしまうのかもしれない。
なぜAIが私たちにそのような道を示したのか? そのような選択を提案したのか? そのような判断を行ったのか? 私たちがそれを理解しようといくら思慮を巡らせても、進化したAIの思考の処理速度と到達深度と変数の複雑性はもはや人間の思考能力や想像力の限界をとっくに超えていて、なにもわからないに等しくなる。わけがわからないまま「この道に進みなさい。そうするのが最善だから」という最終的な“結論部分”だけを突きつけられる。
ある人の未来の姿について、本人の視点では完全に予測不能に見えても、だからといってAIにとってはそうとはかぎらない。AIなら人間がやれば途方もない年月がかかる膨大かつ複雑な計算を瞬時に行って“最適解”を見出しうる。そうして彼に選ぶべき(or 選ぶべきでない)道を指し示す。あるいは社会全体の幸福や安寧のために必要だと判断したなら彼がその次にとる行動をなんらかの方法で強制するかもしれない。
……というのが、ハラリの言いたいことだ。
■ハローワークでAIを活用した「就職マッチング」
少し前までの私ならハラリの未来予測を聞いても「なにを荒唐無稽なことを……」と一笑に付していたかもしれない。しかし世の中はあきらかに「AIがその人の未来(もっといえば運命)を予測可能な形に計算してみせる」方向に進んでしまっている。
AIがその人の未来を予測可能にして、そのうえで“最適解”を提案する——そのわかりやすい試みが、ここ日本ではじまろうとしている。
これまでAIといえば、文章を書かせたりイラストを書かせたりプログラムを組ませたりと、そういった用途で使っている人が多かっただろうが、いま国が導入を検討しているのは「その人にとって最適な仕事はなにかを数千万件に及ぶ膨大なデータをもとに計算して提案する」というAIだ。
ハローワークでの職業紹介業務を効率化し、職員の負担軽減を図ろうと、厚生労働省は2025年度、AI(人工知能)を活用した「就職マッチング」の実証実験に乗り出す。AIに過去のデータを分析させ、求職者の適性に合った仕事の提案を目指す。分析結果に偏りが出ることなども懸念されるため、まずは10カ所程度のハローワークで実験を行い、本格導入するか慎重に検討する方針だ。(中略)
今秋までに始める予定の実証実験では、過去約5年分の求職者約1700万人、求人約3200万件のうち、氏名や住所などプライバシーに関わる情報を除いた数年分のデータをAIに学習させ、どのような職歴や資格を持った人が、どういった企業に採用されたかなどを分析させるという。
読売新聞『求職者に「おすすめ度」をパーセンテージで提示、AIで適職マッチング支援…ハローワークで実験へ』(2025年3月24日)より引用
■「人間の運命」に食い込んできた
その人に最適な仕事を提案するAI——これはこれまでの用途とはかなりニュアンスが異なる。「踏み込んできたな」という印象を持つ。つまりなにが言いたいかというと、AIがいままでよりもずっと「人間の運命」そのものに食い込んできているということだ。
たとえば「仕事」というのは、現代人にとって人生のすべてを司るとまでは言わないまでも、その人が人生で見る景色を大きく決定づける要素のひとつであることは間違いない。その意思決定(≒その人のこれからの人生をもっともよいものにする期待値が高い仕事の選択)にAIが大きく関与するというのは、明らかにこれまでよりもずっと人間の「運命」の領域に踏み込んできている。
写真=iStock.com/georgeclerk
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/georgeclerk
AIは、ハローワークにやってきたその人を評価し人間では理解の及ばない複雑なアルゴリズムのもと、よりよい人生、よりよい未来を描けそうなプランを提供してきているわけだ。だが重要なことは、先述したように「この○○という仕事はどうですか?」とAIに提案された端末の目の前にいる人物は“なぜ”AIが自分にその○○という仕事を提案してきたのかについては、なにもわからないことだ。おそらくその客観的根拠や数理的処理のプロセスを理解することは皆目できないだろう。これはなるほどハラリのいう「馬」の状態に近い。
■論争を呼んでいる「殺人予測プロジェクト」
イギリスではAIが日本のこれよりずっと「その人の運命」に踏み込んだ形で活用されようとしている。「犯罪(殺人)予測AI」である。
〈「未来の犯罪者をAIが選別する」——そんなディストピア的構想が、イギリスで現実になろうとしている……〉
犯罪抑止の切り札か、プライバシー侵害と差別を助長する悪魔のツールか——イギリス政府が立ち上げた「殺人予測プロジェクト」が激しい論争を呼んでいる。
このプロジェクトは、警察や保護観察所から提供された個人情報をAI(人工知能)が分析し将来的に殺人を犯す可能性の高い人物を特定するもの。スナク前政権時に開発が始まり、現在は「リスク評価の改善を目的としたデータ共有」に名称変更されている。
ニューズウィーク日本版『「殺人予測AI」抑止か差別か、揺れる未来の犯罪防止プロジェクト』(2025年4月15日)より引用
映画『マイノリティー・リポート』やテレビドラマ『パーソン・オブ・インタレスト』あるいはアニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』などのディストピア的世界を彷彿とさせる現実がもうすぐそこまでやってきている。人が「これから良からぬことをする/良からぬことに巻き込まれる」可能性を、AIがその途方もない人間社会の織りなすカオスのなかから読み解き、導き出すのである。
写真=iStock.com/ipopba
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/ipopba
■「ロボット憲兵」が事態を“未然”に防ぐ未来
なんらかの犯罪が発生するよりも前に「予防」的に人間に干渉するというのは、人権侵害つまり差別と表裏一体ではないかという批判もある。そうした声を受けて今回のプロジェクトではあくまで「犯罪の前科前歴があるもの」を対象にしてデータを取るとイギリス政府はいう。だが、やろうと思えば全市民のこれまでの人生の記録やその行動観察から市民一人ひとりの「(潜在的)反社会性リスク/犯罪被害リスク」を計算することだって理論的には可能だろう。データを回収する範疇を刑務所の外に拡げればよいだけだからだ。
街のいたるところに張り巡らされた監視カメラや通信機器を傍受したり、あるいはソーシャルネットワークの膨大なログを解析して「これから犯罪の加害者/被害者になりそうな人」を割り出して、AIを搭載した屈強な外骨格を備えたさしずめ「ロボット憲兵」的な自律機構が駆けつけ事態を“未然”に防ぐ——そんな未来もいよいよ現実味を帯びてきている。
■「あなたは重大な犯罪加害者になりうる可能性が高い」
想像をしてみよう。早朝、家にいきなりやってきた「ロボット憲兵」に「近い将来、あなたは重大な犯罪加害者になりうる可能性が高いため、身柄を当局の管理下に置くことになりました」と言われた人がいたとして、その人はなぜ目の前のロボットやAIが“そういう答え”を出したのか、その途方もなく深く複雑な計算や予測をもとに見出された結論を自力で辿ることはできないだろう。AIが人間の脳では処理することが絶対に不可能なレベルの計算と予測のもとで、その人の目の前に憲兵を送ったのだから。
AIの計算能力や処理プロセスを人間がチマチマとトレースすることは不可能になり、人間にはAIが猛烈な速度と深度で計算しつくしたあとの「結論」部分だけが突きつけられる。「犯罪予知AI」が実際に導入された社会では、人間はただ理不尽にその身柄を拘束されることになる。社会全体の安全と安心、あるいはこれから被害者になるはずだった人の財産や生命を守るためにだ。……これもハラリがいうところの「ゾウ」そのものだ。
■「運命」と呼んでいた予測不可能性をAIがかき消す
人間がこれまで「運命」と漠然と——あるいは多少のロマンティックな陶酔とシニカルな自己憐憫を含めながら——呼んできたものは、じつは完全なランダムではなく「人間のアタマでは計算できないくらいに変数が多くて複雑だっただけ」だった。つまり逆にいえば、それを計算する能力があるのであれば「運命」は不可知の謎でもなんでもなくそのミステリアスなベールは剥ぎ取られ、たちまち丸裸にされてしまう代物だった。
私たちが「未来のことはわからない」「人生なんてなるようになるだけさ」などと半ば開き直りながら言っていたのは、本当の意味で真に未来が理論的に予測不能だったのではなく、ひとりの人間の人生の道のりに変化や分岐をもたらす変数とその変数の組み合わせによる影響の複雑な連鎖の往来を計算することが私たち人間の手に負えなかっただけだ。言い換えれば、それらを計算することさえできれば、私たちの運命の予測不可能性はどんどん収束していく。
写真=iStock.com/themacx
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/themacx
人間が運命と呼んでいたものの予測不可能性をAIがこれからかき消してしまう。膨大で複雑なアルゴリズムとその高速処理により、たとえば、私たち一人ひとりにとって最適な仕事を、最適な食事を、最適な生活リズムを、最適な治療を、最適なパートナーを、最適な生き方を提案することで。
■「たのしさ」が失われてしまう
これまではどちらかというと詩的で空想的でロマンティックなニュアンスを込めて語られてきた古典的決定論(※あらゆる自然法則を計算することができれば未来もあらかじめ予測可能であるとする考え方)的な世界がAIというテクノロジーによって現実化する——そんな未来が本当にやってくる。
こうした未来を素朴に歓迎する人がいるかもしれないが、私には人権や自由の観点以外にも懸念していることがある。
私たちの人生の「たのしさ」が失われてしまうことだ。
私たちの人生に主観的・体感的な「たのしさ」があるのは、その長い道のりを行くなかで、私たちにとって思いがけない喜びや幸福にときどき出逢えるからだ。ここで強調しておきたいのは、喜びや幸福と同じかそれ以上に“思いがけない”ことも「たのしさ」を味わうためには重要だということだ。私たちの人生に付きまとう予測不可能性もまた、私たちの人生の「たのしさ」を構成する重要なパーツだったのだ。
写真=iStock.com/Delmaine Donson
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Delmaine Donson
■「楽しく、自分らしく生きる」ことは難しくなる
AIが私たちのこれからの生き方や選択をなんでも見通して「喜びや幸福にいちばん出会いやすい道」を見出せてしまう世界は、一見すると「たのしさ」をも最大化してくれるような道を教えてくれると期待してしまう。しかしきっと、AIがなんでもお見通しの世界は、“つまらなく”なってしまう。そこに「思いがけない出逢い」がないからだ。偶然を装った予定調和が、私たちの日々を織りなしていく。
AIがなんでも先回りして最適な選択を選び、最悪のリスクを回避してくれる人生では「自分で道を切り拓いた」という実感を得ることがなにより難しくなる。そしてそれは私たちにとって「生きている理由」「生きがい」に直結している。人間社会はAIによって大きくブーストして、一人ひとりの暮らしの厚生は大幅に改善するかもしれないが、それにともない私たち人間が「楽しく、自分らしく生きる」ことの難しさは跳ね上がる。
■AIがどれだけ「関与するべきか」を決めるのは政治
ただひとつ、ここで留意しておきたいことがある。
AIが今後の進化の到達点によってあるひとりの人間の運命を丸裸にするポテンシャルを得たからといって、本当に人間の過去—現在—未来を丸裸にして、それをもとに人間の選択や決定に介入してよいかどうか、介入するとしてそれはどの程度まで“認める”のかを決めるのはまた別のレイヤーの議論だということだ。
AIが人間を馬やゾウに変えてしまうくらいの能力を持つようになっても、AIがどのくらい私たちの「運命」に関与する(べき)かを決めるのは最終的には政治になる。私たちはAIによって自分の運命をゆりかごから墓場まで見通され、必要に応じて介入を受けることを本当に望むだろうか? 少なくともAIが人ひとりの人生の折々における「最適ルート」を計算できるくらいに卓越する時代は間もなくやってくる。その時代の到来に備えて、人間側も考えておく必要がある。
「安心安全が完全に達成された社会」や、「ひとりの被害者も出さない社会」を目指すのであれば、人びとは混沌とした社会と隣り合わせの民主主義よりも、AIが万物を見通す目のように君臨する「やさしい監視社会」を受け入れるかもしれない。あなたはどうだろうか?
----------
御田寺 圭(みたてら・けい)
文筆家・ラジオパーソナリティー
会社員として働くかたわら、「テラケイ」「白饅頭」名義でインターネットを中心に、家族・労働・人間関係などをはじめとする広範な社会問題についての言論活動を行う。「SYNODOS(シノドス)」などに寄稿。「note」での連載をまとめた初の著作『矛盾社会序説』(イースト・プレス)を2018年11月に刊行。近著に『ただしさに殺されないために』(大和書房)。「白饅頭note」はこちら。
----------
(文筆家・ラジオパーソナリティー 御田寺 圭)