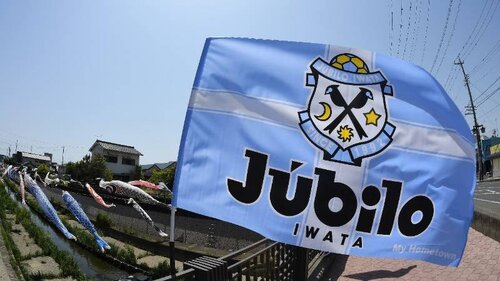SOMPO、ダイハツ、味の素…ブラジル駐在経験者が企業トップに就くケースが目立ち始めた理由とは?
2025年1月14日(火)4時0分 JBpress
「ブラジル」と聞くと、多くの読者はコーヒー、サッカー、サンバといったキーワードを真っ先に思い浮かべるのではないだろうか。ところが、現在のブラジルはそうした既存のイメージを覆し、グローバルサウスを率いる国家へと急成長を遂げつつある。とりわけ金融面では、独自に構築した電子決済システムで世界市場を狙い、日本以上にIT化が進んでいる。本連載では『ブラジルが世界を動かす 南米の経済大国はいま』(宮本英威著/平凡社新書)から、内容の一部を抜粋・再編集。フィンテック領域の躍進や日本企業との関係を中心に、国際社会において存在感を増している南米の大国の「いま」を探る。
第4回では、SOMPOホールディングス、ダイハツ工業、味の素など、国内大手企業においてブラジル駐在経験者がトップに就任する人事が目立ち始めた近年の傾向から、新興国におけるビジネス経験を通じて得られることを探る。
ブラジル駐在から企業トップに
2024年前半はブラジル駐在を経験した日本人経営者を取り巻くニュースが相次いだ。
SOMPOホールディングスは1月、奥村幹夫が社長兼最高執行責任者(COO)からグループCEOに昇任すると発表した。保険金を不正請求した中古車販売大手ビッグモーターとの取引問題からの再生に取り組む。奥村は「不退転の覚悟で企業風土の改革に取り組んでいく」と語った。
奥村はサッカーの名門である筑波大の蹴球部出身だ。元日本代表の長谷川健太が同級生で、後輩には中山雅史や井原正巳がいる。そうそうたるチームメートと共にボールを追いかけた後に、ブラジルに留学してサッカーだけでなく、語学の腕を磨いた。卒業後は旧安田火災海上保険に入社して同国に駐在した経験がある。
いったん退社して投資銀行に勤務した時期もあったが、09年に現在のSOMPOに復職したのはブラジルでの事業にかかわるためだった。同社が買収した個人向け保険マリチマの取締役として、再編を担った。南米安田保険との合併という利害関係者が多い難しい課題に取り組んだ。
14年にはサッカーのワールドカップ(W杯)ブラジル大会があった。サンパウロに駐在していた奥村は当時、日本サッカー協会の国際委員を務めていた。キャンプ地の選定などで協会関係者を手助けしており、社業の枠にはとどまらない活躍が当時の駐在員の間で話題だった。
奥村は帰国後に介護事業の責任者を務めていた際には自転車に乗って普段着で自社の施設を回る現場主義で知られ、海外保険子会社のトップとしては北大西洋の英領バミューダ諸島の駐在も経験した。21年12月、次期社長に決まった際の会見では「現場とコミュニケーションをとり、強い覚悟でチャレンジする」と述べていた。
2月にはトヨタ自動車で中南米本部長としてブラジルに駐在中だった井上雅宏が3月1日付で子会社であるダイハツ工業の社長に就任することが固まった。完成車の認証試験での大規模不正からの立て直しの指揮をとるためだった。
井上は2月の会見で「自身が現場に出向き、自分から話しかけ、信用してもらい、本音の話を聞くことから始めたい」と述べ、コミュニケーションを重視して組織改革に取り組む考えを示した。
井上はトヨタ入社から36年間の会社員人生の約半分を海外で過ごした。社内外から定評があるコミュニケーション能力の高さが売りだ。ブラジルでは現地社員から「Massa(マッサ)」の愛称で呼ばれ、堪能なポルトガル語で距離を縮めてきた。ブラジルの代名詞であるカーニバル(謝肉祭)にはサンパウロで踊り手として参加した経験もある。
3度目となる直近のブラジル駐在では、トヨタにとって大きな決断の遂行を迫られた。サンベルナルド工場(サンパウロ州)の閉鎖である。この工場は1962年、トヨタにとっては海外で初めて完成させた重要な生産拠点だった。60年の歴史の幕引きは地元にとっても重く、慎重な対応が求められた。
井上は労働組合、サンパウロ州、サンベルナルドドカンポ市などと粘り強く交渉を重ねた。当初は2023年11月の工場閉鎖前に、来賓やメディアを招いての式典を計画していたが、労働組合員の反発が強いと分かると修正を決断。販売会社や工場OBら少人数の関係者が参加する形式に切り替える配慮を示した。
日本企業の国際化が進み、新興国の駐在を経験した経営人材の重みは増している。SOMPOとダイハツの共通点は、不祥事に揺れる日本企業ということだ。豊富な海外経験で培ったコミュニケーション能力の高さに加えて、経済や社会の揺れ幅が大きい新興国について熟知した経験を組織再生に生かすことを期待された人事だった。
井上と奥村はサンパウロ駐在が重なった際には毎週のようにサッカーボールを追いかけた仲間でもある。両氏と頻繁にプレーしていた団体職員の井上徹哉は「優れたリーダーシップと明るい人柄は共通している」と話す。プレーでは「井上は堅実で正確なディフェンス、奥村は攻守に秀でた万能型のプレーヤー」なのだという。
ブラジルの駐在を経験した人材が経営トップとなることは、まだまだ決して一般的とはいえない。とはいえ、帰国後に本社で役員として活躍するケースは増えているように思う。日本製鉄の橋本英二会長兼CEOはブラジルに駐在して、同国鉄鋼大手ウジミナスの経営権を巡って、アルゼンチンの鉄鋼大手テルニウムと激しい交渉を重ねた。
日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)社長だった近藤正樹は、三菱商事の食品畑を歩み、コーヒーに詳しい。同社のブラジル法人トップ、ブラジル日本商工会議所会頭を経験した後に、出資先のKFCに転じ、業界団体の日本フードサービス協会(東京・港)の会長も務めた。
2代続けてブラジル経験者が社長の「味の素」
ブラジルの現地法人トップ経験者が2代続けて本社社長になった味の素のような例もある。2013年8月からブラジル法人の社長を務めていた西井孝明は15年6月、本体の社長に昇格した。
西井が6年務めた後、その後任として22年4月に社長を引き継いだのが藤江太郎だ。ブラジル法人でも西井の次の社長が藤江だった。味の素の場合、ブラジル法人の扱っている商品数の多さが、グローバルの責任者としての経営に役立つのだという。
味の素は当時、ブラジルをインドネシアやタイなどと並んで「5スターズ」として新興国の重点地域に位置づけていた。西井のトップ就任が決まった直後、サンパウロにある味の素のオフィスを訪れたことがある。
そこには、調味料、粉末ジュース、飼料用アミノ酸など多くの自社製品が並んでいた。「社員でも別事業にかかわっていれば製品名さえ知らない」。従業員が社長室を訪れた際に、自分が所属する部署以外の製品を知ってほしいとの願いがこもっていた。社内の風通しを良くしようとしてきた西井の方針を象徴するこだわりの部屋だった。
ブラジル時代の西井は社内向けに経営計画を説明する機会も新たに設けて、コミュニケーションを重視してきた。ブラジルは欧州やアフリカ、アジアといった世界各地からの移民で成り立ってきた国で、混血が進んでいる。「多様な価値観を当たり前に認め合っているからこそ、経営がフェアかどうかについての感度が非常に高い」と感じていた。
ブラジル法人の社長を務めていた約2年間で、普段は明るく接してくるブラジル人社員でも、西井を冷静な目で評価している印象を受けた。「ブラジルはグローバル味の素の縮図といえる。非常に良い経験を積めた」と振り返る。
ブラジル法人の社長から本体の社長への就任という事例について、ブラジル日本商工会議所で当時、事務局長を務めていた平田藤義は「聞いたことがない」と話していた。1967年からブラジルに在住し、ロームの現地法人社長を経験したブラジルでの日本企業の生き字引的存在の平田にとっても驚きのニュースだった。
日本企業の現地幹部からは「西井さんのプレゼンはすごく分かりやすかった。リーダーとしての資質を感じる」といった声を複数聞いた。同じ国に、同じタイミングで駐在していると、企業の枠を超えて、交流を深める機会が多い。ブラジルで働いていた「同僚」の出世に、自らの将来を重ね合わせたブラジル法人幹部も多かった。
2010年ころ、「シンガポール派」の伸長が話題を呼んだことがある。パナソニックの大坪文雄、三菱商事の小林健、旭化成の藤原健嗣という各社の社長は、いずれもシンガポールの現地法人の社長や支店長を経験して上り詰めた。「ブラジル経由経営トップ」という道が今後は一段と拓けていくことを願いたい。
<連載ラインアップ>
■第1回 メルカドリブレ、アマゾン、エリクソン…ブラジルのEC市場はどう急成長し、ネットは貧民街をいかに変えたか?
■第2回 ブラジルで人口の約7割が利用する電子決済「PIX」は、なぜクレジットカードを超えるほどの市民権を得たのか?
■第3回 「今後は銀行の実店舗が消える」ブラジル発のネット銀行「ヌーバンク」はいかにして南米の金融市場を変革したのか?
■第4回 SOMPO、ダイハツ、味の素…ブラジル駐在経験者が企業トップに就くケースが目立ち始めた理由とは?(本稿)
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
筆者:宮本 英威