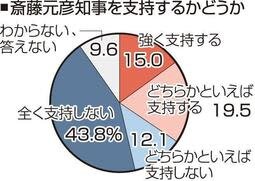「第三者委員会」のルーツは97年・山一證券自主廃業に。会計学者「死を宣告された組織を調べる現場に<第三者の目を入れる>知恵が生まれたのは皮肉なことで…」
2025年1月31日(金)16時40分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
企業や団体が不祥事を起こしたとき、外部の専門家に委嘱して設置される「第三者委員会」。本来は問題の解明や事実関係の明確化を図るための組織ですが、「第三者委員会報告書格付け委員会」に所属する会計学者の八田進二さんは「大半の第三者委員会は、真相究明どころか、身の潔白を『証明』するための<禊のツール>として機能している」と指摘しています。今回は八田さんの著書『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』より一部引用、再編集してお届けします。
* * * * * * *
第三者委員会のルーツとは
第三者委員会の仕組みは、いつどこで生まれたのだろう? 「問題を起こした組織や団体を、それと無関係の外部の人間が厳しく調査し、再発防止策も含めたレポートを提出する」というと、いかにも「欧米的」に感じられるのではないだろうか。
第三者委員会の報告書には、「組織のコンプライアンス欠如」を指摘するものが少なくない。そうした概念を普及、徹底させる仕組みとして、それらと同時に「輸入」されたように感じても無理はないのだが、実際は、そうではないのである。第三者委員会は、純然たる“メイド・イン・ジャパン”のスキームなのである。
その原点ともいえる「組織」が産声を上げたのは、1997年12月のことだ。97年というのは、一定以上の年齢の日本人にとって、忘れられない(あまり思い出したくない)1年かもしれない。
90年代初頭にバブル経済が弾け、くすぶり始めていた企業の不良債権問題は、この年の11月、三洋証券に始まり、北海道拓殖銀行、そして山一證券と続いた大手金融機関の破綻ドミノという想定外の事態で、一気に「見える化」された。
まさか大企業や金融機関が倒れるようなことはないだろうと思っていた人々は、日本経済がいかに深刻なところに追い込まれているのかを、初めて思い知らされたのである。国際的にも「暗黒の11月」と称された変事の中でも最も衝撃的だったのが、旧四大証券の一角を成す山一證券の自主廃業の発表だったと言えるだろう(結果的には自己破産)。
第一号は、あの山一だった
のちに「隆盛」を誇るようになる第三者委員会のルーツは、ほかならぬこのとき山一證券に設置された「社内調査委員会」だったのである。
設置の主目的は、新聞報道などで2000億円とも言われた、「簿外債務」すなわち損失隠しの実態究明だ。これが山一を倒した最大の病巣だった。
同委員会は、委員長には当時の嘉本隆正常務取締役が就き、その他取締役など社内の人間が7名、途中から社外の弁護士2人が加わるという形だった。だから、「名実」ともに、日弁連ガイドラインの第三者委員会には該当しない。
だが、この社内調査委員会が、例によってお手盛りの報告でお茶を濁すだけの組織だったかといえば、そうではなかった。
「社内調査委員会」二つの意義
同委員会は、翌98年4月に「社内調査報告書—いわゆる簿外債務を中心として—」を公表するのだが、実は社外弁護士の一人として調査に携わったのが、現在、われらが第三者委員会報告書格付け委員会の副委員長を務める國廣正氏である。
同氏は、著書『修羅場の経営責任』(文春新書)で、同委員会には二つの意義があった、と述べている(198~199ページ)。

(写真提供:Photo AC)
「一つは、山一の破綻に至る事実関係を、第三者的観点から、詳細かつ徹底的に調査、検証し、これを『社内調査報告書』という形で対外的に公表したということである。これは当時としては前例のない試みだった。
社内調査報告書の公表は、リスク管理不在、先送り、隠蔽、責任回避、官との癒着という巨大証券会社の経営実態を白日の下に明らかにした。加えて、本業そっちのけで財テクに走り、損失が発生すれば自分が『被害者』だとして損失補填を求める自己責任意識の欠如した顧客企業、『見て見ぬふり』をしながら最後には梯子をはずして引導を渡す『官』の実態も明らかにした。社内調査報告書は、うわさや評論としてではなく『事実』として、これらのことを明らかにした点に意味がある」
「第三者の目を入れる」という知恵
「もう一つの重要な意義」は、『誰が会社を潰したか』(北澤千秋著、日経BP社)からの引用である。
「『会社がすでに破綻しているからこそ日の目を見た調査報告書』『会社が潰れる前にこうした自浄作用を発揮すべきだった』という指摘もその通りである。
それでも、企業が社会的存在であることを自覚し、自らの手で破綻の原因と経緯を明らかにするという説明義務を果たそうとした姿勢は、素直に評価すべきである」
危機に瀕したというよりも、すでに死を宣告された組織を調べる現場に、「第三者の目を入れる」という知恵が生まれたのは、皮肉なことだった。ともあれ、この画期的な仕事が、その後第三者委員会という実務に発展していったのは、紛れもない事実なのである。
「とにかく真実を明らかにしたい」という思いから立ち上がった当時の第三者委員会は、十分社会的な意義を持っていた。それを認めるのに、やぶさかではない。
※本稿は、『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 「第三者委員会」とは誰のための存在か?会計学者「大半は真相究明ではなく追及をかわし、あくまで身の潔白を証明する<禊のツール>で…」
- 「日弁連ガイドライン」策定のきっかけ<フタバ産業事件>とは?会計学者「バブル崩壊の後遺症の中、第三者委員会とは名ばかりの調査報告書が目立ち始めて…」
- 「第三者委員会」の社会的な影響力が高まるきっかけ<オリンパス不正会計事件>とは?会計学者「東証まで救済のシナリオに参画した結果として…」
- 経営コンサル「ホリエモンのテレビ局買収が頓挫したのが、日本経済のターニングポイントと考える人もいるが…」<とりあえずの共通了解としてのテレビ局>の価値を考える
- 森且行「オートレーサーを目指した理由。SMAPの5人と出会えたから今の僕がある」