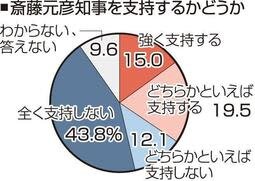「第三者委員会」の社会的な影響力が高まるきっかけ<オリンパス不正会計事件>とは?会計学者「東証まで救済のシナリオに参画した結果として…」
2025年1月31日(金)16時40分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
企業や団体が不祥事を起こしたとき、外部の専門家に委嘱して設置される「第三者委員会」。本来は問題の解明や事実関係の明確化を図るための組織ですが、「第三者委員会報告書格付け委員会」に所属する会計学者の八田進二さんは「大半の第三者委員会は、真相究明どころか、身の潔白を『証明』するための<禊のツール>として機能している」と指摘しています。今回は八田さんの著書『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』より一部引用、再編集してお届けします。
* * * * * * *
オリンパスは第三者委員会に救われた
残念ながら、日弁連ガイドラインが作られた後も、不十分な報告書の量産が続いている。しかし、第三者委員会自体の認知度、ある意味「ステータス」は、確実に高まってきている。
それを象徴することになる事件が表面化したのは、2011年7月のことだ。記憶に新しいオリンパスの不正会計事件である。
簡単に振り返っておけば、悪事の発端は、一部経営幹部がバブル期に行った本業とは無関係の金融商品への投資の失敗だった。その後、彼らは一千数百億円に上る損失を「飛ばし」という手法で隠蔽し続けた末に、企業買収費の水増しなどでその解消を画策したのだった。
隠蔽が過去20年間にも及んだこと、経営トップが主導した不正であったことは、強い衝撃を持って受け取られた。
当時の社長、副社長などが、金融商品取引法違反で東京地裁から執行猶予付きの有罪判決を受けたほか、長年の損失隠しを見抜けなかった二つの監査法人には、金融庁から業務改善命令が出された。
オリンパスが「監理銘柄」に
時間を戻すと、雑誌の記事を基に最初に事件を「告発」したのは、11年に社長に就任したマイケル・ウッドフォード氏だったが、これだけの巨額損失と、それをめぐる不正会計が事実だとすれば、それはオリンパス本体も大ピンチに陥ることを意味した。
「悪質で巨額、かつ長期の損失隠し」というのは、当時の東京証券取引所の基準からすれば、「上場廃止」に相当したからだ。
ちなみに、その5年前には、堀江貴文氏のライブドアがわずか50億円の粉飾で上場廃止になっていた。実際、11年11月10日、4~9月期決算を法定期限(11月14日)までに提出できない、と発表したオリンパスは、東京証券取引所から「監理銘柄」(上場廃止の可能性がある銘柄)に指定される。
こうした一連の事態に慌てたのは、当のオリンパスだけではなかった。「東洋経済オンライン」の同年12月20日付の記事が、当時の「裏事情」を語って余りある。
「(略)金融庁は『事態の鎮静化を図り、課徴金処分で済ませようと動いている』(大手監査法人幹部)。また『経済産業省や厚生労働省も、上場廃止や外資による買収などは、絶対させない意向だ』(外資系銀行幹部)。官主導の護送船団方式による“救済”の道筋が、用意されつつある」
要するに、低迷が続く日本のものづくりの中で、盤石の世界シェアを誇るオリンパスの内視鏡事業を外資に渡すなど罷りならん、ということである。
東証主導で第三者委員会が投入される
この「救済のシナリオ」には、上場の生殺与奪を握る東証自体も参画した。そして、筋書きに説得力を持たせるべく、東証主導で投入されたのが、第三者委員会という役者だったのだ。当時の東証斉藤惇社長の定例会見(同年10月28日)での発言を「ロイター」(同日付)は、次のように報じている。
「オリンパスは第三者委員会を立ち上げ事実関係を調べる方針をすでに示しているが、斉藤・東証社長は、第三者委員会の設置を東証が提案したことを明らかにした。第三者委員会について、オリンパス自らが委員の人選をする場合、その調査を信頼できるかについて斉藤社長は『日本では株主を守る法律の準備ができている』と述べた。オリンパスが意図的に有利な人選をすれば、最終的に株主代表訴訟という選択肢もあることを指摘した」

(写真提供:Photo AC)
甲斐中辰夫弁護士(元最高裁判事)を委員長とする第三者委員会が設置されたのは、同年11月1日である。そして約1ヵ月というスピード調査の末、12月6日、「調査報告書(要約版)」が公表される。
巨額の損失隠しが歴代社長をはじめとする「トップ主導で秘密裏に行われた」ことを認定するとともに、問題を見過ごした経営陣の一新や、関係者に対する法的責任の追及を求める内容だった。
さらにその後、同社は矢継ぎ早に「取締役責任調査委員会」、「監査役等責任調査委員会」を立ち上げて、前者は12年1月7日に、後者は同年1月16日に、それぞれ「調査報告書」を公表したのである。
上場廃止の危機を免れる
こうした経緯の後、東証は、同年1月21日付でオリンパスを「監理銘柄」から外し、あらためて「特設注意市場銘柄」に指定する。同社は、晴れて上場廃止の危機を免れたのである。
事件が露見した際、オリンパスが外資の手に渡るという話は、確かにリアリティをもって語られていた。それを阻止し、なおかつ青息吐息の同社を蘇生させるという「国策」の成就に、第三者委員会は一役も二役も買った。別の言い方をすれば、見事に「有効活用」された。
第三者委員会は、誕生から10年あまりの間にそこまで社会的な影響力を持つ存在となっていたのだ。同時に、東証が“お墨付き”を与えたことで、その存在はさらにオーソライズされることとなった。
※本稿は、『「第三者委員会」の欺瞞-報告書が示す不祥事の呆れた後始末』(中央公論新社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 「第三者委員会」とは誰のための存在か?会計学者「大半は真相究明ではなく追及をかわし、あくまで身の潔白を証明する<禊のツール>で…」
- 「第三者委員会」のルーツは97年・山一證券自主廃業に。会計学者「死を宣告された組織を調べる現場に<第三者の目を入れる>知恵が生まれたのは皮肉なことで…」
- 「日弁連ガイドライン」策定のきっかけ<フタバ産業事件>とは?会計学者「バブル崩壊の後遺症の中、第三者委員会とは名ばかりの調査報告書が目立ち始めて…」
- 経営コンサル「ホリエモンのテレビ局買収が頓挫したのが、日本経済のターニングポイントと考える人もいるが…」<とりあえずの共通了解としてのテレビ局>の価値を考える
- 森且行「オートレーサーを目指した理由。SMAPの5人と出会えたから今の僕がある」