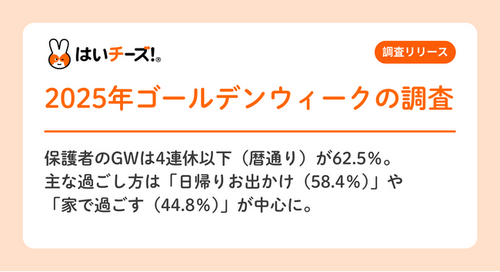2025年の法改正で「介護休暇」が取りやすく。しかし安易な休暇は「介護離職」に繋がる?!介護問題のプロが指摘する「介護における子どもの役割」
2025年3月26日(水)12時30分 婦人公論.jp

介護にはいろいろな悩みが…(写真:stock.adobe.com)
親を介護する際の課題は、「仕事」や「お金」だけだと思っていませんか?実は、もっとも大きな課題は「家族関係」なのです。親を思って介護サービス利用を勧めた結果けんかになったり、自分で介護しようと抱え込んでしまったり……。それまでうまくいっていた家族仲が、介護で険悪になってしまうことも少なくありません。親も子どもも無理せず幸せになれる「家族介護」はどうすればいいのか?外資コンサル会社から介護の世界へ。そして3000件以上の介護相談に乗ってきた川内潤さんの著書『親の介護の「やってはいけない」』より、一部を抜粋して紹介します。
* * * * * * *
介護現場での人材不足や施設不足
日本人の平均寿命は男女ともに80歳を超え、「人生100年時代」と言われるようになりました。
一方で、2025年には団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)となることから、今後は要介護者が増加していき、介護現場で人材不足や施設不足が起こるのではないかと懸念されています。
いわゆる「2025年問題」です。
そうした背景もあり、介護による離職を防ぐ目的で、育児・介護休業法が改正され、2025年4月から施行されることになりました。
改正点は三つ。
一つめは、従業員が家族の介護に直面したとき、事業主は必ず「うちではこういう制度が利用できますけれど、どうしますか?」と伝えて、意向を確認しなければいけないということ。
二つめは、事業主は従業員が聞いてくる前から、介護休暇などの情報を発信しなきゃダメですよ、ということ。
そして、三つめは、会社に入ったばかりでも介護休暇・休業が取れますよ、ということ。
これまでは短い期間しか働いていない人は介護休暇・休業が取れなかったのですが、それが撤廃されました。
問題なのは、介護に関わる家族の側のマインド
「へぇ、介護休暇・休業が取りやすくなるんだ。それなら、親に何かあったときは、会社を休んで面倒を見ればいいんだ」高齢の親を持つ子どもたちが、そう思ってしまったら大変なことになる!それが、私がここで伝えようと思った大きな理由の一つです。
たしかに、今回の法改正により介護休暇・休業が取りやすくなります。しかし私は、これが介護離職を防ぐどころか、むしろ後押ししてしまう結果にならないかと危惧しているのです。
仕事と介護の両立に向けての支援策が強化される流れ自体は、決して悪いことではありません。
この流れを受けて、企業のなかには、介護のための帰省費用を申請できたり、テレワ—クの上限を撤廃しているところも出てきています。
ただ、問題なのは、介護に関わる家族の側のマインドです。「介護休暇・休業=子どもが仕事を休んで親の面倒を直接見ること」だと思ってしまうと、それこそ逆効果。
頻繁に休暇・休業を申請して親の面倒を見たり、安易に同居してのテレワークなどを選択したりしたら、介護離職どころか、高齢者虐待につながる可能性さえ高まってしまいます。そのことをぜひ、皆さんにお伝えしたかったのです。
介護する家族の悩みに答える仕事
私は、大学卒業後、外資のコンサルタント会社に勤めていたのですが、「人の支援」に関わりたいと、介護の世界に飛び込みました。
そして、自宅で寝たきりの方の訪問入浴サービス、老人ホーム、認知症の方専門のデイサービスで働いたあと、現在は、8社ほどの民間企業と契約をして、主に介護する家族の側の相談に乗っています。
とある懇親会で、働きながら認知症の叔母の面倒を見ている方の相談に乗ったのがはじまりです。それをきっかけに、企業から依頼を受けるようになりました。
デイサービスや訪問入浴に携わっていたときは、介護する家族の側の悩みがそこまで深いとは気づきませんでした。
そもそも、介護保険で受けられるサービスというのは、あくまで高齢者の自立を支援するものであって、介護をする家族のためのものではありません。
ケアマネジャーにしてもホームヘルパーにしても、高齢者の支援をしてはじめて報酬がもらえるわけですから、家族のケアはどうしても片手間になりがちなのです。
相談を受けはじめた頃、誰もが知る最先端の企業に勤めていながら、親の介護のために、今にも仕事を辞めようとしている方に出会って、慌てて止めたことがあります。
その方の能力を失うのは会社にとって損失だし、何より、直接介護をしても絶対うまくいかないのがわかっていましたから。
テレワークができそうなので、実家に帰って親の面倒を見ようとしている方には、「いつ転ぶかわからないお父さん、お母さんがいるところで、パソコンを広げて仕事に集中できますか?」と問いました。
そしてこういう方々に、「近くにいてたくさん面倒を見ることが、いい介護ではありませんよ」と伝えてサポートすることが、結果として家族による高齢者虐待を未然に防ぐことにつながるのではないかと思ったのです。

つい声が大きくなってしまう…(写真:stock.adobe.com)
介護における「子どもの役割」
現在は、親の介護に悩んでいる人に対して、「つい声が大きくなってしまうことはありますか?もし、そういう気持ちがあるとしたら、なんでそうなってしまったのか、ご自身で思い当たるフシはありませんか? そうならないために、今日は職場からすぐに家に帰るのではなく、どこかに寄って、息抜きしてみませんか?」。
そんな介護保険法のなかではなかなかフォローできない、家族の相談に乗っています。
問題なのは、日本人の家族意識介護のプロとしての視点からお伝えすると、介護休暇・休業は、入居希望の施設の下見やケアマネジャーとの面談など、介護の体制作りのために取るべきで、直接、親を介護するために利用すべきではありません。
介護における子どもの役割は、直接介護をする「プレイヤー」ではなく、さまざまな人に協力してもらいながら介護を進める「マネジャー」なのです。
ところが実情は、ほとんどの人が「親の介護は子の務め」という日本人特有の家族意識にとらわれて、直接介護をするために利用してしまいます。
その結果、親子の関係がぎくしゃくしてしまったり、きょうだい間でもめたりと、家族の関係を悪化させてしまうのです。そうならないためには、これまでの家族意識をアップデートすることが欠かせません。
そこでここでは、多くの人がやってしまいがちな親の介護の事例を挙げながら、何がいけないのか、どうすればいいのかを解説していきます。
介護休暇・休業が取りやすくなることで、それをどう活用して、どういう介護をしていけばいいのかを、今こそ考える必要があります。
そして、いい介護とはどういうものか、どうしたら介護の醍醐味に辿り着けるのか——今回の法改正が、介護のことを考えるいい機会となり、この本がその一助となることを願っています。
※本稿は『親の介護の「やってはいけない」』(青春出版社)の一部を再編集したものです。