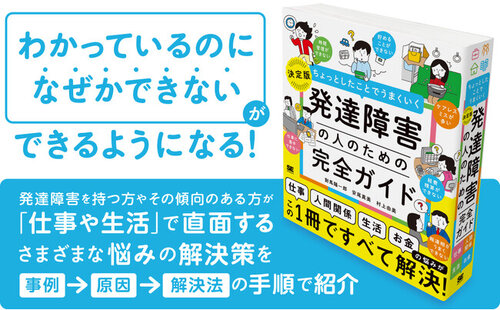『クローズアップ現代』で《子どもの発達障害》特集。発達障害・グレーゾーンの子にとって学校のような集団は「地獄」に?彼らが集団内でパニックを起こしやすいのはなぜか
2025年4月15日(火)17時0分 婦人公論.jp

小嶋さん「発達障害がある子は、体にも「特性」を抱えていることがあります」と言いますが——<『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル』より>
2025年4月15日の『クローズアップ現代』は、「『子どもが発達障害と言われたら…』拡大する“5歳児健診”」がテーマ。児童精神科医・神尾陽子先生が最前線に迫ります。そこで特別支援教育のエキスパートである小嶋悠紀さんが解説した、2023年05月12日公開の記事を再配信します。
*****
「子どもが洋服を着るのを嫌がる」「聞き分けがない」「パニックを起こす」それは単なるわがままではないかもしれません。一方で小嶋さんは発達障害・グレーゾーンの子どもたちへの「声のかけ方」「接し方」を考えながら、これまで2000人を超える人の支援に関わってきました。その小嶋さん「発達障害がある子は、体にも「特性」を抱えていることがあります」と言いますが——。
* * * * * * *
集団に適応できないのは、子どもには「地獄」だから
発達障害の子は、学校のような「集団」のなかではイライラやパニックを起こしやすくなります。そして、運動会・音楽会・文化祭などの行事、およびその練習のときに、とくにその傾向が強くなります。
なぜ集団が苦手なのでしょうか。そこにはおもに、次の3つの原因があります。
(1)集団で行動するのが苦手
集団にはルールがありますが、そのルールにうまく従えない子や、そもそも「みんなと一緒に行動する」ということが苦手な子がたくさんいます。
そういった子を集団のなかに入れて、ある決まった行動をさせようとすると、ストレスが積み重なり、「不安定」「パニック」が起こりやすくなるわけです。
(2)予定が変更されると対応できない
学校のような集団には、たいていルーティンがありますが、そのルーティンはしばしば変更されます。たとえば学校の行事の期間は、とくに変更が多くなります。
発達障害がある子は「見通しがついている予定」によって安定して生活することができます。「予定の変更」が多くなると、どう行動してよいかわからなくなり、パニックを起こしやすくなるのです。

『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル』(著:小嶋悠紀 イラスト・マンガ:かなしろにゃんこ。/講談社)
(3)失敗経験が積み重なる
(1)、(2)のような状態が重なると、子どもはうまく行動できなくなり、失敗や、大人に叱責される機会が増えます。失敗体験や叱責によって心が傷ついてトラウマが残ると、子どもは集団に恐怖すら感じるようになり、さらに適応できなくなっていきます。
このようなわけで、とくに行事は、発達障害の子にとっては「地獄」になりかねません。下のイラストは、ある子が私に実際に語ってくれたことですが、その子のように「ガマンガマンの1ヵ月」を耐えている子はたくさんいるのです。

ある子が語ってくれたこと(1)<『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル』より>
ですから集団のなかにいるときは、余計なストレスがかからないように、そして興奮やパニックが起こらないように、大人が配慮してあげましょう。
問題は脳だけじゃない、体にも「特性」を抱えている
発達障害がある子は、体にも「特性」を抱えていることがあります。私の経験上、低学年の子は次の2つのどちらかのタイプに当てはまることが多いと言えます。
(1)体が緊張して硬くなっている子
この記事の読者に試してほしいことがあります。ちょっと立って、両手を握ってぐっと力を入れ、さらに腕や肩にもめいっぱい力を込めてみてください。どう感じますか? きっと「しんどい」「疲れた」と思うのではないでしょうか。
そんなふうに、一日中「体にめいっぱい力が入った緊張状態」で生活している発達障害の子をよく見かけます。体に少し触れるだけで、あちこちがガチガチに緊張していることがわかるほどなのです。
毎日寝るまでそんな状態だったら、きっと生きづらいでしょう。そういう子もいるということを、大人はよく頭に入れておく必要があります。
(2)体を支えられない子
椅子に座ったときに、体がへにゃっと前に倒れてしまう子や、いつも机に肘(ひじ)をついて座っている子がいます。そんな様子を見ると、大人はだいたい〈怠けている〉〈だらしない〉と感じて、つい顔をしかめてしまいますよね。
でもなかには、「だらしない」姿勢になって支点を多くつくることで、やっと体を支えているという子もいるのです。
原因は体幹の筋肉の発達が十分でないからですが、大人から色眼鏡で見られがちな姿勢しかとれないのも、特性のひとつだと私は思います。
どうしてもだらしない座り方になる子がいたら、その子は、「特別な支援を必要としている子」なのかもしれないと考えてみましょう。
※本稿は、『発達障害・グレーゾーンの子がグーンと伸びた 声かけ・接し方大全 イライラ・不安・パニックを減らす100のスキル』(講談社)の一部を再編集したものです。