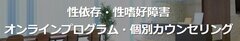「ストローを差して飲んでいる人を見て、これはヤバいと…」若い女性がストロング系チューハイの依存症になりやすい“社会的な背景”
2025年4月22日(火)18時0分 文春オンライン
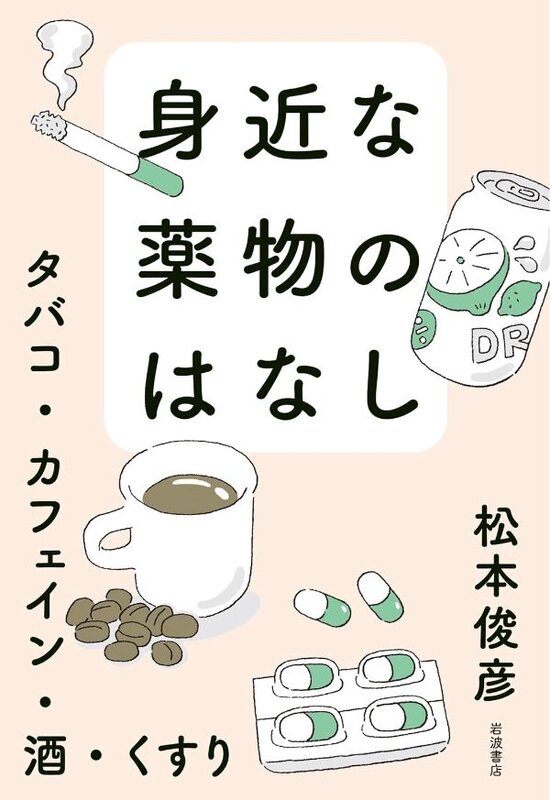
「薬物」と聞くと、多くの人がまず大麻、覚せい剤、危険ドラッグといった「違法薬物」を思い浮かべるのではないだろうか。精神科医として薬物依存症を専門としてきた松本俊彦さんの新刊『身近な薬物のはなし』では、そんな違法薬物ではなく、タバコ、カフェイン、アルコール、医薬品といった、私たちが日々摂取している「身近な薬物」が取り上げられる。
「私は精神科医として30年余り薬物依存症の臨床現場にいますが、大麻のオーバードーズで死んだ人は見たことがありません。でも、市販薬のオーバードーズで亡くなる方はたくさん見てきました。薬物の何が危険で何が安全かというのは、違法/合法という軸では語れないんです」
薬物とは、脳に作用し、精神活動に影響を与える化学物質の総称。そしてそもそも、薬物の合法/違法の区別には明確な医学的基準が存在しないのだという。では、その区別はどのように生まれたのか。本書では、人類と薬物の長い歴史を紐解きながら、その答えを文化的・社会的背景の中に探ってゆく。
「最初から歴史について書くつもりだったわけではないのですが、コロナ禍に感染症の歴史を勉強し始めたら、感染症と薬物の関係が無視できないと気づきました。感染症はコロンブス交換(エクスチェンジ:大航海時代以降に起こったヨーロッパと南北アメリカ間のさまざまな交流のこと)で広がりますが、この時に薬物文化もグローバル化しました。アメリカ大陸にアルコールが、ヨーロッパにはタバコやコーヒー、お茶が伝わったのです」
新しい薬物が伝播すると、規制や弾圧が起きる。だが、酒もコーヒーもタバコも、規制の度に抜け道を探すイタチごっこが繰り返され、やがて税収に生かす方向へと政策転換されてきた。
「叩けば叩くほど、もっと恐ろしいものが出てくるというのが薬物規制の歴史です。そしてそれは税収の場合も同じ。日本ではビールはアルコール度数のわりに課税率が高いので、発泡酒が作られた。すると今度は発泡酒に高い税が課された。苦肉の策で生まれたのが“ストロング系”です」
ストロング系チューハイは飲みやすく、安価なため危険な飲み方をする人が増えて社会問題となった。
「精神安定剤として缶にストローを差して飲んでいる人を見た時に、これはヤバいと思いました。しかも、ストロング系の依存症になってしまうのは、若い女性が多いんです。これには社会的な背景があるだろうと感じました」
松本さんは本書で、〈薬物には「よい薬物」も「悪い薬物」もなく、「よい使い方」と「悪い使い方」があるだけ〉と繰り返す。そして、〈「悪い使い方」をする人は何らかの困りごとを抱えているかも〉とも。
「社会的に許容されている薬物をダメだと言いたいわけでは決してありません。私も喫煙者ですし、お酒もコーヒーも飲みます。依存と依存症は別で、依存は悪いことではないんです」
また、違法薬物についても次のように指摘する。
「日本では違法薬物の使用は厳罰化されていて、お酒の飲み方よりずっと上品な使い方をしていても、それが違法薬物であれば捕まります。そして、依存症の回復に失敗はつきものなのに、一度犯罪者の烙印が押されれば、医療や福祉から疎外され、社会から居場所がなくなってしまう。違法薬物は健康被害より社会的ダメージの方が大きいんです。この本を通して、薬物に関して少しでもニュートラルな見方をしてくれる人が増えたらいいなと思っています」
まつもととしひこ/精神科医。国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長。著書に『もしも「死にたい」と言われたら』、『誰がために医師はいる』(第70回日本エッセイスト・クラブ賞受賞)他多数。
(「週刊文春」編集部/週刊文春 2025年4月24日号)