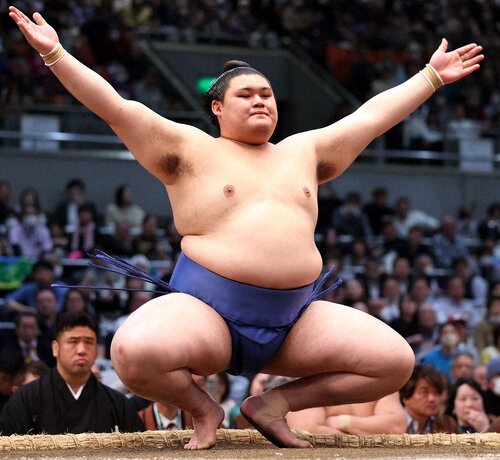夜の海が怪しく光る「ミルキーシー」現象、400年分の目撃記録からその謎に挑む研究者
2025年4月27日(日)21時0分 カラパイア

Credit: Steven D. Miller. Colorado State University/NOAA
ジュール・ヴェルヌが1870年に発表した冒険小説『海底二万里』には、「ミルクの海を航海」する船の様子が描かれている。
「ミルキーシー」と呼ばれる海水が乳白色に光る現象は、1600年代にはすでに報告され、船乗りにとっては伝説的なものとなっている。
それはときに10万平方kmにも広がり、宇宙からも観測できるほど大規模になることもある。しかも最大数ヶ月にもわたって続くのだ。
一体何が原因で海水が光るのか?
米国コロラド州立大学の研究チームは、この長年の謎の解明に挑もうとしている。手始めに始めたのは、過去の400年分の目撃情報をまとめ、調査の手がかりとなるデータベースを構築することだ。
過去400年分の目撃情報をデータベース化
数百年前から語られてきたにもかからず、未だその正体を特定できない理由は、ミルキーシーがきわめて珍しく、滅多なことではお目にかかれないことだ。
コロラド州立大学の博士課程の学生ジャスティン・ハドソン氏は、「データがなければ研究は困難です。
これまでに海上から撮影された写真は、2019年に船から偶然撮影されたたった1枚のみです」と、ニュースリリース[https://engr.source.colostate.edu/with-new-database-researchers-may-be-able-to-predict-rare-milky-seas-bioluminescent-event/]で語る。
この謎めいた現象に遭遇した船乗りたちは、乳白色に光る海を「夜の雪原」や「聖書の黙示録」のような光景にもたとえている。

こちらは人工衛星から撮影された闇夜に光るミルキーシー。青くみえるのは、視覚化のために着色処理されているためで実際は白色をしている /Credit: Steven D. Miller. Colorado State University/NOAA
輝きの正体は発光性の細菌か?
だが一体何が原因で海水が光を放つようになるのか?
その正体を突き止める手がりの1つは、1985年に偶然ミルキーシーに遭遇した船によって採取された海水のサンプルだ。
このサンプルからは、藻類の表面に生息する発光性細菌が原因である可能性が示唆されている。
藻類が大量に発生すると、細菌もまた広範囲に広がり、その光で海水が光ったように見えているのかもしれないのだ。
しかし、このようなサンプルが得られたのは今のところそれ一件のみ。たった1つのサンプルでは、そこにたまたま発光性細菌がいただけかもしれず、はっきりと結論を出すことはできない。
そこでハドソン氏らは、過去400年間にわたる目撃情報をまとめ、いつ、どこでミルキーシーが発生するのか予測するデータベースを構築することにしたのだ。

ミルキーシーには発光性細菌が関与している可能性が高いかもしれない/Credit: S. Haddock / MBARI
インド洋の気象現象との関係性
この400年間分のデータベースは、船乗りたちの目撃談、『Marine Observer Journal』に寄せられた80年間分の個別記録、最近の人工衛星による観測データをまとめたものだ。
そのデータベースからは、ミルキーシーは主にアラビア海と東南アジア海域周辺で発生しており、インド洋における「ダイポールモード現象」や「エルニーニョ現象」と関連している可能性があるという。
それは同時に、やはり生物学的なメカニズムの存在をうかがわせるものでもある。これについて、ハドソン氏は次のように解説する。
ミルキーシーがもっとも発生する海域は、ソマリアやイエメンのソコトラ島周辺の北西インド洋で、既知の発生例の約60%がここで報告されています
同時にこの地域は、インドモンスーンの位相変化が、風や海流の変化を通じて生物の活動に影響することでも知られています(ハドソン氏)

左図(a):ミルキーシーが他の発光現象と比べて、どれほど大規模かを空間的・時間的に示した図。色付きの楕円で囲まれた現象は、同じ色の生物によって引き起こされている。右図(b):2019年8月4日にインドネシア・ジャワ島近海で観測されたミルキーシーの衛星画像(VIIRS DNBによる)。この発光現象は少なくとも45日間続き、10万平方キロメートル以上の広さに及んだ。 https://doi.org/10.1029/2024EA004082[https://doi.org/10.1029/2024EA004082]
炭素の循環と細菌のつながり
同氏によれば、ミルキーシーは、地球という1つのシステムにおける炭素や栄養塩の大規模移動に関連している可能性もあるという。
世界的な炭素の循環については、陸上・海洋のどちらにおいても細菌が重要な働きをしていることが示されている。このことからも、ミルキーシーと細菌のつながりは十分にあり得ると考えられるそうだ。
いずれにせよ、今回のデータを活用することで、今後は偶然の遭遇に頼ることなく、もっと効率的な調査が可能になると期待されている。
この研究は『Earth and Space Science[https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EA004082]』(2025年4月9日付)に掲載された。
References: From Sailors to Satellites: A Curated Database of Bioluminescent Milky Seas Spanning 1600-Present[https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2024EA004082] / With new database, researchers may be able to predict rare 'milky seas' bioluminescent event[https://phys.org/news/2025-04-database-rare-milky-seas-bioluminescent.html]