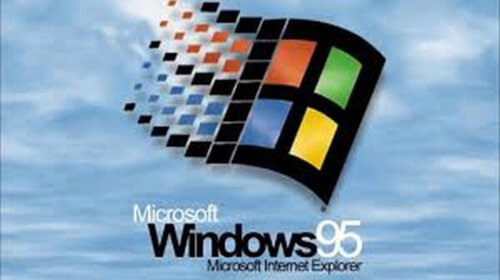国内有数の歴史誇る京都の大学図書館、人が集い憩う場に…仕掛け人の館長は法医学者
2025年4月27日(日)9時41分 読売新聞
新たにオープンした交流スペース「コトスクエア」でくつろぐ学生ら
地域住民も利用可能に
大学図書館として国内有数の歴史を持つ「京都府立医大付属図書館」(京都市上京区)が、府民に開かれた図書館として生まれ変わった。仕掛け人の館長は、法医学者だ。(矢沢寛茂)
1階を改装して今春オープンした「コトスクエア」(約635平方メートル)は、円卓、カウンター、ソファ、畳の小上がり風のベンチなどが開放感のある空間に並ぶ。図書館の一角にありながら授業や会議、談話や飲食も可能で、府立医大生に限らず誰でも自由に利用できる。
ランチ時になると、図書館の隣にはおしゃれなキッチンカーが来る。学生に交じって、府民らが憩う姿も。明るさを増したキャンパスに目を細めるのは、図書館長の池谷博教授(55)だ。2023年春、幹部管理職へ登用され、館長に就任した。
「閑散とした感じ」。図書館に足を踏み入れたときの印象を、池谷教授はそう振り返る。府立医大は、河原町通をはさんで約100メートル離れた二つのキャンパスがある。病棟や研究棟などの「河原町キャンパス」と、主に看護学科の学生が通う「広小路キャンパス」だ。そして、図書館があるのは広小路の方。池谷教授は河原町キャンパスが根城で、図書館にほとんど関わりがなかった。
大学の創立は153年前にさかのぼり、図書館は江戸時代の和とじの本や欧州の古い医学書などの宝庫だった。
しかし、20年前におよそ10万人だった入館者が、この頃は約3万人にまで減っていた。この間、学術誌の電子版の閲覧数はおよそ3倍に膨らみ、運営費の多くは電子版の購入に充てられていた。「研究にも強い大学だから」と納得しかけたが、「これって、おかしい」と疑問がわいたという。
「せっかくなら『変わったね』と言われるような仕事を」。池谷教授は奮い立った。
まずは人を呼び込もう——。二つのキャンパスを行き来する学生が増えるよう、キッチンカーを呼んで、日替わりで両キャンパスに出店してもらった。テラスのように敷地に机や椅子を並べ、共有型の電動アシスト自転車の駐輪場も作った。
15人の司書らには「必要な仕事は自ら見つけるもの」と、多角的な働きを求めた。学生証と館の利用証を一体化したICカードを大学全体に導入する仕事は、図書館スタッフが主力を担った。
図書館改革の目玉と考えたのが、「コトスクエア」だ。ただ、改修費用は数千万円規模で、図書館の予算では到底まかなえない。池谷教授は、300人収容の併設ホールを利用し、幅広く寄付を呼びかける講演会を企画した。「図書館を充実させるために、協力してほしい」。教員の人脈を駆使して、建築家の安藤忠雄さん、エッセイストの泉麻人さん、ミステリー作家の北村薫さんらに講演会への協力を取り付けた。
呼びかけが奏功し、今年1〜3月に実施したクラウドファンディング(CF)では当初の目標額400万円を大きく上回る約1440万円が集まった。
華岡青洲の額などの史料も見つかる
一方、図書館の<地力>に驚かされることも多くあったという。芥川龍之介の短編の一つが初めて収められた雑誌や、世界初の全身麻酔手術を成功させた華岡青洲の額など、想像もしなかった史料も館内から次々と見つかり、「大学の歴史の重さを感じた」と話す。
法医学者は
さらなる仕掛けを準備しているという池谷教授は、にやりと笑った。