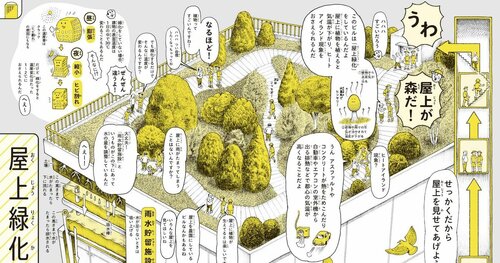5歳の少女が大発見した旧石器時代の彩色壁画…しかし誰一人見ることができないのは、世界遺産として相応しいのか?
2025年5月5日(月)6時0分 JBpress
(髙城千昭:TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー)
5歳の少女が、教科書を書き換える大発見!
1981年に大ヒットしたアメリカ映画「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」は、考古学者インディアナ・ジョーンズ氏が世界中のお宝を探して、まだ見ぬ遺跡へと足を踏みこむ冒険活劇である。だが現実の考古学は、土をコツコツと掘り起こして、出てきた破片を1個ずつ分類するような忍耐強い仕事だ。何も発掘できず、空振りの日が多いに違いない。それなのにアマチュア研究家やド素人が、教科書を書き換える歴史的な大発見をすることが偶然ある。誰もがロマンを夢見るのも無理はないだろう。
例えば世界遺産「秦の始皇帝陵」(登録1987年、文化遺産)では、近郊に住む農夫が鍬で井戸掘りをしている時に、何か硬いものが当たったという。掘り返してみると、人間並みにデカい陶製の人形(俑)が出てきた。これが紀元前3世紀、始皇帝陵の東1.5kmに陵墓を守るため埋葬された、8000体におよぶ軍団「兵馬俑坑」発見のいきさつだ。等身大で1体ずつ顔や装束が異なり、実際の兵士をモデルにしたと考えられる。当初は、緑・赤・青・紫などで鮮やかに彩色されていた。
始皇帝陵そのものは、高さ76m・底辺350mの巨大なピラミッド型の土塁であるが、文化財保護や墓荒らしを防ぐために、発掘は未だされていない。地下30mには都を模した地下宮殿があり、水銀を満たした川や海が存在するらしいが、あくまで伝説に過ぎない。世界遺産の決め手になったのは、兵馬俑坑の“発見”があればこそだ。
今から150年近くも昔の1879年夏、スペイン北部にある洞窟で5歳の少女マリアが手提げランプを片手に、ほのかな明かりに揺らめく天井を見上げた。
「パパ見て、牛の絵があるよ!」
これが、世界遺産「アルタミラ洞窟」(登録1985年、文化遺産)の名高い発見エピソードである。父のマルセリーノ・デ・サウトゥオラはアマチュア研究者で、洞窟の入口付近で旧石器時代の地層を調べていた。そこにはヒトの居住跡があり、動物の骨や角でできた道具類、石器が出土していた。しかし常識に縛られない娘は、光がまったく届かない洞窟の奥へと迷い込んだ。そして横穴の突き当りエリアで、天井を埋め尽くすかの如く描かれた20体の野牛(古いタイプのバイソン)を見つける。小っちゃな子供なのが幸いして、かなり低い位置にある壁画に目が向いたのだろう。
1万4500年前、現代ヨーロッパ人の祖先であるクロマニョン人は、岩肌の凸凹を活かしながら、黒(木炭)で輪郭をとり赤(ベンガラ)でボカシを入れ立体感を出した。野牛がうずくまり・振り向き・吠える姿は写実味にあふれ、先史時代のヒトによる高い芸術性を示している。初めて太古の絵が、現代人の目にふれた瞬間だった。
20年以上かかって太古の壁画と認められた“不都合な絵”
父のサウトゥオラは、翌1880年に「彩色壁画は、旧石器時代のもの」だと考古学会に発表する。しかし当時、太古の絵は知られておらず、野蛮な“原始人”にこんな絵が描けるはずがないと否定された。そればかりか捏造を疑われ、学会が「過ち」を認めるまでに20年以上を費やすことになる。彼はその前に、失意のまま57歳でこの世を去った。
アルタミラの壁画は、進化論を崇めた学者たちにとって“あってはならない”不都合な絵だった。洞窟に住むような未開人は、感性や知的に劣り、十分な技術を持ちあわせない……頑迷な“決めつけ”である。しかし、フランスの洞窟からその後相次いで岩絵や刻画が見つかり、20世紀に入ると否定派も認めざるを得なくなった。見たくない事実に目を閉ざすのは、今なお先住民や人種、性別、信仰へと及び、通底する心理かもしれない。
世界一有名になった1万4500年前の“名画”は一般公開されると、観光客がわんさと洞窟に押しかけた。1973年には、年間17万人もの記録に達する。が、この大人気はアルタミラ洞窟を危機的な状況に陥れてゆく。温度や湿度が上昇すると色素がはがれ、退色してしまうのだ。さらに見学者の吐く息は、酸性化を引き起こす。実はこの洞窟が完璧なまでに良く保存されていたのは、遠い昔に崩落した岩で、入口が固く閉ざされていたからである。
開封して人が接すると、壁画がいかに傷つくか? それは、「世紀の大発見」と語り草になった高松塚古墳が、反面教師として事実を教えてくれる。円墳の石室4面には、「飛鳥美人」をはじめ男女の群像や四神(青龍・白虎・玄武、朱雀はない)が極彩色で描かれていた。模写するために石室に入った日本画家・平山郁夫は、こう証言している。
「人の体温で室内が乾き、瞬く間に壁画の色があせていった」
さらには石室のカビを抑える燻蒸が、逆に壁面を痛めた。結局、黒いカビが大発生して、絵はくすみ消えた箇所もある。文化庁の判断によって、石室ごと解体して“修理”するが、カビの痕跡を消す技術はまだない。もはや元の古墳に戻せないらしい。
アルタミラ洞窟は2002年に閉鎖され、わずかな研究者以外は非公開になった。けれども2014年から週5人に限って見学を許可している。この試験公開は、予約制で年間260人だけ。待機リストはいっぱいで、新規の申し込みは受け付けていない。世界遺産が、すべての人々にとっての宝であるならば、見たいと熱望する人には、最小限でも門戸を開くべきだろう。誰一人見ることができない岩絵では、世界遺産に相応しいと思えない。
今、本物に代わって見学者を受け入れているのが、洞窟の近くにある博物館の3次元レプリカ。岩の凸凹を型どりして再現し、まったく同じ位置に、旧石器時代のアーティスト通りの手法で絵の具もそのまま、寸分違わぬ壁画が作られている。洞窟の闇の奥にあって、呪術的な要素が強かった「人類の傑作」が、身近に楽しめるようになった。
2008年、世界遺産「アルタミラ洞窟」は、大西洋に面した3つの自治州(アストゥリアス州、カンタブリア州、バスク州)にある17の洞窟を追加登録した。その中で、壁画の年代が4万年前まで遡るエル・カスティーリョ洞窟は一般公開中である。
カスティーリョ山にうがたれた石灰岩の穴。氷河期の末期に、狩人たちは獲物を追って転々としながら、岩肌に“自らの証し”を残した。現地に立ち、そこで本物を感じる。世界遺産の醍醐味とは、何モノにも代えがたいその一瞬にある。
(編集協力:春燈社 小西眞由美)
筆者:髙城 千昭