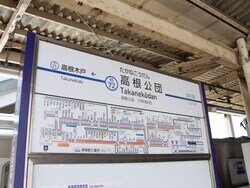2025年4月1日、千葉県の松戸駅~京成津田沼駅間を結ぶ新京成電鉄は京成電鉄と合併し、京成電鉄松戸線として生まれ変わった。カーブが多く、個性的なピンク色の車両が特徴のこの路線について、これまであまり知られていなかった話題をまとめてご紹介する。
千葉県北西部の松戸駅と京成津田沼駅を結んでいた新京成電鉄は、2025年4月1日に京成電鉄に吸収合併され、京成電鉄松戸線として再スタートを切った。ピンク色の車両がカーブの多い路線を走る姿は個性的でもある。今回の合併を機に、京成松戸線の知られざる話題をまとめてみた。
1. ヘッドマークを付けた記念列車

新京成電鉄は京成電鉄に吸収され、2025年4月1日から京成松戸線として再出発した。これを記念して、「Hello Matsudo Line」という記念ヘッドマークを掲出した電車を走らせている。3000形1編成、N800形1編成の2つだ。
3000形は京成本線系統を走っているので、京成松戸線を走るのはN800形1編成のみである。京成津田沼駅から千葉線にも直通しているので、なかなか出会えないかもしれない。
2. 順番が逆になった駅ナンバリング

新京成時代の駅ナンバリングは、SL01(松戸駅)からSL24(京成津田沼駅)までだった。新京成だからSKが妥当だったが、SKは、すでに西武国分寺線で使われていた。それで、Shinkeisei Lineを意味するSLとなった。
京成松戸線に移行するにあたり、京成電鉄の略号KSを踏襲。最後がKS65ちはら台駅だったので、それに続く形でKS66から順に付番した。もっとも、本線との接続を優先したので、新京成時代とは逆になるが新津田沼駅(KS66)から付番し松戸駅(KS88)がラストとなった。
3. カーブが多くくねくね走る理由

京成松戸線の前身である新京成線は、第2次世界大戦後、陸軍鉄道連隊演習線の線路跡を利用する形で1947年に開業した。鉄道連隊演習線は、その名の通り演習が目的だったので、最短距離を結ぶ必要はなく、曲線が多かった。
新京成線設立に当たり、かなり迂回(うかい)を緩和したものの、通常の路線よりも曲線が多くなっている。新京成時代のシンボルマークは新京成の頭文字のSを図案化したものだったが、Sはカーブの多い路線をも表わしていたと言われている。
4. 意外な駅にゼロキロポストがある理由

新京成線としての開業は、1947年12月の新津田沼駅〜薬園台駅が最初だった。そのため、ゼロキロポストは起終点の松戸駅でも京成津田沼駅でもなく、新津田沼駅の松戸駅方面行きのホームにある。
なお、新津田沼駅は再三移転をくり返し、4代目の駅として1968年5月に現在の位置に落ち着いた。
5. わずかに残る単線区間

京成松戸線は、ほぼ全線が複線化されている。唯一の例外は、新津田沼駅〜京成津田沼駅(1.2km)。もともとは現在の新津田沼駅近くにあった京成電鉄の車両工場への引込線であり、それを利用して、新京成線は京成津田沼駅へ乗り入れていた。
住宅が密集している上に、新津田沼駅で下車してJRに乗り換える人も多いので、単線でも何とか間に合っているようだ。
6. 等間隔な列車ダイヤ、優等列車はなく、千葉線直通がある

京成松戸線には快速や急行といった優等列車は設定されていない。全線通しで乗る利用者はほとんどおらず、短区間の利用で他線に乗り換えて都心へ向かう人が多いためと思われる。
全列車が普通列車(各駅停車)で、昼間は10分間隔。朝のラッシュ時は4分間隔の時間帯があり、新津田沼駅〜京成津田沼駅の単線区間がネックになっているので、松戸駅〜新津田沼駅折り返しの電車が何本かある。
また、昼間の時間帯を中心に京成津田沼駅から京成千葉線に乗り入れて千葉中央駅に直通する電車が20分ごとに設定されている。
7. 異彩を放つピンクの電車

新京成時代の2014年にコーポレートカラーが制定された。メインカラーはジェントルピンクで、駅名標やラインカラーのみならず、車体の色にも取り入れられた。電車の色でピンクを使う例は多くないので異彩を放っていた。
京成電鉄になって以後、まだまだピンクの電車は主力だが、少しずつ京成カラーに塗色変更する方針のようだ。写真を撮るなら今のうちであろう。
8. 数多い乗換駅、読み方が異なる八柱と新八柱

京成松戸線は北西の終着駅・松戸駅ではJR常磐線、南東の終着駅・京成津田沼駅では京成本線、その1つ手前の新津田沼駅ではJR総武本線と接続している。それ以外にも、新線が開業するに従い中間駅で乗り換え都心へ向かう利用者が激増していった。
八柱駅ではJR武蔵野線(駅は新八柱駅)、新鎌ヶ谷駅では、北総鉄道および東武野田線(かつては交差するものの駅がなかった)、北習志野駅では東葉高速鉄道に乗り換えができ、利便性は向上したものの、京成電鉄にとっては利用客の減少につながっている。
コロナ禍や少子高齢化の影響もあり、かつては8両編成の電車もあったのに、現在はすべて6両編成と短縮化されている。

乗換駅で双方の駅名が異なるのは八柱駅だ。面白いことに京成松戸線は八柱(やばしら)駅、JR武蔵野線は新八柱(しんやはしら)駅で「は」と濁らない。
9. 大規模団地の最寄り駅
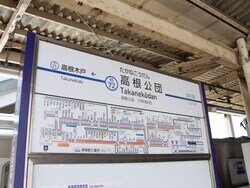
京成松戸線沿線には巨大な団地がいくつもある。その最寄り駅の代表は常盤平駅および高根公団駅だ。常盤平団地、高根台団地ともに当時の日本住宅公団が造成したものだ。通称「公団住宅」と呼ばれ一世を風靡(ふうび)したので、高根公団駅と名乗っても何ら問題はなかった。

しかし、時代は変わり、日本住宅公団は組織の変更に伴い、現在では都市再生機構(UR)となり、UR賃貸住宅などと呼ばれている。公団の名は消えてしまったにもかかわらず、高根公団駅として駅名にのみ残っている。北九州モノレールにも徳力公団前駅があり、どちらも駅名を変更することなくかつての面影を伝えている。
10. 沿線随一の名所・鎌ヶ谷大仏

いくつもの団地や住宅地を結び、通勤通学路線の趣が濃い京成松戸線にあって、唯一ともいえる観光名所が鎌ヶ谷大仏だ。建立されたのは江戸時代でおよそ250年の歴史をもつ。
路線が開業した時に、少しでも行楽客を呼び込もうと駅名も鎌ヶ谷大仏駅としたのだが、およそ大仏とは言えないほど小さな仏像で高さは1m80cmしかない。

駅から至近距離の墓地内にあるが、うっかり通り過ぎて見つけられない人も少なくないとか。がっかり名所などと揶揄(やゆ)されることもあるが、「大仏とされる仏像で、石像以外では日本一小さい」と地元では自慢する。大仏コロッケなる名産品もあるし、駅の改札口脇のパン屋では「大仏」の刻印を押した「プレミアムあんぱん」も販売している。

都市郊外の地味な通勤通学路線と思われている京成松戸線は、新京成電鉄の吸収合併によりがぜん知られるようになった。沿線をつぶさに見て回ると、思わぬ発見もあり、たまには散策してみるのも楽しいであろう。
この記事の筆者:野田隆
名古屋市生まれ。生家の近くを走っていた中央西線のSL「D51」を見て育ったことから、鉄道ファン歴が始まる。早稲田大学大学院修了後、高校で語学を教える傍ら、ヨーロッパの鉄道旅行を楽しみ、『ヨーロッパ鉄道と音楽の旅』(近代文芸社)を出版。その後、守備範囲を国内にも広げ、2010年3月で教員を退職。旅行作家として活躍中。近著に『シニア鉄道旅の魅力』『にっぽんの鉄道150年』(共に平凡社新書)がある。
(文:野田 隆)