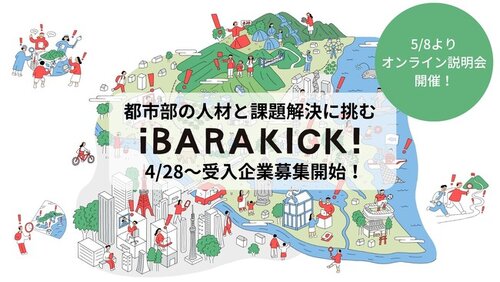絶海の孤島・青ヶ島在住の40歳女性が語る、「日本一人口の少ない村」の“独特すぎる働き方”「週5で働きながら、天気の良い日は朝から漁に…」――2024年読まれた記事
2025年5月2日(金)12時0分 文春オンライン
2024年、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。ライフ部門の第3位は、こちら!(初公開日 2024/12/01)。
* * *
日本一人口の少ない村、青ヶ島村在住のYouTuber・佐々木加絵さんが“島暮らし”を発信する連載企画。
東京都心から約360km離れた人口163人(2024年11月1日時点)の小さな島・青ヶ島。交通手段が限られていて、簡単に上陸できないことから、別名「絶海の孤島」と呼ばれている。
そんな青ヶ島の日常をYouTubeで発信しているのが、佐々木加絵さん(40)。「私にとっては普通なのですが、島外の人からすれば、青ヶ島の日常は非日常なのかもしれない」と話す加絵さんは、いったいどんな“島暮らし”を送っているのだろうか。今回は、「仕事」をテーマに、青ヶ島の日常を紐解いていく。

◆◆◆
青ヶ島で一番多い職種とは?
みなさんは、青ヶ島の人たちが、どんな仕事をしているのか想像できますか。人口約160人の小さな島なので「仕事の種類も限られているのでは?」と思われる方も多いかもしれません。今日は、そんな青ヶ島のお仕事事情についてお話ししていきたいと思います。
早速、読者のみなさんに質問です。青ヶ島で一番就業者の多い職種は何だと思いますか?
正解は、「公務員」です。村役場の職員や小中学校の先生、交番勤務のおまわりさんなどを合わせると、50人以上はいるんじゃないかと。つまり、島民の約3分の1が公務員ということになります。
ちなみに、役場の職員といっても、村役場で働く事務員だけでなく、保育園の先生、村の診療所で働く医者や看護師、発電所の職員など、いろんなお仕事の方がいます。また、小中学校の先生は、東京都の職員です。青ヶ島には、転勤で数年ほど滞在している方がほとんど。
「家族が食べる分の食材は自分たちで用意する」
公務員以外では、島で唯一の金融機関である郵便局、道路や港、村営住宅をつくる建設会社、島の特産品「ひんぎゃの塩」を作る塩工場で働く人も多いですね。
他の地域と比較すると、自営業の人たちも多いかもしれません。農業、漁業、民宿の経営、青ヶ島伝統の焼酎「あおちゅう」作り、電気屋さん、修理業、ブランド牛「東京ビーフ」の畜産など、仕事内容は様々です。
子育て中の方など、短時間だけ働いている人もいます。村役場で短時間勤務したり、老人クラブや民宿のお手伝いをしたり。働いてはいなくても、自宅の畑で野菜を育てたり、港で釣りをしたりと、「家族が食べる分の食材は自分たちで用意する」という方も少なくありません。
週5日で働きながら、天気の良い日には朝早くから漁に…
青ヶ島の人たちは、「兼業」をしている人が多いです。例えば私の弟は、建設会社の正社員をしながら、個人事業主として漁業をし、さらに村議会議員もしています。週5日建設業をしながら、天気の良い日には朝早くから漁に出て、議会があるときは議員の仕事もして……。それで夜は毎晩のように、友人の家をはしごして飲み歩いているんだから、本当にエネルギッシュですよね(笑)。
私自身も、YouTuberとして活動する傍ら、配達業、観光ガイド、デザイナー、実家が運営する民宿「かいゆう丸」の手伝い、島唯一のコワーキングスペース「NYAYA」の運営など、様々な仕事を兼業しています。
私や弟に限らず、青ヶ島では「兼業」が当たり前。建設会社に勤めながら「あおちゅう」を作ったり、民宿で働きながら農業や漁業をしたり。人口の少ない島なので、「1つの仕事だけでは生計を立てられない」という理由で兼業している人も少なくありません。
一方で、趣味や生きがいとして複数の仕事を楽しんでいる人も多いです。特に農業や漁業は、レジャー感覚というか、癒やし目的で取り組んでいる人が多い気がします。もともと自然豊かな島で生まれ育った島民はもちろん、島に移住してくる方も、自然と触れ合うのが好きで来てくれた方が多いですから。
小さい島ならではの課題
兼業の人が多い以外にも、青ヶ島の働き方には特徴があります。例えば、建設業に就いている人は、現状男性しかいません。また、配達業に就いているのはほぼ女性です。
性別以外にも、島内の就業状況には“偏り”があります。島内でも就業人口の多い建設業ですが、それを支えているのは60歳以上の高齢者が中心です。公共事業で成り立っている島のインフラを考えると、若い世代の育成は必須。
とはいえ、建設業界の高齢化は全国的な問題だと思うので、課題解決のハードルはものすごく高い……と頭を悩ませているところです。
他にも、小さい島ならではの課題もあります。島外の方が青ヶ島に興味を持って「移住したい」と思っても、求人が多くないから、仕事が見つからず諦めてしまう人も。気軽に移住を検討できるのは、勤務地に青ヶ島が含まれる都採用の公務員や、フリーランス、リモートワーカーなど限られた人たちとなっています。
「仕事がない」という理由で島から離れざるを得ないケースも
無事に島での仕事が見つかっても、仕事によっては契約期間があったり、いざ働いてみたら働き方が合わなかったりして、辞めざるを得ないこともあります。青ヶ島が好きで移住してきてくれたのに、「仕事がない」という理由で島から離れざるを得ないのは辛いじゃないですか。
本土のように様々な仕事に挑戦しながら、自分に合った働き方を見つけて暮らせる環境を、青ヶ島でも整えていかなければ、と思っています。
最近、「青ヶ島に住みたくて期間限定の工場の仕事に就いたけど、契約期間が終わってしまった。これからどうしよう……」という方から相談をもらったんです。今その方は、島の民宿で働いています。こうやって少しずつ、柔軟な働き方が広まっていけばいいなと思います。
“絶海の孤島”が生み出してきた逸品
さて、青ヶ島の産業についてもお話しさせてください。青ヶ島には、「ひんぎゃの塩」「あおちゅう」「東京ビーフ」など、いろいろな特産品があります。どれも、“絶海の孤島”と言われる独特な島の風土と、そこで暮らしてきた人々が生み出してきた逸品です。
特に「あおちゅう」は島外のファンも多く、酒づくりの季節である秋になると、青ヶ島まで製造の手伝いに来てくれる人もいるほどです。
「あおちゅう」は元々、家庭で作られていて、家庭ごとにつくり方も味も違うお酒だったんです。島には現在10人の杜氏がいますが、昔ながらの製法は現代にも引き継がれていて、作り手によって香りも味も違うのが面白いんですよ。
ただ、杜氏の世界も高齢化が進んでいて、製造中止になってしまった銘柄もあります。
産業や文化が失われていくのは悲しい
他にも、少し前まで島の特産品だった「くさや」や「はばのり」も、今はほとんど作られなくなってしまいました。どちらも、温暖化により原料となる魚や海苔が青ヶ島近海で獲れなくなってしまったことが理由だと聞いています。
時代や環境の変化によって、これまで築いてきた産業や文化が失われていくのは、やっぱり悲しい。一方で、「あおちゅう」のように、島内にも島外にもファンがたくさんいる産業もあります。
「あおちゅう」に関しては、島外から手伝いに来てくれるだけでなく、「引き継ぎたい」と言ってくれる方もいるんですよ。すべての産業を守るのは難しいかもしれないけど、こうやって協力してくれる人たちの力を借りながら、青ヶ島の文化を未来へ繋いでいきたいです。
取材・文=仲奈々
写真提供=佐々木加絵さん
(仲 奈々,佐々木 加絵)