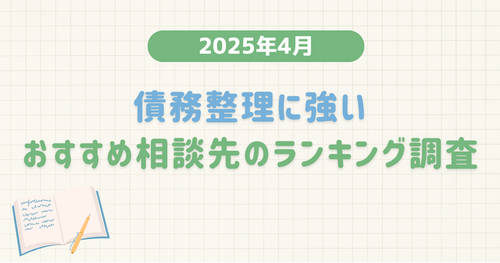「いつ調査に来たのかまったく気づかない」家族に打ち明けられないミシュラン匿名調査員の過酷で孤独な仕事
2025年4月9日(水)10時15分 プレジデント社
3月27日に京都で行われた『ミシュランガイド京都・大阪2025』のセレモニー。日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役の須藤元氏より授与された。 - 写真提供=©MICHELIN
写真提供=©MICHELIN
3月27日に京都で行われた『ミシュランガイド京都・大阪2025』のセレモニー。日本ミシュランタイヤ株式会社代表取締役の須藤元氏より授与された。 - 写真提供=©MICHELIN
■100年以上続くフランス発祥老舗レストランガイド
古都の桜を眺めてみたいと世界中から観光客が訪れる京都で、まさに開花宣言が出された3月27日、『ミシュランガイド京都・大阪2025』が発表された。フランスで1900年からスタートしたあまりにも有名な老舗レストランガイド(現在では世界45エリアを紹介)。日本では2007年から『ミシュランガイド東京』が、続いて2009年から『ミシュランガイド京都・大阪』が発行されている。この間、不定期で地方版も刊行されたが、毎年継続的に更新されるのはこの2エリア版となっている。
飲食業界の人間でなくても「星付きのレストランを予約したから行ってみない?」と言われると、ちょっとゾクゾクしてしまう。星、イコール、ミシュランスターのことであり、現在日本では「食べログ」「Googleマップ」『ゴ・エ・ミヨ』「アジアのベストレストラン50」「Retty」「OAD」など数多のレストランガイドが利用できるが、やはり断トツで業界外にも知名度や影響力を持つのは『ミシュランガイド』だなと実感することが多い。今回もいくつかの飲食店が星の数を増やしたり新たに星を獲得したりし、そこにはドラマがあった。
筆者撮影
時に『ミシュランガイド関西』になったり、和歌山県や兵庫県が仲間入りしたりしながら変遷を続ける『ミシュランガイド京都・大阪』。デジタル版も同時発売され、またアプリ(登録無料)の機能も年々充実している。 - 筆者撮影
■実は知られていないことだらけ
しかし、興味深いことにこの『ミシュランガイド』についてはあまり知られていないことも多い。筆者自身長く飲食業界を眺め続け、この有名すぎるガイドブックのこともなんとなく知ったつもりになっていた。ところが、3年前から実際に取材をするようになってからというもの、目から鱗が落ちること落ちること。今回は、新参者である筆者だからこそ興味を覚えた『ミシュランガイド京都・大阪2025』の着目ポイントをお伝えできたらと思う。
その前に、まずはざっくりと『ミシュランガイド』の特徴を紹介しよう。フランスで100年以上続く老舗ガイドだというのは冒頭でも触れたが、ご存知のように「ミシュラン社」というのは国際的に展開する一大タイヤメーカーだ。タイヤを売る会社がなぜレストランガイドを出しているかというところに、実は『ミシュランガイド』を理解する鍵が隠れている。
写真提供=©MICHELIN
壇上にずらりと並んだ受賞店のシェフたち。壇上に上がる前に胸元に受賞した星の数が刺繍されたスペシャルコックコートが渡され、それに袖を通してから盾を受け取るのが習いだ。 - 写真提供=©MICHELIN
■星の定義はあくまでも「旅人目線」
今から一世紀以上昔のフランス。自動車旅行はまだまだ一般的ではなく、ミシュラン社はタイヤの普及や販売増のために自動車旅行の楽しさを世に伝えたいと考え、1冊の旅行ガイドを編み出した。これがミシュランガイドの始まりで、当時はホテル情報や地図なども掲載していたという。レストランは、旅先での楽しさを伝えるためのレジャー情報だったのだ。「おいしい料理」を示すための指針として星が登場したのが1926年。さらに1931年にはそれが3段階評価となり、1933年からは匿名調査員制度がスタート。ここからは、概ね今と構造的に変わらない『ミシュランガイド』であり、徐々にエリアを広げて今や世界中で刊行されることとなった。
そんなこともあり、「星の定義」の文言はどこまでも旅人目線で書かれている。
三つ星……そのために旅行する価値のある卓越した料理
二つ星……遠回りしてでも訪れる価値のある素晴らしい料理
一つ星……近くに訪れたら行く価値のある優れた料理
とされている。ターゲットが旅人というのは、他のレストランガイドやランキングサイトとは大きく異なる点なのだ。昨今は上記の3つのカテゴリー以外に「ビブグルマン(価格以上の満足感が得られる料理)」「セレクテッドレストラン(ミシュランガイドおすすめの飲食店・レストラン)」「ミシュラングリーンスター(持続可能なガストロノミーに対し、積極的に活動しているレストラン)」が加わり、1冊に掲載される軒数は増加の一途を辿っている。今回の『ミシュランガイド京都・大阪2025』で掲載されたのは469軒で、このうち星付き店は172軒。ちなみに昨秋発表された『ミシュランガイド東京2025』だと掲載総数は507軒であり、星付き店が170軒。関西勢は東京にまったく引けをとっていない。
筆者撮影
「ミシュラングリーンスター」は、持続可能な飲食のあり方に貢献している店に与えられる。若手料理人の中には、星よりもこちらが“クール”だと言って目指す人もいるほど。初めてラーメン業界からこの賞を受賞したヴィーガンラーメン店「ウズ」が会場でも話題に。 - 筆者撮影
■一体誰がいつ“調査”しているのか?
他にも『ミシュランガイド』ならではの特徴は多い。例えば、誰が調査をしているかという点もそうだ。ミシュランガイドの匿名調査員は全員がミシュラン社の社員であり、プロフェッショナルの調査員として“任務”である匿名調査に日々向き合っている。匿名調査員は世界で一つのワンチーム構成となっていて、中には数名の日本人調査員もいると聞くが、何度か“調査”で彼らに実際に出会ったシェフや料理人しかその姿を見た人はいない。また、同じ店の調査に連続して当たることはないそうで、結果としてなかなか素性がわからないようになっているという。調査員であることは伏せて匿名で予約を入れ、一般客と同様にレストランで食事をして料金を支払うというから、多くのシェフたちが「いつ調査にいらしたのか、まったく気づきませんでした」と口を揃えることになる。
調査員は誰でも務められるものではなく、最低限として一定期間のホスピタリティー産業(ホテルやレストランなど)従事経験者であることが求められ、入社後は長期間の本国トレーニングと実地訓練が課されるという。一週間で9回ほどレストランや飲食店での食事調査をこなし、しかも海外を含む出張続きというから、かなり過酷だ。しかもその任務を人に明かすことは固く禁じられている。それは例え、家族であっても。なんと孤独でタフな仕事なのだろうか!
料理の評価はカテゴリーに関わらず世界共通で5つの基準のもとに行われており、①素材の質、②料理技術の高さ、③味付けの完成度、④独創性、⑤常に安定した料理全体の一貫性が丁寧な調査によって測られている。
■レストランランキングガイドも多種多様
私自身は、レストランコンペティションは多彩である方が良いと考えている。飲食店の魅力を測る基準にも多様性が必要だと思うからだ。例えば、同じくフランス発祥のランキングガイド『ゴ・エ・ミヨ』も人気だが、これは事務局(日本にも「ゴ・エ・ミヨジャパン」という事務局がある)が匿名調査員を任命するというシステム。調査員を務めるのは食通ではあるものの一般人・飲食関係者たちであり、『ミシュランガイド』に比べると若手料理人や生産者の発掘に力を入れている印象を受ける。あくまでも個人的な考えだけれど。
筆者提供
『ゴ・エ・ミヨ』2025年のアワードセレモニーの様子。順位を競い合うというよりは、多彩に設けられた賞をもって若手シェフから生産者に至るまでを祝福する雰囲気が特徴。日本におけるファインダイニングのガイドブックとしては唯一、47都道府県を網羅している。 - 筆者提供
「アジアのベストレストラン50」は、各エリアのチェアマン(評議委員長)が任命したボーター(投票者)が、好きな店にオンラインで投票を行うというシステムだ。もちろん、投票するにもルールがあってそれに則ってのこととなるが、「飲食業界のアカデミー賞」と異名をとるだけあり、発信力のある人気シェフや表現力に長けた話題性のある店がランクインするのが特徴的。
筆者提供
「アジアのベストレストラン50」(2024年より)。ソウル、マカオ、バンコク、シンガポール、東京など、アジア各国の主要都市で毎年3月末に開催されており、日本からもここ数年は10軒を超える人気店がランクインしている。 - 筆者提供
「食べログ」や「Googleマップ」は、誰もが好きに自身の感想を投稿できるSNS的な食サイトであるものの、料理批評家によるランキングサイト「OAD」と結果がかぶることも多いという。大人数の総意というのは、批評家でも一般人でも結局は類似するというのが興味深いところだ。ただし、口コミへの無責任な暴言やそれに対する店側の辛辣な応酬などは昨今、問題になっている。私たち食べ手は飲食店に対する強い意見を目にした時、それが「批評」「評価」なのか、それとも「応援」や「誹謗中傷」なのか、判断する必要があるだろう。
■ミシュランガイド独自の“戦い方”を理解する
本題に戻ろう。今回の『ミシュランガイド京都・大阪2025』から、私たちは何を読み解けばいいのかという話だ。人によってその答えは違うだろうが、筆者としての解はこうだ。
一つ、『ミシュランガイド』とは誰をターゲットにしたレストランガイドなのか。
二つ、何をルールに店が選ばれているのか。
いずれも、前述した「星の定義」にはっきりと記載がある。この2つの理解に努めれば、食べ手は飲食業界の今を知って応援する気持ちになれるだろうし、世界有数のレストラン激戦国である日本(大袈裟でなく本当にそうだ)で、それでも飲食店を営みたいという料理人たちにとっては、健やかな野心と希望を持ち続けるための指針になるはずだ。逆に、ターゲット層やルールと自分の店の方向性が合わないなら、別のランキングガイドに力を割く方が精神的にも経営的にもヘルシーではないだろうか。
写真提供=©MICHELIN
『ミシュランガイド京都・大阪2025』で三つ星を獲得した料理人、そしてシェフ。重鎮感たっぷりという印象を受けるのは、壇上の8人のうち7人が日本料理界のレジェンド達であるからかもしれない。 - 写真提供=©MICHELIN
『ミシュランガイド京都・大阪2025』では、掲載店数こそ東京版に38軒及ばないものの、星付き店の数では2軒リードした。しかし、もっと大きい違いはその内訳だ。例えば、京都では三つ星店5軒と二つ星店16軒のすべてを日本料理店が占めた。大阪は「HAJIME」がイノベーティブとして唯一、三つ星を獲得しており、二つ星にはイノベーティブ「カハラ」「フジヤ1935」、フレンチ「ラ・シーム」が入っているが、やはり日本料理及び和食系が強い。
思い立って数えてみたところ、東京版では日本料理が掲載総数のうち20%を占めたのに対して京都・大阪版ではなんと40%。さらに寿司店や天ぷらなどの和食系を含めるとその割合はもっと高くなるから驚きだ。ちなみに、東京版におけるフレンチの割合は27%で、京都・大阪だと12%。ここまでくるとようやくわかる。『ミシュランガイド京都・大阪2025』の結果が示しているのは、この地が世界ナンバーワンの日本料理王国だということだ。
これを旧態依然だとか圧力があるのではとか言うのは間違っている。というのも、先にも述べた通りミシュランガイドはそもそも旅人のために編集されたレストランガイドであり、京都・大阪を訪れる旅客が非日常の風情を味わい、“ニッポン旅行”の食事体験として日本料理店に行くのは当然である。京都や大阪が食文化の拠点として栄えた過去からのバックグラウンドがあるからだ。
対する東京はといえば、旅行客やインバウンド客の他にビジネス需要の絶対数が大きいのも致し方ない。他国に類を見ないバラエティーに富んだジャンル構成が東京フードシーンの特徴になったのもまた、必然なのだ。
■三つ星取得シェフの言葉にヒントがあった
今回、『ミシュランガイド京都・大阪2025』ではアフターパーティーも開催され、会場では多くのシェフたちが緊張から解き放たれた表情で交流をしていたのが印象的だった。そんな中、何人かのシェフたちにコメントをいただいたのだが、その言葉の中にも今回の結果を理解するための多くのヒントがあった。
筆者撮影
大阪「HAJIME」米田肇シェフ。 - 筆者撮影
「(唯一、イノベーティブの料理ジャンルで三つ星を獲得していることに対して)海外のお客様が多い店ではありますが、そもそもフランスでの修業時代から多くの星付き店を食べ歩き、星の数によって料理にどんな違いがあるのか、自分なりに理解に努めました。星の数による違いを自分の言葉で語れるようにならないと、いつかチームを作ってもスタッフに思いや指示を共有することはできないと思っていたので。そういう意味では、思考と言葉も大切だと思います」(大阪「HAJIME」米田肇シェフ:三つ星獲得)
筆者撮影
京都「菊乃井 本店」料理長、村田吉弘さん。 - 筆者撮影
「(なぜ京都・大阪は日本料理店が強いのか、という質問に対して)そもそも、ミシュランガイドの三つ星というのがグランメゾンを意識して編集されていたからではないかなと自分なりに考えています。京都は伝統と文化、格式の町であり、私ら三つ星店の料理人は庭園をはじめとする空間芸術や文化の継承までを、自分の仕事だと考えている。調査対象は皿の上であるとわかっていますが、結局はそういう思いが料理にもつながっていくのではないでしょうか」(「菊乃井 本店」村田吉弘さん:三つ星獲得)
写真提供=©MICHELIN
壇上に並んだ、今回晴れて一つ星を獲得したレストランのシェフたち。初々しい表情、緊張の面持ちが見ていてキュンとするようだった。今後、星を維持するという大きなミッションが生まれ新たな責務を背負ったことになる。心からエールを送りたい。 - 写真提供=©MICHELIN
その一方で、やはり時代は変遷している。今回も、新規の一つ星獲得店の中には韓国生まれでニューヨークでキャリアを積んだ京都のモダンフレンチ「ジャン-ジョルジュ アット ザ シンモンゼン」のハナ・ユーン総料理長や、日本で初めてイノベーティブメキシカンからの星獲得を果たした大阪「ミルパ」のウイリー・モンロイシェフの初々しい笑顔があった。世界で初めてラーメンというジャンルで「ミシュラングリーンスター」を獲得したヴィーガンラーメンの店「ウズ」なども、要注目だ。
筆者撮影
京都「ジャン-ジョルジュ アット ザ シンモンゼン」のハナ・ユーン総料理長。韓国に生まれ、ニューヨークの名門料理学校「CIA」を卒業し、星付きモダンフレンチレストラン「ジャン-ジョルジュ」に勤務。副料理長まで上り詰めた後に、京都への栄転を果たした。 - 筆者撮影
筆者撮影
大阪「ミルパ」のウイリー・モンロイシェフ(右)と彼を支える海外の名店での経験も豊富なソムリエ、長谷川憲輔さん(左)。筆者はたまたまこの前夜、「ミルパ」で食事をする幸運に預かったが、オープン1年未満というのに和気あいあいとした心地良いチームが印象的だった。 - 筆者撮影
■ランキング結果の光と影
今回の結果に昨年のそれを照らし合わせると、残念ながら降格となったり星を落としたりした店も当然ある。移転準備中や閉業、辞退といった理由もあるようだが、「何にも変わってないのになぜ」と途方に暮れている店も当然あるだろう。そもそも、ミシュランガイドに限らず多くのレストランランキングガイドは「飲食業界を応援したい!」という思いに満ちている一方で、はっきりいってお節介でもある存在だ。もし私が突然知らない機関から「あなたの文章はいい感じだけれど、まだまだ残念な部分もあるので星はなし」などと言われたらショックだろうし、憤(いきどお)るに違いない。
それでも多くの料理人たちは、さまざまなランキングガイド、コンペティションに臨み続ける。その結果が集客や収益につながれば、食材の質を上げたりスタッフの数を増やしたりすることが可能となり、夢は膨らむだろう。思いのたけを表現した料理を口にしたゲストから「おいしかった」「楽しかった」と言われると幸せを感じるだろうし、結果として、さまざまなランキングガイドに対して彼らが無関心ではいられない現状を生んでいる。
食べ手も作り手もお互いに思いを通わせつつ、大きくうねりを上げて変遷していく現代の飲食業界。『ミシュランガイド京都・大阪2025』が教えてくれたものは、単なるランキング結果だけではない。
----------
山口 繭子(やまぐち・まゆこ)
食のディレクター
神戸市出身。『婦人画報』『ELLE gourmet』(共にハースト婦人画報社)編集部を経て独立。主に飲食店やホテル、食に関するプロジェクトのディレクションや執筆活動を行う。訪れた飲食店や食した料理などについてはSNSで発信を続けている。著書に自身の朝食トーストをまとめた『世界一かんたんに人を幸せにする食べ物、それはトースト』(サンマーク出版)がある。
----------
(食のディレクター 山口 繭子)