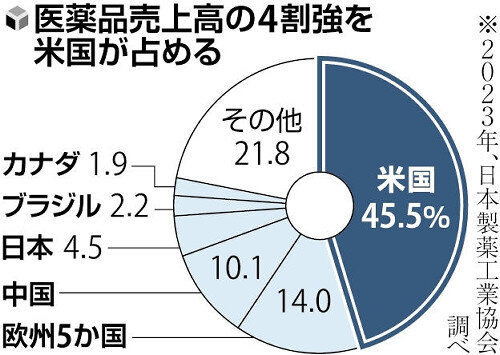新NISAで9割の日本人はカモにされるだけ…荻原博子「絶対投資のアドバイスを受けてはいけない相手」【2025年3月BEST5】
2025年4月14日(月)18時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kokouu
2025年3月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト5をお送りします。投資・年金部門の第4位は——。
▼第1位 「オルカン、S&P500」だけでは危険すぎる…資産3.7億円を築いた脱サラ投資家が「新NISA」で選ぶ最強の投資先
▼第2位 投資した瞬間に「負け確定」…ホリエモンが推す長期投資家が「絶対行くな」という場所、「絶対買うな」という商品
▼第3位 知識がない人は大損する「ねんきん定期便」正しい見方と落とし穴…ハガキが届いたら一番に見るべき項目
▼第4位 新NISAで9割の日本人はカモにされるだけ…荻原博子「絶対投資のアドバイスを受けてはいけない相手」
▼第5位 「オルカン」「S&P500」だけを買うよりずっといい…成功する個人投資家が「新NISAの枠」で必ず買っている有望株
投資で失敗しないためには何に気をつければいいか。経済ジャーナリストの荻原博子さんは「『投資教育』を受けていない人がほとんどなのに、不安に駆られて投資を始め、大損しているというのが現実である。なんとなく株を買ったり、新NISAを始めたりしたらカモにされるだけだ」という——。
※本稿は、荻原博子『65歳からは、お金の心配をやめなさい』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/kokouu
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/kokouu
■「投資をしないと豊かな生活を過ごせない」は本当か
いま、日本では、国をあげて「投資をしよう」の大合唱になっています。
「投資は儲かる」という話を専門家から聞いたり、「過去最高の株価」とテレビで報じられたりしたら、「投資」をしないと損をするのではないかと、不安になるのも無理はないでしょう。
けれど私は、必ずしも投資が儲かるとは思っていません。
実際、私のまわりには「投資さえしなければ、明るい老後が迎えられたのに……」と悔やむ人が、意外と多いからです。
はっきり言って、いまの相場は、素人がラクに儲けられるような環境ではなくなっています。しかも、皆さんが「投資の常識」として教え込まれていることが、まったく通用しなくなっているのです。
ところが、国をあげて「投資」を勧めるものだから、「国が言う『投資の常識』に従えばいい」という風潮になっています。
私からすれば、いまの「投資の常識」は、そうとうおかしいのに。
「投資の常識」について語る前に、皆さんに知っておいてほしいことがあります。
投資で成功するには、それなりの「投資環境」と個人の「投資センス」が必要だということです。
ではこれからから、「投資環境」と「投資センス」という2つの視点で、いまのマーケットを見ていきましょう。
「投資は儲かる」なんて言葉を
信用してはダメ!
■いまの経済環境で投資は「ギャンブル」になるだけ
投資が儲かるのは、基本的に経済が右肩上がりで伸びているからです。その意味では、現在の投資環境はそれとはほど遠いものです。
ウクライナや中東で続いている戦争の影響は、株価や為替といった形で私たちの身近に現れます。そして、これから世界で何が起きるのかは、誰も予測できない。
こうした、先の読めない世界情勢のなかで、金融商品にお金を投じるのは、「投資」ではなくギャンブルそのものです。
世界情勢が不透明化しているだけでなく、国内に目を向けても、景気はけっして安定しているとは言えません。
その大きな要因となっているのが、「アベノミクス」の負の遺産とも言える「格差拡大」と「円安」です。
2013年に当時の安倍晋三首相が掲げた経済政策、アベノミクスは当初、「異次元の金融緩和のもと大企業が潤えば、その雫は、中小零細企業や一般のご家庭にも滴り落ち、みんなを豊かにする」と大宣伝していました。いわゆる、トリクルダウン理論です。
そしてアベノミクスで大企業は大儲けし、2023年度末までに企業の貯金にあたる内部留保を600兆円以上貯め込みました。
その結果、この儲けが雫となって滴り落ちることはありませんでした。給料は上がらず、給料から物価上昇分を差し引いた実質賃金は下がり続けました。
写真=iStock.com/mapo
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/mapo
しかも、当初は「全国津々浦々まで、景気回復を実感してもらう」などと言っていた安倍首相自ら「アベノミクスでトリクルダウンは起きない」と言い出す始末。
そのため、富めるものと貧しいものの貧富の差は広がり、目指した豊かさとは正反対に、モノは潤沢にあっても、思うように買えなくなり、個人消費は低迷し続けました。
■「アベノミクス」のあまりに大きな副作用で円安に
アベノミクスは、「金融」「財政」「成長」の三本の柱で推し進められるはずでした。
けれども、「財政」は途中で消え、「成長」は、戦略がないまま実行されず、結局「金融」の一本足打法となり、なんとか景気を維持するために、日銀が大量の国債を買い上げる大規模金融緩和を10年以上続けていたのです。
一方、コロナ禍で景気を底支えするために金融緩和で金利を低くしてきた海外の先進国も、コロナ禍が収束して景気が再び上向きになったのを見て、軒並み金利を上げました。
それなのに日本だけは、あまりに長くゼロ金利(途中からマイナス金利)を続けたために、物価が上昇したら金利を上げて抑えるという普通の国が行なっている政策が打てなくなってしまいました。
長期間続いたアベノミクスの副作用があまりに大きかったのです。
海外は金利を上げるのに、日本では金利が上げられない。そうなると、海外との金利差が開きますから、円が売られてドルが買われる「円安」が進んでしまったのです。
お金は金利の低いところから高いところに流れますから、金利の低い円が売られて、金利の高いドルが買われ、円安になるのは当然のことなのです。
■不透明極まりない経済環境で投資は危険すぎる
実際、アベノミクスが始まった頃(2013年6月)の為替相場は、1ドル=100円前後でした。ですから、海外からさまざまなものを安く買えたのですが、これが2024年4月末には1ドル=160円を超えました。
わかりやすく言えば、100円で輸入できた品物が160円になったのですから、それが価格に反映され、消費者が「モノの値段が上がった」と悲鳴を上げるのはもっともです。
日銀の黒田東彦前総裁がアベノミクスをやりっぱなしのまま退陣し、その後始末をすることになったのが植田和男総裁ですが、10年間も続いた「金利のない状況」を是正するのは難しかった。
2024年7月末に金利を0.25%引き上げると決定、8月5日には4400円以上も株価が暴落するという状況になり(翌6日には3200円以上上昇)、行き着く先が見えません。
不透明極まりない経済環境で投資するなんて危険すぎる。私には、到底理解できない行動なのです。
「格差拡大」「円安」の不透明な経済環境で、
投資に手を出すのは危険!
■日本で「投資教育」を受けた人は、わずか7%
これまで述べた不透明な経済環境に加えて、「投資教育」を受けていない人までが、不安に駆られて投資を始め、大損しているというのが現実です。
実際、投資の何たるかを知らないまま、なんとなく株を買ったり、新NISAを始めたりしている人があまりにも多いのです。その原因は、国として「投資教育」に力を入れてこなかったことです。
写真=iStock.com/Tomwang112
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/Tomwang112
それどころか、30年くらい前までは、「投資などせずに、堅実に貯金しろ」というのが、国の方針になっていました。
50年前には、夫が「給料の一部で株を買う」と言うだけで、奥さんが泣き崩れ、親戚縁者から「どこでどう道を踏み外してしまったのか」と咎められるほど。投資などする人は、「道楽者で、おかしな人だ」と白い目で見られていたのです。
そんな状況でしたから、「投資」になどほとんどの人が関心を持っていなかったのです。
結果、金融広報中央委員会が約3万人を対象に実施した「金融リテラシー調査2022年」では「『金融教育を受けた』と認識している人」の割合は、日本では7.9%とじつに少ない。
もちろん、証券会社などの金融機関に勤めていて、「投資」の何たるかを学び、その知識を活かして老後の資産を増やそうという人は別です。
けれど、大多数の人は、「投資」のリスクも教えられずに、儲かりそうだという雰囲気だけで「投資」をしようと思い、金融機関の窓口でファイナンシャルプランナーから勧められるがまま商品を買っているという状況は、いまも昔も変わらないようです。
■かつては「株屋」と呼ばれていた証券会社
いま70歳以上の方は、子どもの頃を思い起こしてみてください。
私もそうでしたが、両親から口が酸っぱくなるくらい「投資より貯金しなさい」と言われてきませんでしたか?
なぜなら、戦前・戦後に生まれた世代は、現在では考えられないような徹底した「貯蓄教育」のなかで育ってきているからです。
戦争中は、戦費をまかなうために「愛国貯金」を、戦後は、復興のための貯蓄教育が徹底して進められてきました。
そのため、投資について学んだことがないばかりか、投資はギャンブル、まともな大人のやることではないと、常識として叩き込まれてきたのです。
また証券会社も、戦前・戦後は「株屋」と呼ばれ、「ばくち打ち」というイメージがあったのです。
いまでは考えられませんが、投資も勧めず、投資商品も売らない、お役所のようにお堅い印象の銀行員と比べて、証券会社は社会的に一段低く見られていました。
■「銀行だったら間違いない」は大間違い
いまは、銀行を役所と同一のように語ると違和感を覚える若い方もいるかもしれません。
しかし、金融の自由化が進む2000年前後までは、銀行は「大蔵省出張所」として大蔵省の支店のような役割を果たしていました。どの銀行も大蔵省がつくった住宅ローンや預金サービスを、同じ金利、同じ期間、同じ条件で扱っていました。
荻原博子『65歳からは、お金の心配をやめなさい』(PHP研究所)
これが自由化され、各銀行が独自につくった住宅ローンなどを売れるようになったのは25年ほど前からです。いまや銀行も投資商品や保険を売るのが当たり前の時代になっていますから、隔世の感があります。
いまの高齢者は、まだ銀行が大蔵省出張所だった時代に預金したりローンを借りたりしている人が多いので、「銀行だったら間違いない」と思っている人が多いですが、それは大間違いなのです。
お金を取り巻く環境はどんどん変わってきているのに、昔と変わらない感覚で金融機関に相談したら、簡単にカモにされます。
そんな世の中についていけないと思った人は、無理をしてはいけません。あなたは、投資に手を出す必要はないのです。
投資教育を受けていないあなたは、
いいカモにされますよ!
(初公開日:2025年3月26日)
----------
荻原 博子(おぎわら・ひろこ)
経済ジャーナリスト
1954年、長野県生まれ。経済ジャーナリストとして新聞・雑誌などに執筆するほか、テレビ・ラジオのコメンテーターとして幅広く活躍。難しい経済と複雑なお金の仕組みを生活に即した身近な視点からわかりやすく解説することで定評がある。「中流以上でも破綻する危ない家計」に警鐘を鳴らした著書『隠れ貧困』(朝日新書)はベストセラーに。『知らないと一生バカを見る マイナカードの大問題』(宝島社新書)、『5キロ痩せたら100万円』『65歳からはお金の心配をやめなさい』(ともにPHP新書)、『年金だけで十分暮らせます』(PHP文庫)など著書多数。
----------
(経済ジャーナリスト 荻原 博子)