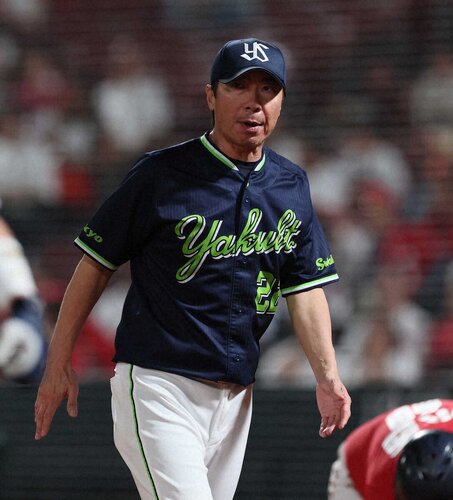「マツダ地獄」から「マツダ天国」へ…この15年で安易な安売りから脱却できたマツダの潔い割り切り
2025年5月21日(水)16時15分 プレジデント社
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/jetcityimage
※本稿は、鈴木ケンイチ『自動車ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/jetcityimage
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/jetcityimage
■ブランドロイヤルティを重視するスバルとマツダ
ビジネス用語として「ブランドロイヤルティ」という言葉があります。ロイヤルティ(Loyalty)の意味は「忠誠心」。つまり、ブランドロイヤルティといえば、そのブランドに対する忠誠心を表します。
具体的には、「いろいろとあるブランドの中から、顧客がひとつのブランドに忠誠を誓って、同じブランドを買い続ける」ことを「ブランドロイヤルティがある」と表現します。顧客がブランドのファンになっていると言ってもいいでしょう。
そうした、ブランドロイヤルティを重視しているのが、スバルとマツダです。
近年のスバルは、アメリカでのビジネスが好調で、業績は安定していますが、数多くクルマが売れているわけではありません。2023年度の世界での販売は97.6万台です。
トヨタの10分の1以下しかありません。
ところが、スバルは昔から「スバリスト」と呼ばれる、強力なファンが存在しています。
それこそ昭和の時代から、綿々と続いているスバルのファンを指す言葉です。何台もスバル車に乗り継いでおり、そしてスバル車に乗っていることを誇りに感じているようです。
■世界最高レベルの安全性能と優れた4WD技術
では、スバルの特徴とは何なのでしょうか? それは技術を重視する姿勢です。もともとスバルは、戦前の中島飛行機を起源とするメーカーです。飛行機を作っていた技術者が集まってクルマを作り始めました。
そのため、いつの時代もスバルは、技術を重視したクルマづくりをおこなってきました。なぜ、この格好なのか? なぜ、この方式を使うのか? ということすべてに技術的な理屈があったのです。
逆に言えば、流行やデザイン、コスパなどは苦手です。しかし、その技術を大切にする姿勢が、古くからファンを獲得する理由となっていたのです。そして、現在のスバルは世界最高レベルの安全性能と優れた4WD技術を持っています。
特に雪道を走らせるのであれば、スバル車ほど信頼できるクルマはありません。北米でも、スバルの顧客は雪の降る地域に偏っています。
そうした状況をスバルもよく理解しているようです。2014年に発表した中期経営計画「際立とう2020」では、「大きくはないが強い特徴を持ち質の高い企業」を目指すと示されています。
写真=iStock.com/yocamon
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/yocamon
強い特徴をもって、ファン=ブランドロイヤルティの高い顧客を獲得するのがスバルというわけです。
■「マツダ地獄」から過去15年でブランドロイヤルティを高めたマツダ
もうひとつの、ブランドロイヤルティの高い自動車メーカーがマツダです。ただし、マツダのブランドロイヤルティの高まりは、それほど古いわけではありません。言ってみれば、過去15年ほどで一気にブランドロイヤルティを高めてきたのがマツダです。
逆に、それよりも前のマツダの評判は、それほど高いものではありませんでした。マツダに対する悪口として「マツダ地獄」という言葉があったほどでした。
これは、「マツダ車に乗ると、中古車の下取りが安いので、新車を安売りするマツダしか乗れない」という状況を揶揄するものでした。マツダから離れたいのに離れられないことを地獄と呼ぶわけです。そこにはマツダへの愛はありません。
また、それは、マツダの安易な安売りで売り上げを伸ばすという手法にも問題がありました。
しかし、マツダも「マツダ地獄」が悪いことは理解しています。そこで、マツダは2000年代後半から、数から質への変換を目指しました。広範囲に顧客を求めるのではなく、強いファンを育てることにしたのです。
これは、北米で「マツダ3(日本名:アクセラ)」を購入したユーザーへの調査が気づきになったそうです。
北米のマツダのユーザーはデザインと走りのよさという、特定の項目への満足度が高かったのです。それに対してライバル車は、もっと幅広い項目で選ばれていました。
その結果を受けてマツダは、平均的な合格点を望むユーザーではなく、個性を求めるユーザーに向けた商品を作っていこうと考えたのです。まさにブランドロイヤルティの重視です。
■「2%戦略」で「マツダ天国」へ
2010年代になるとマツダの経営陣はインタビューで「2%戦略」という言葉を使うようになりました。これは「マツダのシェアは2%しかないから、その2%の人に強く支持されるブランドになろう」という戦略です。
同時にマツダは、「魂動デザイン」「スカイアクティブ・テクノロジー」といった新しいデザインと技術を使った「CX-5」などの新世代商品群を投入します。
2010年代以降に登場したマツダの新型車は、魅力的なデザインと楽しい走りをもって人気モデルとなることに成功しました。その結果、中古車の下取り価格が非常に高くなり、逆にマツダ車からマツダ車への乗り換えを促進することになります。
これを「マツダ地獄」の正反対ということで「マツダ天国」と呼ぶこともあるほどです。
100人のユーザーのうち、なるべく多くを獲得しようとすると、どうしても無難なデザインや機能をもった、ありきたりの製品になりがちです。
その先にあるのは価格競争です。そうではなく、尖った商品にすることで、少数のユーザーに確実に買ってもらう。それが、スバルとマツダの戦略となっているのです。
■北米、中国からあえて身を引いたスズキ
スズキは年間に300万台以上を売る、世界10位となる自動車メーカーです。
ところが、日本だけで言えば、その販売台数は67.4万台(2023年度)ばかり。スズキ全体で言えば、日本での販売は、わずか21%ほどしかありません。
販売に占める日本市場の割合が少ないのは、他の日系自動車メーカーも変わりません。ただし、その内訳は他メーカーと大きく異なります。
写真=iStock.com/PaulMaguire
※写真はイメージです - 写真=iStock.com/PaulMaguire
まず、スズキの世界販売の中に、世界最大級となる中国市場と北米市場がまったく入っていません。スズキは2012年に北米市場から、そして2018年に中国市場から撤退しています。大きな市場から、あえて身を引いているのです。
その代わりに、179.4万台(世界販売の約57%)をインドで販売しています。他に欧州で23.6万台、アジアで17.8万台、アフリカで9.8万台。欧州とアジア、アフリカの3地域を合わせて51.2万台を販売しています。
その中で、インド、パキスタン、ハンガリーなどの10カ国で4輪車販売のシェア1位を獲得しています。インドは大きな市場となりますが、それ以外は小さなところばかりです。
これは「どこの国でもいいから一番になりたい」という、スズキの元社長の鈴木修氏の願いが理由となります。鈴木修氏が社長に就任した1978年当時、75年の排気ガス規制対応の失敗、77年の創業者の祖父と前社長の病など、スズキの社員はみな意気消沈していたそうです。
その中で、社員の士気を高めるため、鈴木修氏が願ったのが「一番になること」だったというのです。そんなスズキは、1975年にパキスタン、1983年にインド、1992年にハンガリーに進出します。
■コスパのよいクルマづくりが真骨頂
当時は、どこも小さく貧しく、他の自動車メーカーが見向きもしなかった市場です。
ライバルのいないところに行けば、小さなスズキでも、その場所で一番になれる! というのがスズキの狙いでした。そして、そこでスズキは結果を出します。
小さなクルマが得意というだけでなく、小さくて安い中でも高いパフォーマンスを実現するのがスズキです。いわばコスパのよいクルマづくりがスズキの真骨頂です。
特にインドのユーザーは、コストパフォーマンスにうるさいことで知られています。ただ安いだけではダメで、お買い得でなければならない地で、スズキはしっかりと認められ、インドの地場メーカーさえも押しのけて、インドナンバー1のメーカーになります。
世界に進出する前の1980年のスズキは、年間50万台規模の自動車メーカーでした。ところが世界進出を果たしたスズキは、1990年代後半には150万台を超えるようになります。
インドとハンガリーに進出したことで、会社の規模が3倍に拡大しました。そして、インドの市場拡大にあわせて、現在は300万台を超えるメーカーになっています。
しかも、スズキは2023年に発表した「2030年度に向けた成長戦略説明会」において、2021年度に3.5兆円だった売り上げを、2030年度には7兆円にまで伸ばす計画を発表しています。そこでスズキが狙っている市場は、インドとアフリカです。
鈴木ケンイチ『自動車ビジネス』(クロスメディア・パブリッシング)
インドは2050年には人口が現在の13.8億人から16.6億人へ、アフリカは12.9億人から23.7億人にまで増加すると予測されています。
人口増加に伴い名目GDPも増加し、2050年には日本の5.7兆ドルを上回る、インド13.5兆ドル、アフリカ9.6兆ドルが予測されています。その大きく成長するインドとアフリカで、スズキは売り上げを伸ばそうというのです。
他の自動車メーカーは、どこも中国や北米など、現在の最大マーケットをターゲットにしていますが、スズキは、それ以外の市場で成長を考えています。他の人の行かない道をゆき、そこで成功を収めてきたスズキ。この先も、そうした歩き方は変わらないようです。
----------
鈴木 ケンイチ(すずき・けんいち)
モータージャーナリスト
1966年生まれ。茨城県出身。大学卒業後に一般誌/女性誌/PR誌/書籍を制作する編集プロダクションに勤務。28歳で独立。徐々に自動車関連のフィールドへ。2003年にJAF公式戦ワンメイクレース(マツダ・ロードスター・パーティレース)に参戦。年間3、4回の海外モーターショー取材を実施、中国をはじめ、アジア各地のモーターショー取材を数多くこなしている。新車紹介から人物取材、メカニカルなレポートまで幅広く対応。日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員。
----------
(モータージャーナリスト 鈴木 ケンイチ)