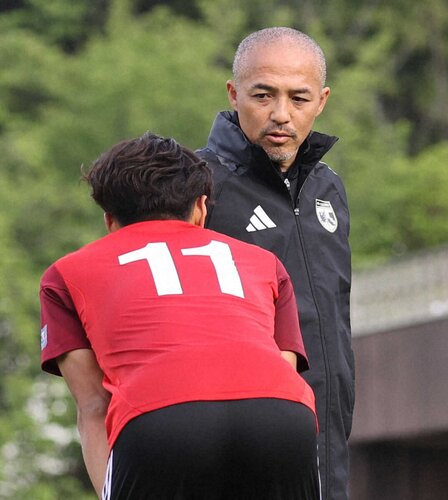APTが増えればJリーグの魅力は上がるのか。欧州との比較で検証
2025年4月2日(水)15時0分 FOOTBALL TRIBE

今2025シーズンのJリーグで、選手のみならず観客や視聴者を戸惑わせているファウル基準の曖昧さ。その元凶となっているのが、開幕直前の2月にJリーグチェアマン野々村芳和氏が打ち出した「APT(アクチュアルプレータイム)」の増加というものだ。
APTとは、試合時間90分+アディショナルタイムのうち、ボールが実際に動いている時間を指す。この数字がJリーグが欧州と比較して劣っていることを問題視した野々村氏が、“思い付き”のように「APTの増加」を打ち出し、現場の大混乱を招いた。
「国際競争力を高めるため」と強弁する野々村氏だが、果たしてそれは真実か。APTが増えることによって、Jリーグは魅力的なものとなるのか。欧州5大リーグと比較して検証したい。
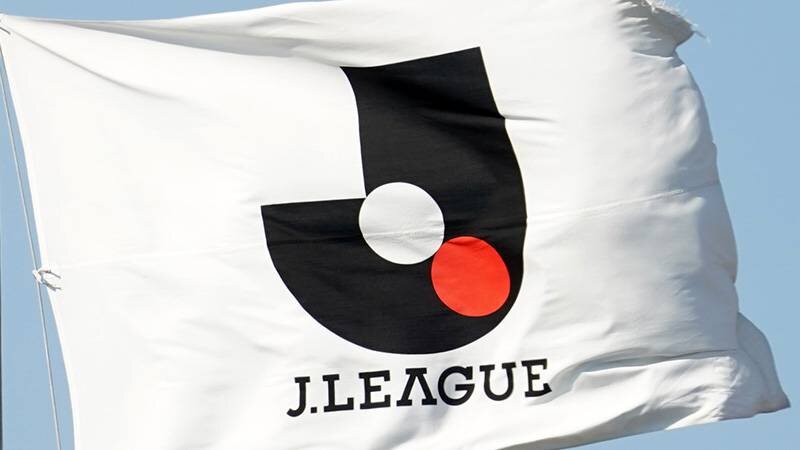
JリーグがAPTを重視する理由
JリーグがAPTを重視する理由には、ファウル、ボールアウト、選手の倒れ込みなどによる試合の中断を減らすことで、テンポの速いサッカーと質の向上を目指すことが挙げられる。Jリーグ公式サイトでも、トラッキングデータ(走行距離やスプリント回数)とともにAPTが取り上げられ、リーグ全体の哲学が反映されている。
Jリーグは発足当初から欧州サッカーをモデルとしてきたが、フィジカルやインテンシティーで差があるのは事実であり、APTを増やしたくらいでそこに追い付くのは一朝一夕では不可能だろう。しかしAPTを増やすことで、試合の密度を高め、選手の技術や戦術を磨く時間を確保しようとする意図もある。特に近年、ACL(AFCチャンピオンズリーグ)をはじめとする国際舞台での競争力強化が課題とされており、APTは改善点の1つとしての物差しとなっている。
また、Jリーグでは、審判員の能力を評価する1つの基準としてAPTが用いられることがある。笛を吹いたことによる中断が長いとAPTが減少し、逆に些細なボディーコンタクトでは笛を吹かずに流すことで、自ずとAPTが増える。当初は審判の質を高める取り組みと考えられていたが、逆に“流すことが正しい”という風潮となったことで、明らかなファウルまで見逃される結果を招き、選手から不興を買っている。

欧州5大リーグでのAPT注目度
一方で、欧州5大リーグ(プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、 リーグ・アン)ではAPTが注目されることは少ない。あくまで“マニアックな数字”として扱われている。
プレミアリーグはフィジカルコンタクトとオープン展開が特徴で、走行距離やスプリント回数、プレッシング強度などのデータが重視される。APTよりも、インテンシティーやゴール期待値が試合分析の中心だ。
ラ・リーガでは、テクニックとボール支配率、パス成功率が注目される。APTについても議論に上ることはあるものの、試合の質を測る指標ではない。
セリエAは、何と言っても監督同士の戦術的な駆け引きが最大の見どころで、守備の組織力やカウンターの精度が焦点で、戦術の完成度が優先される傾向にある。
ブンデスリーガは、ハイプレスとトランジション(攻守の切り替え)が重要視され、走行距離やスプリント数のデータが先に立つ。APTは時折、話題に上るものの、試合の魅力を測る指標とは見なされていない。
リーグ・アンは、アフリカ系選手が多いのが関係しており、個人能力とスピードが強調され、ドリブル成功数やシュート数が注目される。APTは議論にも上らない。

欧州、APTはあくまで結果論
欧州では、試合が途切れることも戦術の一部として受け入れられる傾向がある。例えば、セリエAでは選手が倒れて時間を稼ぐタイムマネジメントも伝統とされ、プレミアリーグでは激しいファウルも試合の魅力と見られている。
例えば、3月23日に開催されたUEFAネーションズリーグ準々決勝のドイツ代表対イタリア代表の第2戦(ジグナル・イドゥナ・パルク/3-3で引き分け、ドイツが2戦合計スコアを5-4として準決勝に進出)。
前半36分にドイツがコーナーキックから2点目を奪った場面で、ボールボーイを務めた15歳のドイツ人少年ノエル・アーバニアックさんは、DFと戦術面を擦り合わせるために一瞬ゴールを空けていたイタリア代表GKジャンルイジ・ドンナルンマの隙を突き、すかさずドイツ代表MFジョシュア・キミッヒにボールを渡しクイックリスタート。MFジャマル・ムシアラのゴールに繋げた。
アーバニアックさんはこの試合で初めてボールボーイを務めたというが、その働きはドイツ国中で称賛された。その機転も大したものだが、APTを意識していたドイツ代表イレブンの集中力の賜物ともいえる得点だ。
また、バルセロナ(2008-2012)、バイエルン・ミュンヘン(2013-2016)を経て、現在マンチェスター・シティ(2016-)を率いる名将ジョゼップ・グアルディオラ監督は、よくピッチサイドにいるボールボーイに声を掛け、素早くボールを渡しリスタートを促すよう“指導”する姿を見せている。
そして現役最後のバイエルン在籍時代にその姿に感化された元スペイン代表MFシャビ・アロンソ氏(2017年引退)は、現在、監督を務めるバイエル・レバークーゼンでのホームゲームにおいて、対戦相手に休む暇を与えず、APTを増やす目的でボールボーイを増やすという試みを行っているという。
しかし欧州5大リーグともなれば、メディアやファンの関心事は、スター選手のゴール数やパフォーマンスであり、APTはあくまで結果論として扱われている。それを逆利用するような戦術や指揮官もいるが、あくまで“例外”だ。

Jリーグ、APTを増やすことが目的化
対してJリーグは、その成長をアピールする目的でAPTを可視化し、発信することで試合の質を担保しようとしている。結果、APTを増やすことが目的化してしまい、ファウル基準の曖昧さを生み出すという本末転倒な現状を生んでしまっている。
JリーグにはJリーグの良さがあったはずだが、欧州に近付くための目標としてAPTを重視したことで、逆にスタイルが確立されていない“発展途上”であることが詳らかになるという皮肉な状態となっている。
Jリーグの2023シーズンの平均APTは約55〜58分だったが、以降は増加傾向にある。これは審判の質向上や、選手のフィットネス面の向上によるものだ。ファウル云々の話ではない。
欧州5大リーグといってもAPTについては国ごとに異なり、プレミアリーグで50〜55分、ラ・リーガで55〜60分、ブンデスリーガで53〜57分程度とバラつきがある。特にプレミアリーグは激しい展開で笛が吹かれる場面が多く、APTが短めになる傾向がある。
JリーグがAPTに注目するのは、試合の質と流動性を高め、国際競争力をつけるための戦略的な選択だった。しかし欧州5大リーグでは、それぞれが既に確立されたスタイルや優先事項(インテンシティ、戦術、個人能力)があるため、APTはあくまで“参考程度”の指標に留まっている。
JリーグがAPTを強調する姿勢は、成長過程にあるリーグならではの特徴であり、欧州とのギャップを埋める1つの手段に過ぎない。APTが試合の質を決めるというのはあまりにも近視眼的であり、そこに囚われるのは目的と手段を取り違えていると言わざるを得ない。APTを重視することを全否定まではしないが、選手別あるいはチーム別の走行距離や戦術の洗練度となどのバランスが今後の課題と言えよう。