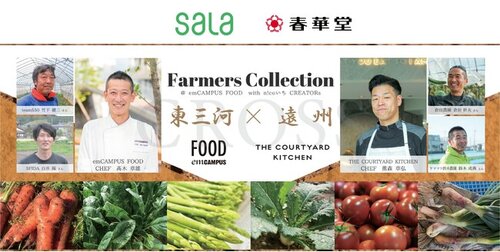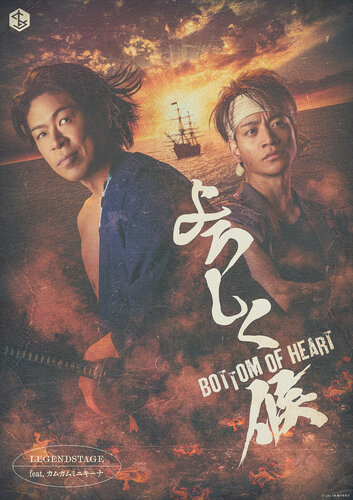京都・大覚寺の名宝が一堂に集う!本尊「五大明王像」、重文指定の障壁画123面、兄弟刀「膝丸」「髭切」の共演
2025年1月30日(木)6時0分 JBpress
(ライター、構成作家:川岸 徹)
京都西北の嵯峨に位置する真言宗大覚寺派大本山「大覚寺」。2026年に開創1150年を迎えることを記念し、優れた寺宝を一挙公開する展覧会、開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 −百花繚乱 御所ゆかりの絵画−」が東京国立博物館で開幕した。
嵯峨天皇の別荘がはじまり
大覚寺の名を聞いて、「嵯峨御所」「院政」「南北朝時代」といった言葉を連想するという人も多いのではないか。まずは大覚寺の歴史をざっと振り返ってみたい。
平安時代初期、嵯峨の地を愛した嵯峨天皇は嵯峨に別荘を設営し、遊猟の折などにたびたび足を運ぶようになった。当初の別荘は小規模なものであったが、檀林皇后との成婚を機に大幅に拡張。これが大覚寺の前身、離宮嵯峨院である。
嵯峨天皇は唐より帰国した真言宗の開祖・空海の理解者でもあり、空海の勧めにより嵯峨院内に五大明王像を安置。自身も旱魃や疫病の大流行に際し般若心経を書写するなど、仏教への信仰を強めていった。嵯峨天皇崩御後の876(貞観18)年、皇女・正子内親王の願いにより離宮嵯峨院は寺に改められ、「大覚寺」と命名。嵯峨天皇が浄書した般若心経は60年に1度しか開封できない勅封として奉安され、今も大覚寺は般若心経写経の根本道場として広く世に知られている。
南北朝時代のきっかけに
その後、大覚寺の名は南北朝時代に再び歴史の表舞台へと現れる。南北朝時代とは建武の新政を主導した後醍醐天皇が吉野に開いた南朝と、足利尊氏が擁立した光明天皇の北朝による内乱の時代として知られているが、そもそもの発端は鎌倉時代末期。1272(文永9)年、政務の実権を握っていた後嵯峨上皇が崩御すると、天皇の後継者争いが勃発し、天皇家は2統に分裂。
幕府はこの争いの対応策として、2つの系統が交互に皇位を継ぐ「両統迭立」を制定。これにより、京都・嵯峨の大覚寺と縁が深い「大覚寺統」と、京都の里内裏のひとつ持明院の御所で暮らす「持明院統」が、代わる代わる天皇の地位に就くことになった。だが、そんなその場しのぎの策がうまくいくわけもない。やがて持明院統は北朝に、大覚寺統は南朝になり、対立が激化。北朝は独自に天皇を擁立することになる。
第88代後嵯峨天皇以降の系譜は下記の通り。
「持明院統(後の北朝)」 89後深草⇒92伏見⇒93後伏見⇒95花園⇒北朝1光厳⇒北朝2光明⇒北朝3崇光⇒北朝4後光厳⇒北朝5後円融⇒100(北朝6)後小松
「大覚寺統(後の南朝)」 90亀山⇒91後宇多⇒94後二条⇒96後醍醐⇒97後村上⇒98長慶⇒99後亀山
1392(元中9/明徳3)年、南朝の第99代後亀山天皇が北朝第6代の後小松天皇に譲位する形で、南北朝の分裂は終わりを迎えた。
本尊《五大明王像》と華麗な障壁画
こうした歴史に彩られた古刹・大覚寺。876(貞観18)年に大覚寺となってから、2026年で開創1150年を迎える。これを記念し企画されたのが特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 −百花繚乱 御所ゆかりの絵画−」だ。
会場には絵画、仏像、書簡、刀剣、工芸品と大覚寺ゆかりの寺宝が並ぶ。特に以下の3つを見どころとして紹介したい。
1つめは、大覚寺の本尊である重要文化財《五大明王像》。平安時代後期に円派の仏師として活躍した明円の作で、優美さと力強さが見事に調和している。5体揃って東京で公開されるのは今回が初の試みだ。
2つめは、寺内の中央に位置する「宸殿」と安土桃山時代に建てられた歴代門跡の居室「正寝殿」の内部を飾る障壁画。襖絵・障子絵など約240面の障壁画は一括して重要文化財に指定されており、展覧会ではそのうち123面(前期・後期で展示替えあり)が公開される。展示空間にずらりと障壁画が並ぶ様子はまさに壮観。これだけの量を「よくぞ京都から運んだ」と感嘆するばかりだ。
123面の障壁画の中でハイライトといえるのが狩野山楽筆《牡丹図》。全18面、総長約22メートルの超巨大スケール。その大きさに圧倒されるが、全面にわたってほぼ実物大の牡丹の絵がリズミカルに配されており、なんとも軽やかで心地いい。狩野永徳の画風を引き継ぐ絵師・狩野山楽の技量を感じ取ることができる。
名刀「膝丸」「髭切」が再会
3つめの見どころとして清和源氏に代々継承された「兄弟刀」を挙げたい。平安時代中期に源満仲がつくらせたもので、大覚寺に所蔵される《太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》と、京都・北野天満宮が所蔵する《太刀 銘 安綱(鬼切丸〈髭切〉)》の2刀が揃って展示されている。
《太刀 銘 □忠(名物 薄緑〈膝丸〉)》は平家物語に付属する「剣巻」にて“名刀中の名刀”とうたわれている刀で、複数の呼び名を持つが、特に「膝丸」の名で知られている。源満仲が刀鍛冶につくらせ、試し切りとして罪人の首を斬り落としたところ、膝のあたりまで斬り下げたため「膝丸」と呼ばれるようになったという。「膝丸」は源満仲から、頼光、義家、義経へ、そして曾我兄弟の仇討ちを経て頼朝へと受け継がれている。
もう一方の《太刀 銘 安綱(鬼切丸〈髭切〉)》は「髭切」の呼び名で有名。こちらは罪人の試し切りの際に髭まで見事に切り落としたため、「髭切」の名が付いたという。源満仲から頼朝に至る源氏の重宝であったが、鎌倉幕府滅亡により新田義貞が手に入れ、さらに義貞を討った斯波高経の手に渡り、その子孫の最上家が継承した。
「膝丸」と「髭切」。東京での同時展示は史上初とのこと。刀剣界を代表する兄弟刀の再会を喜びつつ、じっくりと鑑賞したい。
開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 −百花繚乱 御所ゆかりの絵画−」
会期:開催中〜2025年3月16日(日)
会場:東京国立博物館 平成館
開館時間:9:30〜17:00 ※入場は閉場の30分前まで
休館日:月曜日(2月10日、24日は開館)、2月25日(火)
お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)
https://tsumugu.yomiuri.co.jp/daikakuji2025/
筆者:川岸 徹