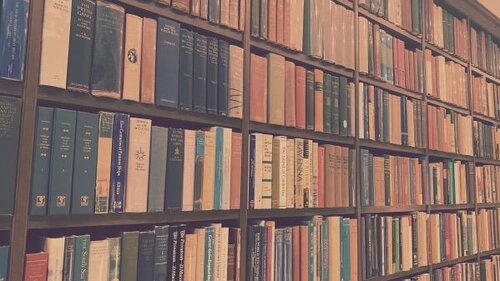伊集院静と<本屋>。「本屋がなくなれば、恋愛もどこか淋しいものになるし、人生で何が大切かもわからなくなるだろう」
2025年3月1日(土)12時30分 婦人公論.jp

(写真提供:Photo AC)
2023年11月24日に永眠された、作家・伊集院静さん。『機関車先生』『受け月』など数々の名小説を残し、『ギンギラギンにさりげなく』『愚か者』を手掛けるなど作詞家としても活躍したほか、大人としての生き方を指南する連載エッセイ「大人の流儀」シリーズでも人気を博しました。今回は、そのシリーズ最終巻『またどこかで 大人の流儀12』から、伊集院さんのメッセージを一部お届けします。
* * * * * * *
いなくなってしまえば
馴染みが消えるというのは淋しいものである。それが人であればなおいっそう寂寥感は増すのだろう。
人でなくとも、街なら、店などがそうであろう。
先日、千代田区神保町の一軒の本屋さんが休業した。休業は別に永遠ではなく、ビルを建て直し、再開するそうだ。昨日、自著が足らなくなって買い求めに常宿を出て、駿河台下の坂道を下りて行ったのだが、そこにいつも開いていた本屋が閉まっていた。
——そうか、しばらく休業すると通知が届いていたナ。
そこで別の本屋をめざしたのだが、“本の街”として有名なこの界隈には案外と新しい本を販売している本屋が少ないことに気付いた。数軒しかない。
たしかこっちにあったなと、すずらん通りを奥に行った。あった。昔、店長と仲が良かった店だ。しかしどこを探しても、私の本は一冊もなかった。何か書店員が選んだ本が表に置かれているのか、この春に出版した3冊のどれもない。
——こんな本屋だったっけなあ〜。
いや、本屋は競争が激しくて特徴を出さねば生き抜いていけないのだろう。それにしても自分の本がないのは淋しいものである。それでもどこかにないかと探し回ったがなかった。少し腹が立ってくる。
——何だ、スカシタ本ばかり置きやがって!
仕方がないので店員に尋ねると、倉庫のほうにはあるらしい。出版社から送られてきても私の本は店頭には置かないのだろう。
——よくまあこんなにツマラナイ本ばかりを並べてやがるナ(すべてではないが)。
ともかく倉庫にある本を買って送ってもらうことにした。
本屋がなくなれば
少年時代、私が暮らした商店街には貸本屋しかなかった。もっと町の中心へ行けば本屋が2軒あったが、新しい本はよほどの時でないと買い与えてもらえなかった。たいがい正月だった。姉たちは本に付いた付録を嬉しそうに開いたりしていた。
本屋に馴染むようになったのは、文章を書くことを生業にしてからである。

『またどこかで 大人の流儀12』(著:伊集院静/講談社)
上京し、大学の野球部の寮へ、母が文学全集、詩歌集を送ってきた時、先輩たちが勝手に私物の段ボールを開けてチェックした。
「おまえ本当にこのモンガクを読むのか?」
——モンガクじゃなくブンガクですが……。
漱石を読める部員は一人もいなかった。
詩集の一節をなんとはなしに諳(そら)んじると、のちにジャイアンツにドラフト一位で入団した同級生のY山に、「おまえどこか身体が悪いのか?」と本気で訊かれた。
今、日本で書店の数はおそろしく減っているが、失くなることはおそらくあるまい。
八百屋がなくなれば、鍋料理ができなくなるように、本屋がなくなれば、恋愛もどこか淋しいものになるし、人生で何が大切かもわからなくなるだろう。
仲の良かった書店員
海外へ取材で出かけることが多かった40代から50代の時、訪れた街で必ず本屋を覗いた。
なぜ本屋へ?
本屋に並べてあるものは、その街の文化の程度をあらわしたり、街の人々が何を好んでいるかがわかる。
本屋はやはりヨーロッパの都市が充実している。パリの美術書が多い本屋、アムステルダムの写真集ばかりの書店、ニューヨークの大統領の自伝が並べてあるブックショップ。
夕刻、訪れたチャイニーズレストランに昼間会った書店員がいたりすると、思わず笑い合ったりした。
書店員で仲の良い人は数人しかいなかったが、中の一人に美しい女性がいて、私のどうしようもない本を丁寧に売ってくれた。
その人の姿が、或る時、店から失せ、ほどなく入院していることがわかり、短い手紙を書いた。退院を待ったが叶わず、彼女は早逝した。今でも彼女のお母さんと連絡を取ることがあるが、やさしく美しい人であったが故に、それ以降は書店員と関わるのをやめた。
本屋大賞
梶井基次郎という作家が、丸善という書店の本の上にレモンをひとつ置いて立ち去り、そのレモンがいつか爆(は)ぜてしまうだろうと書いた一文が、文学だと称した時代は、すでに喪失してしまっている。
ニューヨークの書店は恋愛映画の舞台になることがあるが、日本においてはなかなかそうならないのはなぜなのだろう。
本屋大賞という書店員が選ぶ面白い本というのがある。それに選ばれると本が売れるらしい。
私の疑問のひとつに、どうして、それに私の本が選ばれないのだろうか、というのがあるが、編集者に訊くと、「あれは新人が対象ですから、無理でしょう」と言われた。
「私はいつも新人のつもりなんだが」
「そんなに怖い新人作家どこにもいませんよ」
「…………」
※本稿は、『またどこかで 大人の流儀12』(講談社)の一部を再編集したものです。