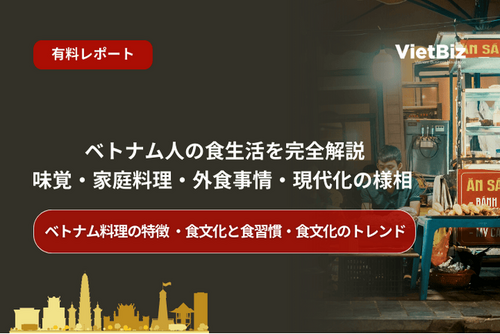春の味覚「シロウオ」の体が透けている理由
2021年3月27日(土)21時0分 Jタウンネット
[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2021年3月15日放送の「なぞの細道」のコーナーで、イサザの生態について調べていました。
石川の春の味とも言える「イサザ」。
正式名称は「シロウオ」ですが、全国で呼び名が変わっていて、能登ではイサザ、県内でも美川あたりではスベリ、茨城や徳島ではヒウオ、伊勢湾ではギャフ、大阪ではドロメなどと呼ばれています。

小さくても立派な大人
石川に春の訪れを告げる「イサザ」。3月になるとイサザ漁が解禁され、独特の網でイサザを揚げる光景がみられますよね。
産卵のため上流に昇っていくところを網で一網打尽にするのがイサザ漁で、水温が上がる3月下旬ころが水揚げのピークです。
このイサザ、茹でると白くなりますが、もともとは透明です。どうしてでしょうか?
実は、ウーパールーパーと同じ現象で、幼形成熟(ネオテニー)しているのです。
幼形成熟とは、子どもの頃の特徴のまま大人になること。
ほとんどの魚は生まれたときは透明ですが、イサザは子供なわけではなく、小さな透明の形をしていても立派な大人なのです。
他の魚から食べられる避けるために、この姿のままだと考えられます。
(ライター:りえ160)