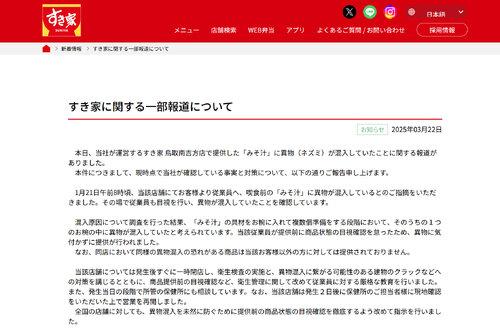ネズミの実験で<オスの負けグセ>が子に伝わることが判明。中野信子「ネズミとヒトで99%の遺伝子が共通する中、楽観的な答えを出すには現実はあまりに残酷で…」
2025年4月10日(木)12時30分 婦人公論.jp

(イメージ写真:stock.adobe.com)
インターネット上の誹謗中傷について、プラットフォーム事業者に迅速な対応を義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法」が4月1日に施行されました。脳科学者の中野信子先生は言語とはその性質上、人間の行動パターンを大きく変えてしまうことがあることを指摘し、「人間の歴史はまじないの歴史」と語ります。「言葉の隠された力」を脳科学で解き明かします。そこで今回は、中野さんの著書『咒の脳科学』から、一部引用、再編集してお届けします。
* * * * * * *
ストレスでネズミの遺伝子に影響が
慢性社会的敗北ストレス(CSDS、Chronic social defeat stress)と呼ばれる、広く用いられているうつ状態の動物モデルがある。
たとえばオスでは、自分の縄張りに別のオスが侵入するとその個体を攻撃するが、侵入した側はその攻撃から自分の身を守るために回避的な行動をとる。この状況が長く続くとき、攻撃を受け続けた側が与えられる負荷は大きくなる。これを慢性社会的敗北ストレスといい、特有の行動パターンや身体的な反応が現れることがわかっている。
一般的な人間の行動パターンを前提に考えれば、必ずしも回避することが敗北とは限らないというイメージがあろうが、これは動物を用いた研究モデルの話であるので、根拠の不明な無意識のバイアスに引きずられることなく冷静に読んでもらいたいと思う。
さて、慢性社会的敗北ストレスにさらされたネズミについて、糞便の菌叢解析や、腸管の遺伝子発現について解析を行うと、やはり腸内細菌の構成と腸管の上皮細胞において異常が見られた。メスでは、体重が減少して不安様行動を示すようになり、免疫系にも異常が生じることがわかっている。オスでは、精子に含まれる遺伝子の活性(DNAに対する化学修飾)の変化が起こり、子どもの性格にまで影響が及ぶことが明らかになった。
実際、アメリカのマウントサイナイ・アイカーン医科大学の研究チームによって行われた実験で、環境的な要因が父親の遺伝子に影響を与え、精子を経由して子どものストレス耐性に影響を与えるという報告があるのでご紹介したい。
子どものストレス耐性が優位に低下
研究チームは、体の大きさの異なる2種類のオスを同じカゴに入れ、体格の大きなオスが劣った側のオスを毎日10分程度ずつ一方的に攻撃するように仕向けた。
そのうえで、さらに効果的にストレスを与えるため、攻撃が終わってからも相手の姿が見えるように、透明なアクリル板で間仕切りをした。また、透明なアクリル板には穴を開けておき、相手のにおいも届くようにした。

『咒(まじない)の脳科学 』(講談社+α新書)
劣った側のオスが十分に慢性社会的敗北ストレスにさらされたところで、精子を採取し、メスに人工授精を行った。人工授精が選択されたのは、オスが性的快感を得て慢性社会的敗北ストレスが軽減されてしまうことを防ぐためである。
こうして生まれた子どもたちのストレス耐性を調べると、そうでない子どもたちと比較して有意に低いということが明らかになった。また、ストレスを与える環境に置かれる前後でのオスの精子を比較すると、1000を超える遺伝子で発現パターンが変化していた。
格差を拡大する慢性社会的敗北ストレス
ネズミで見いだされた結果について、人間にそれをそのまま当てはめるのはやや乱暴に感じられるかもしれない。

(イメージ写真:stock.adobe.com)
とはいえ、ヒトとネズミの遺伝子にどれほどの差があるのかというと、2002年に6ヵ国からなる研究チームが、マウスゲノムをほぼ完全に解読したその成果報告によれば、遺伝子的にはマウスは驚くほどヒトに近く、全遺伝子のうちヒトにも対応する遺伝子が見つかったものは99%であったという。
一方で、種に固有の遺伝子は、全体の遺伝子の数約3万のうち、300個ほどにすぎなかった。
人間の男性においても慢性社会的敗北ストレスが遺伝子活性に変化を与えているのだとすれば、社会経済的地位と相関して子のストレス耐性に差が生じ、世代を超えてその影響が継承され続けていくということにもなる。格差は拡大し続けていく。もちろん幾分かの個体はこれを打開するための努力も工夫もするだろうが、全体的なトレンドに変化を与えるほどのムーヴメントになるだろうか? 楽観的な答えを出すには現実はあまりに残酷であるように見える。
虐待する側から発見された遺伝的素因
自尊感情の低さについてしばしば話題になることがある。これは多様なかたちがあれども、実際に虐待に遭ったことがあるかどうか、またストレスの大きい環境にいたかどうかによって影響を受ける。
虐待をする人について書かれた文章も多い。著者は冷静に書いているようであっても、第三者的に見ればややエモーショナルではないかと感じられるものも少なくはなく、また読み手も当事者ないしは当事者に近いところにいた人物であれば百パーセント客観的にそれを読むということは難しいだろう。
虐待について、その行動が遺伝子を含む生物学的な要因を持つことを示唆する研究があるが、多くの人はこれを認めたくはないのではないかと思う。倫理的にはこのようなことを語るべきではないと考えられがちなことではある。
しかし、実験的な事実として見いだされているものをポリティカルコレクトネスによって歪めてしまってもよいものかどうかというジレンマは、科学がややもすれば世間から冷たいものとして見られてしまうある種のリスクとともに、常に科学者が抱えているストレスにもなっていることは明記しておかねばならない。
素因を持っているとはいえ、ある人が虐待を実際にするかどうかというのは、遺伝的に決定される性格的な要素とは別の後天的な理由も介在するということも、当然考慮に入れるべき変数となる。けれども、依存症が遺伝的な素因を持つことと同様で、その素因そのものは環境要因によって変化するものではない。変容するのは行動であって素因があるという事実は変わらない。要は、行動に起こしてしまうかどうかが後天的に制御できる部分であって、その回路自体は生物学的に存在することを否定するのは少なくとも科学的な態度とは到底言えない。
虐待された側がする側になるという説
巷間言われがちなことに、人が虐待をする理由として、親や他の家族から虐待を学んでしまうから、自分も他者に対してそのように振る舞うのだ、という言説がある。

(イメージ写真:stock.adobe.com)
幼少期の被虐待の経験や、身近にいる大切な存在がくり返し言葉や暴力によって虐待されるのを見たりすることで、行動の内的モデルがそのように歪められてしまい、自分もそれがスタンダードな行動であると信じてそう振る舞うようになる、というものだ。
この考え方にも理がないわけではない。虐待を受けた人は、その記憶を想起することによって、自分がかつて傷つけられたことを実感すれば想起のたびに二度、三度と心理的に傷つくことになる。
それを回避するために、虐待は攻撃ではなく普通の行動であったのだ、ないしはあれは愛情だったのだと認知する。すると、自分が同じ行動をとったとき、それは相手を傷つけているのではなく、その人を思ってそうしているのだ、その人のために自分はあえてこのような行動をとっているのだ、と言うだろう。
児童虐待の件数増加の背景に
けれども、この考え方だけでは、被虐待の経験のない人でもこうした攻撃を他者に対してすることがあるのはなぜなのか、という説明がつかない。
ハーバード大学の研究グループが2021年に、子ネズミを虐待するネズミで、そのときにだけ活性化する神経回路を視床下部に発見した。オスかメスかには関係なく、この回路は、性フェロモンを受け取る器官などからの入力を受け、視床下部と大脳辺縁系の一部を活性化させる。すると、子ネズミへの虐待が行われる。
この発見が興味深いのは、子ネズミに対する攻撃以外ではこの回路が活性化しなかったという点である。大人のネズミ同士の喧嘩、メスに対するオスの攻撃などでは活性化せず、ストレスに対しても反応しない。
子ネズミを虐待するときにだけ働くこの神経回路は、場所を特定してその部位だけを刺激する特別な方法を用いると、果たして子ネズミへの虐待を人為的に引き起こすことができた。また、その神経の働きを弱める薬品を投与すると、虐待行動は止まったのである。
子ネズミの虐待のためだけに作動する神経回路をネズミが生まれつき持っているということは何を意味するのだろうか。何のためにこのような回路が存在するのか。
子殺しはめずらしくない
生物界では子殺しは決してめずらしいことではない。もちろん人間の世界でも子殺しや育児放棄は起きている。
ライオンやシマウマでは新しいリーダーとなったオスが、自分の遺伝子を残すためにその群れの子どもを皆殺しにする。子どもが殺されないと、メスが発情しないからである。また、リーダーが変わると妊娠中のメスは流産するという種もある。これはブルース効果と呼ばれ、交尾相手以外のオスと接触したり、その性フェロモンに暴露されると起きる。
ネズミの虐待回路が性フェロモンによって活性化されることを考慮すれば、これらは無縁の話ではないのかもしれない。ヒトでも、実子に対する虐待と比較すると、連れ子への虐待は約6倍多いという統計がある。虐待死のリスクは数十倍から100倍にもなるという。
注意しなければならないのは、リソースの不足がこの回路の活性化の誘引とはならないという点だ。豊かな時代、裕福な環境であっても条件がそろえば起きる。むしろ近年の増加数を見れば、豊かさこそが児童虐待の原因ではないか? と思えてしまう。子どもの虐待は人間の性質の一部ではないか?
このような問題提起が、多くの人の否定的な反応を引き起こすのではないかと気がかりな思いもあるが、それが自然なものならなおさら、止めるのもまた人間に本然的に備わる知性という仕組みでもあろう。
※本稿は、『咒の脳科学』(講談社)の一部を再編集したものです。
関連記事(外部サイト)
- 中野信子が警鐘「イケニエへの攻撃がやめられないのは脳の仕組みに由来。あなたも制裁の快楽をむさぼる<コンプライアンス中毒>に陥っていませんか?」
- データによると<恋愛経験の豊富な人ほどウソつき>。中野信子「ウソをつくことで次世代を残す可能性が高くなるのであればその子孫はおそらく…」
- 誹謗中傷で人は死ぬ?衝撃の<ノーシーボ効果>とは。中野信子「目隠しされた男性は<今から首を切る>と濡れた布を首にあてられただけで…」
- 脳科学者・中野信子 科学的に証明された<運をよくするコツ>とは?「根拠のない自信」で成功確率はグッと高まる【2023編集部セレクション】
- デーブ・スペクターさんが『徹子の部屋』に登場。脳科学者・中野信子さんと語った「日本人以上に日本を知るために行っている情報収集法」